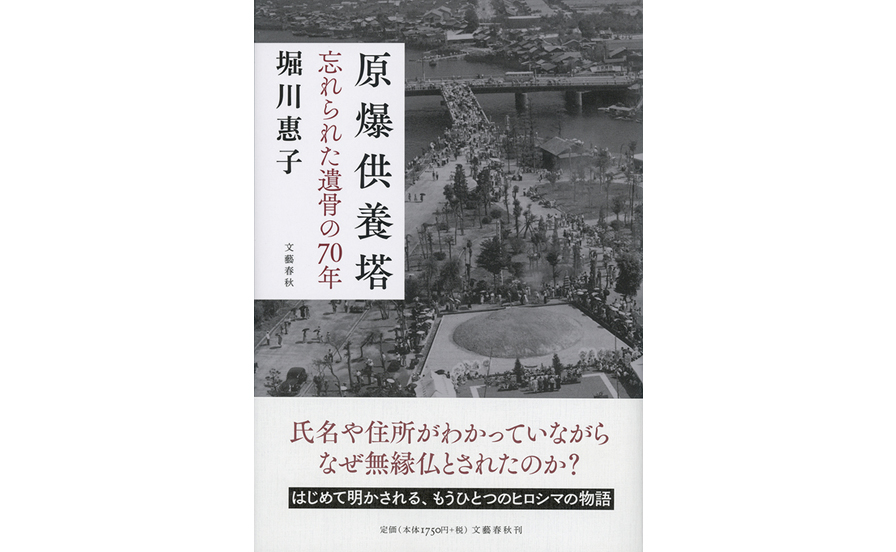ホロコーストの記憶の変容を構造的にとらえるとナショナル・アイデンティティの変容
2018.04.24
歴史認識、記憶の構造的変容ーと国民的主体の形成・編成は表裏一体を
―ドイツはホロコーストの記憶と真摯に向き合ってきた。それにもかかわらず、日本は真摯に歴史に向き合おうとしていない。―
…などということを私もつぶやきがちだが、高橋秀寿著『ホロコーストと戦後ドイツ 表象・物語・主体』(岩波書店、2017年)の「おわりに」の以下のくだりにはっとさせられる。歴史認識を「そのような道徳的な規準で判断するときに、その議論は、「八勝二敗で日本の勝ち」のような国民間の優劣を競う居酒屋論争に陥ってしまうであろう。それは日韓や日中の歴史認識をめぐって国民間の優劣を競うようなネット上で頻繁にみられる発想と同じレベルの議論にすぎない」。
むしろ、社会構造の大きな変化とともに、歴史認識と記憶の文化も構造的に変容していること、それが国民的主体の形成・編成と表裏一体の事象であることを観察、分析していく必要がある、と著者はいう。というと、あまりに抽象的で難解に響くかもしれない。しかし、ホロコーストが30年以上の歳月を経たのちに発見され、その想起が「ブーム」として全世界に広がり、続いているのかを詳細に辿る本著を読み通せば、表象の変遷が私たちのアイデンティティの変容をもたらす過程を具体的に理解できるだろう。
発見直後は「戦争犯罪のひとつ」だったホロコースト
ドイツ国内でホロコーストの記憶が発見されたのは30年以上を経た後とあるが、それまで全く顧みられなかったわけではない。
むしろ、強制収容所解放直後に、アメリカ軍はその報道価値を素早く認識した。その前にソ連軍がアウシュビッツを解放したが、ソ連軍の報道を西側は重視しなかった。当初から「取り上げるべき事実」の抽出に恣意がある。連合軍は解放を目的として強制収容所を占拠したのではなく、発見は偶然だった。しかし、米軍従軍者に生じた感情は、まず、犠牲者に対する同情よりも、加害者への怒りと憎悪だったという。それまで、アメリカ人は対独戦争に意味を見出していなかったが、多くのアメリカの雑誌と新聞が強制収容所の写真を公表したことにより、突如として、戦争目的が正当化された。事後的に。それらの報道において、ホロコーストは、解放者としてのアメリカ人、加害者・罪人としてのドイツ人、受動的犠牲者の三者の登場人物によって展開された物語のなかで語られた。
他方で、ドイツ人は、驚愕しつつ、「集団的罪」のテーゼを否定し、無知を強調し、自分たちも騙されたのであり、ナチズムの犠牲者であるととらえた。さらには、連合軍による空襲被害が強制収容所の惨劇に匹敵するとみなしたり、強制収容所での犯罪で名誉を傷つけられたという意味で自身が犠牲者であるという見方もあった。
強制収容所の現実は10数年の歴史的変遷のなかで一様ではなかったし、強制収容所によって、あるいは犠牲者の国籍や民族的範疇によっても現実は異なっていた。
当初、英米軍が解放し、撮影した収容所の現実がホロコーストの「現実」となった。英米軍が解放したドイツ国内の強制収容所において、ユダヤ人収容者は少数であり、犠牲者がユダヤ人に特化されない戦争犯罪のひとつであった。世界史的意義を見いだされたのは後のことである。
普遍的な悲劇・青春ドラマとしての受容
西ドイツがナチズムと共産主義を同一視する物語を形成し、両者の犠牲者からなる共同体になっていく過程で、ホロコーストには積極的な意味を与えられなかった。しかし、1950年代に「アンネ・フランク・ブーム」が起きる。アンネ・フランクの日記にまず価値を見いだしたのはアメリカだった。そしてそのブームはドイツにも波及する。なぜか。アンネの苦悩の民族性、歴史的脈絡は捨象され、人類が普遍的に経験しうる悲劇として受け止めることができたからである。母親との軋轢や恋愛の体験を通しての成長という、青春ドラマとしても解釈されえた。
しかし、希望を持ち続ける無辜の犠牲者という普遍的なイメージは、レジスタンスの英雄物語を求めるユダヤ人にとっては苦々しいものであった。
人種主義に基づく犯罪としての理解へ
1950年代末に若者が反ユダヤ主義的な言動を発露することが社会問題となり、ホロコーストに関する「沈黙」が西ドイツの信用を損ないかねないと意識されてから、現代史教育の拡充が図られるようになる。その過程で、この事件を「普遍主義的」に人間の問題として解釈するのではなく、「特殊主義」的に「私たち」=ドイツ人の課題として「私たち」の責任を意識する重要性が説かれるようになる。そして、敗戦直後は帰属が明確でなかった犠牲者はユダヤ人によって表象=代表されるようになった。ホロコーストは「戦争犯罪」のひとつにとどまらなくなり、強制収容所だけに限定されることもなくなる。日常的な差別から迫害と強制移住と強制労働、そして強制収容所でのガス殺に至るまでの体系的に実践された民族殺戮の結末であることが認識されるようになるとともに、何より、人種主義に基づく犯罪として描き出された。
このような理解は、ホロコーストを歴史的状況のなかで理解する「機能派」ではなく、ナチス指導部の意図が貫徹された結果とみなす「意図派」の解釈に基づいている。となると、その罪の責任は、「ヒトラーとその側近」にあることになる。このころの表象として、下からの反ユダヤ主義やユダヤ人迫害からの受益、傍観といった一般市民のかかわりの示唆が消されていることが興味深い。ナチ党員に話しかけている女性市民の姿をわざわざ切り取ってナチ党員だけの写真を掲載する、といったことがなされたのだ。そして、犠牲者はあの有名なゲットー蜂起写真で手をあげた子どものように、抵抗する術をもたない女子どもとして表象された。それは、英雄像を望むイスラエル建国後のユダヤ人にとって好ましいものではなかった。しかし、西ドイツの若者にとっては、犠牲者が無力であるほど犯罪の重大さを実感し得た。とはいえ、ドイツ人も抵抗の余地のない受動的存在として受け止めた。
「受動的犠牲者」の史上最大の事件との認識から「ブーム」へ
1979年に西ドイツで放映されたアメリカのテレビ映画『ホロコースト』は、犠牲者を脇役から主役へ転じ、その視点からのユダヤ人迫害の歴史を物語った。西ドイツ人は、ユダヤ人犠牲者に自己同一化しながらも、自分たちも連合軍の爆撃によって無辜の女子どもが殺されたと犠牲者であることも見いだす。「受動的犠牲者」の史上最大の事件として歴史的価値が認識された後、その記憶は「ブーム」となった。
1993年のスピルバーグによる『シンドラーのリスト』は、抵抗の余地がないために英雄とはなり得ないユダヤ人収容者と、戦争受益者として利益を生み出す安価な労働力としてユダヤ人を救済しながらいつしか破産してまで救済するようになったシンドラーという気まぐれな人物のストーリーであった。この映画は、ホロコーストという「唯一無二」の出来事を表象するという最悪の反則を犯したと、『ショアー』の監督であるランズマンに批判されたが、むしろその後多数のホロコースト映画が製作されることになり、ひとつのジャンルとして成立することになった。
他方、1980年代に興隆した日常史研究と歴史運動の中で、忘却されてきた第三帝国の歴史を掘り起こし、日常の中からの「ホロコースト」を再発見しようとする動きもある。ナチ総統府などがあったかつてのナチの中心地区を記憶の場として形成したり、ベルリン市内のシナゴーグの跡地が強制移送のための集合場所として想起するべく記念碑が建立されたりといった、空間の歴史を想起する試みが興味深い。
記憶認識のありようの変化は、フォーディズムからポストフォーディズムへの社会構造的な転換によってもたらされた…といった分析は、研究者たる著者の真骨頂であろう(しかし、私の能力の関係から割愛…すみません…)。
「私たち」は決して所与のものではない。過去の記憶のありかたによって、日々、形成されていくものだからだ、「私たち」は課題として、闘争として、つねに私たちの前にある。
…という「おわりに」の最後の言葉を読みながら、「慰安婦」をめぐる歴史認識に思いを馳せる。著者も、日本の右翼的な政治家やジャーナリズムが日本軍による「強制」が働いていなかったことをことさら強調するのは、犠牲者たちの「受動性」を恐れているからだ、と「おわりに」で書き添えている。
歴史的な想起をナショナリスティックな憎悪や排除の契機と陥らせないようにするにはどうしたらいか。困難な問題に足を踏み入れる手がかりとなる労作である。