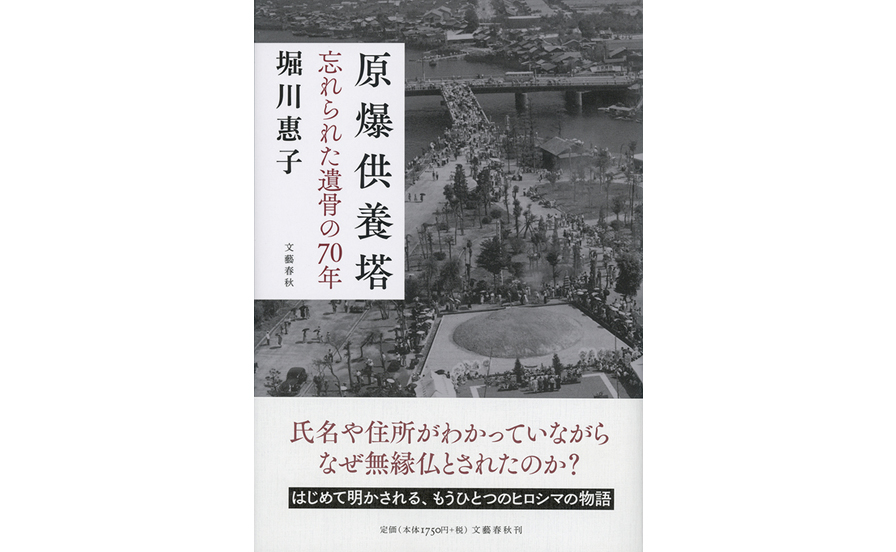「NASAを支えた知られざるヒロインたち。実話に基づく感動のサクセス・ストーリー」
こんなセールストークとともに、3人の黒人女性が毅然と前を向いて歩いている写真の映画広告に、感動する意欲満々となった。が、あえなく忙しくて観に行けず、原作のマーゴット・リー・シェタリー著・山北めぐみ訳『ドリーム NASAを支えた名もなき計算手たち』(ハーパーBOOKS、2017年) を読んでみた(なお、原作のタイトルは『Hidden Figures』であり、副題の「名もなき計算手たち」のほうが近いだろうか)。
帯には、宇宙飛行士の山崎直子さんの「彼女たちの挑戦は、壁を超える勇気を与えてくれる」という推薦文が載っている。いや増しに期待が盛り上がる。
差別にあっても頑張ることの尊さ、しかし…
1943年5月、人種隔離されたラングレー記念航空科学研究所(のちにNASAのラングレー研究所)で、5人の黒人女性が働きはじめた。研究成果を軍事産業に普及させる責務を負っていたこの研究所では、「勝利は空から!」と声をかけあう職員らが、航空機の開発にしのぎを削っていた。その開発に必要なのは、物理学、そして数学。1930年代から「小娘girl」が計算手として働き出し、当初は「女などに任せられるか」という男性技師たちも女性計算手の能力を認めるようになっていた。1941年、当時の黒人労働組合の会長がルーズベルト大統領に高賃金が見込める戦争関連の仕事を黒人にも開放することを要求した。同年、大統領は軍需産業における人種差別撤廃を命じた大統領令等に署名。その2年後の1943年、黒人女性たちの応募書類がラングレー記念航空科学研究所に届くようになったのだ。
黒人女性たちがラングレーの門をくぐったことは、間違いなく大きな前進といえるだろう。しかし、前進は一挙にというわけにはいかなかった。たとえば、彼女たちが門をくぐる前に「有色人種女子用」と刻字した金属製のトイレ用標識が用意されていた…。トイレはどこか?と周囲にきいても、「あなたのトイレを私が知っているわけない」という含みの薄ら笑いをされる屈辱、想像がつかない。彼女たちの日常には、人種差別、さらには性差別が歴然と壁としてあった。
しかし、彼女たちは、それぞれ、困難な中で、家事も育児も仕事も頑張り抜く。頭脳明晰な黒人女性たちが当時つける仕事は教師だったが、それで得られる賃金は黒人ではなく女性ではない教師よりも低く、夏休みになれば洗濯物工場などで働いて臨時収入を得る等して家計をなんとか支えていた。その待遇に比べたら、研究所の待遇は抜群であった。
彼女たちは、貧しくても身なりを整え、勤勉であることを心がけた。そして、倍の効果をあげてようやく半分認められるのが、黒人、女性だ、と肝に銘じていた。少しでも気が緩んでいたら、「やはり黒人は」「やはり女は」「ダメだ」という思い込みを補強してしまうことになる、自分たちのふるまいが、次の世代の道を開くか閉ざすかを左右する、という気負いが、まぶしいというより痛々しい。
彼女たちの健気な頑張りは胸を打つ。差別はストレスだ。判然としない場合もストレスなのだ。たとえば、冷たい扱いをされたら、それは人種差別主義によるものではないか?と疑いがよぎる。自信が喪失し、負のスパイラルに入ってしまいかねない。その疑いを払拭し、自分には幸運が待っていると意識を集中する。そうすることで、差別主義者か?と思われた人物とも信頼関係を築けた経験を持つ女性もいる。そのようなエピソードの一つ一つに「立派だ」と思う。が、人種差別の克服が、被差別者の気持ちの持ちよう、ということにならないか、そういうことではないのだが、とつい思ってしまう私は、素直ではないのだろうか。
超えられない壁に「耐えたまで」?
彼女たちは男性の数学者や技師よりも待遇の悪い「準専門職」であり、研究所の収益増加にも「貢献」した。後述するように、「国家的プロジェクトへ君たちも貢献しているっ」と強調されても、平等には扱われなかった。能力があっても、女性たちは賃金の低い計算手扱いで、男性技師より下の扱いであった。中には、粘り強い交渉で、男性たちだけが参加していた会議に直接参加するようになったり、論文を発表できたりした輝かしいパイオニアの女性もいるにはいる。しかし…何かに感じる違和感と同じものを抱く。あれだ。多くの女性が非正規雇用として不安定で低待遇を余儀なくされ、超人的なごく少数が「女性の活躍」例としてメディアの脚光を浴びるときの苦々しさのような…。
主要な登場人物の1人ドロシー・ヴォーンはリタイアした後賃金差別をめぐる集団訴訟を持ちかけられた際に「払うと言っただけの額はきちんと払ってくれました」とだけ答え、原告に加わらなかった。ドロシーが問題意識がなかったわけではないだろう。彼女は、計算手がコンピューターに取って代わられる前の7年間、チームリーダーであったが、その後その肩書きを外された。リタイア直前に何らかの栄転をしたが、それは不本意だったようで、娘にもその地位を話さなかった。しかし、失望自体胸にしまった。
ドロシーが、ある歴史研究者に、「変えられることは変えました。変えられないことには、耐えたまでです」と1992年に語ったことは示唆的である。理不尽なことにも耐え、自分の胸にしまい、決して権利を主張しない。そのような行動が、節度ある女性の「分をわきまえた」態度が素晴らしい…と思うよう誘導されているような気がする。
山崎直子さんの推薦文とは異なり、いくつかの壁は超えても、超えられない壁には耐えるスルー力の悲哀を感じる。当時を生きた女性たちに、耐えてどうする、闘えば良かったのに!ということは酷だろう。でも、2016年に原著を著したときには、まだまだ闘っていいのだという一言がほしいところである。
コンピューター誕生前夜、複雑な計算を担った女性たちは、開発競争という名の戦争の勝利に貢献していた。彼女たちの愛国心、国への貢献ぶりを、本著は称える。しかし、私は、彼女たちが「日本への最後の爆撃の一翼を担った」といった高揚したフレーズに、いちいち立ち止まる。彼女たちが懸命に開発に協力した爆撃機で殺害された人々を想起せざるを得ないからだ。
第二次世界大戦が終わってからも、アメリカはソ連と宇宙軍事競争を繰り広げた。優秀な黒人女性たちは、計算がコンピューターに取って代われるようになっても、そのコンピューターを駆使し、国家的プロジェクトに貢献する。
差別に自暴自棄になることもなく、母親としてもずば抜けた労働力としても国家に貢献した女性たち。本人は主体的にコミットしているつもりだが、安く活用できる都合のいい労働力であった面があり、宇宙軍需競争での勝利という国家的目標の道具、客体とされてもいたのではないか。
リケジョの頑張りにときに涙がこぼれる。スーパーウーマンであるリケジョたちが、たくさんの黒人女性たちに希望を与え、若い黒人女性たちが理系の研究者やNASAを志望することになったことは間違いない。
しかししつこいようだが、これがドリームかと言われれば、そうではないと即答したい。翻って日本では「女性の活躍」が喧伝される中、機会を与えられたごく少数の能力のあるスーパーウーマンが取り上げられる。これもまた、少女たちに希望を与えるだろう。しかし、社会構造を捨象して、本人の並外れた努力や心構えでなんとかなる、というサクセス・ストーリーは、危険ではないだろうか。ことに、国家主義的色彩この上ない宇宙軍需競争のただ中ということが、彼女たちの誇りもあった。そのことを直視すれば、壁を超えてもその先がユートピアとは限らない、更なる陥穽もありうると構えていなければならない、とつくづく思う。
頑張った女性たちをリスペクトしたい。しかし、注意深くもありたい。