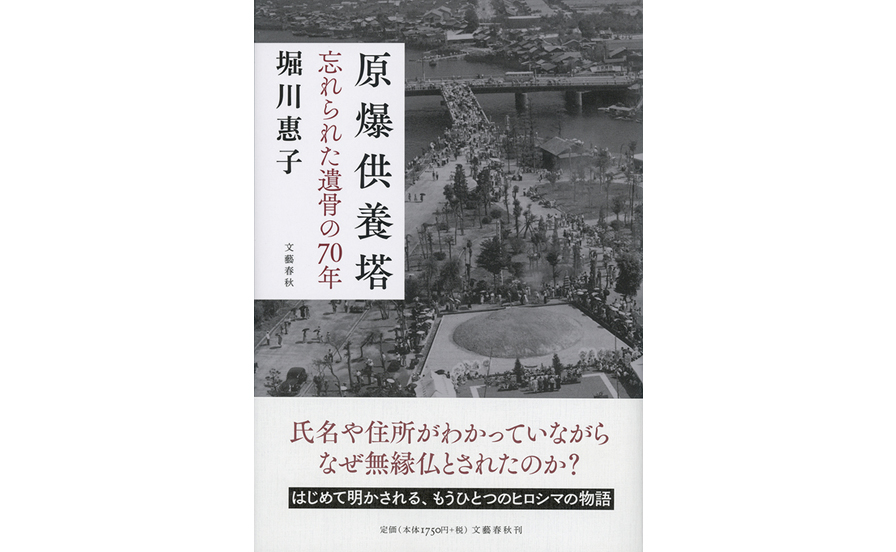昨年9月の民進党代表選挙はいったいなんだったのだろう。前原誠司が「ALL for ALL」をスローガンに枝野幸男を抑えて代表になった。今でもネット上で、「ALL for ALL」の文言の下に「危機的状況の中、党再建の先頭に立ち、政権交代可能な政治をつくる」といった前原氏の政権をまとめたパネルが読める。その後の展開を思うと、もの悲しさが募る。
さて、代表選挙の際に前原誠司のアドバイザーとなっていたのが、井出英作慶應義塾大学教授である(現時点でどうかは知らない)。当時、読んでみようと思って手に入れた、井出英策教授らによる『分断社会を終わらせる 「だれもが受益者」という財政戦略』(筑摩書房、2016年)を購入したものの、積ん読となってしまった。「前原氏って…」と首を傾げているうちに、いつまでも読むタイミングが到来しないと思い、手に取り一気に読んでみた。
読んでみれば、非常に興味深い。(しつこいが)「あの代表選挙ってなんだったの…」と色眼鏡をかけずに読んでみる価値はある。
「三つの罠」
「この社会を覆い尽くしている漠然とした重苦しさはいったいどこから来るのかー。この本は、財政を切り口として、その解決策を打ち出すことをめざして書かれている。」(10頁)
本著は、日本社会が他者に冷淡な分断社会となっている現状を示す。
日本社会は「三つの罠」に陥っている。ひとつ目は「再分配の罠」。弱者を救済しようとする人間の温かい心が、かえってその他の人たちの反対を招き、格差を生み出す原動力となりうる。日本では、この再分配の罠にむしばまれている。パイが減少する中で、低所得者層への限定等の選別性は、ねたみや嫉妬の原因となる。受益のないところに共感はないというリアルな現実が突きつけられている。
二つ目の罠は、「自己責任の罠」。成長に依存し、社会保障や教育は個人と市場に委ねる、「勤労国家レジーム」では、みんなで税を払ってみんなの生活を豊かにするのではなく、「自助努力」をつうじて自分と家族の生活を豊かにするものとされた。それは、支出の削減を正当化した。財政が厳しくなる中、更なる自己責任化が求められ、人々は弱者に厳しくなった。自己責任社会で成長が難しくなり政府の役割が大きくなるときに、成長への依存が強まり、政府への不信感も強まるという負の循環が止まらない。これが「自己責任の罠」であると本著はいう。
三つ目の罠は、「必要ギャップの罠」。現役世代向けの支出は、高齢者の多くが必要としない。これが世代間対立を強める。「勤労者」の「自助努力」、「夫が働き」、「専業主婦が高齢者を支える」という保守的イメージが、現実の社会状況と一致しなくなった。誰をどのように守るべきかという前提自体が、世代間で齟齬がある。そのために生み出される「必要ギャップの罠」。
このような罠にはまった日本は、分断され、冷淡で不機嫌な社会となった。その現状が第2章ではこれでもかこれでもかと明らかにされる。諸外国に比べて日本はもっとも高齢者への政策に対する支持が低い。失業者への対策にも不寛容。このような状況で、「救済に値する人」を探し出し再分配をしようと声高に言っても、支持は集められない。むしろ「本当に救済に値する人」を正しく判定することは不可能であり、弱者切り捨てをかえって正当化しかねない。
労働市場における正規と非正規雇用の分断。雇用の分断は、性別間の分断とも関わる。女性は「男性(父・夫)に支えられるもの」という社会規範は、男女ともに自己責任論を突きつける。雇用の非正規化により所得が減少した男性は、「女性を養う経済力がない」として、晩婚化・非婚化、少子化の原因にされてしまう。女性も結婚・出産・非婚・労働いずれも「自己責任」とされる。自助も共助も困難な現実を無視して、さまざまなリスクを家族に、ことに女性に押しつける政治は間違っている、というくだりは膝を打つ。性別間の分断は、男女とも苦しめ、社会の生きづらさを増幅させている。
悲観的な私たちが変わるべきなのか
このような分断をむしろ最大の推進力として財政再建論が進められてきたが、本著は第2章でそれがいかに誇張され、矛盾に満ち、社会を分断へ導くものだったかを明らかにする。
「数字の魔術」によって財政破綻への恐怖をかきたてられ、政府支出の削減に同意するよう余儀なくされてきた点が、数字に弱い私には目から鱗であった。数字という根拠が示されれば、何か客観的な印象を受けてしまう(文系の弱み)。しかし、報道機関が財務省という権力が示す数字をちりばめながら、権力と一体化して、その意向に沿った主張を展開している例を読んで、「「御用機関」とは、原発関連だけではない」と顎が外れる。財務省が「財政再建」に関する発表を増やせば、記者クラブ制度を通じて、新聞にはこれに関する記事が増え、私たちの脳裏に「財政再建が至上命令である」とすり込まれていく。分断され、対立をあおられ、「不公平」を是正するというスローガンのもと、政府支出を削減することが必要だ、と私たちは認識してしまう。
どんよりとしたところで、第3章「不幸の連鎖からの脱却」、第4章「来るべき時代の胎動」というように、オルタナティブな社会への処方箋が示される。
人間の生活を支えるための適切な制度や政策を実現できれば、私たちは安心して暮らせるようになり、結果的に格差は是正され、経済も成長する。
市場原理に対抗する理念として、必要原理。必要原理に支えられた財政では、教育に財源を投入する。アメリカの研究では、就学前教育を行うことで、所得や労働生産性の上昇、生活保護の削減効果などがうまれ、投資収益も上昇したという。財政へのメリットも大きい。高校卒業率が高まり、犯罪発生率が下がり、将来の所得は増える。そのため、政府の支出は増え、税収が増えることが期待される。
この国の「成長=救済型モデル」を「必要=共存型モデル」へ転換し、「救済型再分配」を「共存型再分配」に置き換えていく必要がある、と本著は説く。
改革は、政治不信があっては実現できない。民主主義に対する支持がなければ、租税抵抗は緩和されない。改革に向けた決断を私たちはできるのか。という本著の問いかけに、まだ明るくなれない。悲観的な私たちがいけないのか。悲観的にならざるを得ない社会と悲観的な私たちのどっちが変わるべきか、にわとりとタマゴ。
本著は読者を悲観的なままで終わらせないよう、むしろ減税に反対した世論(サービス低下への反発から)におされて増税に転じたスウェーデンなど他国の例や、過疎地その他の地域での様々な活動例を紹介してくれる。
「家族の解体・個人化」…?
誰もが納税者となり誰もが受益者となるオルタナティブな社会はあるはずだ…と読み進めた第4章で立ち止まる。幼児や高齢者、誰もが人間らしく生きていくための基盤となる家族。近代家族が破綻した今、家族の原理を地域にも拡張していき、誰もが支え合う地域モデルを考えることが必要だ、と本著は指摘する。
近代家族のように女性に一方にケア責任を課すのではなく、男性も女性も、誰もが、とはあるのだが、近代家族という私的空間で女性にのみ責任を課され、一つ下にみられてときには暴力もふるわれ、家族内で隠蔽されてきた歴史的経過を思えば、何か破綻した「近代家族」への郷愁を感じるような記述に立ち止まる。
終章でも、駆け足で「家族の解体・個人化」「血縁関係からの離脱」が、価値観の共有を難しくした先進国の危機的状況としてあげられていることにびくっとする。家族の多様化や個人個人が尊重されることを押しとどめようとする保守的な言説と似通っていくようで心配になってしまうのだ。
「婦人会」等の壊滅的な衰退などが問題視されていることも、戦前、総力戦体制を支えた婦人会のありようの本を読んだばかりの私はうろたえる。そのすぐあとで、愛国心などの理念を共有することではなく、共同体の中で「生存と生活の基礎的ニーズ」、公正な分配の理念の共有こそ、臨まれるともある。また、家族国家主義的に編成された国民たちが数々の強制のもと、生命の犠牲を伴う筆舌に尽くしがたい苦しみを味わった歴史を踏まえて、個人と自由を大切にする国を目指してきた、ともある。ならば、危機的状況として「個人化」なる言葉を使うのはどうなのだろう。個人化と個人主義は違う、ということなのだろうが、混乱する。
コンパクトなこの本の駆け足の記述の行間を読み取るべきなのだろう。だが、終章にはまだ戸惑っている。
消化できないところはあるものの、目から鱗の現状分析、御用言説に惑わされないで、だれもが受益者として分断を乗り越える社会への提案として、「あの代表選…」と揶揄することなく真摯に読むべき本である。