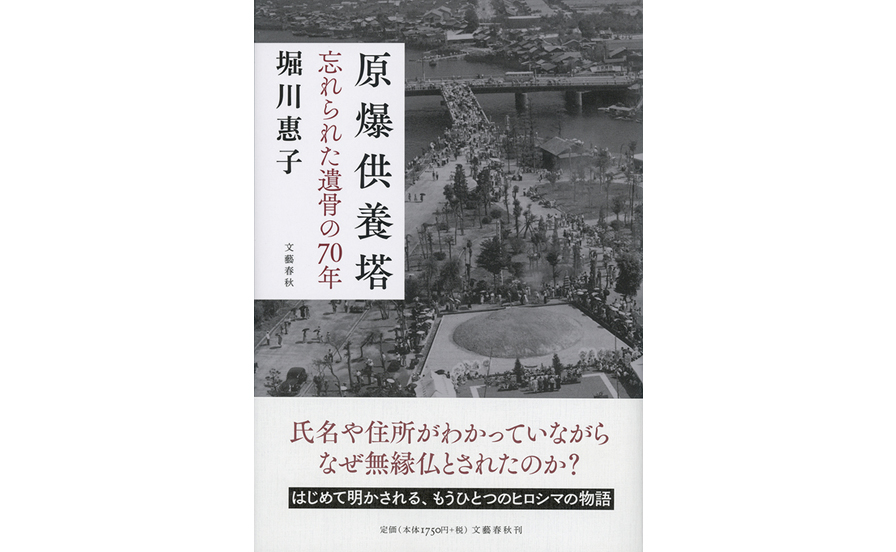自己責任ととらえることの弊害
前回、子どもの貧困が政策課題として意識されるようになっても、その解決策として家族主義を強化することはかえって貧困の連鎖について社会の責任を不問にし、逆効果であることを明らかにする諸論文を収めた松本伊智朗編著『「子どもの貧困」を問いなおす 家族・ジェンダーの視点から』法律文化社を取り上げた。
家族・ジェンダーの視点から問い直すべき子どもの貧困として、経済的貧困だけではなく、関係性の貧困にも着目しなければならない。必ずしも経済的に貧困層ではないが関係性の貧困にある家族の中で、弱者である子どもが虐待され死に追いやられることもあるのだから。
杉山春『児童虐待から考える 社会は家族に何を強いてきたか』(朝日新書)を読み進めると、多様なハンディキャップを追った人の困難を自己責任ととらえ、家族規範の押し付けることが、孤立している人々をますます支援から遠ざけてしまい、そのため、子どもを救済するどころか、一層追い詰めてしまいかねないことがわかる。
厚木事件…「残酷な父親」と非難すればいいのか
2014年厚木市内のアパートで白骨化した子どもの遺体が発見された事件を記憶している人も少なくないだろう。生きていれば中学1年生の優紀くん(仮名)の母は優紀くんが3歳のときに家を出て行き、以後父である健一(仮名)は、実家や勤務先にも一人で子育てをしていると伝えず、ガス、電気、水道が止まった部屋で、雨戸を閉め切り、ガムテープでふすま等を止め、優紀くんを閉じ込めていた。
発覚するまでの7年以上、月額6万円の家賃も払い続けた(総額500万円以上)。発覚後、衰えていく優紀くんの状況を「リアル」に伝えるかのような(実際は警察発表をもとにしたもので、リアルとはいえない)センセーショナルな新聞記事を読むのも辛く、優紀くんの絶望と悲しみに思いを馳せ、健一について「なんと残酷な父親か」と憤った。
しかし、本著第1章で、著者の取材と分析を通して健一を見つめていくと、「残酷な父親」との憤りはあまりに皮相的だったと愕然とさせられる。
著者の観察は細かい。法廷に現れた健一は、被告席に足を投げ出すような座り方をして、「幼いようにも、横柄なようにも見えた」。証言は二転三転した。記憶にないと語る場面も多く、検察官から「信じられない」「非常識だ」と責められる。自分に有利な証言も変えてしまう。優紀くんの死を発見したときのパニック、その前の自身の行動も優紀くんの様子もあいまいで、かつ変遷する。それは「無責任」として一層の「悪質さ」を法廷で印象づけることとなった。
健一は、幼いころから高校時代までの記憶も抜け落ちている、精神疾患を発症した母は入退院を繰り返し、端から見れば奇異な行動により全身やけどを負うこともあった。記憶が曖昧な理由について、母親の行動が嫌で何でも忘れるようにしてきたからだと述べたが、その点情状として考慮されなかった。そして、健一は精神鑑定によると「正常下位と軽度精神遅滞との境界域の知能」であったが、この点も情状の理由にはならなかった。
科学的根拠より感情に訴えられた判断
検察側証人の医師は「死亡の1ヶ月前から拘縮が始まった」として「やせ衰えた優紀くん」というイメージを描いた。遺体を解剖した医師は弁護人側証人として、死因は不詳とし、骨の中から「拘縮」があったと言うのは言い過ぎだと述べた。
しかし、一審の裁判員裁判を通じて「残酷な父親」というイメージは覆らず、判決では殺人罪の成立を認めた上、懲役19年に処すとした。控訴審では弁護人側が提出した医師の意見書をもとに保護責任者遺棄致死罪を適用して、懲役12年を言い渡した。一審では「拘縮」があったから飢餓があったとした上、優紀くんには「拘縮」がみられることを前提としたが、「拘縮」が翻ったのである(そもそも「拘縮」と飢餓とは結びつかないのだが)。
裁判員裁判については、反対する見解も多々あるが、職業裁判官による裁判に比べて無罪推定といった原則を真摯に受け止めてもらえ、また捜査官の手が入りやすい供述調書よりも公判での証言をもとに客観的証拠と照らし合わせて判断するという本来あるべき公判中心主義に立ち返りうるものなどと、評価すべき面がある。
しかし、本件の場合には、要因を重視しないまま供述態度を問題視したり、あるいは、感情に訴えられ、科学的に依拠する姿勢が欠けるなど、裁判員裁判のマイナス面が目立つ(職業裁判官であればこのようなことはない、ともいえないが)。
軽度の精神的遅滞があっても、社会生活を送ることは支障がなく、実際仕事に従事していた。高校卒業後専門学校を中退したが、仕事をはじめ、勤務態度は良好であった。情状証人である父親は、法廷で、子どもとほとんど関わったことがないと言いながら、息子は頭脳明晰だったと答えた。そのように答えることが健一に不利になること、ありのまま理解してもらうことが重要であることが、わかっていないのだ。健一へ専門学校その他多額の経済的援助を与えた父親だが(優紀君が放置されたアパートの大家への多額の保証金も支払った)、困難な状況を認識する能力に欠けていたのだろう。その能力に欠けた父親も、病気の母親を妻として必死だったかもしれないが、子どもの育ちに必要なものを与えることができなかった。
孤立した親は社会の支援を得ることもできない
健一は結婚し、厚木市内のアパートに住む。そして優紀くんが生まれた。3歳だった優紀くんが一人で早朝4時半に裸足で震えながら歩いているときに通行人に通報されたことがある。児童相談所が、引き取りに来た母が反省していること等を理由に、「虐待」ではなく「迷子」として処理したことが、惜しまれてならない。「虐待」としてその後優紀くんの安否を確認しようとしていたら、命を救うことはできたはずなのだから。母は引き取った後その日のうちに健一に優紀くんを引き渡し、買い物に行くと出かけてそのまま戻らなかった。
その後健一は周囲に助けを求めず「仕事と子育ての両立」の困難を抱え、2年後に優紀くんが亡くなる。健一にとっては、閉じ込めることを虐待と思っておらず、それが唯一の誰にも頼らず問題を解決できる現実的な方法だったのだ。控訴審の判決文には、「一人で養育することに困難があったのであれば、公の援助を求めるなど取りうる手段は多く存在していた」等と述べ量刑の事情とした。
しかし、知的な力がボーダーライン上にある親たちが、支援を求められずに孤立し、結果的に子どもを虐待してしまう例は、虐待の現場では珍しくない。私自身、児童相談所の嘱託弁護士を長くしていて現場を垣間見ているというのに、この事件を知ったとき「残酷な親」との非難の大合唱に加わるだけだったことを反省する。
現実に向き合うこともできず、家族を維持できなくなったという「マイナス」を直視することもできない。また性別役割意識が強く、その役割を果たさなかった妻への怒りは強かった。その妻への意地からケアを続けてしまった。また仕事が第一でケアは二の次という強い価値観もあったのではないか。「健一は、見えにくい困難を何重にも背負いつつ、仕事も子育ても家庭でなすべきという家族規範を守ろうとする中で、追い詰められていったのではないか」。
そして、「ほとんど自己主張のない、声が小さく、語彙の乏しい5歳児」の優紀くんが亡くなった。多様なハンディキャップを負った人たちの困難を、個人の責任のみに帰した判決文に、著者とともに疑問を感じる。ハンディキャップがありながら個人の責任として背負い込んだからこそ、孤立し、状況が悪化したというのに。
国家の幻想で犠牲になった女性たちの性
第3章の「国家と家族のあいだで―「満州女塾」再考」には、現代の児童虐待のルポの本と思っていた読者として驚いた。しかし、副題の「社会は家族に何を強いていたのか」こそテーマであると読み直せば、この過去の事実を忘れられるべきではないと書き留める労力は貴重であるとわかる。虐待等をルポライターとして取り上げ、国家と家族と自分の関係を理解しようとしてきた著者の最初の著書は、1996年刊行の『満州 女塾』(新潮社)であった。
日中戦争が始まり、満蒙開拓青少年義勇軍として送られた少年たちの妻を養成するために、「満州 女塾」が作られた。結婚させられることを知らず、社会の役に立ちたいと志願し、志願先で結婚を強いられた。インタビューした20人ほどの女性たちは誰もが敗戦時悲惨な体験をしていた。そもそも、「女子拓殖事業」のハンドブックには「目的」として「民族資源の量的確保と共に大和民族の純血を保持すること」などという文句が並ぶ。「一滴の混血も許されないのである。女性は深くこの点に思いを致し、自ら進んで血液防衛部隊とならなければならない」。
女性の性を「大和民族」の「純血」という国家的幻想に奉仕させようという意図を堂々と明らかにしている。そして、開拓農家の主婦となれば、労働を補助し、ケアを担当するという性別役割を課された。
そのよう女性一人ひとりの尊厳を無視した政策の果てに、戦局が悪化するや女性たちは棄てられた。聴き取りを行った女性たちのほとんど全員が性被害にあっていた。そして、子どもの命が危険にさらされる。
孤立しがちなニューカマーの子どもたちの受け入れを
第4章で取り上げた川崎中1殺害事件及び川崎区のニューカマーフィリピン人女性とその子どもたちの状況から、日本で育ち一見日常会話に困らないように見える子どもでも、言語の発達は配慮が必要であると著者は指摘する。
怒りが爆発したとき、それを言語化できないことの苦しみは壮絶だろう。社会の中に居場所がないことの怒りを、一人の少年に向けてしまったのではないか。外国につらなる子どもたちの未来をも見すえた施策が必要である。
家庭教育支援法案では解決しない
終章では、虐待対策として必要な施策を検討した上で、家族規範を強める動きもあるとして、家庭教育支援法案も取り上げる。私も24条変えさせないキャンペーンの呼びかけ人として、法案には大いに疑問があるところである。著者が指摘するように、自分が行政から一方的に不適切な親であると判断されることへの恐れが広がるとともに、家族の中に公的な力が入ってくることに不安がある。必要な支援は家族規範を強化することではない。
新書ながら、重厚な一冊である。是非、必要な支援とは何かを考えるために、ご一読いただきたい。
院内集会のご案内
24条変えさせないキャンペーンでは、1月29日、著者の杉山春さんらをお招きして、「家庭教育支援法案の何が問題か?」と題する院内集会を開催する。是非多くの方にご参加いただきたい。
日 時| 1月29日(月)15時~16時半(通行証は14時40分からお渡しします)
場 所|衆議院第2議員会館第1会議室(定員60人)(地下鉄永田町駅・国会議事堂前駅)
進 行|発言 24条キャンペーン|家庭教育支援法案の問題点について 角田由紀子さん| 24条と対立する家庭教育支援法案-24条の意義を再確認する 清末愛砂さん|日本国憲法と家庭教育支援法案-自由権と社会権を取り違えないために 杉山春さん|家庭教育支援法案によって虐待やネグレクト、引きこもりは防げるのか-厚木男児遺棄放置事件から