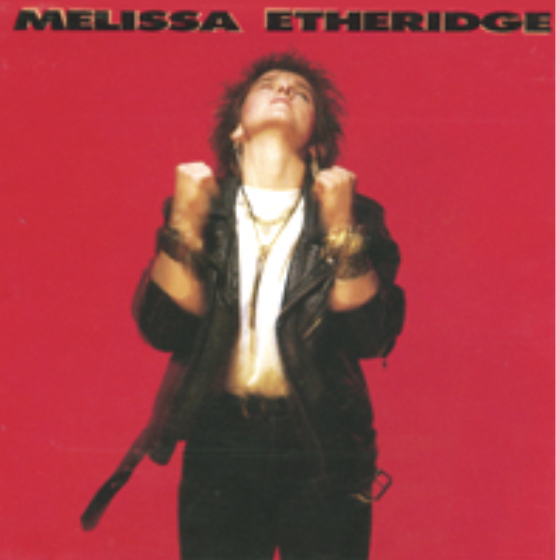人生は夢の旅、ある女子プロレスラーの座右の銘。日々あわただしく過ごす中で見慣れた風景をながめながらゆったりと呼吸をするときいつもこの言葉が浮かぶ。魂の宿る芸はそこに居合わせる者たちの日々の生活の中に溶け込み、ひとときの夢を育み、明日からの生きるエネルギーとなる。音の記憶、音魂の気配が漂う空間で立ち上がる音、奏でられる音に触れたとき、私の身体は震える。
イスタンブールのホテルにて起きぬけに聞こえてきたアザーン(ムスリムが1日に5回行う礼拝(サラート)時間に全てのモスクからの発せられる呼び掛け)ではじめて触れたオリエンタル。私のからだは震えた。
かつて参加したリズムエヴォゲーションというワークショップ。アフリカの太鼓を叩きながら、十数人の参加者が自分自身にとって自然な声で「あーー」と発声し続ける。いつしか様々な音程の「あーー」が時間をかけて溶けあいポリフォニーとなる。その瞬間に体験した音の魂の震え。
仲野麻紀さんの著書「旅する音楽 サックス奏者と音の記憶」を読んで私自身が体験した音の震えが甦った。パリを拠点に世界中サックスを携えて演奏の旅を続ける仲野麻紀さんの音楽を探す旅。ブルキナファソ、レバノン、磯部、ブルターニュ、モロッコ、五知、エジプト、福島、安乗、それら各地で奏でられる音楽は、小さな村で代々楽士として音楽を奏でてきた演奏家が祭事として行う演奏、儀式として奏で継がれている音楽であったりする。資本主義からなる音楽産業とは全く無縁の、純粋に演奏することを生業とする音楽家たち。仲野さんもそんな演奏家の一人なのだろう。
アフリカ、アラブの民俗楽器がもつ音の揺らぎと仲野さんが奏でる西洋の楽器サックスが試行錯誤を繰り返しながら調和していく過程がスリリングだ。この調和の源となるのが演奏者同志における信頼。
〈彼らと共に演奏し、彼らの生活の一部である音空間に居合わせる。その時、「表現」は必要ない。むしろ「表現」という言葉のもっと向こう側にある根源的な人類の切望envieを意識した時、はじめて音世界との関係の中に居ることができるのだ。〉(「旅する音楽」仲野麻紀 せりか書房)
1959年ベイルートで西洋ピアノでアラブ音階の4半音を弾くことに生涯を捧げたアブダッラー・カマンジャ。カマンジャが発明した「オリエンタルピアノ」はシンセサイザーの出現により輝かしいものではなくなってしまったが、カマンジャが固執したアラブの音と西洋の音の融合、そして調和への道を、1981年ベイルート生まれのゼイナ・アビラジェットがコミック「オリエンタルピアノ」(河出書房新社)で描き伝える。ゼイナ・アビラジェット自身が、15年にも及ぶレバノンの内戦でフランスに渡り、アラビア語とフランス語、レバノンとフランスという2つの言語、2つの国の間で自己を形成していく過程が、カマンジャの姿と折り重なって描かれる。
「オリエンタルピアノ」と題したゼイナ・アビラジェットさんのライブペインテイングと仲野麻紀さんのサックス、そしてステファン・ツァピスさんのピアノ、ヤン・ピタールさんのウードが奏でるパフォーマンスを10月末の冬の訪れを待つ神楽坂の赤城神社で聴いた。ゼイナが舞台中央でカッティングしていく切り絵、異国へ旅立つスーツケース、その中に込められた語りえぬ想いを、カマンジャがそうしたようにフェルト生地のトルコ帽子をかぶって奏でるステファンのピアノと仲野さんのサックスが描き出す。
第2部のセッションではフェイルーズの「シャラビーの娘」が演奏された。フェイルーズは1935年レバノンの小さな村で生まれたレバノン人。アラブ世界では知らぬ人はいないほどの有名な女性歌手だ。仲野麻紀さんの「シャラビーの娘」を聴きながら世界はつながっている、小さな世界で魂の宿る音を探して旅する人たちは、時も国も超えてつながっていると確信した。
仲野麻紀さんとヤン・ピタールさんが結成したユニットKyの最新アルバムは「DESPOIR AGREABLE」。タイトル曲の作者でもあるエリック・サティ、フェイルーズなどのナンバーに、サックスとウードが絡み合う。静かな夜、じっくりとこのアルバムに耳を傾けていると、家の前を流れる神田川の水流の音が、道路を走る車の音が、時と場所を超えた空間の中に共に存在し立ち上がる。
〈心地よい絶望Desespoir Agreable。この現実の前で、わたしたちは生きるしかありません。〉(同掲出)