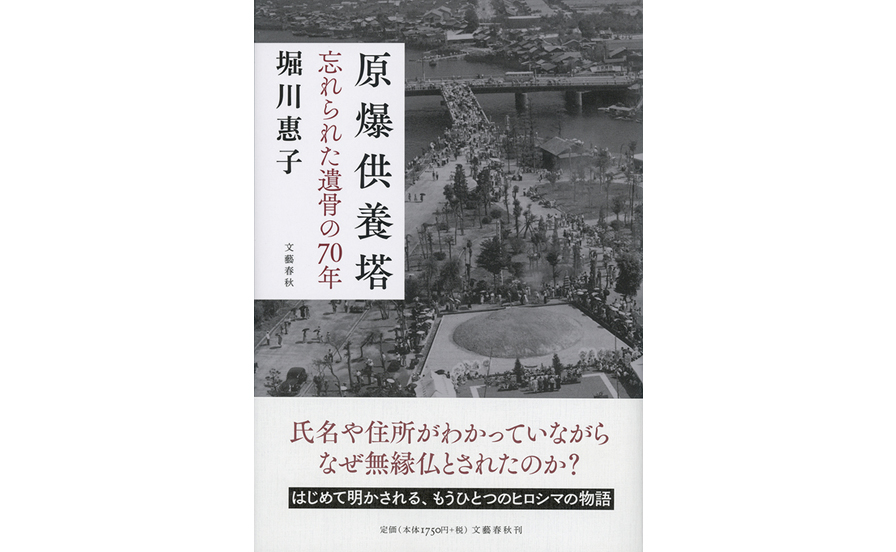小さいころ繰り返し読んだ本中でも、ローラ・インガルスの『大きな森の小さな家』から始まる一連の『大草原』シリーズはダントツだ。なぜあれほど惹かれたのだろう。『大きな森の小さな家』はいきなり豚を屠殺し、解体するシーンから始まる。
大人たちが大勢で、肉をいぶし保存食を作っていく傍ら、子どもたちは豚のしっぽをあぶってかじったり、膀胱をふくらませて風船として遊んだりする。大人になった今は、児童書にしては、相当、強烈なシーンではないかとも思うが、わくわくしながら読んだ。ベークド・ビーンズ、ウサギの丸焼き、マッシュドポテトとグレイヴィ、ひきわりとうもろこしのパンや、パンプキンパイ、ホットビスケット、バター作り、かえでの木から少しずつ採取するメイプルシロップ…。それが何か食べたこともないのに、「おいしかったあのころの食」を懐かしむかのように読み込んだように思う。
しかし、子どものころはうっとりしながら読んだ『大草原』シリーズだが、多忙な中年になってからふと手に取ったらそうは楽しめないことがわかり驚いた。むしろ、お父さんとお母さんが州境を超えて移住していくのは、始終働いき続けても貧しく暮らしていけなかったからだと察し、生活の苛酷さが胸に迫ってくるのだ。わくわくした保存食作りも、豊かな実りがあるときに蓄えなければ飢えてしまいかねないことを予期しながらの必死な作業だと思えてくる。
土地を開墾し、耕し、でも不作になることもある。銃を手入れし、危険と隣り合わせの中獲物を探すも、獲れないときもある。お母さんは年がら年中洗濯、縫い物、掃除、保存食作り、調理をし続ける。そして、ふと登場する、インディアンたちの描写が子どもの視点とはいえ無頓着ではないかと、痛みを感じる。インガルス家など開拓者の生活(苛酷なものではあれ)が、インディアンの生活基盤を根こそぎ奪った上でのことだったとも知っているからだ。
郷愁を感じながらも
貧しくても、季節の移ろいを大切にしたあのころ…。
石牟礼道子の『食べごしらえおままごと』にも、経験はしていないのに、郷愁を感じる。石牟礼は、「お料理」というと「料理学校を出た優等生みたいで恥ずかしい」と、この書名にしたという。食道楽の本ではない。石牟礼の家は、雛人形まで差押され持って行かれたことがあるほど、貧しかった。それでも、季節ごとの食材に手をかけてご馳走をつくる。女たちが大勢で作り、大勢で食べる。
「貧乏、ということは、気位が高い人間のことだと思い込んでいたのは、父を見てったからだと私は思っている」と書く。「ようござりやすか。儂(わし)やあ、天領、天領天草の、ただの水吞み百姓の伜、位も肩書もなか、ただの水吞み百姓の伜で、白石亀太郎という男でござりやす」と、痩せた反り身になった父がにじりよると、「わかりました」と相手は両手をあげてしまったという。痛快だ。
父は包丁の研ぎ方も教えてくれ、鯖のぶえんずしの作り方を教えてくれた。「天草の男衆は料理がみんな上手ばい」と母が喜んでいたという。
とはいえ、石牟礼の思い出の中で始終食べごしらえを担当しているのは女たちだ。食にまつわる様々な情景が鮮やかだ。まだ若い石牟礼の母が三番目の男の子を産んだが5日目の晩に死んでしまい、気落ちし忌中であるがやることにしたお正月、女衆たちに微笑まれはやしかけられながら、幼い石牟礼がはじめてお米を研ぐ。ほめられてうれしくなり、キビナゴの尾引もやってみる。「ご馳走になろ、みんなで」目を細めてたべてひときれずつ食べる大人たち。愛おしい思い出だ。
昔の食材がなんと新鮮で豊かだったか。「山の精気を、根にも茎にも芽の先にもぎっしり詰めながら育った」独活など、「木の芽どき、春から初夏にかけて芽の出るもの」。新牛蒡になる前の茎を間引いて茹でて晒すと、「みずみずした芽を食べる儀式のような、つつましく新鮮な食膳」となり、「神さまと食をともにしていた時代の名残り」の気分を感じる。等々の描写に、これまたうっとりする。
そして、「この頃の鰯は違う。皮をとるのに、さりっと一気にはげるというぐあいにならない。鮮度のよさそうなのを選りに選って買っても、皮をはぎにかかるとたんに、べれべれ、べれべれと途中で幾度も破れてしまうのである。海の中はいったい、どうなってしまったのだろう」、「この頃青シソのことを大葉というようだが、ビニールにくるまれた貧弱な葉で、すしにはとても使えない」等と、今どき(といっても1994年に刊行され23年も前だが)の方が表面的には豊かになったようで衰えてきているのではないかと悟らされる記述もいくつもある。
「おいしいものには共通点がある。お皿の向こうに人間の顔が見えているのだ。(略)そういうものぜんたいが「今は失われた」というベールをかぶっている。みんなもうないのだ。(略)行事に応じて集まった人々は誰もいなくなってしまったし、素材も何か嘘くさいものに置き換わってしまった」と本著の文庫本の解説者池澤夏樹は嘆く。確かにそう書きたくなる面もあるが、石牟礼は「古き良きあのころ」と郷愁にひたるだけではないのだ。
石牟礼によれば、水仕事、と女たちがいうときの主な力仕事は、鉄の羽釜や鉄鍋のお尻を磨くことだった。亀の子タワシで洗うと墨が四方八方にはねて大変なことになる。必ず藁を縄にしてそれを掌の大きさにまとめたものが適している。腰に力を入れて全身でわっしわっしと磨きにかける。
すすが墨になって、きれいな流水に溶け去ってしまうと、鉄特有のカネ色が光を帯びてあらわれる。洗い上げたお釜の尻を指で撫ぜ、墨がつかないならば、井戸端の先輩たちも目を細め、上の方の段で孫のお守りをしている婆様たちから合格点をもらえる。世代を超えた女たちのネットワーク。しかし、石牟礼はそのことを単に懐かしむだけではない。石牟礼はこの水仕事で、若い頃爪を切らずともよかった。鍋のお尻とともに磨き切れてしまったからだ。あのようにまでせずともよかった、「読まねばならぬ本があったのに、女が本を読むなどもってのほかという空気に、やはりめげそうになっていた」と今爪を切るたびにもの悲しく思い出す、と書く。
「30幾年前」、鹿児島の農家で、「100歳をこえたお婆さん」が石牟礼に「あたいなんどの時代には、おなごちゅうもんは、もぐらよりか蟹よりか、哀れなもんごわしたど。後生にゆくまでも、骨病みをば持ってゆくとじゃろかいなあ」、女が難儀な農作業を続け、男衆たちは早く上がってしまい、囲炉裏端を囲んで女たちに肴をと「当たり前のように言いつけ」た、「おなごは息をつくひまも、ありません、冬のさなかでもまだ泥足のまんま、寒か土間におって、炊いて食わせて仕舞をして」、それでも終わらず朝の食事の用意をし、床に入ってからも子どもを外便所に連れて行き…。お婆さんは、「わが御亭ともなあ、本心語りおうこたなかった」と笑った。語ることができなかった無数の女たちの胸の底の思いに胸がつかれる。しかし、解説者である池澤には印象に残らなかったのだろうか。池澤が男性であることと無関係ではないように思えてならない。
「料理は母親の愛情の証」を超えて
大草原の小さな家シリーズや『食べごしらえおままごと』に描かれた女たちに比べて、今の女性はずいぶん楽なはずだが、しかし、料理を含む家事の負担が「大きい」と感じる女性たちは多い(私もだ)。
家庭料理の衰退を憂う声が多いとはいえ、「家族のために料理を」と努力しようとする女性たちがまだまだ少なくないのだ。阿古真理著『料理は女の義務ですか』(新潮新書、2017年)は、そのタイトルから、「私作る人、僕食べる人」(昔批判が殺到、今でいう炎上により放映中止になったCM)といった料理と食べることをめぐる性別役割分業の見直しがテーマか、と思いきや(確かにその点もテーマだが)、「スープの底力」の章はなんと人類が最初に火を使ったころにまで遡る等、古今東西の煮炊きの歴史をたどっていく。
「保存食は楽しい」の章はもう少し近い時代からといっても、古代ギリシャのソーセージからだ。石牟礼が『食べごしらえおままごと』で描いたような、日本の山村の四季にあわせた自給自足の生活での保存食のことも取り上げる。牧歌的に描くのではなく、台風や長雨、病虫害などさまざまな自然の脅威にさらされ、食糧不足の危険があったために大量の備蓄が必要だった厳しさも示す。
しかし、今や、梅干し、梅酒などの梅仕事や味噌など、保存食づくりは、「スローフード」ブームの中で見直され、趣味として見いだされている。阿古が指摘するように、大きな経済システムに取り込まれてはいるが、部分的にでも生産を取り戻すことで、誇りを再び取り戻せる。保存食作りにはまるのは、そのためかもしれない。
「常備菜の再生」の章は、戦後の食料大量生産体制の確立や住宅や家電の進化、農作業や商売に追われず家事育児に専念する主婦が増え(後減り)、料理メディアが発達したことなどの変化を追う。
その中で、「女性が結婚と同時に自らの姓を奪われる世界で唯一の戸籍制度が戦後残され、現在まで存続していることを考えると、女性が男性の家長に属する明治以来の家父長制の残滓があると思わざるを得ない」というフレーズが登場して、夫婦別姓訴訟弁護団の事務局長だった私は思わず涙した。そうなのだ。既に共働き世帯が専業主婦世帯を上回ってはいるが、女性の地位や所得が低いままなのは、与党が作った枠組みが残っているから。しかし、もうすでに時代は変化しており、性別に関わりなく暮らしも仕事も担うことへの理解を深める時期、と阿古が記すが全くその通り、と大きく頷く。
土井善晴の『一汁一菜でよいという提案』(グラフィック社、2016年)は、阿古がいう、社会進出したが「家族のために」と料理を作り疲れている女性たちには、ぐっとくるタイトルである。楽することが手抜きではなく、理論的に正しいのだっとお墨付きを与えてくれるのだろう…。と自分を都合良く励ましてくれる本と誤解した私のような女性が多数いそうだ。
私の持っている本著は、2017年7月25日に初犯第18刷発行であるのだ。しかし、そんなに甘い話はない。そもそも、一汁一菜のレシピがずらりと並んでいる本と誤解していた…。
「暮らしにおいて大切なことは、自分自身の心の置き場」といった、精神論の本であるとは知らなかった。「日本人は昔と変わらず、自然に対する感性を持ち続けているように思います」といった文章が繰り返し登場するが、実証主義的でない日本礼賛と感じてしまうのは、私が敏感すぎるのか。その点は措くとしても、「母親が台所で料理をする気配を(子どもは)感じているのです。まさに料理は愛情です。」阿古は、この点、土井に批判的だ。「家族が愛情に溢れた関係だと決めつけられると、「当たり前」でない自分を発見し、傷ついてしまう人がいる。」と。愛情をかけられずに成長した場合、「人生の基礎が間違った自分」として自己評価が低くなりかねない。逆に、料理ができたら、人生が変わりうる(アメリカの本だが、『ダメな女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』が読みたい)。
また、食を家庭に囲い込むことはない、という発想の転換もある。料理の「シェア」。格差社会を背景に貧困が深刻になっているからとはいえ、子ども食堂その他の「シェア」というあり方もそこかしこに見られる。
選択的夫婦別姓や憲法24条のことばかり考えていないで、時には別の話題を…と思ったのだが、どうも家族における「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」(24条2項)はまだだと首をふるような読書経験となった。かつてと現在の女性たちの経験を掘り起こすことは、結局憲法24条に結びついていく、ということなのだろう。