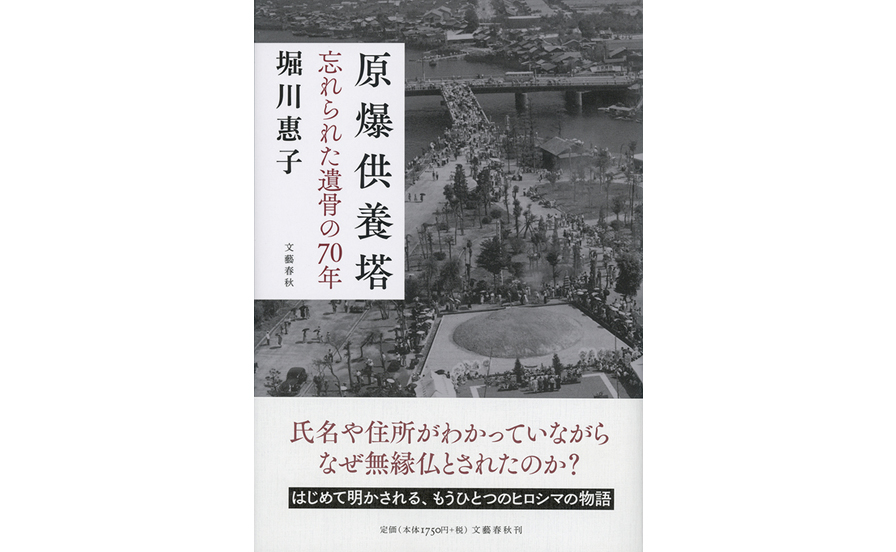忘れられない一言
「僕自身は、部落や在日を差別しない。だけど、僕が部落や在日の人と結婚したら、親が悲しむ。だから、結婚はできないな。」
記憶力が衰えた私は何十年も前の学部生のときの記憶があまりない。しかし、飲み会で隣になった男子大学生がこの言葉を口にしたときの、ぞっとして体が冷えたような感覚を覚えている。私は差別主義者を初めて見た、とまじまじと彼を見た。普通の、さわやかなイケメン。差別主義というものが、ナチスの親衛隊の制服やKKK(クー・クラックス・クラン、白人至上主義の秘密結社)の三角の白いロープを身にまとった,見るからに禍々しい様相の人々だけではなく、ごく普通の人々の中にも巣くっている、ということを悟った瞬間だ。さらりと言い放った彼に、「あなた自身が差別してるよ」となんとか言った。彼の親が本当に差別する人たちなのかどうかわからない。でも、親が差別するだろうと予想し、それを困ったことではなく、尊重すべきことと考えている彼が、自分は差別していない、というのは違う、それなのにそう言い切ることに義憤を覚えた。しかし、彼は「いいや僕は差別しない」と全く響かなかった。彼はきっと何十年も考えを変えていない。あのとき、どう言えば良かったか。そう時々思い返していた。
その記憶が重い私は、齋藤直子著『結婚差別の社会学』(勁草書房、2017年) をタイトル買いし、一気に読んだ。
本著は、部落出身者への結婚差別を扱った学術研究書である。部落出身でない者が部落差別にリアルに向き合うのが結婚。何十年も前の男子大学生のように、「差別するかしないか」という抽象的な問いには「しない」と言いながら、いざ結婚となるとその人を迎え入れたくない、と差別する、ということがありうる。結婚は当事者の合意のみによって成立するのだが(憲法24条1項)、親の承諾を受けたい、承諾が得られなければ結婚に踏み切れない、というカップルは少なくない。結婚したい相手を紹介したら、親から相手の「身元」を問題視され、反対される場合がある。本著は、「部落出身者」であることを問題視された場合に、当事者や親との間で、どのような対立や交渉や和解、あるいは決裂が生じるかを、何組もの当事者や支援者から聴き取り、考察している。
「寝た子を起こすな」論の誤り
第1章「部落問題とは何か」は、部落問題についての基本的な知識と現状をまとめる。「部落出身者」とは何か。一応、系譜的連続性と地域的要素、職業の3つの要素が重なっているが、その要素のいずれもが揃っていなくても、あるいはいずれの要素がなくても、部落差別を受ける場合がある。そして、「人々が間違われそうなこと」を避けようとすることで(部落に住まない、部落出身者と友人にならない、結婚しない、食肉産業を避ける、等)、部落を排除し、差別の構造を維持することになる。なぜ差別・忌避しているか、示されない言説もある。みんなが避けているから避ける、という差別。ネット上の身元暴き、戸籍謄本等不正取引事件(2011年発覚。不正請求された一万件に及ぶ戸籍謄本等から得られた情報等が身元調査等に利用された)、連続・大量ハガキ差別事件(日本全国に400枚以上の差別的な内容(「えたに人権はない」「殺しても罪にならない」等)の葉書や手紙が送られたりした。2003年に東京食肉市場に葉書・手紙が届いたのが事件の発端)など、差別は残っているのに、「部落差別はもうない」、「黙っていたら、部落差別はなくなるのでは」という「寝た子を起こすな論」というものがある。しかし、寝た子論は、部落問題に無関心であることを正当化する言い回しではないか、という著者の主張に頷く。避けることなく、差別を許さないという決意のもと、解消するため努力しなければならない。
カップルと反対する親との対立、交渉のプロセスを丹念にみる
結婚差別には決まったプロセスがあるわけではない。個々人の体験は様々である。しかし、本著は様々なケースの分析のために、そのプロセスを「うちあけ」「親の反対」「カップルによる親の説得」「親による条件付与」の段階に分けて、各段階ごとに分析をすすめる。
第4章の「うちあけ」では、うちあける側の「ふるいたたせないと言えない」、関係が深まってからそれが原因で別れたりするのが嫌だから別れることになるなら傷が浅くて済むうちに言わねば、という緊張感と、うちあけされた側の「全然気にする問題じゃないやん」「別に関係ないやん」という軽い受け止め方の非対称性に考え込む。「関係ない」という言葉に、差別しないという肯定的メッセージと捉える人もいよう。しかし、部落への無関心や忌避からきている言葉で、アイデンティティを否定されたと感じることもあるかもしれない。実際に、その後関係が終わる場合もある。ところで、うちあけ後に関係が終了したけれども、それが部落差別が要因なのか、確証がつかないことがある。恋愛の先には結婚がある、ということが自明ではなくなり、別れることの障壁が低くなった現代。部落以外の何らかの理由をつけて交際を絶つことが容易となる。もやもやとした差別を経験する若者たちは、ストレートに怒りを表出することさえできない。
結婚差別には、親の承認や同意が深く関わっている。第5章は「親の反対」をテーマとする。あの手この手で行われる反対であるが、ある程度の「型」がある。自分自身の忌避感の表明という「明示的忌避」もあるが、一般的に部落が忌避されているから反対という「ステレオタイプによる正当化」もある。「よりよい結婚の可能性」もある。「親戚の人たちが結婚するときに差別を受けたらどうやって責任をとるの」といった「親戚の忌避の予期」、さらには「世間の忌避の予期」がある。これらは明示的忌避よりも巧妙だ。反対する親自身の差別を隠蔽した反対であるのだから。ところで、親の反対に「型」があること自体、個人的に思いついた考えというより、未だ差別が残る社会に流布した差別的な言説を学習してきた考えであることが察せられ、辛くなる。
第6章の「カップルによる親の説得」では、熾烈な反対にあってもあきらめず説得しようというカップルたちに涙が出る。弁護士である私は、つい、差別は許されない、という「正論」で説得したくなる。というか、そもそも、結婚に親の承諾は不要だ、とも思う。しかし、カップルは,親から承諾を得ようと努力する。それは、必ずしも婚姻に戸主の同意を必要とした明治民法の家制度の残滓が意識に残っているから、ではないならしい。戸主に従わねばということではなく、愛情をもって育ててくれた家族の祝福を得て結婚したい、ということかもしれない、と本著での指摘に、なるほどと思う。露骨な支配服従ではなく愛情で結ばれた親からの反対というのは、相対化が難しい。熱意、「人柄」、既成事実(妊娠)、縁切り(のほのめかし)、など。しかし、「人柄」をアピールすることは、部落はひとまず考えないでほしいという主張であり、部落を否定的なカテゴリーであることを説得する側も認めてしまうことになり、危うい戦略である。「既成事実」である妊娠で慌てて容認する親もいるが、中絶させる親もいる。縁切りのほのめかしで親を折れさせることもあるが、決裂し会わなくなるケースもある(しかし20年かけて関係を修復したケースもある)。理屈ではない反論、説得の困難さ…。
親がカップルの説得に譲歩し結婚を容認するが条件を提示することがある。その条件は、部落差別を温存するものになりがちである。第7章の「親による条件付与」は、親が出す条件と、その撤回に向けてのカップルの説得を取り上げる。部落解放運動に参加するな、部落外に住め、周囲に部落出身であることを言うな、子どもを産むな(「孫が差別されるのは見たくない」)といった条件も、反対と同様、ひとつのケースに限らず、「型」がある。
当事者を支援するには
「親戚、世間の忌避」等、「差別はいけない」という反論が無効にされてしまう巧妙な反対に、疲弊していくカップルを、どう支援するか。学術研究書は、分析だけでいいはずである。しかし、本著は、第10章「支援」を設け、支援のヒントになる語りをたくさん収録し、結婚差別に悩む人や彼らを支援したい人への実践書ともなっている。この章は、博士論文にはなかったパートだという。この章がなかったら、差別の現実だけを目の当たりにし、絶望してしまっただろう。これが解決マニュアル、というものではないが、様々な実践的なヒントがある。
たとえば、家庭内コンフリクトで双方が疲弊してしまう膠着状態から脱するために、家を出て距離をとる。そのアドバイスにより家を出てから改めて家族会議で結婚への強い意志を表明したことで、親の容認を引き出した、というケースがある。
あるいは、支援者は、何らかのアドバイスができなくても、カップルの話にひたすら耳を傾けることで、本人たちが決断する、ということがある。今は支援者のひとりのエピソードにじんとくる。恋人の親に交際を反対されて、アドバイスを乞うために先輩のもとを訪れたが、先輩は高熱で寝込んでいた。「俺ら、差別されてんねん!どうしよう」と一生懸命言っても、ふうふうと言われるばかりで、気が抜けて、「大丈夫?」と言っているうちに、落ち着き、考えの整理がつき、結婚の意思が固まった、というのである。冗談のようだが、そんなこともある。理屈ではなく熱意が人を動かすケースが多いとはいえ、部落問題を学習することで、苛立ちが消え、態度に落ち着きが生まれた、という当事者もいることから、部落問題が社会問題と知ることの重要性もあらためてわかる。その学習は、部落出身かそうでないかを問わず、必要なことだ。
結婚差別を受け、精神的に追い詰められ、自死に至る人がいる。そのような悲しいことが起こらないようにするにはどうしたらいいのだろう。第8章に収められた部落解放同盟福岡県連合会書記長の吉岡正博さんの語りは示唆に富む。自死した人の遺書には、「差別を糾弾する」という怒りはない。自分を責めている。「こんちくしょう、許せんぞ」って思っていたら、死なない。「運動が必要なんです。僕はそう思う。」確かに。しかし、地元での青年活動がなくなり、部落の若者たちは孤立している。見守り、専門家につなぐなどの支援をする必要がある。
そして、相談者が、全てを引き受ける必要はなく、多様な人々を巻き込んだ支援のネットワークの構築が必要である、など、部落差別に限らず私が関わることが多いDV被害者支援etc.にもあてはまる支援者へのヒントも多数ある。
専門家だけではなく、出会った人のちょっとした一言が、当事者を救うこともある、ということも。支援者の連れ合いが、ふと、「あなたたち2人に壁はない。」「壁があるのはさ、反対している人でしょ」と声をかける、など。何も専門性もない、私たちひとりが、サポートしうるのだ。ただ、私たちひとりがその役割を果たすようになるには、やはり教育や啓発が引き続き必要ともいえるだろう。
冒頭の数十年前の男子大学生は今や中年だ。子どもの結婚に「親戚の忌避」etc.を持ち出して巧妙に反対しているかもしれない。この人は変わらない、とたまたま隣に座った他人であるだけの私は早々に諦めてしまった。しかし、それでも彼のような人の子どもは、親との関係を諦めきれず、傷つき、苦悩し続ける。孤立しないでほしい。自分を責め続けないでほしい。そして、親も、長い時間をかけて変わる場合もある。
問題の深刻さに絶望しそうにもなるが、様々な解決の糸口をつかめる実践の書でもある本著が、広く読まれるように、願ってやまない。