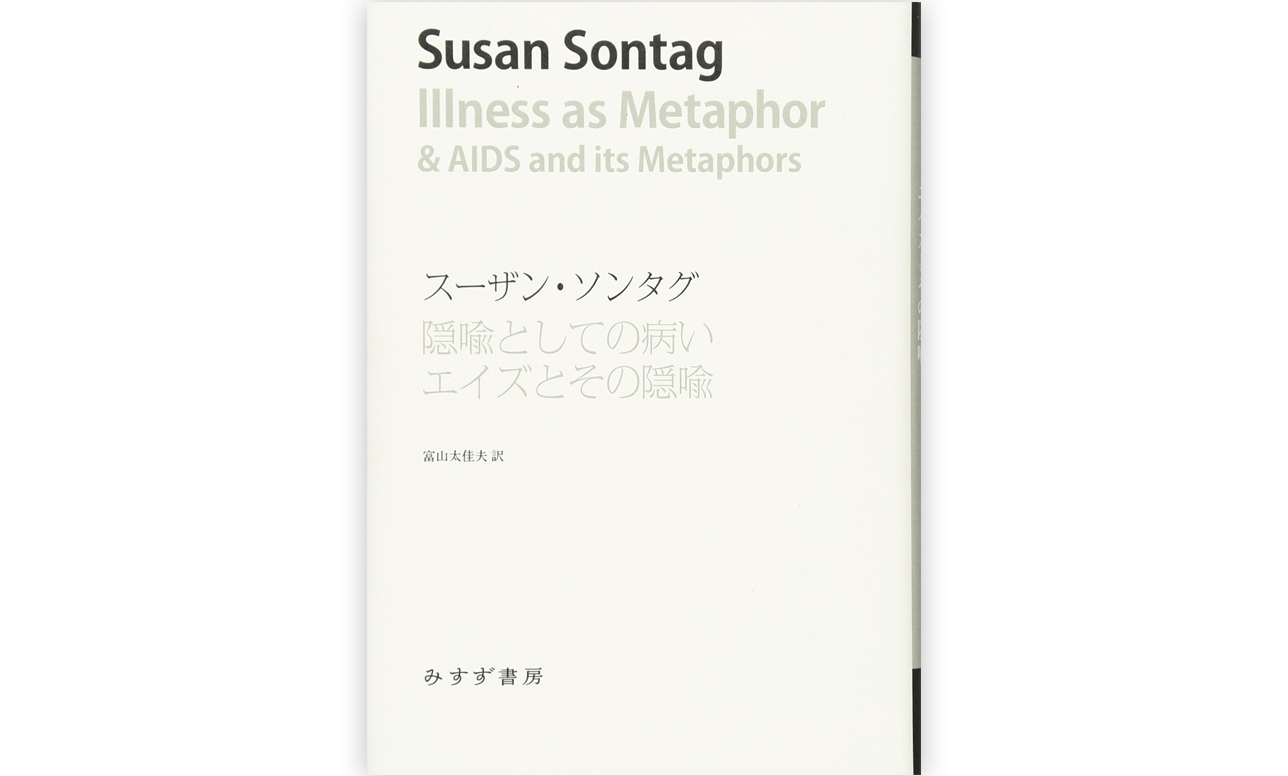長らくお休みさせていただき、大変失礼しました。入院したり手術したりでバタバタしてしまい、休養をメインに過ごすことをお許しいただいておりまして。ま、先は長いものと想定して、自分なりのペースに戻しつつ書いていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
人生の折り返しを過ぎてみると、本にせよ映画にせよ、「好きなもの」がさらに明確になってきます。私は、「血縁であってもなくても、世代を超えて『情』とか『想い』をバトンにして手渡していくこと」を描いた作品がやっぱり好きなんだな、と再確認しています。
もう何年も前のことですが、ラブピースクラブさんの連載で、ペドロ・アルモドバルの映画『オール・アバウト・マイ・マザー』について書いたことがあるかと記憶しています。子どもを交通事故で失った女性が、血縁ではない女たち(女装のゲイひとり含む)と、情とか想いを交わしていく映画です。
「情」とか「想い」は、俗に「母性」と呼ばれているものなのかもしれないけれど、この映画は私にとって、「母性と呼ばれるものがあるとして、それは“血を分けた母から子へ”に限定されるものではないはず。男の中に(作品中ではゲイの中に)生まれるものでもあるし、年の近い(かつ病に倒れた)同性の友人に注がれることもあるし、その友人が遺した子どもに注がれることだってある」ということをはっきり示した映画でした。「想い」がバトンになってつながっていく、その幅広さを示してくれた作品なのです。
で、現在も進行中の作品で、もっとも好きなもののひとつが、有間しのぶの漫画『その女、ジルバ』です。
この作品については、昨年の4月にこのメディアグルメで取り上げたことがあります。
そのときは単行本の3巻までが刊行されていたのですが、この春に4巻が発売されました。ちょうどそのとき私は入院だの手術だので、入手するのがずいぶん遅れてしまいました。
いかした高齢ホステスたちの懐の深い愛情に見守られ、40歳から新しい道を歩いている、主人公の笛吹・新(うすい・あらた。源氏名はアララ)。私は前回のコラムで、「この作品は女たちのサバイブの物語である」ということを書きました。そして、「女たちは、血縁以外でも、何十年の長きにわたってでも、バトンを手渡していける」ということを真正面から描いている、有間しのぶの力作だとも書いています。
で、3巻までの時点で、私は「アララは、先輩たちに触発され、先輩たちからバトンを受け継いでいく役目である」と思っていました。つまり、「情」の流れる方向、「バトン」が渡されていく順序は、「先輩ホステス→アララ」だと勝手に思っていたわけです。
4巻では、伝説の女・ジルバ亡き後、お店のママを務めている「くじらママ」の若かりし頃が、アララに語られます。それは、くじらママからの「アララ、あたくし花売り娘をしていた頃が今でも苦しいの」というつぶやきがきっかけでした。そうつぶやいた後、くじらママは自分でも驚きながら「なぜ、話すの? 乗り越えてきたじゃないの。墓まで誰にも話さず抱えていくと決めていたのに」と心の中で自分に語りかけています。
粋で優雅な大先輩が、ずっと誰にも話せなかった地獄の日々。それを聞いた最初の人間になったアララは、涙を流しながら、ママにある言葉をかけ続けるのです(それを書くのはさすがにネタバレもはなはだしいと思うので控えますが)。
「情」が流れる方向が、「アララ→先輩ホステス(ママ)」になった瞬間でした。もっと正確に言えば、「情が流れる方向は、決して一方通行ではない」「癒す者と癒される者は、その役割をお互いに替えてもいい」という「了解」が、親子以上に年の離れたアララとママの間に生まれた瞬間でした。
「年齢を重ねた女には、自分を癒してくれる人はもう現れない」「自分より年上の人間の苦しみを癒すことはできない」という固定概念に、有間しのぶが鮮やかに「NO」と示したわけです。
くじらママが1巻で口にした、「人はもっと寄り添って生きたほうがいいわね」という言葉が、この4巻でさらに重い意味をもってよみがえってきたのです。
女たちが世代を超えて、苦しみを打ち明け合い、理解し合い、励まし合い、癒し合う。その「意味」は、今後ますます深く描かれていくことでしょう。
私自身、昨年に出した本『恋愛がらみ。』はもちろん、過去に出したすべての本で一番に心に留めていたのは「私も多くの人から何かしらの情やバトンを受け取ってきたので、それをなるべく手渡していけたら」という思いでした。それができていたかどうか、それは自分が判断することではありませんが、あと何年生きるか正直なところ未知数なので、今後はもっと自分を律して、できる限りのことをやっていかなくては、との思いにかられています。47歳の私ですが、「いまから数年でくじらママ的な威厳を身につけることも、決して不可能ではないはず」と、自分を奮い立たせていますわ。うふふ。