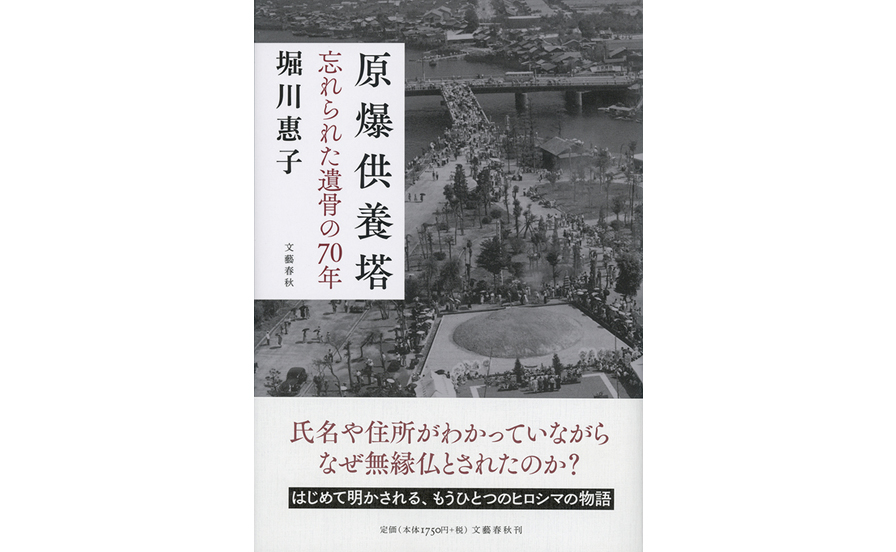民主政を支える報道の自由
表現の自由は、民主政に資するという近代市民革命の原動力となった権利である。イギリス市民革命では、15世紀に発明された活版印刷技術を利用した新聞・パンフレットが大量に頒布され、政治的な主張が拡散された。国王側はこれを抑えようと出版許可制度を向けたが、激しい批判を受けた。表現の自由の歴史は、政府に対する批判の自由を核心として展開したのである(渋谷秀樹『憲法第2版』有斐閣、2013年)。表現の自由は、それによって人々が政治的意思決定にコミットするという、民主政に資するという機能(自己統治の価値)、それによって自己の人格を発展させるという機能(自己実現の価値)があるがゆえ、憲法上保障される(21条)。そして、表現しても、その情報の受け手の自由が保障されていなければ、意味がない。最高裁も、知る自由が、13条、19条、21条に基礎づけられて保障されていることを認めている(「よど号」ハイジャック新聞記事抹消事件・最大判昭和58年6月22日民集37巻5号793頁)。そして、私たちが必要とする情報は今や膨大にあり、自分でこつこつ調べていけば集められるものではなく、報道機関による報道によってようやく様々な情報に接することができる。最高裁も、報道の自由について、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがって、思想表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」とした(博多駅事件・最大決昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁)。
「って、憲法の教科書みたいな話をいきなりどうした」と思われるかもしれない。しかし、国境なき記者団による報道の自由度ランキングで順位を下落させ2016年には72位まで下がっている。大手メディアの経営トップが安倍首相と会食を繰り返していることが話題であったが、森友問題で追及が始まっていた2月27日夜、安倍首相が赤坂飯店でメディア関係者と会食したことは注目を集めた(果たして、森友問題についてのメディアの取り扱いはその深刻さにあわないスピードでしぼんでしまった)。今村雅弘復興大臣が記者会見で原発事故の自主避難者への住宅無償提供の打ち切りに関連して国の責任を問う質問を繰り返したフリージャーナリストに「うるさい」等と言い、それでも会見の場にいる他の記者たちは皆「とても静かで何も言わず」という状態だったという(「今村大臣激怒で見えた日本の記者会見の特異性。「フリージャーナリストは本来の仕事を果たした」」週プレニュース2017年4月20日)。その上政権に少しでも批判的な報道をする機関や記者が、web上、さらには街宣で「反日」等と罵られもする。多々報道の自由の重要性をこの社会が認識しているか疑わしい事態が起こっているので、あえて声を大にして説明したかったのだ。
権力監視型の調査報道は絶えていない
しかし、報道機関、記者を「マスゴミ」と十把一絡げに嘲笑するのは乱暴だし、不毛だ。高田昌幸・大西祐資・松島佳子編著『権力に迫る「調査報道」』旬報社を読めば、引っかかりや疑問を頭に置き、地道な作業の末に突き詰めていく、そんな調査報道に取り組む記者たちが確実にいる、ということがわかる。
本著でインタビューを受けた記者たちによるスクープや成果は、以下の通り、いずれも民主主義において私たちが知るべき情報で、かつ、記者たちの地道な取材を経なければ知ることができなかった情報といえる。イラク戦争時、空自は国連関係者を運び、人道的復興支援に限っている、と政府は説明していたが、実は米兵を運んでいた(1章)。首相にも防衛大臣にも内密で自衛隊が独断で海外情報活動を行っていた(1章)。福島県民の健康調査で県側が委員を集め秘密裏に準備会を開き、予め「がん発生と原発事故に因果関係はない」ことなどを共通認識とした上で本会合のシナリオを作っていた(2章)。福島第一原発事故直後に避難指示区域に向かって現場を取材(3章)。集団的自衛権の行使容認へ憲法解釈を変更する際に法制局が記録を残さなかったことを、情報公開請求で明らかにする(3章)。世界の100人以上のジャーナリストが連携しながらやり遂げたパナマ文書報道(4章)。
1章の記者たちは、一匹狼が組織の中に人脈をつくり、一緒に飲みながら、引っかかりを感じて防衛の秘密に切り込んでいくという、「調査報道」ときいたときに浮かべるイメージそのままだ。折角取材に協力してくれた人の関係が切れるかもしれない、と書くことを遠慮するか。それはない。「書くためにやっているんだろう」(石井暁氏・共同通信)。正論だが、サツ回り(警察担当記者)などは「関係が壊れてしまうから、書けない」とよく言うとか。「憲法に由来する…」といったところで、こういった泥臭い人間関係に現実は左右されるとリアルに感じる。報道の自由を行使し実践するのは、個々の人間。前述した今村大臣の記者会見時、他の記者は静かだったというが、どうして静かなのだ。石井記者は、防衛大臣の記者会見で激論をしたことがある。記者も人間。「他紙の若い記者(略)から「いつまで聞くんだ」という視線が前と後ろからバシバシ来る。すごく精神衛生的には悪いんです。けれど、定年退職まであと5年しかないので、聞きたいことを聞こうと、覚悟を決めてやっています。遠慮しないし、恥ずかしがっている場合ではない、と」。静かな記者たちは、KYと思われたくない、精神衛生的に悪いことはしたくない、とお行儀良くしているのだろう。ストレートに権力から弾圧されるわけでもなくても、容易に報道の自由というものは萎縮してしまう、という様相が生々しい。しかし、KYだろうと拷問を受けるわけでもなんでもない。せいぜい、冷たい視線を浴びるとか、ネットで炎上するくらいだ。石井記者のように、勇気をだしてほしい、と切に思う。
情報公開請求という手法
夜間に取材先の自宅を訪問する「夜回り取材」をやらなくても、わかることはたくさんある。日下部聡氏(毎日新聞)は、サンデー毎日時代、石原都知事の交際費の現金出納簿を調べ、飲食に莫大な支出をし「都政を私物化」していることを明らかにした。その結果、区議たちが交際費や旅費について住民訴訟を提起し、一部で勝訴した。情報公開制度の前では、記者も一般市民も同じ立ち場。それでも、記者が情報公開を駆使していく意味はある。「多くの市民は日々の生活に忙しくて、なかなか情報公開制度を使って何かを調べようという気にはならないでしょう。一方でわれわれは職業として伝えるべきニュースは何かを常に意識しているわけです。」他方で、森友問題にみられるように、あって当然の文書がない、とされる事態も生じている。その場合には、「あって当然の文書がないケースを次々に報じていく」べきなのだ。
本来残すべき記録が全然残らなくなり、何があったかを後世の人が検証できない社会。それはもう民主主義社会とはいえない。情報公開請求を利用した報道は、そうであってよいのか、を私たちに気づかせてくれる。
国境を越え組織を越え連帯するジャーナリズムの可能性
4章に登場する、パナマ文書報道に参加したアレッシア・チェントラ氏(フリージャ-ナリスト)は、「「これは、私のスクープだ、」といった、独占的なジャーナリズムはもう死んだと思います。死んだというか、意味がない。」と語る。
パナマ文書報道に一章を割く澤康臣氏の『グローバル・ジャーナリズムー国際スクープの舞台裏』岩波新書は、まさに、「これは、私のスクープだ」という独占的なジャーナリズムが可能だった時代の印象的なエピソードから始まる。1963年のケネディ暗殺のニュースの第一報を世界に発信したUPI通信記者は、歴史的な速報を送った後、車載電話を抱え込み、ライバルのAP通信記者に「電話機を寄こせ」と殴られまくり罵倒されまくっても、ひるまなかった…。それから、半世紀を経て、今や市民が携帯電話で写真や動画を撮影し、ネットで世界に発信できる時代となった。それでもなお記者の存在意義はあるのか。澤氏も、日下部氏と同様、情報を見分け、価値と文脈をはかりながら真実に迫り、掘り下げ、深くわかりやすく伝えることをあげる。
ビジネスも欲望もグローバル化した現在、汚職も詐欺も横領も国境を越える。国境を越える問題を負い、暴露するには、個人の仕事、ひとつの組織にこもった仕事ではできない。国や組織の違いを越境して、連帯して仕事をする。第1章のタックスヘイブンの匿名法人の秘密をパナマ文書報道は、そのひとつの成果だ。参加した世界中の約400人もの記者は、一斉に報じるまでプロジェクトの秘密を誰もが守り抜いた。各国当局のみならず同じ会社の同僚に対しても。電子メールではプロジェクトについて記述しない、暗号化ツールを用いるなど、デジタル技術を駆使するのも、現代的だ。
中には、自宅で覗かれないよう窓を黒いビニールで覆い薄暗い部屋で孤独な作業を続け、収入も途絶え、クリスマスをどう迎えるか家族で困り果てたアイスランドの記者クリスチャンソンのような人もいる。世捨て人のような生活の果てに、アイスランド首相に聞きたかった質問を聞く。その後、首相の辞任を要求するアイスランド史上最大規模のデモが行われる事態になり、首相は辞任へ。史上最大のグローバル報道作戦ともいえるパナマ文書報道は、クリスチャンソンのような、地道で実直な人々に支えられたのだ、と涙がこみ上げる。
ノウハウも独占するのではなく、共有する時代だ。『権力に迫る「調査報道」』に収められたインタビューの各氏は、調査報道のスキルを若手に受け継ぎたいという思いを口にする。特に高田昌幸氏の記者ゼミでの講演録は、ずばり調査報道をどうやればできるかがテーマである。ミラクルを生む魔法があるわけではない。日常的な取材が基礎。証言だけではなく証拠のブツを(弁護士も同じ)。日常的な取材の中で疑問に思ったことを必ず問うていく。日常的に公開されている情報で何がわかるかを知る。取材のプロセスは明らかにするが、内部告発者は徹底的に守る。
ノウハウといっても、案外常識的なことなのだ。澤氏の『グローバル・ジャーナリズム』では、アメリカ調査報道記者編集者協会の2016年大会の多数の「記者による記者のための講座」の様子を伝えるが、「良い人間関係を築くこと」、「人間らしく、正直に」、など「当たり前のこと」が説かれている。拍子抜けしそうになるが、やはり、基本のキは、デジタル時代、グローバル時代でも、同じく地味なものなのだろう。
女性ジャーナリストたち
取材源と毎晩飲みながら話す。「肝臓が心配なんです」(石井暁氏・共同通信記者)。こういったスタイルでは、女性たちは仕事ができない。Webを駆使し他のジャーナリスと連帯するグローバルジャーナリズム時代は、女性たちも力を発揮できる可能性がある。パナマ文書報道に参加したアレッシア・チェントラ氏(『権力に迫る「調査報道」』4章)が女性であることは、何か象徴的だ。
もっとも様々な逆風がある。そもそも、新聞その他はどの国でも縮小傾向にある。アレッシア氏はフリーランスとして記事一本1ユーロの報酬しかもらえないことすらある。
澤氏の『グローバル・ジャーナリズム』には、女性記者は「お前のような女は強姦する」といった性的な攻撃コメント、侮辱コメント、ネット上の嫌がらせの標的になりやすい。欧州安全保障協力機構によると、Twitterでは女性記者は男性記者の3倍も罵倒コメントを浴びているとの研究結果もあるという。やはり、と思う。せめて、応援しなければ。
応援しなければいけないのは、NHKでの安定した職を辞して、調査報道NPOを立ちあげた立岩陽一郎さん(『権力に迫る「調査報道」』4章)、その他、隠された事実を引っ張りだし、私たちに伝えてくれるジャーナリスたち。早稲田大学を拠点にした調査報道メディア『ワセダクロニクル』がクラウドファンディングを実施中だ。丹念な調査と取材による報道を期待したい。
私たちの民主政を民主政であり続けるため、彼ら彼女らを応援しなくては、と切に思う。