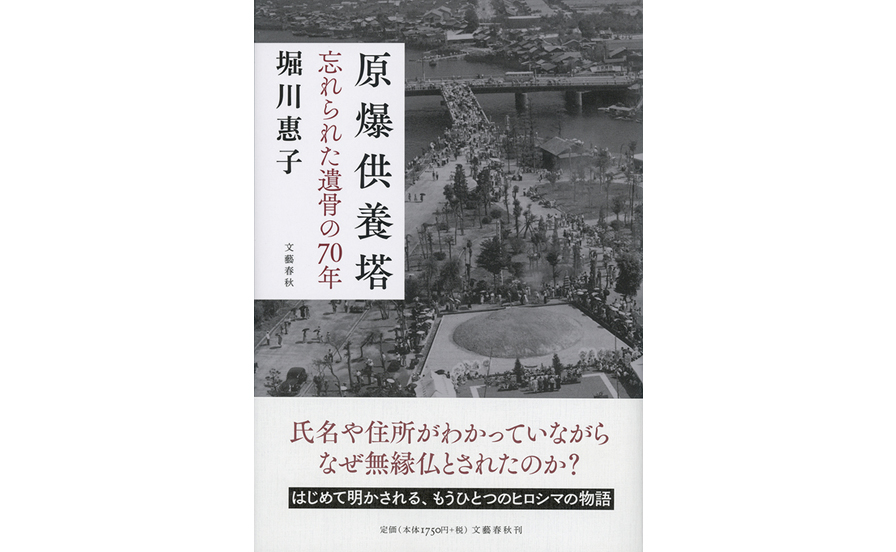私たち、<女>の経験は、歴史の中で、かえみられてこなかった。実際、子どもの中学校の歴史教科書をぱらぱら読んでみると、登場人物はずらり男たち。<男>の歴史だ。女たちの歴史は周辺化したまま、放置され、忘れ去られていく。男たちが華々しく活躍する歴史の中で女たちが埋没していることと、現在なお女たちがすみにおいやられ消耗していくこととは(「輝く女性」だのと持ち上げているようで、日本は世界経済フォーラムが2015年公表したジェンダー・ギャップ指数(GGI)で145ヶ国中101位という有様)、パラレルであるように思える。女たちを脇に追いやるのではなく、どんな生き様であったかを探ることは、現在生きる女たちが自分たちは「存在なきもの」ではない、排除されるべき存在ではない、と知ることにつながる。
女性を主体に取り上げた女性史研究の取り組みが盛んになったのは、そのような問題意識の広がりも背景にあろう。しかし、「私たち、<女>」とひとくくりにしていいのだろうか?「私たち、<ひと>」とひとくくりにした歴史が、マジョリティの男を主体とみなして女などマイノリティを周辺化してしまうように、「私たち、<女>」の歴史が、性別以外ではこの社会ではマジョリティの女たちを主体とみなし様々な女たちを周辺化してしまうことにならないか。見えない存在ではいたくない、と見えない存在から脱却しようとして、他のルーツを持つ女を見えない存在にしてしまうなんて悲劇は、避けたい。それには、どんな歴史を紡いでいくといいのだろう。
ミリネ編・皇浦康子責任編集『家族写真をめぐる私たちの歴史 在日朝鮮人・被差別部落・アイヌ・沖縄・外国人女性』(御茶の水書房、2016年)のページを繰りながら、「ああ、こんなふうに歴史を紡ぐ本が読みたかった」と胸が熱くなった。
本著で、日本に生きる(生きた)、在日朝鮮人、被差別部落、アイヌ、沖縄、アジア(フィリピン、スリランカ、ベトナム)出身の20代から70代の女性たち24人が、「家族写真」を手がかりに、「私は」を主語にして、自分や家族の生を綴っていく。編者のミリネとは、朝鮮語で「銀河」という意味で、点在する「在日」の女性たちが集まり、銀河のように輝きたいという思いでつけたとある。今まで、家族写真展のほか、「慰安婦」問題教材ビデオ等を制作してきたという。ミリネの仲間たちで家族写真を持ち寄り時間をかけて語り合ったところ、一口に「在日」といっても、それぞれが異なる多様な歴史を持っていることに気づき、その多様な状況を理解するアートを始めたのだという。「日本に存在しているのに、ないもとされていることに気づかされるような表現」の方法はたくさんあるはず、「私の表現」を模索していきたい、と皇浦さんは書く(17頁)。この本はそのひとつの成果だ。
皇浦さんは、在日朝鮮人二世の母に、小学校の卒業式には、着物で出席してほしいとねだり、着物姿の母の写真を自分が撮り、誇らしく写真をアルバムにはった。しかし、「これでもう日本人になれる」という思いは、指紋押捺を経験し、外国人登録証の常時携帯が始まり、打ち砕かれる。学校を早退して、外国人登録証の更新のために出かけた市役所で、文字の読み書きができないおばあさんが、係の人に怒鳴られている光景。日本語が達者な父を同伴した自分は丁寧な扱いをされたが、それでもインクをべったりつけた指を押さえつけられ指紋を押したときのいやな気持ち…。読者もまざまざと実感する。皇浦さんは、母が亡くなった後、忘れかけていた母の着物姿の写真を見つける。母をいじめ抜いた日本人のふりを強要した自分が恥ずかしい、ないものにしたい。その写真を破り捨てた、という(27頁)。どうか自分を責めないで、と呼びかけたくなるが、痛みの大きさに比べてなんの慰めにもならないと、口ごもる。
過去、さらには現在にも残る差別に、胸が苦しくなる。
在日2.5世の李さんは、90歳のオモニの薄れゆく記憶をたよりに、その生きてきた軌跡をたどる。1940年ころ皇民化政策が浸透し、朝鮮服地の商売はできなくなる。創氏改名で日本の名前を持たされるが、日常生活では朝鮮名を呼び合い、朝鮮語で話した。しかし、「協和会」(皇民化を推進した警察主導の組織)の取り締まりのときは外出できなかったとオモニは悔しがる。
在日3世の朴さんは、4歳のとき初めてチマチョゴリを着てうれしそうに笑う自分の写真からつづりだす。おしゃまな笑顔はとてもかわいい。たくさん写真を撮ったオンマに、「陽子ちゃんに見せに行ってくるわ」と玄関に出ると、「やめとき」と鋭い声で止められる。陽子ちゃんが七五三のときにきれいな赤い着物を着て見せてくれた、と言っても、オンマは怖い顔で、あかんの一点張り(64頁)。1978年のころだ。そのころでも、差別を恐れなければならなかったということに、胸が重くなる。
原田さんは、自分がアイヌと知ったのは、小学校に入学してすぐ、男子から「アイヌ!」といわれたときのこと。たんたんと書かれているが、すさまじいいじめを経験した。姉も弟も不登校になった。もちろんいじめが原因だった。しかし原田さんは、いじめられない日はないんだから慣れるわなって感覚で通い続けたという。お母さんはバキュームカーの運転をしていた。「うんこくみ!」ともいじめられたが、いつもアイヌといじめられ慣れていたし、誰かがやらなければいけない仕事だし、誰でもできる仕事ではないから、母を尊敬していた、という。写真の中の、母、姉、原田さんの3人の穏やかな笑顔が愛おしくなる。
露骨な就職差別も痛ましい。小学校から高校まで、日本の公立学校に通った鄭さんの日本人の友人たちは、商社や大手金融機関に就職した。しかし、成績も上位だった鄭さんには、受験できる企業ははじめから「ココとココ」と限定された。両親の言う「一所懸命がんばる」ことの無意味さを知ってしまう(39頁)。
結婚差別が未だに深刻であることにも、愕然とする。被差別部落の夫と結婚し、部落解放運動に関わるようになった谷添さんはいう。2人の息子には結婚を意識したら、出自を伝えることが望ましいと話をしてきた。息子たちは恋人に伝えた上で、結婚した。自分も、息子たちも、結婚差別はなかったとカウントされる。しかし、なぜ大事な人に出自を伝えるかどうか悩むこと自体が、差別ではないか、と述懐なさる。そのとおり。なぜそんなことが続くのだろうか。
ルーツだけではなく、女ということでも辛い経験をしている。写真は晴れやかなシーンを切り取る。苛酷な経験で精神を病んでいった女たちの、病んでいく前の笑顔がなおさら切ない。祖父・父から暴力をふるわれた祖母・母という記憶は頻繁に描写される。たとえば、川﨑さんが語る、部落出身の祖父から暴力をふるわれた後、日本酒一升瓶を抱えて顔色一つ変えずに飲んでいた祖母の様子など、脳裏に浮かぶ。しかし、もちろんそんな写真はない。
専業主婦でたとえば、李さんのオモニは、シオモニ(父の母)からのいじめでPTSDに苦しみ、ひとり台所で電気もつけずに洗い物をしながら暗闇に向かって怒鳴っていたりした。そんなシーンの写真もない。そのオモニは李さんを女だからと兄弟と差別した。兄と弟がテレビを観る一方で自分だけが洗い物をするのが嫌で嫌でいつも反抗したという。オモニを苦しめたシオモニも、実は「李家」をいいものだと思わず、貧困と重圧の中で苦しんできた。苦しんだ女たちが相互に苦しめあうことの悲しさ。
女だから女に寛容になる、というわけではないのと同様、被差別の経験があれば、差別に敏感になる、というのでもない。1986年生まれの瀬戸徐さんの母は、韓国から1985年に日本に来て、被差別部落で仕事をする父と結婚した。瀬戸徐さんは、物心をついたときから、母が韓国人であることと、父がどこで仕事をしているかを言ってはならないと言いつけられていた。日本の親類から、朝鮮の血が「汚い血」と差別された。なぜ、部落差別の痛みを知っているのに、他者に「汚い」といえるのかと怒りを感じつつも、瀬戸徐さんの気持ちは複雑だ。その親戚たちに、たくさんの愛情ももらい、育てられたのだから(90頁)。
部落出身の上本さんの家庭では、年に数回、父がちゃぶ台をひっくり返し、母を殴った。「お母ちゃん、どっかに行ってしまわへん?」と訊くと、母は「お母ちゃんには、どっこも行くとこない」と答えたという。DV被害者の事件を積極的に担う私としては時代を遡って「いや、手段はある」と励ましたい。このムラで生きるしかない部落女性の経験を、私はよく知らないのだから、いい加減なことを言ってはならないのではないか…とためらいもよぎる。しかし、部落出身の熊本さんが書くように、コミュニティは「差別に抗して生きていくためのシェルターである一方、女性に対する差別や抑圧を生むものとしても機能している」ともいえる。やはり暴力への救済について、「コミュニティの独自性」等を前に臆してはならない、とも思い返す。
巻末に収められた萩原弘子さんへの皇浦さんのインタビューにあるように、家族写真は、会えない家族、死んでしまった家族を身近に引き寄せ、今を生きる自分の支えとなる。他方で、真実を写し出しているのではなく、こうでありたいという姿を切り取るものでもある。本著は文章で「写っていないもの」までひもときながら、女たち、女というだけでなく様々な属性をもった女たちの生きてきた歴史をつむぐ、薄いけれども重厚で、大切な一冊である。