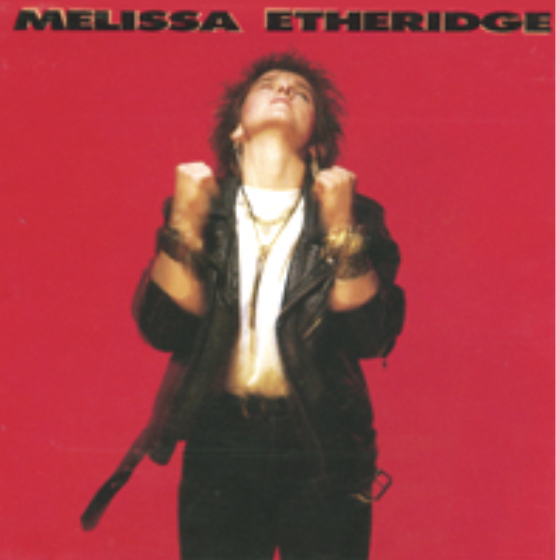三年ほど前の年末年始、十数年ぶりの海外旅行でイスタンブールに行った。『そして、私たちは愛に帰る』(2007年ファティ・アキン監督)という映画を観てはげしく胸を打たれ、その映画の舞台であるイスタンブールに行きたいと、居ても立っても居られない衝動に駆られたのだ。せっかくトルコにいくのであればトルコではどんな音楽が現在進行形で生まれているのかと興味が湧き、探っていくとこれがまた面白い。タルカンやセゼン・アクスといった大物のターキッシュ・ポップはさておいて、メルシャン・デデ、ババズーラなど、西欧とアジアが融合したクラブ・ミュージックやロックに心うばわれた。ヨーロッパ大陸とアジア大陸を隔てるボスポラス海峡を眺めながら、遊覧船の船着き場の傍の屋台でほおばるサバサンドのおいしかったこと!近いうちにまた訪れたい、そんな魅力にあふれたトルコ、イスタンブールがいま大変な事態になっている。
7月には軍のクーデター未遂、ニュースではエルドアン大統領の強権政治が日々増していくかのような、反体制派への弾圧、メディアの閉鎖、人々の拘束。私がトルコという国をはじめて意識したのは80年代にユルマズ・ギュネイ監督の『路』という映画を観た時だ。政治犯として捕らえられていたギュネイ監督が、刑務所から仲間に指示をだしながら完成させたという『路』はカンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞した。トルコというのは言論・表現の自由が多大に侵害される国なのかと当時思った。それが〈いつのまにか〉、民主化(世俗化)が進み一大観光都市となっていたのだ。いまその途を逆行しそうなほどの危機感を感ぜざるを得ないトルコ。その〈いつのまにか〉の間に一体何があったのか知りたくて、トルコについての本を数冊ふむと読んでみて、政治の変遷、クルド問題、宗教、そして泥沼化している戦時下の中東などに関して大まかに理解はしたが、事態のあまりの複雑さにこれでは日本のメディアが伝えるわずかな情報だけではとても把握しきれない。
そんないま、トルコでの悲しい惨事が報道されザラザラと気持ちが陰る折に、“トルコのジョーン・バエズ”ともいわれた、セルダ・バージャンを聴いている。2011年にリリースされた『セルダ・バージャン/ハルクム』Selda Bagcan HALKIMは還暦を過ぎたセルダ・バージャンの懐の深さが堪能できる貫禄の歌声だ。1948年生まれのセルダの音楽は、アナトリア(トルコ共和国の国土の99%を占める半島地帯)のフォーク・ミュージックが主軸となっている。70年代から活躍している大ベテランなのだ。もちろん全曲トルコ語で歌われており、CDには詞の和訳も英訳もないので、どんな内容の歌なのかは残念ながらわからない。サズの演奏を伴って歌われる、かつての曲の数々は、社会的なメッセージが込められた内容のプロテスト・ソングが中心であったという。80年代には幾度かの拘束にも屈せず、トルコの第一線で活躍をつづけ、彼女の歌を糧に日々を暮らすトルコ人たちもいるという。『ハルクム』のCDにあるステージ写真では、真っ白な衣装を身に纏ったセルダが、頭にスカーフを被ったおばちゃんと手を握って歌っている。アナトリア地方の伝承曲や吟遊詩人たちの歌が中心ということだが、その土臭さはトルコという広大な地のエネルギーのようだ。70年代のセルダの曲にはサイケデリック、プログレッシブなロックの要素もあり、その当時のセルダの先鋭的な一面を垣間見る。アグレッシブな精神と不屈の闘志が、歳を重ねるごとに大きな包容力となり、いまもなおトルコの老若男女から支持され続けているのではないだろうか。
『そして、私たちは愛に帰る』の劇中、くりかえし流れるトルコのプロテスト・シンガーの歌がある。キューズム・コユンジュが歌う「Ben Seni(私は貴方を)」。キュームズ・コユンジュは2005年に33歳のときガンで他界した(映画ではチェルノブイリのせいだという)。アジアの果ての郷愁あふれるこの哀歌が、セルダ・バージャンのアナトリアへの深い思慕と邂逅する。