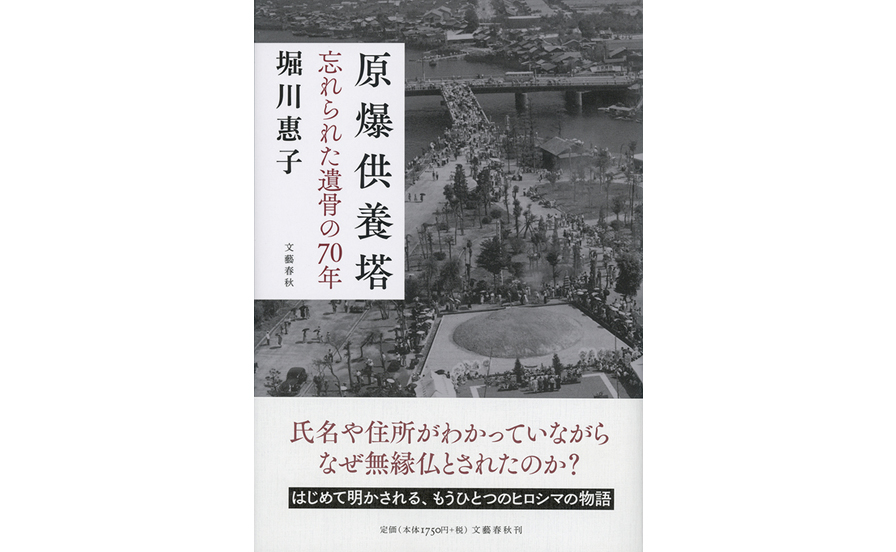無名の女たちの生を知りたい
先日、カフェの隣のテーブルから、「やっぱり歴史に名前を残す人ってすごいよ。歴史を学ぶのが面白くなってきたよ」という若い人の声が聞こえてきて、椅子からずり落ちそうになった。過去は無数の、歴史に名を残さない人たちが生きてきた。勝者による取捨選択を経て歴史に名を残した人たち(それもほとんど男で支配者たち)の伝記抜粋のような歴史など、もう飽き飽きだ。そんなため息をつきながら、ふと思い出した本が、山家悠平著 『遊郭のストライキ 女性たちの二十世紀・序説』(共和国、2015年)だ。
本著は、遊郭の女性たちによる待遇改善のためのストライキや集団逃走に光をあてる。遊郭の状況改善運動の側面だけではなく、女性たちがどのような希望や目的をもって生活していたのか(それを踏まえて初めてストライキや集団逃走という選択がなぜなされたかを考えることができる)もみていく。みていく、とサラリと書いたが、簡単ではない。社会の底辺にいた女性たちの日常を知る手がかりは乏しい。しかし、本著は、回想録のほか地方紙を含む小さな記事を丹念に読み込むことにより、今までの男性文学者たちが遊郭に通う中で描き出したノスタルジックな遊郭文化の回想録とも、廃娼運動家という外側の「救済者」を軸にした女性史研究とも異なる、遊郭の中の女性たち自身に焦点をあてた叙述をなしとげた。
「自由意志」という建前が原動力に
女性の「自由意思」による売春という建前のもと隔離し性病検査など医学的にも女性を監視と搾取の対象においた近代公娼制度。しかし、「自由意思」という欺瞞的な建前は、女性たちが自ら廃業する可能性に道を開いた。女性たちが解放を志向し行動する原動力となったものは、矛盾を孕んだ制度のほか、あからさまな暴力をふるわれても挫けなかった人々による廃娼運動、識字率の向上(女が制度の建前を知る。廃娼運動を知る)など。
戦時下の抑圧によって労働運動そのものが解体された1940年代までに限ると、遊郭のストライキや集団闘争は、警察が遊郭の待遇改善という方針を打ち出した1926年5月から10月にかけてと、大不況を背景にした労働運動の高揚と機を一にした1931年からの2年である。第1の時期は、集団闘争と自由廃業要求が特徴である。第2の時期となると、自由廃業というより、待遇の改善や楼主の不正を改めさせることが主となる。不況下で失業者になれば、前借金(廃業しても残る)を返せないし、自分、あるいは自分を頼りにする家族を養えない。生き延びるための「労働」を続けざるを得なかった女性たちにとって、待遇改善も解放と同様切実だった。
待遇改善要求の一環として、女性たちは警察に楼主などから受ける性暴力の訴えを告発もした。待遇改善とは別次元の問題と思われるが、遊郭の改善が内外で意識されるようになってはじめて娼伎たちは楼主の強姦を告発する力を得たのであろう。本著が指摘するように、売春を日常的な仕事としていた当事者の意識の中で、決して侵害を許さない身体の領域がしっかりと保たれていた、ということに感じ入る。
第一のピーク時の女性たちの行動から、娼伎や芸伎たちは、遊郭のなかで自分たちの状況について相談し、改善のための方法を模索していたことがわかる。そうでなければ、連署で抗議文を作成したり、タイミングを見計らって集団で逃走することはできない。また、自分自身に対する虐待や搾取だけではなく、ほかの娼伎に対する虐待への憤りなどからも動き出す。女性たちのシスターフッドを感じる。もっとも、逆に、ひとりの娼伎が優遇されているといったことでのストライキもある。現実はうるわしくまとめられるほど簡単ではない。こうした細部が実に興味深い。
本著は、元娼妓の回想録中の他愛のないやりとりも丹念に読み込んで、表立った逃走ないし闘争以外の日常の生活を浮かび上がらせる。機嫌が悪く楼主とも怒鳴りあいの喧嘩をする娼妓、物を投げて壊す娼妓。しかし、孤独に自暴自棄になっているばかりではない。食事時に粗末な食べ物について不満や怒りを口にする。相づちを打つ。そうしたことが、娼妓たちの中に共感と連帯感をはぐくんでもいた。元娼伎の女性の回想録からは、遊郭が悲しみや自己否定、さらにはそれ以上に強い怒りが充満した場所であったことがわかる。その怒りについて共感を重ねることが、脱出や告発という明確な目標にもつながっていった。
遊郭からの逃走や遊郭における待遇改善のストライキについて、当時の新聞は必ずしも好意的ではなかった。見出しや本文から、揶揄や嘲笑、冷笑が垣間見られる。そこには、現在でもセクシュアルハラスメントや性被害について女性が告発した際に向けられるまなざしと同様のからかいや冷ややかさを感じる。しかし、そういった書きぶりでも、女性たちの闘いが取り上げられたことの意義は大きい。識字率の向上(本著は徐々に向上した娼妓たちの就学率のデータなども照会してくれる。遊郭にいながら通信教育を受けていた女性もいる)を背景に、記事の切り抜き帖を作っていた娼妓がいる。切り抜き帖を手がかりに、娼妓たちは協議を重ね、逃走を決行した例もあるのだ。
待遇改善を求めた孤立した闘い
1931年から2年間の女性たちの闘いは、廃業というより、不正の追及や具体的な改善要求が特徴的である。不況を背景に、廃業しても前借金が帳消しにはならず、それを返す手段もないのであれば、労働条件の改善(「病気のときは早く医者の手当てをうけさすこと」、「便所を二階に一ヶ所増設」など、労働条件という以前に切実な要求であるが)を目指すことのほうが、現実的な闘いであったろう。
この点で、外部の支援者である廃娼運動家との齟齬があらわになる。ある集団逃走事件では、警察署に駆け込んだ芸娼妓たちに、本意が待遇改善にあるのか自由廃業にあるのかを確かめるために、廃娼運動家が面会を要求する。しかし、警察署は彼女たちは待遇改善を望んでいるとして廃娼運動家に手を引くことを要求した。このケースでは、楼主側から上着を引き裂かれるような暴力を受けた廃娼運動家が手を引いたことを責めるのも酷である。そして、警察を介した伝聞での女性たちの要求が真意であったかも疑わしい。しかし、廃娼運動家は、女性たちが自由廃業を求めるならば支援するが、待遇改善を求める争議であれば、「失敗」であり、支援に値するとは捉えなかった。運動家により救済された女性たちも確かにいた。しかし、待遇改善を求める女性たちにとっては、結局運動家の支援を得られず、孤立した状況で、圧倒的に不均衡な力関係の相手方である楼主側と、困難な闘いを強いられたということなのではないか。
廃娼運動家が女性たちの要求が待遇改善であれば支援から手を引いた要因には、彼ら彼女たちが、遊郭で働くこと自体を否定していたことがあろう。「醜業婦」と驚くような蔑称で呼び、その存在が国家の安定の脅威である、「反社会的反国家的」で「非国民」などと謗った廃娼運動家もいた。彼ら彼女らの欺瞞は当時も与謝野晶子や伊藤野枝が指摘していた。軽蔑する眼差しそれ自体が、女性たちを差別するのだとの伊藤の指摘は、さほど関心を集めはしなかったし、「男性の要求」を「本然」とする、また、「賎業」であるとは捉えていたなど、現在のセックスワーカー論を踏まえれば、あまりに粗雑であり、限界があった。しかし、なお、女性たちを中心に据えた点で、廃娼運動に欠けた視点があり、運動家と女性たちとの連帯につながる可能性があった、と本著は指摘する。
新聞記事や廃娼運動の記録の中で、女性たちがアクションを起こしても、その要求はすぐ背景に退いてしまう。すぐさま、「矯風回VS遊郭組合」の対決図式に回収されてしまう。そのあたりの変容も、当事者に突き動かされたはずの運動の中で、当事者の声が背景化されてしまいがちなことと同様の様相があろう。
本著自体が、あとがきの中で、「近代国家による性管理をはじめとする、より大きなコンテクストについてほとんど言及することができなかった」と、本研究の限界を認める。「近代国家の底辺女性からの性的収奪としての公娼制度は、植民地の女性を巻き込んで拡大し、「従軍慰安婦」制度へと繋がってゆくものであった」、それらの大きな歴史的文脈のなかに芸娼妓の抗議やストライキを位置づけ、そこから近代公娼制度を捉え返していくことを、今後の研究課題としたい、とする。大変意義のある研究テーマであり、次なる研究成果が待ち遠しい。
直視する無名の女たちのパワー
私の手元にある初版は、素人目でも、相当お金がかかっているカバーである。格子窓状に切り抜かれた部分越しに、半透明のカバーを通してぼかされた女たちの姿がみえる。格子窓状の第一のカバーをまず外す。すると半透明のカバーにおおわれてぼんやりしてはいるが、満面笑顔で万歳した女性たちが見える。半透明のカバーにはイタリックで薄らと「strike」と大きく左下から右上に流れるように表紙をはみ出るように大きく書かれている。その半透明のカバーも外すと、女性たちと目が合う。彼女たちははっきりとこちらを直視している。この表紙だけで、この本が誰を主体とした歴史を探究しようとしたかがわかる。歴史研究の中で主役とはされてこなかった、あたかも格子窓越し、半透明のカバー越しに眺められてきた女性たち。廃娼運動に関する研究でも運動家が主体であって、女たちは「救済される客体」ではなかったか。先行研究も乏しく、資料も乏しい。それでも丹念に探れば、格子窓を外せ、カバーを外せ。必死に、主体的に生きようとし、こちらを直視している女たちが見えてくる、本著のメッセージを伝えようとする意欲に満ちたカバーに、著者のみならず編集者、ブックデザイナーの意欲を感じ、既に心打たれる。しかし、二刷以降はこの素晴らしい装幀ではないらしい。コストのためだろうが、残念である。
後書きとプロフィール欄を確認すると、著者の山家氏は、京都大学大学院博士課程修了し、本著のもととなる博士学位論文を提出しながら、研究職についておらず、「大手前大学学習支援センターに勤務」。その前には「大学での有期雇用撤廃」に向け「まさか自分自身がすることになるとは思っていなかった」「ハンガーストライキ」まで行ったこともあるようだ(しかし結局雇い止めにあったようだ…)。貧困のためやむなくその世界に入り、劣悪な労働環境で酷使され、「醜業婦」と蔑視されながらも、解放を、あるいは、待遇改善を求めた女性たちのパワーに感化されての行動ではないだろうか。ひとりひとりの、勇気のある、しかし歴史のなかでは埋もれてしまう小さな闘いを拾い上げた著者の非正規労働者としての闘いも、きっと次なる闘いにつながっていくといい。