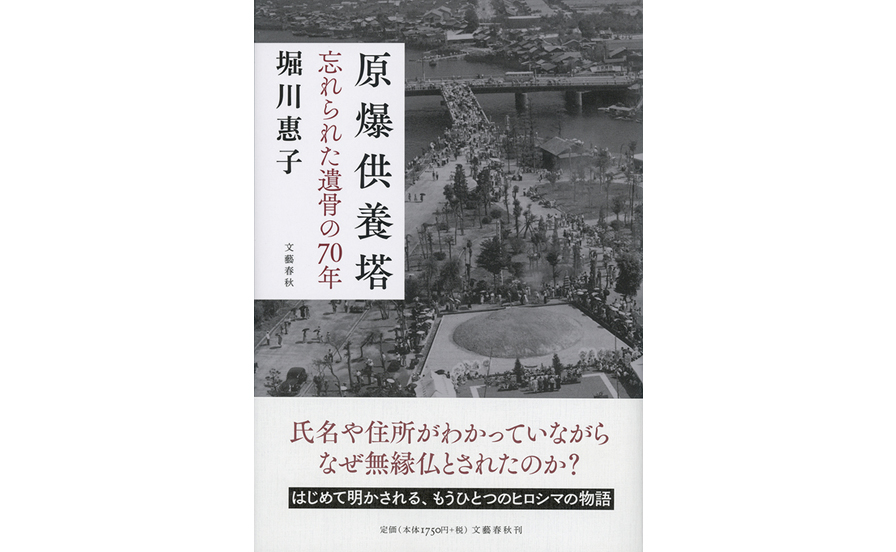ヘイトスピーチ対策法、しかし都知事選…
参院選が終わったと思ったら、ただいま都知事選のまっただ中。候補者のポスターが貼られた掲示板を通り過ぎるたびにどんよりする。在特会(在日特権を許さない市民の会)の前会長桜井誠が都知事選に立候補し、「都内在住の外国人への生活保護支給停止」等を掲げたポスターを堂々と貼っている。民団の前で街宣もしているという。
5月24日にヘイトスピーチ対策法がようやく成立した。禁止規定や罰則がない同法にどれだけの意義があるのか、疑問の声もあった。しかし、同法の施行日(6月3日)直前の6月2日、横浜地方裁判所川崎支部は、同法の趣旨を踏まえて、在日コリアン排除を訴えるデモを申立人である社会福祉法人の半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出した(朝日新聞デジタル2016年6月3日3時5分河井健記者・金子元希記者)。川崎市も、周辺の公園使用を不許可とした。しかし、県警がデモのための道路使用を許可し、5日にヘイトデモが実行されようとしたが、反対する市民らがデモ隊を取り囲んだ。神奈川県警の説得もあり、がデモは出発直後に中止となった(朝日新聞デジタル2016年6月5日19時40分)。今まで、ヘイトデモを「護衛」し、カウンター側をあたかも護衛し、カウンター側を排除するかのようと批判されてきた警察(たとえば、3月にカウンター側の女性の首を絞める警察官の映像は衝撃的であり、瞬く間に拡散された)が、ヘイトデモ中止を説得するとは。法務省は、川崎市の現場へ、ヘイトスピーチ対策法についての広告宣伝車を出した(6月8日法務大臣記者会見)。
時代は変わる。進歩する。と涙していたところに、都知事選。ヘイトデモとしてではなく、選挙運動として実施されれば、それに抗議する活動は、「選挙妨害罪」公職選挙法225条・230条に該当することになってしまいかねないと懸念されている(民団新聞2016年7月13日)。苦々しい。さらには「一歩リード」と既に言われている小池百合子は、街頭演説第一声で、「外国人地方参政権反対」に言及したが、過去に、そよ風主催・在特会女性部協賛の講演会の講師を務めてもいる。その点、追求したのは日刊ゲンダイ
だけであろうか。自民党の推薦が得られない、組織票がないなどという「クリーンさ」だけが押し出されているようで気になる(実際には公明党支持者などが応援しているようだ。それまたゲンダイが報じている)。
絶望に覆われる中でも希望を抱きたい
希望を抱きたい。しかし、絶望の引力の方が強い。
深沢潮著『緑と赤』(実業之日本社)は、安易な希望を抱かせてはくれない。
大学3年生で在日韓国人の知英は友人の梓とグアムへ行くことにしたが、パスポート上の名前が通称と異なること、色が赤ではなく緑であることを、隠しておけるならそうしたい。在日という出自を知るのは「重い」のではないか。勇気を出して告白してみれば、K-POPSファンの梓は屈託なく受け入れ、むしろグアムでなく韓国に行こうと言い出す。「行ったら、自分の国、好きになるよ」と目を輝かす梓と、韓国を「自分の国」とは思っていないと説明する気力もない知英との、早速のすれ違い。すれ違いは徐々に積もっていく。梓には悪気がない、とわかっていても、梓がK-POPSファンつながりで知り合った良美に自分のことを「在日」だと話したことを機に、溝は深まる。知英は、「在日」とわかったとたんに梓の自分に対する態度が変わった、嫌だときつく言う。自分なりに胸を痛めていたのに言いがかりを言われたと梓も、知英に腹が立ってくる。
一方、もともとはK-POPSファンだっただけの良美は、梓からヘイトデモ動画を見せられて急に正義に目覚め、差別問題についてアツいツイートをしまくり、カウンターの現場にも行くようになる。その息巻きぶりは、「はたから見れば痛い人」。良美ほどではないがアツい中年女である私にとっても、その痛い描写にはぐさっとくるものがある。単純に、自分のタイムラインには気持ちのいい言葉が並んでほしい、正義の言葉であっても激しいものを敬遠する梓の気持ちは、多くの人が共有しているかもしれない(ますます、すみません、という気持ちになる)。それでも、梓はカウンターに参加してみる。デモに抗する人々に感動もするが、自分は新大久保で「楽しい嬉しいという気持ちだけでいたい」という違和感がぬぐえない。
良美は、10年前に離婚して、以後毎日嫌みを言う母に世話になるしかない、わびしい毎日だ。カウンター活動は、そのわびしい毎日を劇的に変える。それは良美にとって、目的ではなく、退屈な日常を変えるスパイスだとしたら、動機が不純であるように、読者には映る。現に、カウンター活動を通じて男性との出会いを待ち構えているようでもある。社会の差別をなくすことを高らかに掲げながら、現実には身近な母の差別意識も変えることができないことにも、哀感が漂う。社会を変える運動に身を投じてきた叔父は、運動に夢中になっている良美に、「今は空っぽで虚しい、世の中は変わらない、小さな幸せを求めた方が良かったんだ」と諭す。でも、今までの生活だってずっと虚しかった良美は、叔父の言葉を受け止めながら、カウンターを止めない。
韓国で知英に出会い、在日韓国人であることを打ち明けた龍平は、知英が在日同胞であるのにそれを言ってくれなかったことを知り、腹を立てる。友人の佐藤は、なぜ腹を立てるのか、龍平も自分たちにずっと黙っていたではないか、と諭す。龍平は、帰化したことを在日同胞の元恋人に糾弾された苦い思いを思い出す。隠していた知英に自分自身をみるようで腹立たしかったのではないか。
在日韓国人である事実からは逃れられない。その事実を意識し始めると、嫌韓本がランキング上位といった2014年初春の日本は、知英にとって耐えがたい場面があまりにも多い。それでも知らなければと関東大震災時の朝鮮人虐殺の本など読んで恐怖心がどんどん強まっていく。引きこもってしまい、命を絶ってしまった父親と同じようにならないか、母は心配する。心身ともに落ちていく知英を引き留めるものは。抱きしめてくれる母の体温と心臓の鼓動。龍平が心配してくれている気配。韓国人に失恋して一時期韓国嫌いになったけれどもそんな自分の変化も知英を傷つけたという梓の気づき。痛いと感じられた良美がカウンター活動を続けテレビでインタビューを受けている様子だって、「悪意ばかりの世の中ではない」と希望を抱かせる。
出会えば、わかり合える、乗り越えられる、というほど楽観的にもなれない。出会っても、鈍感だったり、残酷だったりして、傷つけてしまうことだってある。溝を一層深くすることだってある。しかし、それでも、救われることもある。もがいていれば、ともにのりこえることだってできる、かもしれない。絶望をとことん見据える本著を読み終えたときには、ほのかな希望も見いだすことができるはずだ。