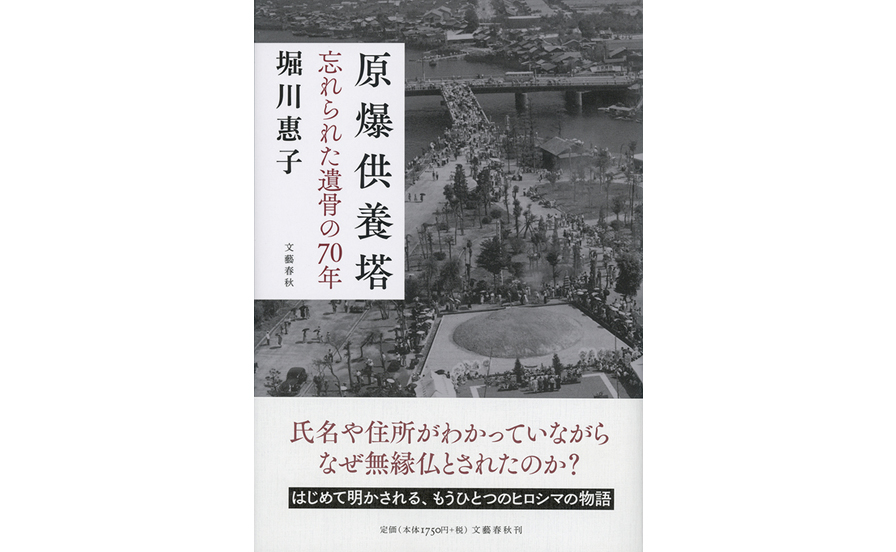取材アクセスを失うことを怯えて報道の自由を放棄?
参院選が間近だ。元最高裁長官・判事や憲法学者がこぞって違憲と疑義を表明し、菅官房長官が「合憲だとする著名な憲法学者もたくさんいる」と大見得切ったにもかかわらずたった3人の名前しか挙げられなかった安保関連法が施行した後の国政選挙だが、政権支持率はさして下がらない。SNS上で安倍政権批判に「いいね!」をしあって安心したくなるが、どうも情勢は違う。
一私人の発信よりも、やはり報道機関に期待したい。報道の自由は、憲法21条の表現の自由より派生する知る権利を充足させるために重要な役割を果たすことになるので、憲法21条より保障される。憲法の入門で必ず学ぶことだ。権力から独立した報道機関が権力を監視し、チェックし、それを市民に教えてくれる。市民は報道によって政策の問題点を知り、批判し、異を唱えることができる。それができるかできないかが、民主主義国家と全体主義国家の根本的な違いである。ところが、民主主義国家であるはずの日本は、国境なき記者団(RWB)が発表した2016年のランキングで180カ国・地域中、72位。2010年11位だったのに、2014年59位、2015年61と年々順位を下げている。
いったいどういうことだろうか。日本取材歴20年のニューヨーク・タイムズ前支局長のマーティン・ファクラー氏の『安倍政権にひれ伏す日本のメディア』(双葉社、2016年)には、第二次安倍政権誕生以降の報道機関の目を覆わんばかりの腰砕け状態が詳細に描かれており、ぼんやりランキングの数字の変化を眺めていてはいられないと、焦燥感にかられる。
国家による統制へのメディアの危機感は乏しい。高市早苗総務相が今年(2016年)2月、放送局が「政治的な公平性を欠く」放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条を理由に、電波76条に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。この「電波停止発言」にはさすがに言論統制につながる等批判が起きた(たとえば、毎日新聞2016年2月18日夕刊「特集ワイド 高市氏の「停波」発言 ホントの怖さ」)。しかし、民主主義の根幹を揺るがしかねない発言をした高市総務相へ辞任を求める声は小さく、何事もなかったように大臣の椅子に座り続けている。民主党政権時代、福島第一原発事故後、同原発周辺を視察した大臣が「残念ながら(略)死のまちというかたちだった」と述べたことで集中砲火を浴び、辞任においやられたことは記憶されているだろうか。そのような状態になったことを喜んでいるのではなく、残念に思うということなのに、あのときのメディアの喧噪は何だったのだ。あの当時の猛烈なバッシングを想起すれば、民主主義の根幹にダメージを与える国家の介入発言へのメディアの反応のぼんやりさ加減は際立つ。
安倍政権のメディアへの統制への志向は、高市総務相発言のような露骨なかたちであらわれるだけでなく、もっとにわかには目につかない、巧みなかたちで浸透している。権力と癒着した報道機関同士、報道機関内部での統制によるのだ。具体的には、調査報道ではなく、「官邸への取材」(=官邸から提供される情報の受け売り)を自らの仕事と考える記者クラブ所属の記者たちは、官邸への取材アクセスが制限されたり切られたりすることを危惧する。そこで、たとえば、テレビ朝日の政治部記者が、同テレビの「報道ステーション」のスタッフに、「菅官房長官はオマエのところの番組についてここまで文句を言っているぞ」とクレームをつける。「原発再稼働問題についてこういうことを言えば官邸が怒る。だから事前に偏った発言ができないようにチェックをいれるべきだ」という意図をあからさまにして。表立って「要望書」を送りつけたり、裏から官房長官や官房副長官のスタッフが直接電話をかけたりもするほか、仲間であるはずのテレビ局の人間も官邸の味方につける。陰に陽に真綿で首を絞めるように圧力が加えられ、報道ステーションは自由な言論を展開できなくなってしまった、とファクラーは嘆息する。
海外メディアへの幼稚な対応
権力への取材アクセスが制限されたり切られたりすることを恐れるべきではない。ファクラーは、安倍首相に一度も単独インタビューができなかった。また、ファクラーの記事に、在ニューヨークの領事館職員がニューヨーク・タイムズ本社に抗議にきたという。本社は、「オマエは何をやっているのだ」と非難するのではなく、「官邸が言うことを鵜呑みにしなかったわけだな。プレッシャーに負けずに良くやった」と応援してくれたという。「政権に媚びた報道をし、覚えがめでたいメディアに成り下がるくらいなら、取材ルートなど遮断されたほうがよほどマシだ」(33頁)等、いくつも赤線をひいて、安倍首相と夜の会食を繰り返すメディア幹部に本書を寄贈したくなる。
ファクラーとともに、外務省の海外メディアへの対応の幼稚さに驚く。彼らは、海外メディアの記者について「この人たちは日本の敵」「この人たちは日本の味方」といった安直な見方しかしていなかったという。東京支局長として永田町の首相官邸の国際報道官(外務省からの出向者)に挨拶をした際、猛烈な勢いで前支局長が政権を批判したことについて難詰され、そればかりでなく、「もし官邸から取材の協力がほしければ、前支局長の記事を批判し、自分は前支局長とは違う報道をするという旨を文書で提出するように」と言われた(!)。その言葉は、ファクラーにとって、驚きでもあり、懐かしいものでもあった。AP通信の記者として中国にいた際に、当局から言われた言葉と同じだと。そう国際報道官に伝えると、「いや違います」と慌てていたという。とはいえ、ファクラーが安倍首相に単独インタビューする機会が一度もなかったのは、「誓約書」を出さなかったためだろうか…。
国内メディアと同様にはあしらえない海外メディアの記者に対する日本政府の幼稚な対応に比べて、韓国政府(少なくとも著者が仕事をしていた李明博政権時代)はもっと洗練された対応をする。政府を批判する記事を書いたファクラーを恫喝するようなことはしない。「我々からすると、前回の記事には××という問題点がありました。」として、ディープな取材源を紹介する。そもそも、メディア対応担当者に、メディアを知らない外務省からの出向者などあてず、メディアを熟知したインテリジェンスのプロに担当させる。彼らは、行き当たりばったりに「反日」(!)などと攻撃するのではなく、「イメージ外交」を重視し、積極的かつ戦略的に海外メディアにアプローチする。韓国だけではなく、各国が国益を考えてやっていることだ。子どもっぽいやり方よりそのほうがずっと国益にかなうというのに、なんたる愚かなことか…。めまいがする。
朝日新聞バッシングで報道機関は皆敗者に
陰に陽に圧力を加えてくる巨大な政治権力に対抗するには、報道機関内部の、そして報道機関の団結が必要だ。しかし、2014年の吉田証言報道取り消し、吉田調書報道取り消しを端緒とした朝日新聞バッシングでは、まるでその正反対のことが起きた。
ファクラーは、朝日新聞の報道の意義と問題点を丁寧にフォローした上で、吉田調書を隠蔽した政府を批判すべき産経新聞や読売新聞が批判の矛先をまっすぐに朝日新聞に向けたことに疑問を呈する。彼らは絶妙なタイミングで吉田調書の全文を入手した(経緯からして、出元は官邸周辺と考えるのが自然…)。安倍政権の手となり足となっているかのような彼らは、ジャーナリズムとしてのピントがズレすぎている。
さらには吉田証言については朝日新聞が単独で報道してきたわけではない。猛烈な朝日バッシングをした産経新聞他の全国紙、通信社、地方紙、テレビ局が報道してきた。意図的に誤報したわけでもない。19世紀に正しいと思われたニュートン物理学を20世紀に入ってアインシュタインの相対性理論が発表されたからといって、ニュートンに関する記事をニューヨーク・タイムズがすべて取り消すだろうか。冥王星が2006年に惑星ではなく準惑星となったからと行って、ニューヨーク・タイムズがそれ以前の冥王星は惑星と書いている記事をすべて取り消すだろうか。ただ単に、その時点の情報をアップデートすればいいただけのことだ。ところが河野談話を見直そうとする動きの中、同談話をひっくり返せないことに苛立つ勢力は、同じく敵視する朝日新聞にプレッシャーを加え、取り消し記事を書かせたあげく、猛攻撃した。
ファクラーとともに、一般的には朝日新聞と論調が近いイメージがあった毎日新聞をも朝日新聞バッシングに荷担したことに、私も驚いた。本書で取り上げられた14年9月11日の小川一編集編成局長の署名入りの記述もある「国際社会に誤解広める」と大見出しがつけられた毎日新聞の朝日批判記事は非常に印象に残っている(私は、編集編成局長に対し記事を批判する手紙を送ったと記憶している)。この毎日新聞の記事に、ワシントンで取材を受けた4人の専門家が怒り、長文の抗議声明を発表したことは、本著を読まなければ知らなかった。第一次安倍政権時代の07年6月、アメリカで日系人のマイク・ホンダ下院議員が「日本政府の慰安婦に対する謝罪要求決議案」を可決させている。毎日新聞の記者は、この決議案の草稿を書いた議員の元スタッフ4人に取材した。記者に決議案と朝日新聞との関係を問われた4人は、そもそも朝日新聞を読んでいない等、全く関係ないと答えた。しかし、毎日新聞は、彼らのインタビューを反映させず、全く異なる記事にまとめ、小川編集編成局長は、「朝日新聞の一連の報道で、「吉田証言」のような軍の組織的強制連行があったとの誤解が世界に拡散したとされる…」と書いた。全くのミスリードである。
朝日新聞の「慰安婦報道について検証する第三者委員会」の林香里教授による「データから見る「慰安婦」問題の国際報道状況」は日本、韓国、欧米の新聞の「慰安婦」報道を洗いざらい調べた貴重なレポートである。その結果、そもそも欧米では「慰安婦」問題はほとんどニュースになってこなかったこと、韓国でも日本より少なく、少ないながら増えたのは、第一次安倍政権の時期及び第二次安倍政権の時期だということが判明した。すなわち、安倍政権がやたらと言挙げして政治的に利用した結果なのである。そもそも、国際社会では朝日新聞を誰も読んでもいない。首相から草の根のネトウヨ、さらにはリベラルな知識人と思われた人すら、「朝日新聞が国際社会における日本人の名誉を傷つけ、日韓関係に影響を与えた」という根拠のない言説を口にするようになったことに、うろたえる。
毎日新聞が安倍政権の主張に沿うような誤った言説をなぜふりまいたのか、記者がねじ曲げたのか、何か上層部の意向が働いたのか。朝日のように攻撃を受けたくない、官邸への取材アクセスを開いてもらいたいのか、とファクラーは疑う。しかし、朝日が受けた攻撃を、明日は毎日が受ける可能性もある。今は政権寄りで安全圏にいると錯覚している読売産経だってわからない。いろいろと問題のあるアメリカだが、それでも右派だろうと左派だろうと、ひとつの報道機関が権力に攻撃されたら、左右問わず報道の自由のために結束して抗議する。会社の垣根を超え、権力と対峙して朝日新聞を擁護しようとしないジャーナリズム精神の欠落。報道の自由をみすみす放棄するメディアの危機は、私たちの危機でもある。権力が知らせたい情報だけ鵜呑みにするのではなく、権力が市民に知らせたくない情報をも知ることができなければ、権力をチェックすることが不可能なのだ。
朝日新聞を擁護しないどころか、攻撃し、商機とばかりに「朝日新聞が日本の名誉をどれだけ傷つけたか」を強調するパンフレットを大量配布した読売新聞は、朝日新聞の読者を奪い取ることに成功せず、朝日新聞以上に購読数を減少させた。見苦しい朝日新聞叩きは、新聞全体への不信感を強めたということになる。ざまあみろ、と言っている場合ではない。ジャーナリズムの劣化は止まらず、民主主義の根幹が崩れていくだけだ。
ディストピアを招来しないために
ずいぶん長くなってしまったが、本著には元朝日新聞記者の植村隆氏や北海道猿払村役場へのネット右翼の攻撃とそれぞれの孤立無援状態、「世論操作」のような世論調査など、危機的な日本の言論状況をあぶり出しており、是非読んでほしい。
終章には、希望を抱ける様々な動きが紹介されている。良質な調査報道(朝日新聞バッシングが潰してしまった…)を目指す大学の研究所、「偏っていますが、何か」と潔く言い切る神奈川新聞、在京メディアと完全に毛色が異なり在野精神を堅持する沖縄二紙など地方紙の奮闘、など。しかし、圧倒的な流れに比べて、なんと微かなきざし…。
私たちにできることは何か。このようなメディアを「マスゴミ」と誹ることはたやすい。新聞の購読を打ち切ることも、テレビをつけないこともたやすい。しかし、それで社会が変わるわけでもない。
岡田憲治著『言葉が足りないとサルになる 現代日本と言語力』(亜紀書房、2010年)=岡田憲治 のメッセージを思い出す。政治とは、言葉で世界を切り分けて「これが現実」と認識させる、人間の営み。とすれば、言葉足らずを放置しておくと、誰かにとって都合のよい「現実」の中に多様な現実が封じこまれてしまう。幼児語(「マスゴミ」もしかり)ばかり使っていると、現実をコントロールする者たちの解釈に封じ込まれてしまう。オーウェルの逆ユートピア小説『1984年』のように。
悲観的になりすぎて口をつぐんでいても、ディストピアを招来する。ならば楽観的になろう。「自分の利益を超えて私たちの利益を念頭に、言葉を発していこうという勇気を奮い起こしている少数の人々」は必ずいる。そんな勇気がなければ、その人々を応援する。諸般の事情でおおっぴらには応援できなくても、陰ながらでもその人々を孤立させない努力を淡々とする。特別な能力がなくても、それぞれができることはある、という岡田前掲書のくだりに、涙する。「脱ポチ宣言」(=政権にかわいい犬になるな)の紙を掲げていた朝日新聞特別報道部を他の報道機関判しつつも応援すべきだったのに、あれだけ叩いて潰してしまった…。私たちも便乗したり、傍観したりしてしまった…。その痛手は大きい。おっとまた暗くなる。反省し、賢明になろう。そして、権力を監視するジャーナリズムを応援し、自分でもできれば発信しよう、小さい声でも。
ファクラーがこう書いていてくれる。「日本で最もジャーナリストらしい活動をしているのは、記者ではなく弁護士ではないだろうか。「人権派弁護士」と呼ばれる人たちは、「国策捜査」だろうが冤罪事件だろうがものともせず、検察や裁判所と真っ向勝負で戦っている。彼らには個人の価値基準を超える法律、憲法という強いアイデンティティがある」(151頁)。うおおおお…。いろいろいますけどね、この業界も…、いや人はともかく自分はどうか…。汗顔の至り、ではなく、そうですとも、ええっ、と胸を張って言いたい。