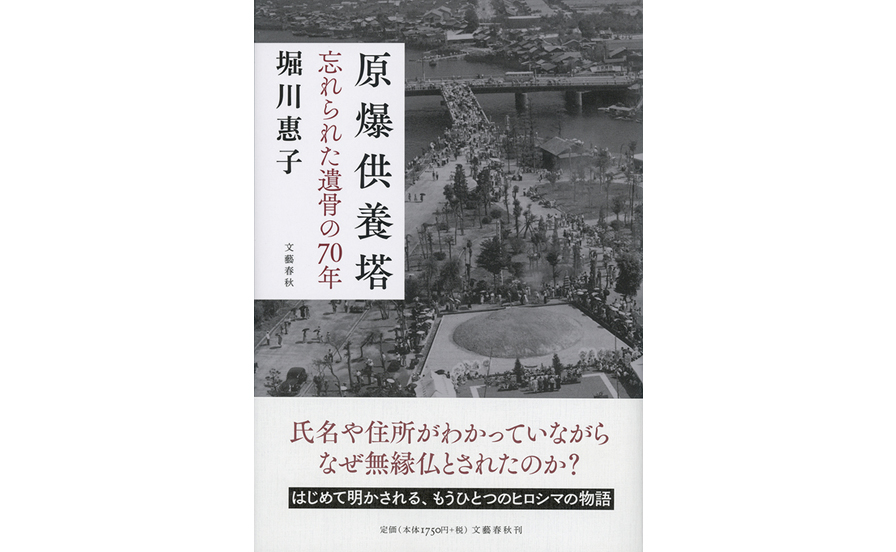「おなかいっぱい、幸せ!」のコツを教えてくれたカツ代さん
手当たり次第読んでいるつもりだが、やはり好きなジャンルというのはいくつかに絞られてしまう。そのうちのひとつが料理のレシピ本やエッセイ本だ。自慢じゃないが、料理はさして好きではない。読みまくってもほとんど実践しない。でも、「おなかいっぱい、幸せ~!」、そんな気持ちのおすそ分けをいただけるから、料理本が好きなのかもしれない。
ほとんど実践せずと言ったが、そんな私でもそのレシピを実際に参考にした数少ない料理家の筆頭は、やはり小林カツ代さんだろう。肉じゃがなど、彼女のレシピはいったいいくつレジェンドになっているだろうか。
今年まとめられた『おなかがすく話』河出文庫は、1996年の単行本を底本に、本田明子氏の「弟子が語る、その後の話」と本田氏及び小林カツ代キッチンスタジオによるレシピをあらたに増補したものである。カツ代さん自身の子育て真っ最中の日々がそれほど遠くなかった時期に書かれたらしく、実感をこめて、「時間がないからできるだけしなくていい手間は省いて、なるべく手早く、家族のために美味しいものをつくりたい」という母親たちに、「こうすれば大丈夫!」と実際的な提案を続々としてくれる。晩年にはさらにジェンダーバイアスに意識的になり、「母親として家族のために」色を抑え、男でも女でも、家族がいてもいなくても、美味しいものをちゃちゃっと作って食べるって素敵だね、ということを、説教臭くなく楽しく読ませるようになった。『小林カツ代のお料理入門』文春新書はその時期の本。シニア向けの料理本には、「ひとりでも健康で長生きするために」マジメに作らなくてはと寂寥感が漂うものがあるが、本著は違う。「ひとりすき焼き」とか、「炊き上がったごはんの一番おいしいところである真ん中の上のところを食べる」とか、ひとりだからこそ美味しい!楽しい!とわくわくさせてくれる。
『おなかがすく話』にも、私たちを固定観念から自由にしてくれる箇所が随所にある。アメリカ人の女性がランチパーティにごちそうしてくれたポークビーンズが美味しかった、それはカン詰めで、そのまま温めるのではなく、オーブンでグリルして市販のマスタードを小さじ1ぱい加える、というコツに目を輝かす、等々。カツ代さんは、「市販のものに頼るな、手間暇かけたほうが美味しいに決まっている、それぞ愛情」といった「道徳的料理家言説」から、主婦たちを解き放ってくれたのだ。
カツ代さんは、「九条の会」に賛同のメッセージを寄せている。選択的夫婦別姓等民法改正を求めるmネット民法改正情報ネットワークの呼びかけ人でもあった。「弟子が語る、その後の話」には、「(師匠は)いつの日も、若い人や子どもたちには平和で楽しいクリスマスでありますようにと願い、平和への思いがどんどん強くなっていった」とある。「食に携わる人間は、つねに政治に敏感であること」。「え?」と飛躍を感じる人もいるだろうか。
平和であってこその食べ物の話
小林カツ代さんの言葉に飛躍も何もないことは、斎藤美奈子さんの『戦下のレシピ 太平洋戦争下の食を知る』岩波現代文庫を読めばわかる。本著は、敗戦の年まで生き残った数少ない婦人雑誌(『婦人之友』『主婦之友』『婦人倶楽部』)が戦下でも説き続けた料理や食の工夫の引用から、「銃後の暮らし」を描き出す。悲惨さに圧倒されそうになるが、今も雑誌は読者の生活ありのままというよりも「ちょっとワンランク上の憧れ生活」であることからすると、実際の人々の生活はいったい…と、胸が苦しくなる。
日中戦争前の昭和のモダンな食文化から、日中戦争開始後の大東亜共栄圏の影、太平洋戦争下配給時代、空襲下の決選非常食、敗戦後の焼け跡の、レシピという以前に食料の圧倒的不足でのサバイバルまで。数年単位で刻々と時代の空気が変わり、華やかさがいつの間にか薄れ、飢えと隣り合わせの破滅的な緊張感の張りつめたものへと一挙に転じていくのが恐ろしい。
まずは、昭和初期。女学校でのお嬢様・奥様がクッキングリーダーとしてハイカラな本格西洋料理を紹介した。「米ばっかり+漬物」程度の食生活に、突如栄養学の知識を伝授したのはこの時期の婦人雑誌だ。また、それまで、農家や商家では女性も大事な労働力、炊事なんかに時間は割けなかった。一方、裕福な家庭では炊事は使用人の仕事。いずれにせよ、愛情と料理の間に何か関係があるとは思われていなかった。ところが婦人雑誌は、「手作りの料理は母の愛情のあかし」という「家庭料理イデオロギー」と呼ぶべきものを広める。おお、小林カツ代さんが私たちを解き放ってくれようとした「道徳的料理家言説」はこんな時代からだったのか。とはいえ、この時期のハイカラなレシピを読むのは楽しい。料理エッセイ本名著ベストテンなどあれば必ず入る石井好子さんの『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』河出文庫に「バター」ではなく「バタ」と書いてあるのが美味しそうで好きなのだが、なんだ、その表記は石井さんオリジナルではなくこの時代の婦人雑誌はそう記載していたんだなど、他愛もない気づきも楽しい。
しかし楽しさは一気に減じていく。日中戦争が始まった1937年ころから、婦人雑誌も戦争気分を盛り上げる勇ましい記事を載せるようになる。「伸びゆく日本!大東亜建設の時代を担うお坊ちゃん方のために」という「端午のお節句料理」といった戦意高揚料理は、手間がかかるわりに美味しさは微妙だったのでは。「鉄兜マッシュ」「軍艦サラダ」「飛行機メンチボール」。これは何か見覚えが…。あ、あれだ。キャラ弁だ。やたらとこまかい細工で「母の愛」を示そうというあたり、キャラ弁と全く同じ。でも、主婦は忙しかった。そこまで凝った軍国料理はそうはなかったらしい。
太平洋戦争が始まる前にも既に米不足が問題となり、官民あげての「節米ブーム」。その一環として推奨された「毎月興亜奉公日毎の興亜建国パン」など、小麦粉に大豆の粉、海藻の粉、魚粉、野菜くずなどを混ぜた、家畜の餌かというもの。「節米」のため、うどんを米代わりに工夫した奇天烈なレシピもある。うどんはうどんとして食べればいいではないかとツッコミどころ多々。このあたりも、「ああ今も大真面目にこんな場当たり的なことが沸き起こりそう…」という気がしないだろうか。
1941年に太平洋戦争が始まってから、婦人雑誌も俄然緊張感を増す。配給に1日2時間~4時間半(!)行列、というだけでも、想像を絶する。その上、売り惜しみされたり、量を誤魔化されたりもした。量も少なく、質も粗悪だった。そんな時代に婦人雑誌は、少しの肉を、魚を、野菜を、どのように「多く」するか(生大豆粉や野菜を混ぜ込み増量する等)の工夫を説き続けた。このころ、昭和初期に栄養学的な知識が披露されるようになってから定着した「大さじ〇杯」といった分量の記載がなくなる。素材が自由に手に入らなくなった時代には、そんな記載は合わないのだ。
本土空襲が始まった1944年以降は、レシピではなく、議員や軍人が説く「都市住民は一人残らずが戦闘員」といった無茶な精神訓が掲載されるようになる。空襲でおちおち寝ていられない。配給の行列に並ぶほか、調理の時間も大変だ。一応食べられるようにするために時間が異様にかかる。玄米を棒でついて精米する、雑穀を石臼でひく、ほうろくで炒らなければいけない食材がある、そこかしこでかぼちゃやさつまいもを育て、干しいもにする。量は少なく、食感や歯ごたえもなく(増量のため粉にしたので)、調味料不足で味もなく、食材の質も悪い。燃料もなく、あったかくも冷たくもない。日々の食事も足りないのに、空襲時の「防空食」の準備も必要だ。焼け跡生活を前提に「主婦自身の手で道端の土を掘ってかまどを作りましょう」と古代の野戦場並みのノウハウも掲載された。炊事以外にも縫い物、繕い物、さらには隣組、婦人会の仕事もあった。読者である主婦たちは、いかに疲れ切っていたのだろうか。
「婦人之友」に掲載された牧野良三衆議院議員の説教中には「主婦の力を積極的な戦力として活用」といったフレーズがある。これほど疲れ切っていてもまだ「活用」しようとしたのか、とめまいがする。しかし、これまた「遠い昔」の気がしない。男女格差がありながら仕事をこなし、育児家事も専ら担い、寝不足で疲れた女性たち。それでもまだ「活用」だの「活躍」しろとの標語が躍る現在のこの空気感と、当時はさほど違わないのかもしれない。
食べ物は人々の健康。いやそれどころか生命をつなぐため必須のもの。それなのに、ここまで食がおろそかにされたということから、戦下で、私たちの尊厳は全く度外視されることを悟らざるを得ない。非常事態になったときに、私たちは無力で、その環境を根本から変えることはできず、必死にサバイバルするよう努力するしかない(この点も、福島第一原発後、放射能汚染に怯えながらもこの国で生きていかざるを得ない私たちには、リアルではないだろうか)。斎藤さんが後書きで書く通り、本著から、「耐えること、我慢することの尊さ」を学ぶべきではない。私たちの食が、そして尊厳が損なわれないように、政治や国家に向き合わなければならないと悟るべきだろう。
『戦下のレシピ』を読んで一層、カツ代さんがお弟子さんたちに繰り返し「政治に敏感であれ」と説いたことの意味が腑に落ちる。『おなかがすく話』の2014年衆院選の日に書かれた「解説」の次の一文は、元最高裁長官も主だった憲法学者もこぞって違憲と指摘する安全保障関連法が成立した(成立にも疑義が指摘されている)現在、なお一層胸に迫るものがある。「師匠が私たち弟子に最も伝えたかったことは、意外かもしれませんが、レシピや技術ではありませんでした。平和なくして食は語れず。世界中の子どもたちがおなかいっぱい食べられること。おなかがすいた人がいないこと。そのために食の現場を通して言い続けること、訴えていくことー」。