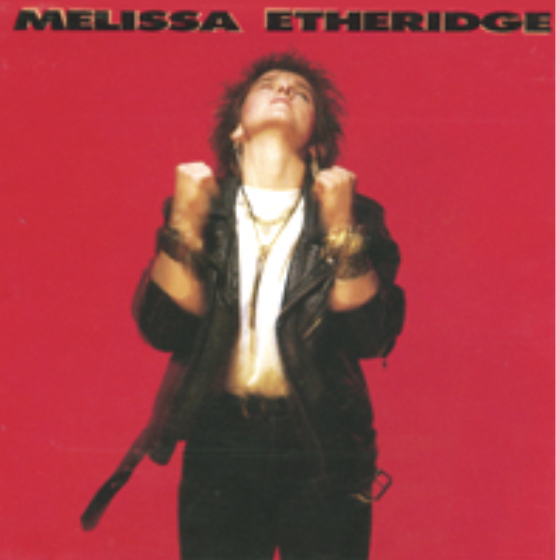日本のポピュラー音楽がいつしかJ-POPとよばれるようになったころから、私はいわゆるJ-POPといわれるような音楽をほとんど聞かなくなってしまった。だからCoocoというミュージシャンは知っていたけれど(人気があり有名なことも)、どのような歌を歌う人なのか、どんな人なのか、この映画を観るまで何も知らなかった。この映画というのは2008年につくられた『大丈夫であるように―Cooco 終わらない旅―』。『そして父になる』の是枝裕和監督、そしてチラシの解説にあった六ケ所村と沖縄米軍基地とジュゴン、この言葉が気がかりで8月下旬から2週間緊急上映された映画館へ足を運んだ。
映画はCoccoの『想い事。』というタイトルのエッセイが刊行された後の日本国内ライブツアーを追ったトキュメンタリ―だ。1977年那覇市に生まれたCoccoの、沖縄での家族やおばぁとの交流、インタビューを軸に各都市でのライブ映像が都市ごとに表情を変えふんだんに映し出される。このツアーのきっかけとなった青森県六ケ所村からのファンレター。核再生処理施設を擁するこの村のファンの少女は「それでも私はこの村が大好きなのです」と手紙に綴る。この少女の痛みを、Coccoは米軍基地を擁して混迷する沖縄、そこで悩み苦しむ自分自身の痛みと重ね合わせ、六ケ所村を訪れる。青森でのコンサートでこの六ケ所村の少女の手紙をステージで読み、この手紙を貰うまで沖縄と同じように、日本という国から被る歪みの犠牲となる土地が存在することを知らなかった、皆にこのことを知ってほしいとステージから投げかける。
Coccoの歌には生きとし生けるものたちへ、生き続けて…という想いが込められている。「強く儚い者たち」という曲は、人はとても弱いものよ、そしてまたとても強いものよ、と歌う。弱いものへ限りなく寄り添いながらも、弱きものであるがゆえに強く、強くなって生きろ、生き続けろ。そこに必要なエネルギーをCoccoの歌は宿している。
激しく掻き鳴らされるギターをバックに自己の壁をぶち壊すような「雲路の果て」、疾走するような爽快感で駆け抜ける「樹海の糸」、シネイド・オコナーを想わせるような息遣いでのびやかなヴォーカルがかっこいい「音速パンチ」、エイサーを盛り込み沖縄の魂(こころ)を散りばめる「ニライカナイ」。
映画『大丈夫であるように…』の沖縄宜野湾コンベンションセンターでのライブシーンでは、ひめゆりのおばぁたちが客席にいた。Coccoのエッセイ『想い事。』に「ひめゆりの風」という章がある。
〈いつかまたひめゆりの風が吹いたら 私は歌をうたおうと想った。もっと耳を澄ませて もっと心を傾けて やるべきことをひとつずつ。いつか辿りつけるように。〉
Coccoは多くのひめゆりのおばぁたちからたくさんの話を聞き交流を深めたという。Coccoの曲に込められた“生きろ”というメッセージは戦禍を生き延びてきたこのおばぁたちの生きてきたエネルギーと一線上でつながっていく。
豊かな海、森、草花、海のいきものたち、動物たち、それらと戯れて育ってきたCoccoにとって、ジュゴンやサンゴが殺されていく破壊は自らの身体を押しつぶされるような痛みと感じる想いだろう。「ジュゴンの見える丘に」という曲ではCoccoのそんな切ない祈りを感じずにはいられない。
数か月前に公開された辺野古で米軍基地建設に抵抗する様を追った三上智恵監督のドキュメンタリー映画『戦場ぬ止み』。ナレーションはCoccoだった。映画に登場するキャンプシュワブのメインゲートの最前線で体を張って戦うおばぁ文子さん。15歳の時、島が戦場となり糸満の壕で米兵の投げた手榴弾で左半身に大火傷を負いながらも生き延び、笑顔を絶やさない文子さんが「(わたしは)ぶれてない」という。音楽にとどまらないCoccoの向かう表現世界もまたぶれていない、と私は想う。
ちょぴり遅すぎたCoccoとの遭遇。昨年リリースされたアルバム『プランC』のダイナックなポップサウンドに身を委ね、これからわくわくしながら彼女の足取りを追っていくよ!