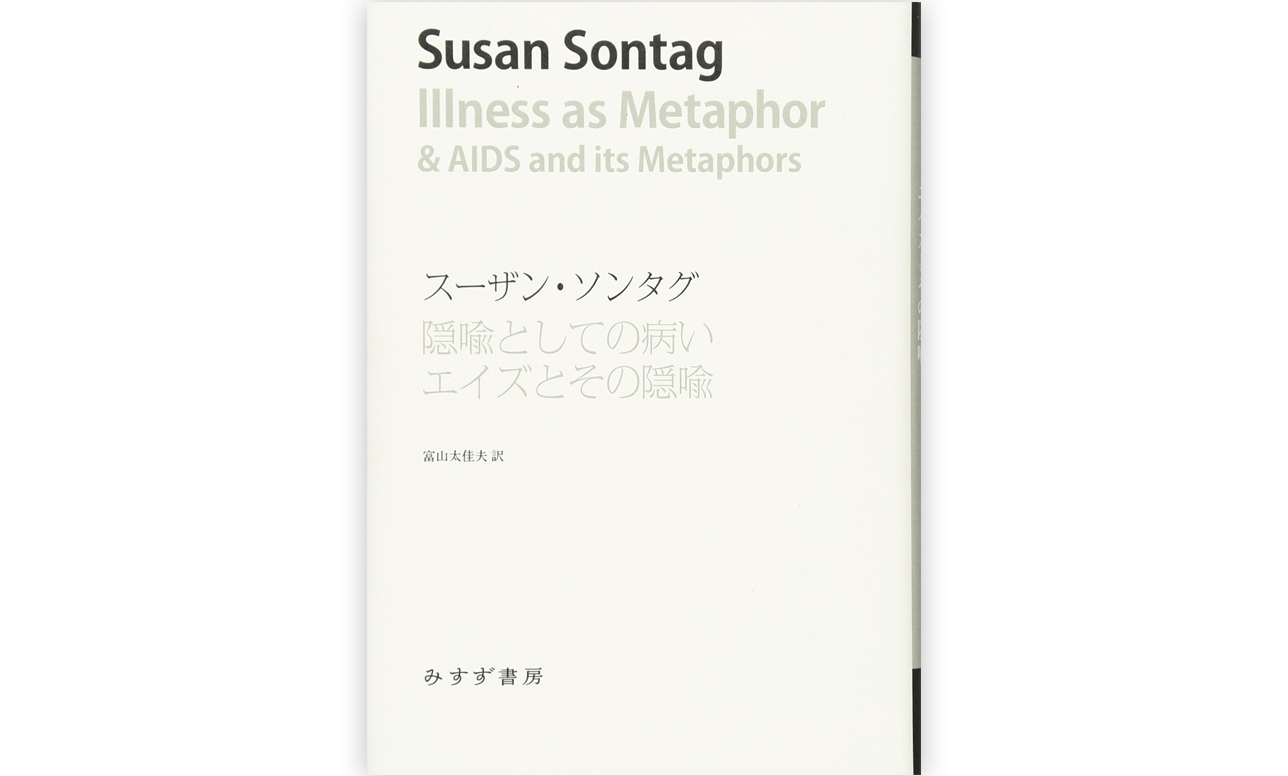好きな作家や映画監督、俳優女優、ミュージシャンの作品をすべて見ていない、聴いていない人に、「○○が好き」と言う資格はない…。そうおっしゃる方はいますか? あたくしは、そういう人たちに「ダメな受け手」と判断されてしまうタイプです。オールタイム・フェイバリット女優、たぶんこの先も「あたくしの中の第1位」の座を譲ることはないだろうジャンヌ・モローの出演映画すら、全部見てはいません(日本公開していないものもたくさんあるの、と自己正当化は当然いたします)。
その大前提で言わせていただくなら、観賞した作品だけをもって「好き」という作家は本当にたくさんいます。漫画家にももちろんいるわ。その中の一人が、東村アキコ。『ママはテンパリスト』『海月姫』『かくかくしかじか』、そして最近加わった『東京タラレバ娘』と、さらに「モーニングツー」という雑誌で新しく始まった『ヒモザイル』しか読んでいない、極めて不実なファンではありますが、好きなのです。
東村アキコの作品にほとばしる、あの疾走感やリズムの、どうしようもなく「今」な感じ。あれはなんと言うか、時代に選ばれてしまった人のものだなあと思います。それは90年代中盤には岡崎京子のものであり、2000年をまたぐあたりには安野モヨコのものでした。選ばれてしまった人は、自分の何が選ばれたのか、よくわからないまま神輿に乗せられることになる。まあ、作品を一読して、「そもそも異常なほど勘が鋭い」のがわかる岡崎京子はもしかしたらうっすらそれを理解していたかもしれませんが。
さて、話は急に変わりますが、人が生きていく、成長していくうえで、善きにつけ悪しきにつけ大きな影響を与えるのは、どんな人でしょうか。あたくしにとっては、それが「それまでの自分にこびりついた価値観や固定概念を壊す人」と「自分自身のはるか先を行き、かつ指標となってくれる人」でした。便宜的に前者を「クラッシャー」、後者を「メンター」と呼ばせていただきます(心理学的にもっと正しい表現があるかもしれません)が、いい漫画、面白い漫画にも、主人公にそういった影響を与える登場人物が出てくるものが非常に多い。東村アキコの既読の作品でいえば『ママはテンパリスト』はクラッシャーとしての息子・ごっちゃん。『海月姫』ではクラッシャーもメンターも、政治家の息子でありながらレールを拒否してファッションの世界に行こうとする蔵之介。自伝的作品である『かくかくしかじか』では型破りな絵の先生・日高が、東村アキコ自身のクラッシャー&メンター。そして『東京タラレバ娘』では、たぶん恋人を亡くしたという設定の、新進イケメンモデル・キー(東村が好きであろう韓流スターの影響がモロに出ているビジュアルなのも印象的)がクラッシャー80%、メンター20%(3巻終了時点。あたくし測定)。です。ものすごく乱暴にくくってしまうと、東村アキコの作品においては、クラッシャーもメンターもオトコが担っているわけです(ノンケ女装1人を含む)。
あたくしがほかに好きな漫画家の作品で、これを当てはめてみますと、槇村さとるの『おいしい関係』『Real Clothes』では、のちに恋人になるオトコが最初にクラッシャーになり、後半ではお互いに影響を与え合う存在になりますが、それ以上に強大な、絶対的なメンター(時々クラッシャー)として君臨するのは、『おいしい関係』では「千代ばあ」こと織田千代、『Real Clothes』においては「美姫さま」こと神保美姫。どちらも主人公よりかなり年上のオンナです。ちなみに『イマジン』ではクラッシャーもメンターも、母親の美津子が担っていました。
もう一人、大好きな吉田秋生が、超久しぶりに「リアルな人間」を描いた『海街diary』においては、「クラッシャー」「メンター」のような強烈な人間を登場させない代わりに、主人公の4人姉妹に影響を与えるのは、姉妹同士を除けば、主に学校とか勤め先の仲間や、食堂の主人(女主人が亡くなり、風来坊のような男主人に変わる)になる。その「男女が混交している」度合いは、「作者が非常に注意深く配合しているのでは」と思うほどの半々っぷりなのよ、少なくともあたくしが受け取る限りでは。
「選ばれてしまった作家」で名前を出した安野モヨコの『ハッピー・マニア』では、主人公シゲタのメンターは親友のフクちゃん、岡崎京子の漫画は、あたくしが読んだ限りでは一貫して「クラッシャーとかメンターとか、そんなことをしてくれる人などいるはずがない」というトーンでした。
とは言え、あたくしの勝手な印象をもってして、「東村アキコは結局『オンナに影響を与えるのはオトコと相場は決まってる』と思っている」と言い切るのは野暮の骨頂というものでしょう。『東京タラレバ娘』において、イケメンモデルのキーが話すことは、実はこれすべて、東村アキコ自身が独身のアラサーに向けて出すダメ出しであることがわかる(っていうか、本人があとがきで描いている)わけだし。むしろあたくしは、「同世代女子(あえてここは『女子』と言います)に向けた、ぶつけられるほうは大流血必至のダメ出しを、どうしてオトコの登場人物に言わせるのか」というあたりで、東村アキコの恐れ(意識的であれ無意識的であれ)を感じずにはいられないのです。
それを痛感したのが、『ヒモザイル』の第1回。「内容をざっとご紹介するため、どんな言葉を使えばいいか」と、ここ3週間くらい折にふれ考えていましたが、なんと講談社が第1話をネットで無料公開してくれていました。
http://www.moae.jp/comic/himoxile
お読みくださいました? いや、なかなか凄いでしょ? 「オヤジ社長が自分の下で働いている女性社員や女性スタッフにコレをやったらセクハラ&パワハラのダブルコンボ」とか、「人間関係が豊かそうに見えて、参謀役として招集できたのが、プライベートで親交のある仕事のできるイケメンではなく、『ああ、仕事上、部数を持ってる作家の命令は断れないよねえ』と容易に想像つくようなオトコ3人(しかも、ルックス的には彼らの後ろの壁に掛けられているハンガーのほうが上とまで言われるオトコ)だけだった悲哀」とか、「登場する独身バリキャリが『夫』として欲しいのは、『自分の代わりに家事をしてくれる夢追い人のオトコ』ではなく『家事を外注すること、ハウスキーパーを雇うことを快諾する余裕がある(それ用の出費をすべて自分の稼ぎから出すことをOKする、という意味の)オトコ』じゃないかしら」とか、「自分の人生の切り売りを作品にするのはOKだけど、他人の人生を使って『ドキュメント』(東村アキコ談)とか言っちゃうのはどうなの?」とか、「人の人生に上から目線で口出しをする前に、自分の名前しかクレジットされない作品のために身を削ってくれるアシスタントたちの待遇を、違う観点から考えてあげましょうよ」とか、「歯に衣着せず、痛快で面白い」とか、人によっていろいろな感想は出ると思いますよ。っていうか誰よ、「最後の意見だけとってつけたようにこのオカマは…」とか言ってるのは!? うふふ。
あたくしが何より印象的だったのは、オトコのアシスタントたち、友人の独身バリキャリたち、参謀として招いたオトコ3人に万遍なく失礼だった(バリキャリの友人たちに向かって「まーたあんたら女だけでこんな高い店来て…」と言うときの表情、友人たちの会話を聞きながら「いつも同じ話題でもう正直うんざりだ」と心の中でつぶやくときの表情、それぞれの画力が凄まじい)東村アキコが、唯一、それらをはるかに上回る勢いでオトコのアシスタントたちに失礼(というか、ほとんど非礼)だった、お金かかってそうで上品なルックスのママ友に、何も言い返せなかったことです。
自分の子どもを無償で快くあずかってくれた人たち、しかも子どもがその間、本当に楽しい時間を過ごすよう心を砕いてくれた人たちのことを、その機会をセッティングしてくれた人(東村)に「どうしよう。うちの子があんな風になったらどうしよう…」と言う母親が、「非礼区トップ当選」なのは誰の目から見ても明らかです(東村も、それを読者に感じてもらうように描いています)。しかし、東村はそのママ友に向かってブチ切れるでもなく苦言を呈するでもなく、かと言って「アシスタントが自分のネームを作れるはずの時間だったのに、こんな人のために使わせてしまった」と反省するでもなく、「どう考えてもあっちのほうが圧倒的に普通だ」「あの人は意地悪でそういうことを言ったんじゃない」とまで自らに言い聞かせ、何も言い返せなかった自分を正当化しにかかります。『かくかくしかじか』で、鬼のように恐ろしい日高先生にもタメ口を利き、ときには「無視」というカードまで切って、果敢に自分なりの意志を表明した東村アキコが、です。シングルマザーで子どもを育てるという苦労の中、ワーカホリックど真ん中の遮二無二ぶりで仕事の成功も手にし、現在は二度目の結婚もし、かつ、前出のママ友と経済的にはまったく同じ(むしろそれを上回る)ような生活レベルを自分にも子どもにも与えられるはずの東村アキコが、です。
「メンター」の姿をした鬼に対してでさえ通せるほどの自我を10代の頃から持ち合わせ、現在では経済的豊かさも手にした人間が、なぜ「受け取るだけ受け取って、なおも異常に失礼(これこそが人間関係において『下品』と呼ぶべき性格です)な人」、つまりは「メンター」としてはとことん不適格な人に、全面降伏してしまったのか。あたくしには、そのことが何よりも強い印象を残したのです。「ママ友の世界ってのは『子どもを人質にとられているのと同じ』って側面もあるのかしら」とも思いましたが、それが本当に心配だったら、そもそもあのママ友を「誰の目から見ても失礼な人」として登場させること自体しないと思いますしね…。
東村アキコがクラッシャー&メンターたる「鬼」よりも恐れているもの。東村自身の歩みを半ば力づくで決めてしまうもの。それは「女の幸せ」という名の圧力、それから、「『女の幸せ界』で、身も心もリラックス&ハッピーで生きることができ、『格下』と見た人間相手には自覚なく矢を放てる人たち…。そんな、東村にはほとんど別世界の生き物のように見える人間の、異常なまでの安定感」ではなかろうか(いみじくも東村は、ママ友を「こっち」ではなく「あっち」と表現している)。
そして東村が自分のどこを(実は)いちばん歯がゆく思っているのかといえば、「『女の幸せ界』で、どうにも居心地の悪い自分を持てあましている。そんな自分自身の往生際の悪さ」なのではなかろうか。
…と、ついつい、そんなことを考えてしまったわけですよ。と言うのも、まあ推定4人の読者の皆様もお分かりになると思いますが、人間ってのは往々にして、「自身のプライベートライフの幸と不幸、幸のほうを見ているときは、他人のプライベートライフを見るときも幸のほうを見る。あるいは様々な解釈を施して『自分自身が幸せなら、それがいちばんだよね』と『本気で』思う」ものだし、「自分の中に不幸やら煮え切らないものを見ている人は、他人のプライベートライフのそういう部分ばかりに目が行ったり、『ああ、アンタも(私と同じように)煮え切らないんだね』と解釈したがる」ものだからです。『東京タラレバ娘』は、煮え切らない独身アラサーをぶった斬ることのみで構成された作品だわね。「しかし」というか「だからこそ」というか、あたくしはあの作品の中に、煮え切らない自分をもまとめてぶった斬りたい東村アキコ自身の葛藤を(勝手に)見てとります。
先に申した通り、『東京タラレバ娘』の巻末のあとがきマンガで、東村アキコは「これは同世代のアラサーにむけて描いたもの」ということを明言しています。本編では、登場人物のキーや、酒の肴の大定番・レバーと鱈の白子を擬人化したキャラ(2つ合わせて「タラレバ」)に、けっこうザクザクくる毒舌を「愛ある説教」の形で吐かせていますが、同時にそのあとがきで、「私も2回結婚してる。でも、結婚なんて言うほどいいものじゃないんだけどね」と、(キーやタラレバの言葉ではなく)東村自身の言葉として書き記している。この葛藤は、そのまま「未婚の女たちから嫌われること」への恐れ、というか保険になっている。それが『ヒモザイル』では、「『女の幸せ』界で安定しまくっている同性」に対する恐れと、「我ながらナイスアイデアだと思うよ!」という、未婚の同性への保険となるのです。
「女とゲイを一緒にしないで」という、至極まっとうな異論が出るのは百も承知ですが、あたくしは『東京タラレバ娘』と『ヒモザイル』を並行して読みながら、いままでに会ってきた、そしていまでは連絡先も知らない何人かのゲイたちの顔を久しぶりに思い浮かべました。「同性婚」がまったく現実のものとして考えられていなかった時代に、「世間体があるから」とか「やっぱりゲイの世界なんて心もとない。結婚という形に入らないと自分の人生は安定しない」とか「いつまでもやってられない、こんなこと」とか、様々な、しかし意味はたった一つ、「自己正当化」の言葉を声高に口にして、既存のノンケ圧力に入っていったゲイたち、その顔を思い出したのは、10年以上ぶりでした。
彼らのあの声の大きさには、いまとなってみれば、あたくしたちのフラフラ・フワフワ(彼ら談)をなじるというよりはむしろ「そこまで大きなボリュームで言わないと、自分の耳にすら届かない。自分の心に跡すら残せない」という切迫感や哀しみ(あれは悲しみではなく、哀しみだったわ)があったなあ、としみじみ思いだしてしまったあたくし。そして彼らのあの声は、「あたくしの、もうひとつの声」だったとも…。東京からはるか離れた、結婚圧力の強さにかけては全国でも指折りだったであろうクソ田舎に生まれ育ち、ヘタに成績だけはよかったせいで地元の国立大学に行って親の会社の経理部門も切り盛りする公認会計士になることを熱烈に求められ、長男であるあたくしのためにすでに買ってある土地(実家から超近いの)に家を建て、妻と子どもと暮らす…。そんな青写真を高校2年ごろまでパピーにガッツリ描かれていたあたくしが、もしかしたら抱くことになった「もうひとつの声」だったのかもしれない…。そんな大昔の記憶まで引っ張り出すことになってしまったり。もちろん、あたくしのこの感想は、「彼らは彼らで、いばらの道ね。知らず知らずのうちにそれに付き合わされることになった配偶者の方は、余計に」という、あたくしの勝手な思いから出た、想像の産物でしかないのも承知しているのですが。
さて、今後『東京タラレバ娘』と『ヒモザイル』は、どんな展開になっていくのか。あたくしはまだファンとして心待ちにしています。ただ、願わくば、東村が、『海月姫』の特に初期において、「『あっち』にも『こっち』にも、そりゃあそれぞれ難しさや虚しさもあるかもしれないけれど、それぞれに刺激だってあれば幸せだってある」という「可能性」を、時代に選ばれた人特有の、きらめくようなトーンと素晴らしい疾走感で描いたこと、その再現を、ファンとしてどうしても期待してしまうのです。それがほんの数年前にできていた東村アキコならば、そして、「人生でもっとも影響を受けたのは、あの鬼(日高先生)だった」と、あれだけペーソスあふれる画風で描けた東村アキコならば、アシスタントたちに鬼よろしく「(おまえらにシッターやってる時間があるのか! 自分の作品を)描け!」と竹刀を振るい、その一方で彼らが「こっち」にいたままで手に入れられる、彼らが本当に望む幸せを考えてあげられる…そんな人になれるはず、と、まだファンであるがゆえの、勝手な期待をしてしまうのです。
「『あっち』側に片足突っ込んだって、『こっち』側の矜持を忘れちゃいないぜ! あっち側から見たら、そりゃクソのように見える矜持かもしれんがな!」というプライド。両側に片足ずつの立ち位置を持ちながらも、しかし真ん中から引き裂かれたりしない…。そんな「可能性」の、片鱗だけでもいい、それを見せてくれたのなら、あたくしは一生、東村アキコについていきますわ!
PS
ご報告が遅れましたが、前回からこのエッセイは、毎月第2、第4月曜日のアップ(予定)になります。体調次第で遅れることはあるかもしれませんが、推定4人の読者の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。