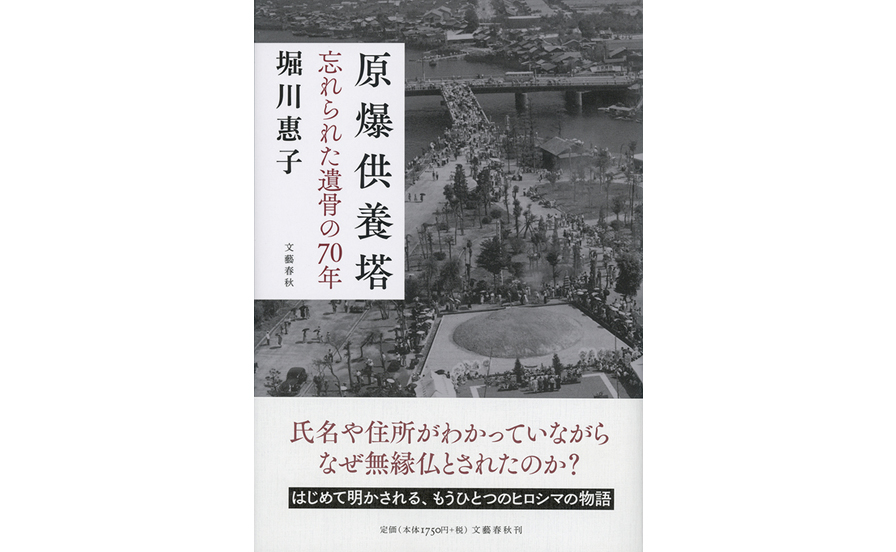安保関連法案へ「女」たちの異議
安保関連法案に、「女として」、「母として」反対する、という声が様々に上がっている。戦い続ける男たちを止めさせようと「セックスストライキ」を敢行し、見事平和を実現するアリストパネスの戯曲『女の平和』とアイスランドのレッドストッキング運動に触発された女たちが、1月と6月に、赤いストッキング他を着用して、国会を取り囲んだも全国各地でデモを実施している。
女やママたちではなく、学者(安保関連法案に反対する学者の会ほか)、大学生(SEALDs ほか)、高校生、若者のがんばりに触発された中年やお年寄り(戦争法案に反対するミドルズ、OLDs)など、様々なくくりで、街頭で、Web上で、反対運動が繰り広げられている。どんなくくりでも、集まって、声をあげる。素敵だ。目頭が熱くなる。
ま、多少フェミニストとしては、「女であり母として平和を望む!」というアピールは、「男=戦争、女=平和」という本質主義的な二項対立図式によっているような気がしないでもない。セックスストライキで男を困らせ、エロスで男たちを参らせて和平を導いた、という戯曲『女の平和』は、お色気戯曲、それに「女は頭より体ってことかっ?」と真面目に怒るのはヤボとはいえ、それに触発されての運動ってどうかとも…。ハ!いけない。ああだこうだ、つまらないところで足を引っ張らず、連帯だっ!
「妻として母として平和を望む」は自明ではない
もっとも、「平和を望む女たち」は決して自明ではない。もっといえば、妻、母として「平和」を望むといったときに、どんな平和を望んでいるのかも自明ではない。上記の各デモに比べてあまりに人数が少なく気の毒なくらいではあるが、7月15日、福岡で、「戦争反対=安保賛成!」とする女性と学生のデモが行われたことからしても。
戦争のときはどうだったのだろう。女性たちは平和を望み、戦争をストップさせるよう努力したのだろうか。あるいは、戦争に翻弄された、一方的な被害者だったのだろうか。
いやそうではなかった。女性たちも積極的に戦争に協力もした。加害者性も否定できない。
戦時中の庶民の生活を描くテレビドラマや映画(実は年代的にずれていて不正確だとか。本書参照)には、かっぼう着にたすきがけ、日の丸の小旗を掲げて出征兵士を見送りに、帰還兵士を出迎えに繰り出す女性たちのイメージが定番。その「銃後を支える妻、母たち」の情景は、昭和7年にわずか40人で発足しながら、10年後に1000万にふくれあがった驚異の組織、国防婦人会のイメージだ。
藤井忠俊著『国防婦人会 日の丸とカッポウ着』岩波新書と加納実紀代『女たちの<銃後>』(筑摩書房)は、国防婦人会(国婦)が予想しない拡大を続けていく過程を詳細に描き出す。1932年大阪国防婦人会が発会した際、せいぜい40人程度であり、当時ありふれた献金活動のひとつであった。それが1934年には全国で100万人の組織になった。なぜか。藤井は、まず、ほかの献金活動とは異なる国婦の特性をあげる。すなわち、台所から出て兵士の見送りや出迎えに行き、身体を使ってお世話する、という行動の特性だ。
他に例をみない発展を遂げた要因にはほかにも様々考えられる。意図的、戦略的な要因もあれば、偶然性もある。たとえば、当初より、警察と憲兵隊に親しい後援者がいた。しかし、だからといって、最初から反動的な色彩の濃い団体であったのではない。あくまでも、思想的というよりも日常的な警部や曹長と「兵隊ばあさん」たちとのつながりの中で、意見を交わし、相談に乗ってもらうという関係から築かれていくというのが、興味深い。もっとも、発展していく段階では、大阪でもまだ小さい組織なのに、東京に乗り込んだ際は、ハッタリをかまし、荒木陸軍大臣の妻に関東本部の本部長に就任してもらい、それをまた大阪にはねかえらせた(「お墨付き」を利用するしたたかさ)。「満州事変」を機にリベラルな志向から軍部判を控え、極力軍部を支持することへ方向転換した(!)大阪朝日も国婦を好意的に取扱い、宣伝に力を貸した。在郷軍人婦人会が発展せず、国婦が異常に発展したのは、前者が在郷軍人家族に範囲を限定しがちであったこと、これに対して国婦は軍人と関係のない市民として軍事後援を始めたために、社会的なひろがりの契機があったこと、による。
陸軍の意図が色濃い趣意と活動実態のずれも興味深い。国婦が会員募集のため配布した「本会の特色」には、「我国伝統の美俗たる家族主義に則り、まず我が家を整え…」云々、「我国伝統の婦徳を益々宣揚し、この婦徳を基にして…」、「温順かつ貞淑でしかも犯し難い強い正しい意志の下に…」云々と、軍の思想がよくあらわれている。しかし、当の女性たちは、「我が家を整え」「婦徳を基にして」「温順かつ貞淑」たらんとしてはいない。家庭をかえりみず社会的に活躍する意気で始めたのだし、実際に見送り出迎えには、「台所を守る」のではなく「台所を出る」必要があった。国婦は、その中心人物が一応陸軍の支援者と意気投合するようでいて、陸軍が鼓舞する、国家主義的・家族主義的な理念についても、とりたてて深い関心を示さないくらい無思想な集団であった。
国婦が女性組織の実力ナンバーワン勢力にのしあがると、既存の女性組織との軋轢が顕在化していく。良識派の平和意識をもった婦人平和協会などは、「国際正義」を見つけ出すのが難しくなっていく日本軍の行動に、戸惑いつつ弁解がましく理屈っぽく正当化し、「転向」していくが、それでも広がることはなかった。そこまでの自己撞着はなく現実に適応していく女性組織でも、若干「理屈つき」では、「理屈なし」の国婦には抗しがたかった。平和を語ろうとするその時にも兵士はどんどん出征していく。まず見送ろうではないかという庶民の行動には打ち勝てなかったのだ。
「女性解放」の側面もあったけれども
権利を主張することなく活動の場を広げる国婦を苦々しく思っている女性は当時もいた。市川房枝らの婦選同盟だ。しかし、その活動の意図しない意義も理解していた。市川は自伝に、農村の女性たちが、半日家から解放されて講演を聴くことだけでも、女性の解放の側面があったと書いている。
無思想であり、意図しない女性解放の効果もあった国婦の活動。しかし、加納が指摘するように、出征にあたって旗を振り、かいがいしく世話をしてくれた女たちを思い起こすことで、戦場にある兵士たちが皇軍兵士として自らを奮い立たせたとすれば…。女たちも、兵士たちの銃剣の先の血に無関係とはいえない。
後篇では、さらに藤井と加納の両著から、国婦の展開とそこから女たちが学べることを抽出したい。
後編は8月18日の更新です。楽しみにお待ち下さい。~編集部より~