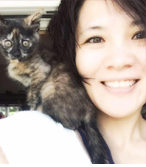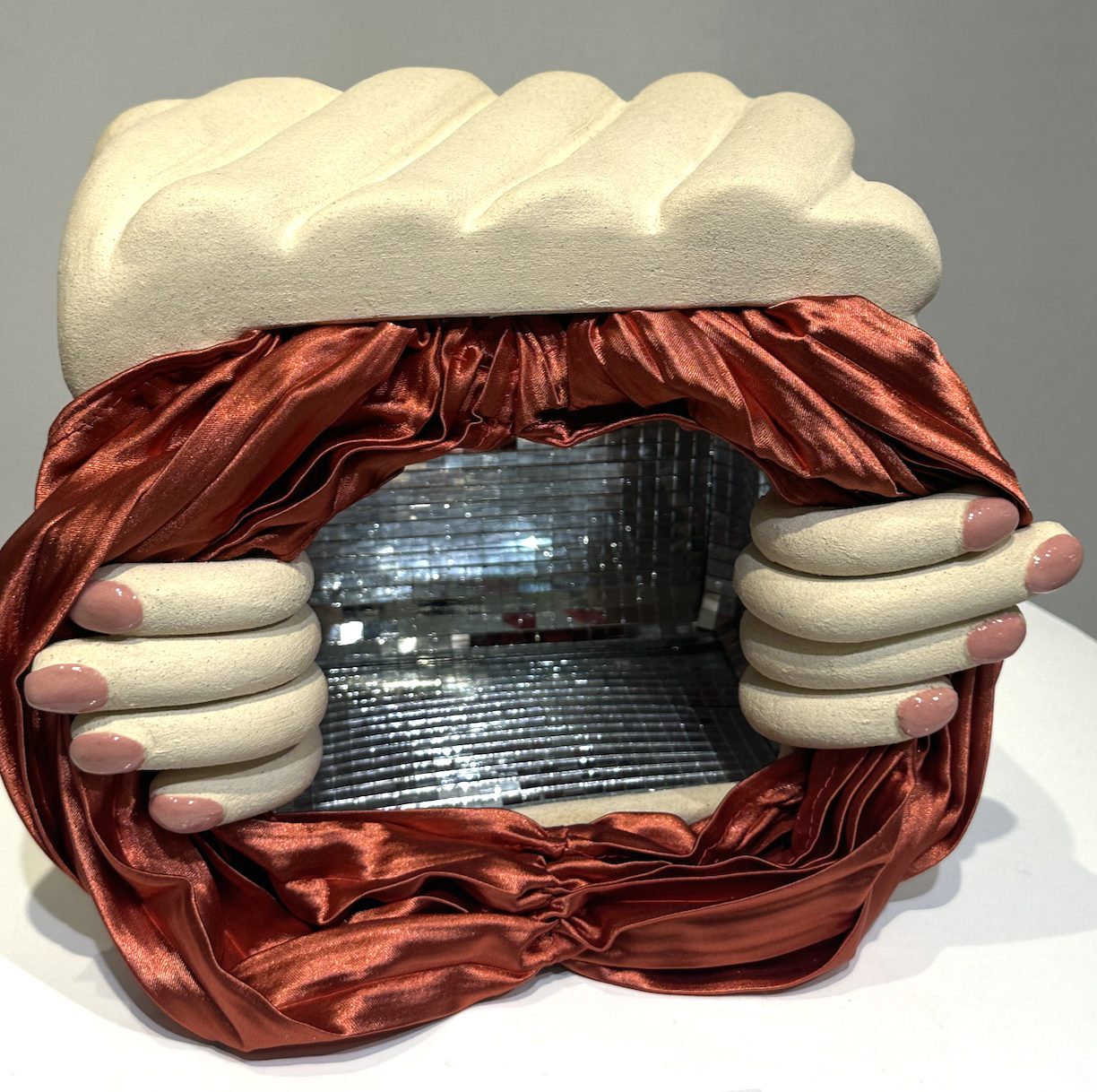今朝、友人と電話で話したこと。昨年12月のクーリエ・ジャポンに掲載された「拝啓 伊藤詩織さん」と題された記事について。少しのつもりだったのに、記憶が記憶を引き出すように互いに言葉が止まらなくて、1時間近く私たちは話した。
ローマで6人の女子大学生が性暴力被害にあった1993年春、私たちは海外に卒業旅行に行く“女子大生”だった。「女子大生レイプ」はオジサン向けメディアの「娯楽」だったのか、白熱した週刊誌は扇情的に事件を書き散らしていた。多くは「ブランド好きの頭も尻も軽い女子大生が陥った罠」といった、女性の落ち度を強調するような報道姿勢だった(その中でも『週刊現代』は当初から被害女性に取材し、強姦神話に陥ることない報道姿勢だった。この時のことは近々発表する記事の中で記したいと思う)
あの当時、私たちは何を思っただろう。これを書くのは本当に恥ずかしいことだが、私は自分が「6人もいたのに、どういう状況なのかな」と不思議に思ったことをハッキリと覚えている。友人は、母親との「ヨーロッパは怖いわね、注意しなくちゃね」といった会話を覚えていると言った。
25年前の事件なのに、不思議なくらい、明確な記憶。
それは、自分たちが“当事者”であることも分かっていて、“女子大生”がどのように扱われるかを知っていたからこその冷酷な“他人事”だったのか。
どちらにしても私たちは、被害を受けた女性の立ち場で考え、共感の声をあげるという発想はなかった。
なんて、鈍かったのだろう。
本当に、鈍かった。
もうセクハラという言葉はあったのに。自分たちも性暴力被害に日常的にさらされていたのに。フェミニストでありたい、私はフェミニストだ、そう思って上野千鶴子も小倉千加子も熟読してたのに。
それなのに。
鈍さの話しは、まだまだあった。例えばそれは。
90年代、AV監督バクシーシ山下の『女犯』を観る会に、私と彼女は参加したことがあった。
「女犯」は、女性が殴られ、顔にゲロを吐かれ、泣き叫び逃げ惑う姿が延々と描かれる“アダルトビデオ作品”で、その“リアリズム”からか監督は”天才”と評価されていた。その時のことを彼女は語り出した。
「あんな映像をみんなで観て『これはアリなのか?』という議論をしていたことが恐ろしい」
もちろん私たちは批判するためにも「観なければ」という意識で集まったわけだけど、今であれば、心的外傷を考慮した十分なケアのもとで、十分に十分を重ねた配慮のもとで、それでも躊躇するような形でしか上映会など出来ないだろう。でもそこにはあまり疑問を持たずに、私たちは集まった。
鈍かったね・・・アリなのかどうか・・・そんな議論そのものがナシだろう! だろう!
しょうもない鈍さ、平成初期の私たちのフェミニズム。
真っ暗闇ではないが、十分な明かりのない荒れ地で、言葉を探していた。
時代のせいにするわけではないが、私たちは「平成の性暴力史の入り口」に立っていたのだと思う。
あの頃、女性が泣き叫ぶAVを知識人たちがこぞって評価していた。
AVは斜めから楽しむサブカルとして地位を得て、サブカルこそがカルチャーのようにみえてきて、男のエロを“男のように楽しめる”ことこそが女の解放のような気分があった。
憧れのフェミニスト上野千鶴子さんや、藤本由香里さんが暴力ポルノですらポルノとして肯定的に捉えていた。”エンコー”にしたって、年上のフェミたちがこぞって、”女性が純潔教育から解放された証拠”とか”性の自己決定の証”のようなことを言っていた。
一方で、性暴力表現やロリコン表現を「これは暴力だ」「これは犯罪ではないか」と真顔で訴える人たちは、サブカルの文脈(=日本のメインカルチャー、日本の今の空気)が分からないババア(一部ジジイ)、といった印象付けがされていった。
性風俗を構造的差別の文脈で語るのではなく、「今はセックスワークって言うんだよ」という”新しい声”が広まりつつあった。
女性の人権を訴える人々が「セックスカルチャー」に体当たりし嘲笑されていく姿を、私たちは遠巻きに観ていた。「古い」のにも「今とされているもの」にも、どちらも乗れないような中途半端さで。
平成の「性」は、そんな風に始まったのだと思う。
AVがサブカルになり、性暴力表現がより洗練されたビジネスになっていった時代。
痛みですら消費材料で、そんな鈍さが平常心。
先日ラブピースクラブに訪れた20代の女性が、「メディアに対し、ジェンダーイクオリティの観点から、警告を発する団体が必要だと思う」と話してくれた。
1970年代〜80年代にかけてメディアの性暴力・性差別表現と戦った「行動する女たちの会」のことを彼女は深くは知らないようだったけれど、「行動する女たちの会」がなくなった平成の最後の年に、「そういう団体が必要だ」と考える20代が出てきたことに、私は息をのみ、そして光を感じる。
暴力は深まったかもしれないが一方で、フェミの言葉も成熟してきたのだとも思う。
特に性暴力被害者からの発信、そしてその声を私たちがどのように受け止め、何をすべきか。
そのようなことを、少なくとも国際社会でフェミニズムは深く貢献してきた。その言葉が、きちんと、下の世代に繋がりはじめている。
今年に入ってからSPA!の性差別記事に対する抗議の声がどんどん大きくなっている。山本和奈さんという20代の女性があげた真っ直ぐな声が、現実を変えつつある。SPA!に名指しされた大学が出版社に抗議し、海外メディアもこの件を取材し、SPA!に謝罪を求める声は4万近くも集まっている。
「女性を軽視した出版を取り下げ謝って下さい」
山本さんの、シンプルなこの抗議に胸が詰まる。
「ロリコン社会に疲れました」
率直な一文に、胸が詰まる。
女性をモノ化して評価して楽しみ値段を付けて消費する。女が沈黙することで許されてきた慣習。
もう黙らなくていいんだよ。そういうメッセージも含めて、山本さんがあげた声は、私たちの大きな一歩だ。
「この程度の”男のおふざけ”に真剣に怒るフェミニストの方は文脈読めてない」
そんな反論がフツーにあった空気すら変える、それは強い声だと思った。
SPA!のことも、今朝、私たちは話した。
1993年のあの事件当時、薬害エイズ問題で戦い人権派左翼のイメージがあった小林よしのりさんは、SPA!で連載していたゴーマニズム宣言で、被害女性たちがお尻を突き出すような漫画を描いていた。
そう、これは今に始まったことじゃない。「そういう空気」がずっとずっとずっと、あったのだ。
それを本気で終わらせるために、私たちは話して、そして声をあげて、つながりたいのだと思う。つながる時なのだと思う。
フェミな視点からいえば、平成は性暴力史そのものだった。
私たちも、時代に呑まれながら困惑し、そして嘲笑されながら、それがフェミの宿命なのかと思いながら、細々と話してきた。そろそろ、そんな平成フェミの反省会をしなくちゃね。もう平成の性暴力を次の時代に渡さないためにね。
長電話の最後は、そんなことを言って切った。
さて。そんなわけで、近々、オーバー40の女たちと平成フェミ反省会をしてみることになった。
過去を振り返り、過ちを繰り返さず、未来につなげていくことが大切。
そしてつながってくれる新しい若いお友達も、今年はいっぱいほしいな。
そんな年明け。
山本和奈さん、そしてそのお友達たち、本当にありがとう。
そして、みなさま、今年もよろしくお願いします。