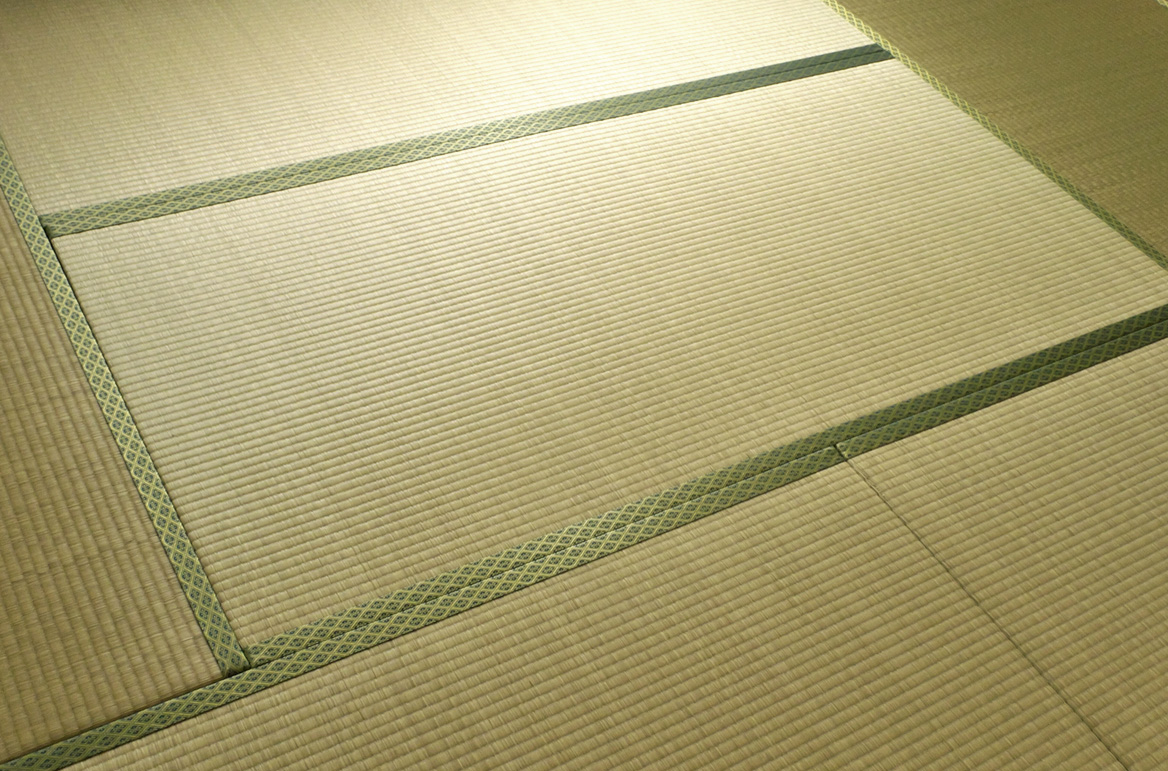動揺するのは二流の営業だと、昔、誰かに叱られたことがある。営業デビューしたばかりの頃だった。それ以来、正常な判断が出来なくなりそうになったり、心が不安定になりそうな時には笑顔を作るようにしている。そう心がけていたら、そのうち、意識しないでも咄嗟の瞬間に笑顔を浮かべるようになった。だから、間野君が見つけた私は薄ら笑いを浮かべていたに違いない。
私の座っている場所から間野君と証券の男が見えるということは、あちらからも私が見えると言うことだ。
視線をずらしつつグラスに口をつけて顔の半分くらいは隠したが、空いた席を探して店内を見回していた間野君はすぐに私を見つけ、意外そうな顔をしている。
後ろの証券の男は地主に会う時のような笑顔を浮かべて会釈し、私もまた地主に会う時のような笑顔で手を振った。間野君は一瞬こちらに歩きかけ、一歩目を踏み出したところで近寄ってきた店員に連れられて遠くのテーブル席へと連れて行かれた。間野君は何度かこちらを振り返り、私は口角を上げたまま彼らを見送った。愛想が良いとか悪いとか、そういう話ではない。
意外そうな顔をしていたということは、私がつばさちゃんと一緒に先輩と飲みに行かなかったことを知っているのだろうか。それとも、こちらのテーブルにはグラスが2つ置いてあって少し後ろにひかれたままの椅子は明らかに誰かと一緒だということを示していたので、不審に思われたのだろうか。
証券の男とは、担当している地主、それも、農地改革以前からの地主のところへ一緒に行ったことがあるな、と、わたしは割とどうでもいいことを思い出していた。彼はプロ人材の活用とかいう施策で銀行に出向してきている証券会社の男で、すこぶるデキる敏腕営業で、出向してくる男性はだいたい四、五十代だったが、彼だけは私やつばさちゃんと同い年だった。ちなみに彼は既婚者で、間野君は未婚だ。
「ブタちゃん酒ねーじゃん」
戻ってきたお花ちゃんは私の顔を指差し、「お前なんでグラス齧ってんの?」と聞いた。
「お花ちゃんがお手洗いに行ってる間に、間野君たちが入ってきた」
「まのくん? あ、会社の男?」
「そう」
「やっべーじゃん!」
「やばくないよ」
二人が案内されていった店の奥の方を見ると、残念ながら間野君の顔が見えた。証券の男はこちらを気にする様子も無く身振り手振りを交えながら間野君相手に何か話しているが、間野君はチラチラとこちらを見ている。
「だって、ここから間野君見えるし」
「やべーじゃん、俺、超見られてるじゃん。ていうかどこに座ってんの?」そう言いながらお花ちゃんは目だけで辺りを見回し、「あっ、いや、何となくわかったからいいわ」と緊張した面持ちで続けた。
お花ちゃんが焦ると、私は逆に冷静になった。
「別に、気にすることないよ。平気だよ。堂々としてなよ」
「お前どうなってんだよ」
お花ちゃんがこんな風に狼狽えているところを久しぶりに見た気がする。
けれど間野君は私の同僚で、お花ちゃんの世界には関係が無い。本来狼狽えるべきは私だ。
「じゃあ、ともかく、向こうより先に出よう。それでいいでしょう?」
「ババァがそう言うんなら、いっか。じゃ、もう一杯飲めるな」
そう言ってメニューを手に取ったお花ちゃんは、私の分までビールを注文した。
間野君には結婚式の招待状を渡している。(同期なので)
こちらの様子が気になってしょうがない間野君の様子を考えると、何だかもう、結婚式に招くこと自体が申し訳ない気がしてきた。間野君は更に誰かに言うだろうか。例えば、課長とか、支店長とかに。
前の支店の時のように『なんとなく仕事面に不安が残るが、愛想が良くて素直な新人』のままだったら、私もお花ちゃんと一緒になって慌てたかも知れない。
けれど、今の支店に異動してきた私は『素直な新人』ではない。
お店を出る時に、タイミング良くこちらを見た間野君に笑顔で手を振って、店を後にした。
翌日、案の定、間野君は朝から妙な顔をしていた。
けれども、妙な顔をしていたのは間野君だけだった。
課員の予定はめいめいのスケジューラーで公開されていて、私は間野君の予定をこっそりと確認した。
午前中、担当先に訪問アポイント取得の電話。午後、集金。
ひとりで行動する予定しか入っていない。
結局、夕方になるまで間野君は声をかけてこなかった。
薄暗い廊下の突き当りで一日に出た全てのゴミをシュレッダーにかけていると、後ろから「菊池ちゃん……?」と声をかけられた。
「あっ間野君」
上手く微笑めない間野君に私はにっこりと笑い「昨日はびっくりしたよぉ」と言った。
「あっ、びっくりした? え、俺も」
「あはは、間野君めっちゃ口開けてたよね」
「いや、いや、そうかなぁ」
私が黙ると間野君も黙った。
顔に「あの男、何?」と書いてあるような気がした。
「私、偶然支店の近くに知り合いがいてね、一緒に飲んでたの。大学時代の先輩がこの辺り地元だったんだよねぇ」
「あっ、へ、へぇ、な~んだ、そうだったのかぁ」
間野君はマンガみたいに脱力して、持っていたゴミ箱をガタンと置いた。落とした、と言っても差し支えないかもしれない。私は書類が突っ込まれたゴミ箱を見ながら、間野君は考えに考えた結果、ここ、シュレッダーの前で私に話しかけてきたのか、と思い何とも言えない気分になった。
緊張が切れたらしい間野君は、途端に饒舌になった。
「俺、どうしようかと思ってさぁ。ほんと、どうしようかと思って。だって、前見た写真の旦那さんと全然違うしさ、ほんと、どうしようかと思って……。でも、そっか、なんだ、先輩かぁ、先輩ね、いやぁ、心配して損したなぁ、はは」
どうしようかって、どうするつもりだったんだ。説教でもするつもりだったのか、説得するつもりだったのか。心配って、何を心配したのか。損したってどういうことなんだ。
間野君の、出所不明の正義感にクラクラする。
「正義感が強いんだね」
「えっ、え、そうかなぁ」
間野君は嬉しそうだ。
「あっ、でも、俺、誰にも言ってないから」
「はは、別に気にしないよ」
銀行員の人間関係は意外と爛れていて、不倫や浮気や何だかんだの不祥事で、人が異動したりいなくなったりすることは少なくない。
行内のシステムを使ったメールで逢瀬の相談をしたり、乗り換えに使う人が多い駅のラブホテルに行ったり、もっと簡単にバレる場合は、自分から言いふらしてしまったりするからそれがいつの間にか問題になる。
私は、きっとみんな心の奥底では隠す気なんてないんだろうと思っていた。今回の件で、自分にもそういう気持ちが少なからずあったんだと気付く羽目になった。
だから、間野君は感謝している。