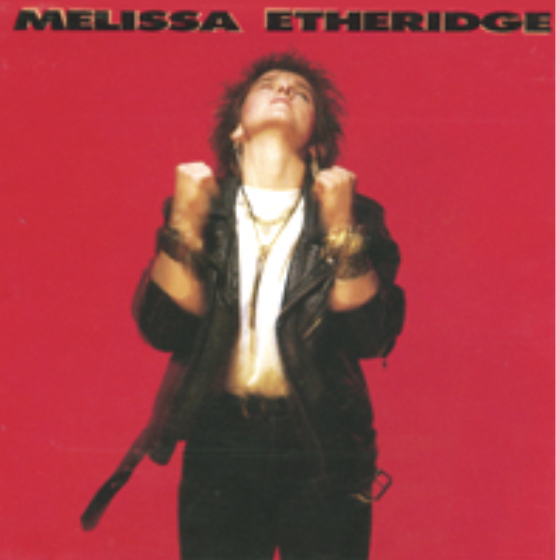“鳥のように自由”、ミシェル・ンデゲオチェロ(Meshell Ndegeocello)とはスワヒリ語でこのような意味を持つ。ジャズ、ロック、ファンク、ソウル・・・、あらゆるジャンルを越境し、彼女のアイデンティティの一部をなすであろう人種やセクシュアリティにかかわることなどを問いたて、しかしそれを直截に露わにはせず、ミシェル・ンデゲオチェロでしか表現しえないリズムとダークブルーに彩られた音の響きで抽象化していく。
1993年にマドンナが創設したマーヴェリックよりデビュー。変幻自在なメロディに最先鋭のアーティスト達が参加し常に研ぎ澄まされたアルバムを創り出してきた。そのどれもがビターな味わいと静謐な情感にあふれている。
ユニヴァーサルミュージックからのバイオグラフィーによると、ミシェル・ンデゲオチェロは1969年米軍にいた父親の赴任先であったベルリンで生まれ、その後家族と共にワシントンD.C.に移りクラブで演奏しながらベースの腕を磨いたという。全米で最も有名な黒人大学といわれる名門ハワード大学で音楽を学びプロを目指すようになったという。
10年くらい前に観た彼女の来日公演では、スタイリッシュなジャケット写真とはまったく異なり、骨太で職人肌なベーシストという意外な面に驚いた。全編ジャムセッションのようなステージ、恥ずかしながら最初はどこにミシェル・ンデゲオチェロがいるの?と思ってしまったくらいにバンドに溶け込みワン・オブ・ゼムで演奏していた。
時に抑制と解放をあわせ持つフリージャズのように、時に緻密で幻想的な宇宙感を携え聴く者を魅了してきたミシェル・ンデゲオチェロ。2012年にリリースした『至高の魂のために~ニーナ・シモンに捧ぐ』、続く2014年発表の『コメット・カム・トゥ・ミー』(Comet, Come To Me)、この近作からミシェル自身の歌声がより鮮明に浮かび上がる。
「一人のアフロ・アメリカンの女性として確固たる信念を持ち、強靭な意志と深い知性でもって人種差別や性差別に抵抗し続け、デビュー時からすでに既存のカテゴリーからはみ出していた」(渡辺亨『至高の魂のために~ニーナ・シモンに捧ぐ』ライナーノーツより)、そんなミシェルが、リスペクトという言葉をも超えるほど愛してやまないであろう黒人女性ミュージシャン、ニーナ・シモンの膨大なレパートリーから厳選した14曲を、ミシェルのほかにアフリカン・アメリカンの女性トシ・レーガン、リズ・ライト、ヴァレリー・ジューン、同じくアフリカン・アメリカン男性コーディ・チェスナット、様々な差別や偏見と闘ってきたアイルランド女性シネイド・オコナーらをヴォーカリストとして招き、ニーナ・シモンの孤高の魂を紡ぎだす。
『コメット・カム・トゥ・ミー』では気だるさに包まれながら揺れる心地よいメロディがアルバム全編に満ちている。そのリリックでは、愛や友情の不確かさ、人と人とのつながりは移ろいやすくとてもデリケートなもの、そして育むもの、といった世界観が見えてくる。クールでストイックな佇まいがエロティックな余韻をも生みだす。
2014年7月、ビルボード東京でのミシェル・ンデゲオチェロのステージを観に行った。ステージの中央、シックな装いで立つ彼女の真摯な演奏、型通りな愛想などはくりださず1曲1曲を丁寧にうたう姿は10年ほど前に観たステージでは観られなかった気高さに溢れていた。私の前のテーブル席には会社の接待で来客したと思われる6人ほどの男女が豪勢なディナーを会食しながら彼女のステージを楽しんでいたのだが、ワインでほろ酔い気分にでもなったのであろうそのうちの女性2人が席を立って軽く踊りはじめた。ひとりが「えっ、あの人女の人だったの?ずっと男かと思ってた~」ともうひとりに驚嘆して話していた会話におもわずほくそ笑んでしまった。ミシェル・ンデゲオチェロはそういうお客さんをも、いい気分にさせてくれるプロフェッショナルなアーティストでもあるのだ。