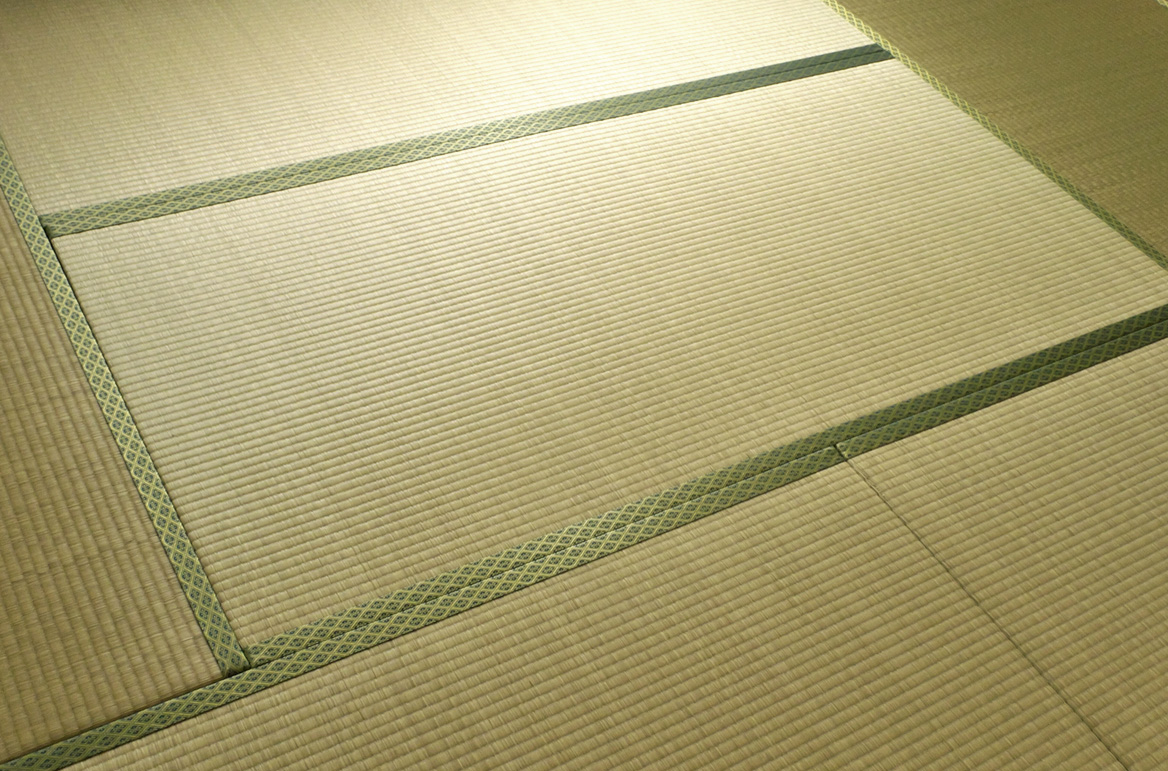ところで、在宅酸素療法中だったお嬢さんの病状はじわじわと悪くなっていっているようで、ひと月に1回は仕事中に恵美子さんから電話がかかってきて、お嬢さんが救急搬送された先の病院へ私も駆けつける、というようなことがあった。私は相変わらず、私生活全てをさらけ出すスタイルの営業をやっていたので、お客様に事実をそのまま伝え、特に問題なく予定をずらすことができた。本来アポイントが入っていたご婦人たちは口を揃えて「時間はいくらでもあるし、別の日で大丈夫よ。それよりミナトちゃん、しっかりね」と言ってくれる。
異動を経験し、もう新入行員として配属された支店ではないので、本来なら孫スタイルの営業はそろそろ辞めなければならない。けれど、同じタイミングで異動してきたつばさちゃんもどちらかと言うと孫営業スタイルだったのを良いことに、私は依然として孫スタイルに徹し、お客さまにもそれ以外にも全方向に甘えていた。
ちなみに、銀行的には『プロ人材の活用』というスローガンの元にガンガン受け入れた保険会社&証券会社から出向してきたおじさん達の運用が軌道に乗ってきた頃だったので、急に私の都合が悪くなってしまっても、ちょうどよくどうにかなった。例えばそれが契約の日で絶対に外せないアポイントだったとしても、プロ人材が私の代わりに一人でお客様を訪問して契約手続きを済ませてこられるのだ。ちなみに、契約はおじさんと私、双方の成績になる。最高だ。
救急搬送されたとは言え、お嬢さんは独りで救急車に乗ったわけではなく、119番に電話をかけるのは恵美子さんだった。だから、本当は毎回私が行くこともない。そういうような内容のことをやんわりと、課長の周囲にいた代理格の男性に一対一で言われたことがあった。
「いくら義理のお祖母様がご高齢っつったって、そもそもお義父さんもいるんだろ?」とも。
「俺だってこんなこと言いたくないんだけど」と続けた代理の背後には、もっと偉い人の影がチラチラと見えるような気がした。
「ご迷惑をおかけしてしまって、本当に心苦しいのですけれど、義理の父は義理の母と家庭内別居状態にありまして、非常時でも出て来ないんです。お恥ずかしい話なんですけれど。後で課長にも改めてご説明した方がいいでしょうか」
そう廊下の暗がりの中詫びると、代理は妙な顔をしたままいなくなり、それ以降はもう誰にも何も言われなくなった。
お嬢さんのことで病院に呼ばれたり入院手続きを恵美子さんの代わりにしたりする度に、少しずつ山田仕郎の家の内部事情がわかってきた。
一番最初に病院から呼び出されたのは、入籍してすぐの頃だった。
営業先から戻ると机の上に取り次ぎメモが残っていて、課長の字で「お義母様ご自宅から救急搬送され現在入院手続き中とのこと。急いで行ってあげてください」とあった。営業は全員出払っていて、ひとり残った課長が恵美子さんからの電話をとったようだ。携帯を見ると支店からの着信が2件入っていた。運転中で気が付かなかった。自分の机のところで携帯とメモを見比べていると、遠くから課長が「早く帰りなさいよ!」と叫んでいるのが聞こえた。
その後何度も通うことになる病院は西新宿にあって、病院に着いた時にはもう入院手続きが済んでいる時もあったし、まだ処置室の隅のベッドで薬で眠っている時もあったが、初めて行ったのは処置室の方だった。
「家族の者です」
そう言って部屋に入ると、ベッドの横には既に山田仕郎の妹がいた。
お嬢さんは酸素マスクをしたまま眠っている。
山田仕郎の妹は「おばーちゃんは今入院手続きに行ってて、私も今来たところで」と蚊の鳴くような声で言い、私は途端に自分がここにいるべきではないような気がしてきた。妹にかける言葉は「大丈夫ですか」でも「元気出してください」でもない。私は所詮、血の繋がりがある人間ではなかった。入籍は済ませたので戸籍の上では他人ではないが、まだ結婚式も挙げていないし、一緒に住んでいるわけでもない。居たたまれなさを感じるだけの余裕があった。
気まずい気持ちで立っていると、通りかかった看護師の女性が私の方を見て「あら、娘さん! 来れたんですね」と言いだして私は自分の耳を疑った。
「私は長男の嫁で、こちらが実の娘さんで」
そう言われた看護師の女性は妹の方をチラッと見たが、妹はこちらを見ない。
「今、入院手続き中だって聞いたんですけれど」
そう言ってみると、看護師はそれほど緊迫感の無い様子で「けっこう前に行かれたので、もう戻られると思いますよ」と言った。そして「ミナトちゃんってお嫁さんのことだったのね、スーツ姿のミナトちゃんが来るから、目が覚めた時に居てちょうだいねっておっしゃってましたよ」とも。
私が営業スマイルを浮かべて看護師さんの言葉を聞いている間、妹は微動だにしなかった。
病室が決まり、個室に移動する頃には山田仕郎の妹はいなくなっていた。職場に戻ったのだ。彼女は薬剤師の仕事をしていて、調剤薬局は人繰りが大変らしい。
個室で目を覚ましたお嬢さんは暫くぼんやりしていたが、私に気がつくと酸素マスクのままニヤッと笑い、こちらに向かってピースをしてみせた。私の後ろで恵美子さんが笑っている。
お嬢さんの病気は、『間質性肺炎』といって、肺が線維化して固くなり、膨らみにくくなって肺活量が落ち、息を吸っても吸っても全然吸った気がしない、というものだった。その日、お嬢さんと恵美子さんから直接聞いた。
「かんしつせいはいえん」とお嬢さんが言い、後ろから恵美子さんが「肺がカッチカチになっちゃうんですって。吸っても吸っても苦しいらしいのよ」と続けた。病室の壁には酸素が出てくる穴が開いていて、無色透明の液体がポコポコと音を立てていた。
「これ、お水ですか?」
ポコポコと空気の泡が立つパックを指差して尋ねると、背後から恵美子さんが「酸素だけ吸ってると、喉の粘膜が渇いちゃうのよ」と教えてくれた。
考えてみれば、お見合いの話が出る頃に知ったお嬢さんの不調にもかかわらず、私は何カ月も具体的なことを聞いていなかったのだった。銀行員には、基本的にはお客様に聞いてはいけない、聞いたとしても絶対に記録してはいけない『機微情報』というのがいくつかあって、門地や信教、傷病に関することなどがそれに該当する。だから、と言っては言い訳がましいのだけれど、私はその手の具体的な話を聞くことを避けていた。
「何か買ってくるもの、ありますか?」
部屋を出る口実を探して恵美子さんに尋ねたものの、「私が買ってくるわ」と言って逆に恵美子さんが出て行ってしまった。
お嬢さんと二人きりになった部屋で、暫くポコポコと言う水の音と空調の音だけが聞こえる。お嬢さんもピースサインなんかして、元気な風に振る舞ってはいるが、少しでも喋り続けると苦しいのだろう。
訪問先でも、沈黙する瞬間はあるしな、と思ってぼんやりとパックの中に発生する泡を眺めていると、突然お嬢さんが「あの子は?」と言った。
「あっ、妹さんですか?」
お嬢さんがウンウンと頷いている。
「私よりも先にいらしてましたよ。心配だったんでしょうね、憔悴した様子で、」
「帰ったのね」
「いや、お仕事を抜けて来られたようだったので、戻られたんじゃないでしょうか」
処置室での看護師さんとの会話を思い出しながら説明していると、お嬢さんは「あの子は、冷たい子なのかしら?」と言った。
「昔ねぇ、母に、あの子を養子に欲しがってる家があるから、って」
続けて喋るのは苦しいらしく、そこで一旦言葉を切ると息が落ち着くのを待った。
「3,000万円でどうか、って言われたことがあってね」
「ええ」
「結局、話は無くなったんだけれど」
お嬢さんが息継ぎの為に口をつぐむと「ごめんなさいね」と言った。