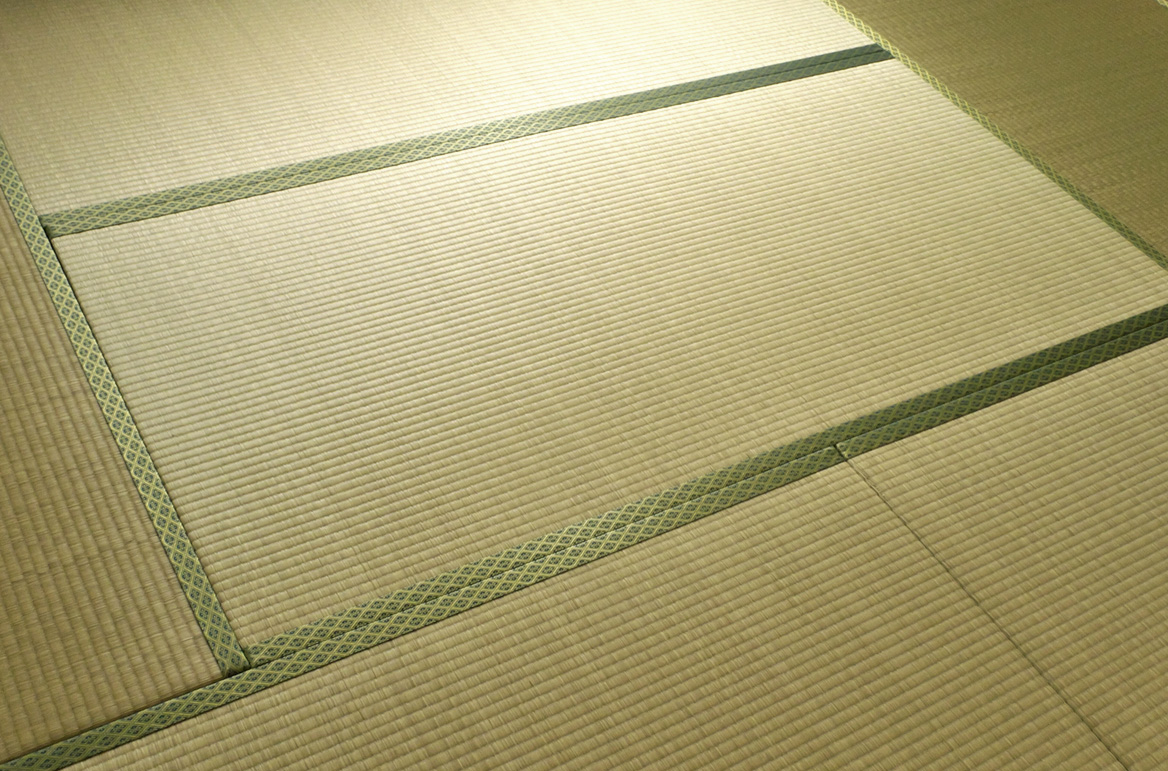式場が決まり、主賓から親族に至るまで大体の招待客のリストが出来上がり、コース料理の内容や引き出物の詳細、当日の司会者から式場を担当するフローリスト等々、曖昧だった細部がどんどんクッキリとし、結婚式は現実に近づいていた。いや、最初から現実だったのだけれど、それまではゴールテープも見えないようなところを一人ですたこら走っていたのが、どんどん山を越えるうちに沿道に立つ人が増え、ユニフォームにはスポンサーが付き、盛り上がるゴール付近の歓声が遠くに聞こえてきたような感じだった。
「前の店の同期は、結婚式の打ち合わせをしてると大体毎回喧嘩になっちゃうって言ってたよ。菊池ちゃんのところはそーゆー話聞かないねぇ」
そう、無邪気に尋ねてくる同僚のつばさちゃんに、「ウーン、多分、喧嘩になるほど思い入れがないんだと思うよ」と返した。
「根が深いね」
場所は営業課の机が固まったシマで、私とつばさちゃんは斜向かいに座ってその日の書類を処理していた。課長たちの机が固まったところとは少し離れていて、あちらのオジサンたちが会話に入ってくるようなことはない。外訪担当は私たち以外に誰も戻ってきておらず、内部管理責任者という肩書の書類チェック専門のオジサンが私の隣の隣に座っているのだが、植物のようにひっそりと座っているので私たちは好き勝手に喋っていた。
「一生懸命やらないと、悔しかったり悲しかったりしないもんね」
そう言って、つばさちゃんは壁に貼られた模造紙を見た。めいめいの名前の横に、丸いシールが貼られた模造紙である。小学校の教室の壁に貼ってあるようなやつだ。
センスの欠片も無いのワードアートで『目指せ目標達成!』というスローガンが掲げられた実績管理表には、めいめいの運用性商品の実績件数と収益額が丸いシールで集計され、一目瞭然でその月の成績がわかるようになっていた。
「今月マジでヤバい」と私は言い、つばさちゃんも「私も材料が無い」と頷いた。
丸いシールが途中からスマイルマークのシールになったので、他の先輩はその掲示物のことを『獄門さらし首』とか『首塚』と呼んでいる。
私は今月夏休みをとってしまうので、つばさちゃんよりも余計にヤバい。
「私、夏休みがあるから7営業日減る」
「ああー」
つばさちゃんは憐みに満ちた眼差しで私を見つめ、ふと視線を感じて横を見ると内部管理責任者のオジサンも同情的な表情を浮かべてこちらを見ていた。
夏休みの予定はひとつ、ウエディングドレス選びである。
式場と提携しているウエディングドレスのサロンは全部で13箇所あって、殆どの新婦さんは13箇所全てを回ります、という事実をウエディングプランナーに教えられた瞬間、隣に座った山田仕郎の目が死んだ気がした。見えたわけではないが、真向かいに座ったウエディングプランナーの表情でわかる。
ただ目が死んだだけならまだしも、更に山田仕郎の口からは「ええ~……」等と小学生のような声が漏れだし、私はあまりの素直な反応に「フハハ」と笑ってしまった。
今思えば、こういう瞬間に世の一般的なカップルは喧嘩になるのかも知れない。
しかし私は脳内で「小学生かよッ!」と芸のないツッコミを入れ、いやいや、もしかして『新郎も一緒に行くべきです……、お遍路のように粛々と13箇所全てを回ることで愛情を示すのですよ……』という天からの啓示でもあったのかしら、と幻聴を疑っていた。
「菊池様はお母さまと回られますか」
熟練のウエディングプランナーであるサトウさんは何気ない調子でそう尋ね、私が
「母が、『ドレスを一緒に選べるのは娘を持つ母親の醍醐味よねぇ』とよく言っているんです」
とにこやかに答えると、隣の山田仕郎がわざとらしく大きなため息をつくのが聞こえた。
やはり、世間一般のカップルならどちらかが怒り出してもおかしくない。
翌日から夏休み、という金曜日の夜、私はいつものように仕事が終わると駅の向こう側に行った。
お花ちゃんのバイト先のコンビニに着くと、お花ちゃんは駐車した軽自動車の中で缶コーヒーを飲んでいた。
「ババァ、遅かったじゃん」
「引継ぎしてたらこんな時間になっちゃった」
お花ちゃんは何の脈絡も無く「デブだな~」と言いながら車から降り、コンビニのゴミ箱に空き缶を捨てた。
代わりに私が運転席に乗り込んで、お花ちゃんは助手席に座る。
ペーパードライバー研修以来、私は夜の営業エリアで助手席にお花ちゃんを乗せ、路上教習しているのだった。虚飾性と自己中心性がD評価、という大変な診断書を見せられたお花ちゃん本人の発案である。
「明日から夏休み!」
私がアクセルを踏みながらそう言うと、お花ちゃんは「うおっ」と叫んでから「いいなー」と呟いた。
「いいことなんてあるかい、営業日は減るわ目標はそのままだわ、課長に詰められるわで大変なんだよ」
「フーン」
お花ちゃんは実感のこもらない声でそう言うと、後部座席に手を伸ばして何かを引っ張り出した。
「まぁ、シュークリームでも食えば?」
「お花ちゃんって、私のことデブだデブだって言う割に甘いもんくれるよね」
「いらねーの?」
「いるけど、私、運転しながらシュークリーム食べたら絶対に事故っちゃうから」
お花ちゃんのバイト先である駅前から5分も車で走ればそこはすっかり住宅地で、もっと行くと四市にまたがる大きな沼がある。
お花ちゃんは取り出したシュークリームを自分で食べながら「ブレーキ踏むの早いよ」とか「左も見ろ、ほら」等と言いながら私を沼のほとりにある公園まで誘導していく。沼の両岸には送電の為の鉄塔が連なり、夜は航空障害灯の赤い光が明滅していた。公園の脇で運転を交代し、お花ちゃんの運転でラーメンを食べに行くのがいつもの教習コースなのだった。
私はヘッドライトの向こうの暗い夜空を眺め、この状態で事故を起こしたらあらゆる意味で大ごとになるのに、お花ちゃんは何を考えてこの教習を提案してきたんだろう、とぼんやり思った。