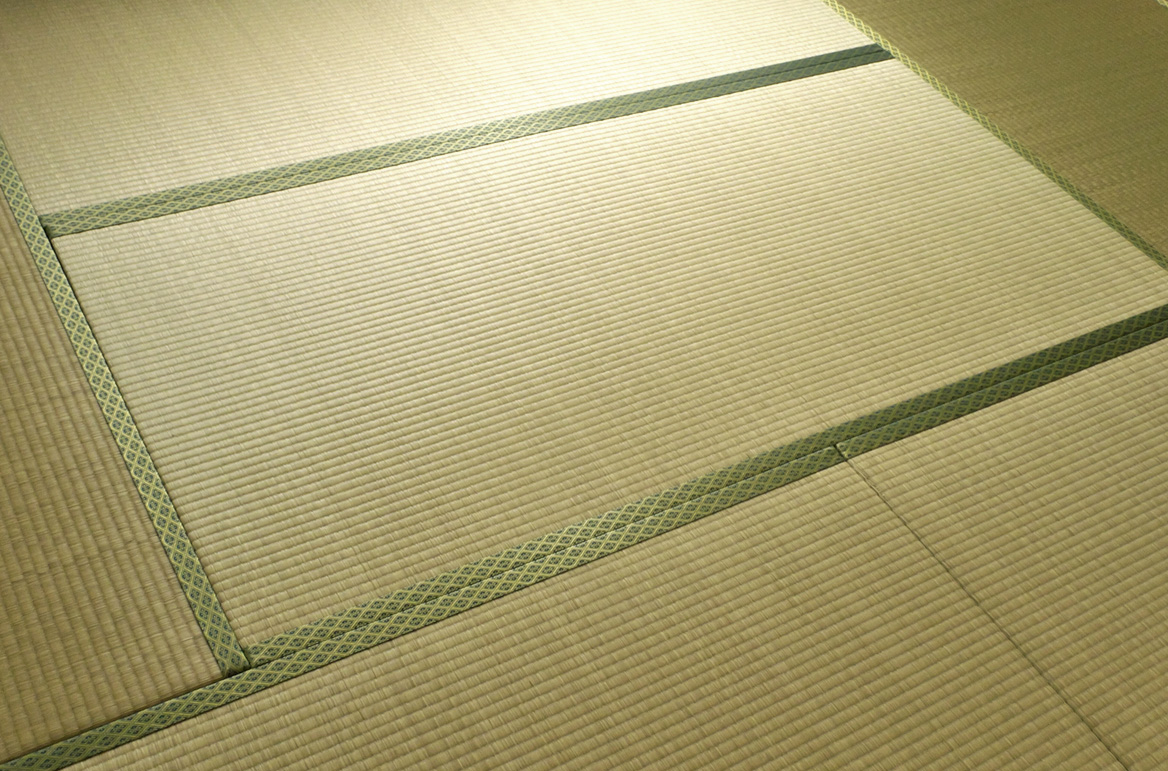ところで、私の結婚が決まったことは、課長の鶴の一声で突如公表された。
課長と支店長に報告して以来、ずっと公表を控えてきたのは、ひとえに、誰にも祝福されたくなかったからだ。
これまで同様のニュースに対して表面的な「おめでとう」しか言ってこなかった私である。他人から同じように表面的な「おめでとう」を言われたとしても、それはただの因果応報、身から出た錆だ。完全に自分のせいなのに、かつて自分が恨み妬み嫉みに苛まれながら笑顔で「おめでとうございますぅ」等と言い続けたことを思うと身の置き場のない気持ちがするのだった。そしてもし、万が一にも心からの祝福を受けるようなことがあったのなら、それはそれでより一層息が詰まる思いがするのだった。つまりどっちに転んでも「おめでとう」を受け入れられる気がしなかったので、私は公表を拒み続けていた。
しかし、一企業の中で社会人生活を送っていて、そんなワガママがいつまでも通る筈もない。
課長と私の面談に同席していたせいでこの件を知ってしまった近藤さんは、「俺、ちゃんと黙ってるよぉ」と弱々しい声で申し出てくれたのだが、課長はその申し出を断固拒否した。
「近藤さんにもバレたことだし、この機会に発表しよう、なっ」
大胆な笑顔を浮かべる課長を前に私は抵抗を諦め、有言実行の課長は本当に翌朝の課の朝礼で「菊池の結婚が決まった」と発表した。たまたま他にめぼしいニュースもスキャンダルもない時期だったので、その情報はたちまちのうちに建物内の全ての人間に知れ渡り、課の朝礼で発表されただけなのに朝礼の小一時間後に外出しようと裏口を通ると守衛さんに「菊池ちゃん、結婚するんだって?」と聞かれ、お昼に食堂に上がっていくと法人を担当している支社のおじさんにも「菊池さん、結婚するんだって?」と聞かれた。
お見合いで知り合った、十歳近く歳が離れた医者。
課長が最初の朝礼で山田仕郎の個人情報をそこまで言ってしまったので、会社のおじさん達は皆、山田仕郎のことを「ドクター」と呼んだ。
「菊池さん、ドクターと結婚するんだって?」
「ドクター、かなり年上なんだって?」
これらは、おじさんたちが既に知っていることの確認の為に私に投げてきた、特に意味のない質問だ。
おじさんたちが、挨拶程度の軽いノリで聞いてくる質問はいくつもあって、中には不可解な内容のものがいくつもあった。
中でも、「結婚費用はやっぱり全額ドクターが持ってくれるんでしょ?」が一番意味不明だった。
質問の体裁をとってはいたが、やっぱりそれはただの確認のようで、何か大前提となる事柄があるような尋ね方だった。
私の結婚以外のニュースに皆の関心が移ってゆくまでに、結婚の話をしたおじさんは全部で五十人くらいいた筈なのだが、確実に三分の一以上のおじさんから聞かれたと思う。
あまりにダイレクトなお金の話題に、最初のおじさんには面食らってしまったが、二人目のおじさんからは「そんなわけないじゃないですかぁ~」の一言で否定し、逆に「お宅は全額負担されたんですかぁ?」と聞き返すことにした。聞き返されたおじさんたちは「菊池はなんでそんなことを聞くんだ?」というような顔をしていることが多く、私の質問に答えてくれたおじさんのうち何人かは新郎側が全額負担していた。
お金の話は何かとデリケートな話題で、普通に生活していたら、なかなか突っ込んだ話は出来ない。でも、お客様と四六時中プライベートなお金の話をしている行員同士となると、デリケートも何もなく、まるっきりガバガバなのであった。
一方私は、相手が誰であれ全額出してもらうつもりなどさらさらなかった。
母が花嫁資金と言って管理している私名義の秘密の貯金があるのは知っていたが、お花ちゃんと結婚しようと決めた時から、そのお金のことは無いものとして考えていた。ただ結婚するなら快く使わせてもらえるだろうが、お花ちゃんとでは駄目だ。それは予感ではなく、日々の積み重ねから得た確信だった。
そこで私は、結婚式に備えて口座を開設していた。
そしてその口座には、貯金が四百万円あった。全額、自分で貯めたお金だ。
何でそんなに貯めてしまったかと言うと、それはもちろんお花ちゃんと結婚したかったからだ。
お花ちゃんは清々しいまでにアンチ結婚式派だったので、私は全額自分で出すことを考えて、式にかける平均予算に一割の諸費用を上乗せした金額を目標に貯金していたのだった。
「金の無駄だろ」
と、いうのが、お花ちゃんの主張だった。出会った大学生の頃から、ずーっと言い続けていた。
「結局は自己満足じゃん。それに、たった一日に何百万円もかけるくらいなら、うまい店で飲み会でもやって皆に楽しんでもらった方がずっとマシだろ」
確かにそうだ。
結婚式は自慰みたいなものだ。オナニーだ。
素人の公開オナニーなら、見せたい人、やりたい人がお金を払うべきで、それならお金はもちろん私持ちだ。
「俺と結婚式挙げたいんだったら、流す曲は全部メタルだな」
お花ちゃんは決まってそういう無理難題を言い、私は「ハードロックもヘビーメタルもオルゴールアレンジにしちゃえばOKOK」と言い返した。
結婚相手はお花ちゃんではなくなったが、自慰という認識に変わりはない。
それなら、自分が払って、自分の好きなようにやる。自分を慰めるのに、人のお金を使うなんておかしい。
まぁ、この主張は包んでいただくご祝儀のことを棚に上げてはいるのだけれど。
ブライダルフェア当日、相変わらずお行儀良く完璧なテーブルマナーで模擬挙式の試食ディナーを食べる山田仕郎に、我々の結婚式はイメージできているのか尋ねてみた。
「そうですなぁ、皆が自然と笑顔になってくれるような式にしたいですね」
スラスラと口から出た素晴らしいビジョンだが、それは山田仕郎の言葉ではない。フェアの冒頭でウエディングプランナーの女性が言っていた言葉、一言一句そのままだ。
ホテルウエディングのブライダルフェアだったので場内にはかなりの人数のカップルがおり、どこのテーブルも楽しげに談笑しながら食事をとっている。一方の山田仕郎は周囲の雰囲気などお構いなしに、沈黙を守って皿の上のオマール海老を切り分けることに熱中していた。
「もっと具体的に」
「具体的に?」
山田仕郎は一回の返答で質問が片付かなかったからか、ムッとした調子で聞き返してきた。海老の殻から、慎重に身を剥がしていた最中だったので、邪魔されたくなかったのかも知れない。私はふた口で食べてしまったので、もう殻しか残っておらず暇だった。
「私の経験だけで言いますけど、結婚披露宴って色々な人をお招きするわけじゃないですか。そうしたら、どうしたって、そこに座っている全員が心から祝福してくれているとは限らないと思うんですよね」
努めて静かに話そうとする私の話を聞いているのかいないのか、山田仕郎はナイフの先端3cmくらいのところを見ながら海老を切り分けている。
「でも、社会人として皆さん出席してくださるわけですし」
そう言った瞬間、会場の照明がフッと消えた。
暗闇の向こうで、山田仕郎が舌打ちをするのが聞こえ、私は少し驚いた。舌打ちとか、する人だったのか。
模擬新郎新婦が遠くのテーブルに居るのを見て、思い出す。そう言えば、ウエディングプランナーから説明があった。新郎新婦が、式の最中に各テーブルを回ります、と。水に触れると発光する特殊素材の造花を使った新しいタイプのキャンドルサービスです、と。
暗闇の中でカトラリーを置いてしまった山田仕郎に「こういう演出って、自己満足の極致だと思いませんか」と言ってみた。
「そうですなぁ」
「ゲストをもてなす為に我々ができる最大限のことって、食事を本当に美味しいものにして、不自由を感じさせないお酒のラインナップにして、余分な演出でストレスを与えないことだと思うんです」
次々と周囲のテーブルで花が発光し、会場内はほんのりと明るくなっていた。
山田仕郎は顎に手をあてて、何かしきりに頷いている。
「仕郎さんはどう思いますか」
「いや、あなたの言う通りだと」
「全然ロマンチックじゃないこと言ってると思います?」
「いや、現実的でいいんじゃないでしょうか」
「私、人の結婚式で楽しかったことってほとんどないんですよね」
「そうですか」山田仕郎は無感動に頷き、暗闇に目が慣れたのか再びナイフとフォークを取った。海老の続きを食べるのだろう。
「僕もそうですよ」
幸せそうな笑顔を浮かべた新郎(モデル)と新婦(モデル)が我々のテーブルを訪れ、造花を発光させて去っていった。
金魚鉢のような容器の中で、ゆらゆらと発光する花びらがめちゃくちゃロマンチックだった。リトルマーメイドの世界みたいだった。