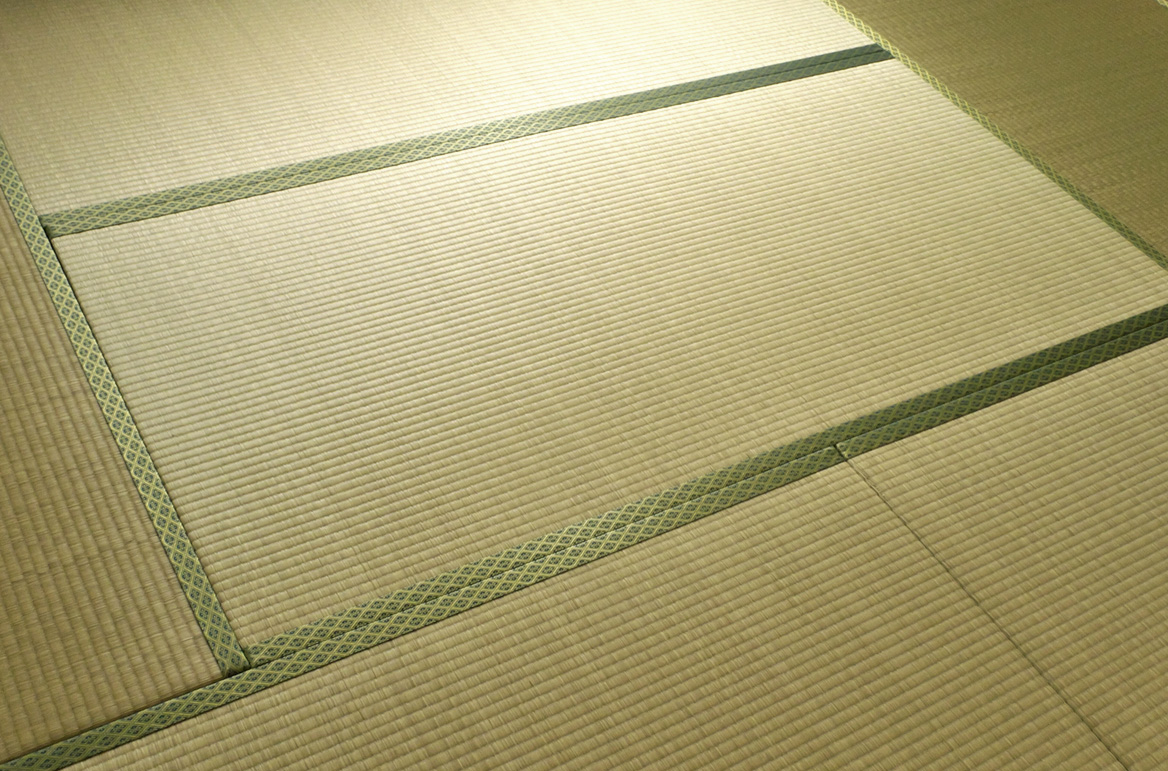私には、参考にすべき姑のご意見サンプルが大量にあった。運用性商品の営業として担当したお客様が、ことあるごとに語って聞かせる嫁の愚痴である。何十人ものご婦人が垣間見せる姑の顔は、十人十色の逆鱗ポイントを私に叩き込んだ。それは時間をかけた刷り込みだった。
保有する投資信託に生じた七ケタの含み損をどうするか、という話をしている時は淡々とした口調で語り泰然と印鑑を押し然有らぬ調子でハイリスク商品への乗り換えをしていたご婦人が、「泊まりに来た息子の嫁がエプロンを持って来なかった」という話題になると口調が豹変する。2年間くらい同じ話を聞いているのだが、まるで昨日経験したばかりのようにフレッシュな怒りを以て語り、かつ登場人物の台詞と情景描写は回を追うごとに洗練されていく。結果、大抵のご婦人のお話は語り部が語る日本むかしばなしのように美しくまとまった愚痴ストーリーへと進化していった。私は訪問先で、その語り部の話をひたすら拝聴するのである。
ご婦人たちの怒りは、ロビン先輩が言った「期待しちゃだめよ」という一言を思い出させた。
「期待しちゃダメ。裏切られた気持ちになると、自分が損するんだから」
社会人になる前は、母と言うフィルターを通じて嫁の目線から嫁姑間の揉め事を見させられた。
社会人になった後は、姑の目線から語られるアナザーストーリーを拝聴している。
自分自身に置き換えて言えば、私は既に、恵美子さんたちに期待をさせてしまった。営業中の私とお花ちゃんの前の私には凄まじい隔たりがあるのだ。
せめて期待させた分は裏切らないようにしなければ。明日は我が身だな、と、結婚の話が本格的に動き出した後の私は、他所のお嫁さんの話を訪問先で聞かされながらぼんやりと思っていた。
そうして私は、一泊分の荷物と手土産を持っていつものマンションを訪れた。
滞在スケジュールは、こうである。
土曜日、お茶の時間にマンションに到着。向こうのご家族と夕食をいただきそのままお泊り。翌日の昼前に失礼して、母が待機する自宅へ戻る。恐らく質問攻めだ。
ジャケットも書類の詰まった仕事鞄も持たずに、仕事でしか訪れたことのない場所に立つのは不思議な心持ちがした。
いつものように呼び鈴をを押し「こんにちはぁ」と叫ぶと程無く、「開いてますよぉ」とお嬢さんの声がした。鍵のかかっていないドアを開けて室内に入ると、廊下の突き当りからお嬢さんが「ミナトちゃ~ん」と言いながら顔をのぞかせている。ダイニングに入ると、お嬢さんはピーターラビットの絵本に出てくるような、ひらひらとした薄紫のエプロンをして、手にはゆで卵を持っていた。
「今日はよろしくお願いします」と言いながら手土産を紙袋から取り出したものの、お嬢さんは剥き身のゆで卵を持ってニコニコしているので渡せない。キッチンから顔を出した恵美子さんが「まぁまぁどうしたのそんな大層な」等と言いながらゆっくりと歩いてきて、私からクッキーの包みを受け取り、「則子が、ミナトちゃんが来るからって張り切っちゃってねぇ」と続けた。
食卓の上には左から順に、大量のゆで卵、エッグスライサー、スライス済みのゆで卵が入ったボウルが置かれていた。銀行の用事でお邪魔する時には食卓の上は片付けられているので、このような状態の食卓を目にするのは初めてだった。食卓の隅には、粗品でよく貰うサイズのタオルがきちんと折りたたまれて置かれている。台ふきん代わりだろうか。
お嬢さんは私に目くばせをするとエッグスライサーの窪みの上に持っていたゆで卵を置き、慎重にワイヤー部分を押しつけてゆで卵を10枚程度にスライスした。実印を押す時のような慎重さだ。
「一般のご家庭にあるの、初めて見ました」
と私が言うと、恵美子さんが満面の笑顔で「則子はこれを使うのが上手なのよねぇ」とお嬢さんを褒め始めた。
私があっけにとられていると、お嬢さんは「ミナトちゃん」と言いながらスライスしたゆで卵を鷲づかみにして、ボウルに移し、また新しいゆで卵をセットした。そして続けた。
「私、料理は母に任せっきりですけどね! コレだけはとっても得意なのよ!」
恵美子さんは先ほど渡したクッキーの包みを持ったまま、うんうんと誇らしげに頷いている。
お嬢さんは、還暦をとうの昔に過ぎたご年齢である。
喉元まで「えっ?」という疑問が出かかっていたが、私はそれを飲み込んで一緒に微笑んだ。
なお、私は誰とも知らないどこかのお嫁さんの反省を活かし、荷物を詰めたボストンバッグの一番上にエプロンを入れていた。エプロンは着いて5分で引っ張り出され、お嬢さんがスライスしまくったゆで卵は、着々とポテトサラダになりつつあった。
使い込まれた木製のまな板の上で人参を薄くスライスしながら、ふと思い立って「そう言えば妹さんはお仕事ですか?」と聞いてみる。なし崩し的に一緒に料理を始めてしまったが、山田仕郎の妹はずっとここに住んでいる筈だし、普段はお祖母ちゃんである恵美子さんと一緒に料理するかも知れない。そう思うと、途端に居心地が悪くなった。
「あの子なら寝てるわ」
「あっ、お休み中なんですね」と私は深く考えずに頷き、「ところで仕郎さんは」と続けた。
恵美子さんはマッシャーを手に大量のジャガイモと格闘する手を止めて、壁の時計を見た。
「この時間はテレビを見ているわねぇ」
どこでだ?
怪訝な顔をしてしまわないよう、私がにっこりとすると、お嬢さんが「仕郎は、今日は朝からこっちに来てますからね! 心配しなくても、隣の部屋にいますよ」とお菓子を食べる手を止めて教えてくれた。
そうこうしているうちに人参、胡瓜、玉ねぎを切り終えて塩で揉んでしまってもまだ、恵美子さんは大量のジャガイモと格闘していた。座ってお菓子を食べているお嬢さんは還暦を過ぎているが、恵美子さんも、もう八十を超えているのである。
私はマッシャーを受け取り、満身の力を込めて茹でたジャガイモを粉々にしながら、もう、どっから突っ込んでいいのかわっかんねぇな! と思った。
けれど、何となくわかる。多分、この環境であれば、私は自分で釣り上げたハードルくらいまでならばクリアできる。期待とか、そういうレベルの話じゃない。まだ家の敷居を跨いでから1時間も経っていなかったが、私は何となく確かなものを掴んだ気分でジャガイモを押しつぶし続けていた。