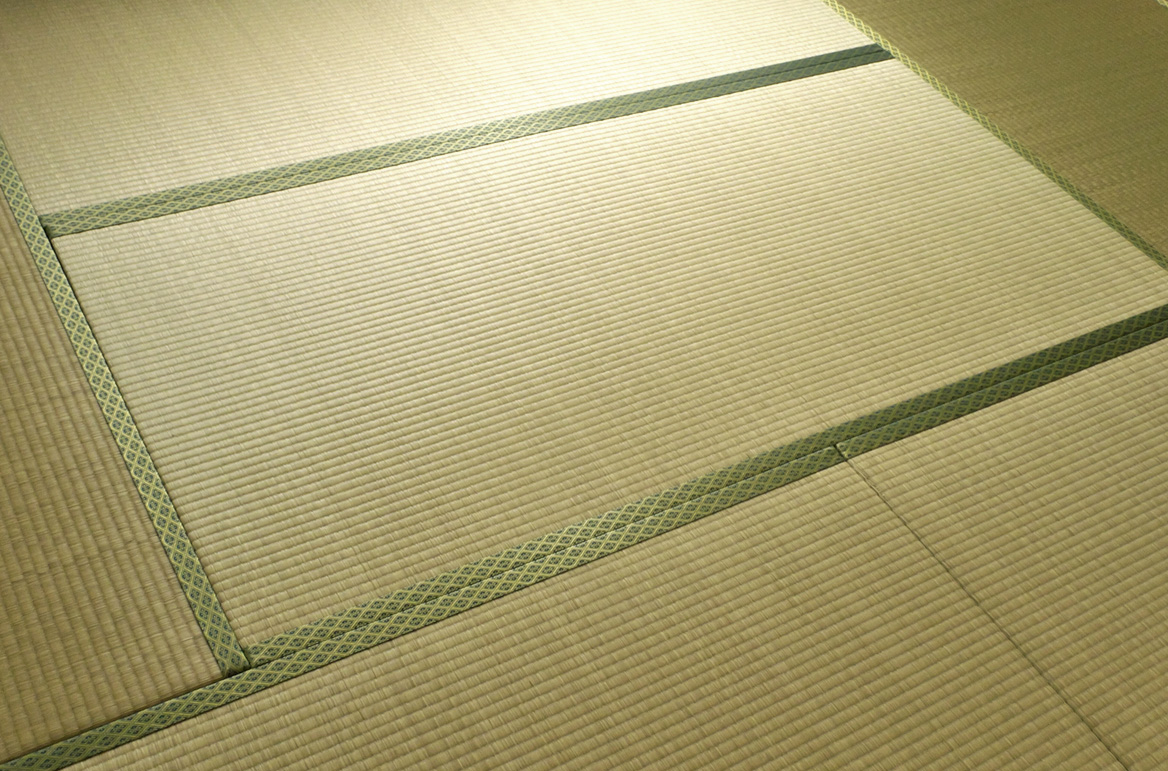今の時代、インターネットでちょっと検索すればいくらでも欲しい情報は手に入る。
私が調べたお見合いの手順は、釣書交換、お見合い、プロポーズ、親族顔合わせ、結納でとりあえずゴールだった。3月の釣書交換、4月にお見合い、肝心のプロポーズは、『エスカレーターで』『私から』『返事は「よろしくお願いします」の一言』、という奇妙な雰囲気だったが、ともかく言質は取った。当人が担当顧客のお孫さん、という、就業規則的に最高にNGと思われた件は、たった一回支店長を連れて恵美子さんのお宅を訪れるだけでどうにかなった。
私が身構えていた人事部からの呼び出しは、面談から数日経ち、一週間経っても何もなかった。逆に、人事部が面談に来ることもなかった。どうやら、私がお客様のお孫さんに手をつけた大罪人である、という情報は、支店長で止まったらしい。
新商品の勉強会や、業務監査や、日々の目標やらに紛れて、私が課長とコソコソと面談していたことも数週間で忘れ去られたし、ロビンちゃんもマミーポコも何も聞いてこなくなった。
一方、母は浮かれていた。
会社への報告も済ませ、親族顔合わせの食事会の予定も決まったある晩、帰宅するとゼクシィがダイニングテーブルに置いてあった。
初めてまじまじと見たゼクシィは、電話帳だった。電話帳にしては表紙がツヤツヤでファッション誌のような見た目だったが、そんなことよりも、殺意を持って握りしめ、その角で殴りつけたら流血の惨事くらいは引き起こせそうだな、というのが日本一売れていそうなブライダル情報誌を見た感想だった。「ゲスト」「おもてなし」「絶対後悔しない!」「ドレス」等の文字が大小さまざまなパズルのように表紙を埋め、外国人モデルがウエディングドレスに身を包み慈母のように微笑んでいた。
私は鞄からその日の日本経済新聞を取り出し、表紙の上に重ねてからそっと持ち上げて横にどかした。私が食事をとるスペースの真ん中に置いてあったのだ。
あまりの重さに「ウッ」という呻き声が漏れ、キッチンの母が振り返った。
「今日、ゼクシィ買ったのよ~」
見ればわかる。
「ありがとうございます」と私は言い、「重かったでしょう?」と続けた。
「それがねぇ、ゼクシィって、専用のバッグがあるのよね、ママ初めて知ったわ」
見せられた不織布のトートバッグは、それはそれは可愛らしく、ウエディングを夢見るオンナノコをイメージしたんだろうなぁ、と思わせる色合いと柄だった。
あっ、これ、見たことあるわ、と思い、私は会社の更衣室でゼクシィを見せられたことを唐突に思い出した。あれは窓口のお姉さまだった。あのお姉さまも、「専用のバッグがあるんだよ~初めて知ったよね~」とか何とか言っていた気がする。何故皆一様に同じようなことばかり言うのだろう。
「まさかママがゼクシィを買う日が来るなんてねぇ」と母は浮ついた様子で続け、私の返事を待つようにチラッとこちらを見た。『ありがとうございます』はさっき言ってしまった。『よかったですねぇ』は他人行儀すぎるから逆に怒りを買う。『あなた自身のことじゃない!!!』とヒステリックに叫ばれる未来が見え、私は更衣室でお姉さまから聞かされたネタを使った。確か、本屋でお祝いの言葉を言われるのだ。
「本屋さんで、おめでとうございますって言われませんでした?」と私が尋ねると母は嬉しそうに
「そうなのよ~」と頷いた。
出してもらった食事に箸をつけながら、聞いたところによると、母は本屋で娘の結婚を祝福され、大変得意な気分になったらしい。曰く、「レジに並んでいた後ろの人が、こちらを見ているのがわかった」と。
私はニコニコと話を聞きながら、猛烈に不愉快、と思った。けれどその不愉快さの正体はわからない。ただひたすらに不快だった。ゼクシィを振りかざして暴れたくなった。
「そう言えば、あちらのお宅との顔合わせ、秀ちゃんも大丈夫だって。ちゃんと連絡しておいたわよ」
そう、母が上機嫌な口調で報告してくれた秀ちゃんとは、私の弟である。
弟は、社会人2年目で、メーカーの営業をやっている。
激務のあまり帰宅時間がどんどん遅くなり、ある時から都内に住んでいる彼女の部屋に転がり込んでしまった。そのまま、なし崩し的に同棲し続けている。
弟の住居の変遷に母は寛容だったが、私がある時「秀ちゃんの今の状態って同棲?」という内容のことを聞いた時、「ママ、あなたがお花ちゃんと同棲したら気が狂って死ぬわ」と噛み合わない返事があって呆然としたことがあった。空恐ろしい宣告だった。
母は常日頃からお花ちゃんを認めていないと公言していたけれど、恐らく心の内では、はっきりとした脅威として認識していたのだと思う。あえて存在を無視している、と口に出して言うことで、存在を丸ごとなかったことにしたかったのかも知れない。
かくして五月の吉日、都内某所で親族顔合わせの食事会が行われた。
もちろん、事前の打ち合わせがあった。恵美子さんとお嬢さんのお宅を例によって例の如く外回りのついでに訪問し、段取りの説明を受けたのだ。
「ミナトさんを僕に下さい、って仕郎に言わせますからね!」とお嬢さんは大興奮しており、私は「あら本当ですか、楽しみです」等と笑った。
実際、楽しみだった。山田仕郎は、何となく段取りがちゃんと出来ていないとうまくそういうことを言葉に出来なさそうだったし、現にこの前の食事の時はしびれを切らした私が意思確認をしてしまった。
だから、流石に今回ばかりはちゃんときめてくるだろうと思っていたのだ。
しかし蓋を開けてみると、二人きりの食事会とほとんど同じで、山田仕郎はゆっくり食事をするだけで殆ど何も喋らなかった。恵美子さんとお嬢さん、それに私の母で女が三人寄って楽しくお喋りしてしまったところに、接待モードの父と弟が入ったので、食事会自体は傍目には大成功だったと思う。
瞬く間に2時間ばかりの時間が過ぎ、親同士で子に関するあらゆる情報交換され、全員が息を継ぐタイミングが奇跡的に重なって、ふいにシン、とする瞬間が訪れた。
チャンスだ、と思った。
今まで黙って粛々と食事をとり続けていた山田仕郎、今がチャンスだ。
少なくとも私が男だったら、このタイミングで「お嬢さんを私に下さい」と言う。むしろ、今しかない。
だって、盛大に盛り上がっている会話に上手く溶け込みながら話の流れを自分の方に誘導し、「ところで……」等と切り出すことなど山田仕郎には不可能そうだったから。
けれど、沈黙を破ったのはお嬢さんだった。
「ところで、ミナトちゃんを本当にいただいてよろしいんでしょうか」そう、感極まった声でお嬢さんは言い、母が「もちろんです」と答えるまでがワンセットだった。ワンセットの茶番であった。