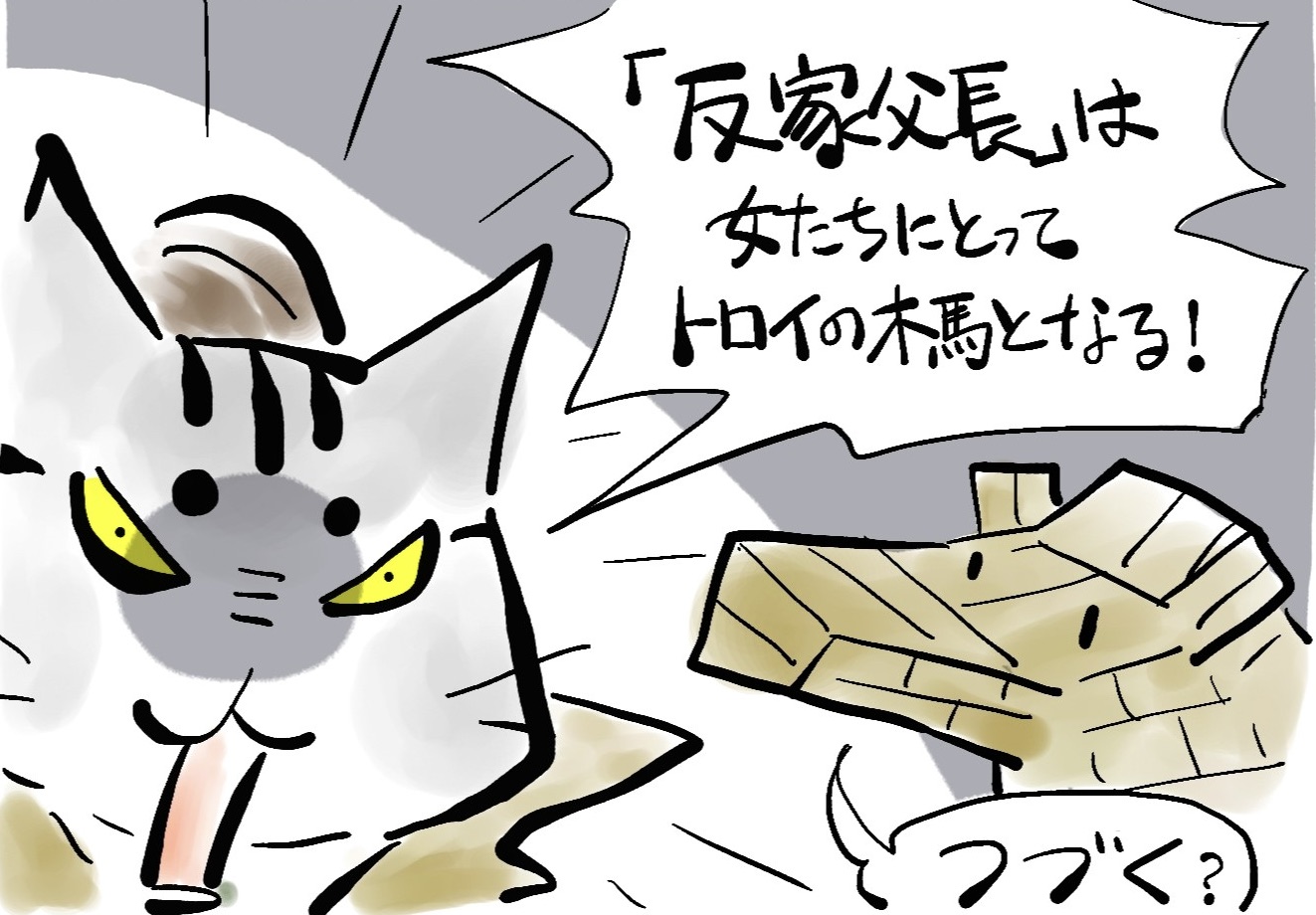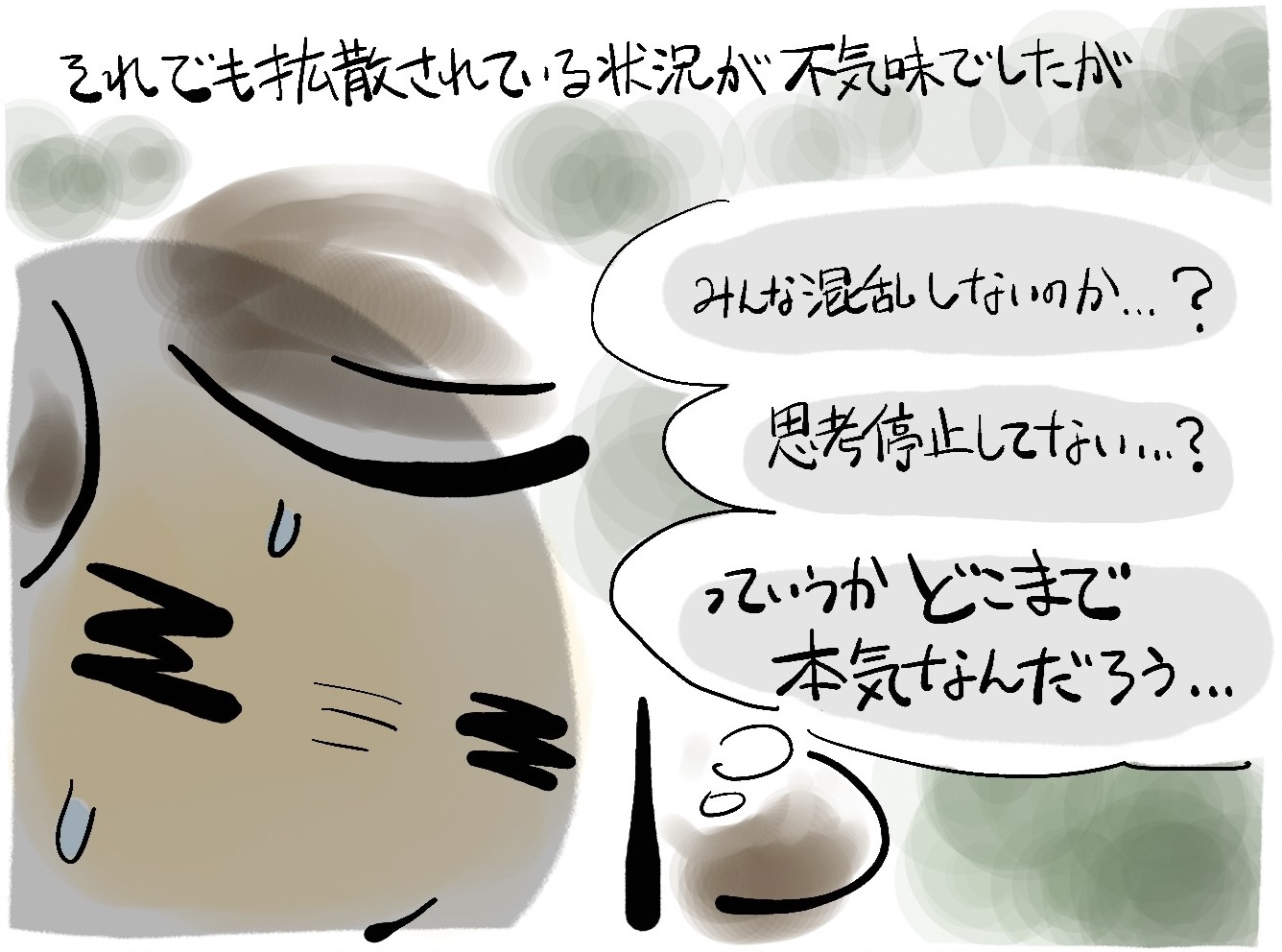あと、見ていないのは『君の名は』だけだわ・・と、誰かのツイッターを見たときに知りました。
この夏の日本映画で見に行ったのは、『シン・ゴジラ』と『後妻業の女』と『怒り』という作品でした。
それは、冒頭のアニメ映画を含めて、すべて東宝だというつぶやきでした。
すっかり東宝にやられてました。職場の店舗改装でくそ忙しい時に限って、映画に行ってしまいます。現実逃避かストレス発散です。
それでいえば、ゴジラと後妻業は「あーおもしろかった」ですみました。助かりました、ありがとう、と隣近所に醤油を借りに行った感じです。したことありませんが。
『怒り』は、もやっとしました。
【*観ていない方は、ネタバレ注意!】
まただわ・・、と既視感です。同じ原作者と同じ監督の前作『悪人』を見たときのことを思い出しました。あの時も、妻夫木聡の裸を見なければいけないので見に行ったのでした。動機が不純なうえに、どちらも原作を読んでいないので、またとんちんかんなことを言い始めますが勘弁してやってください。
『悪人』のときは、すべての登場人物が気持ち悪くて感情移入できず、また、その世界の設定にも共感できなかったのでした。そんなことを職場の同僚に言ったら、「よくそこまでねじまがった視点をもてるね」みたいなことを言われて、このコラムでもそのことについて書かせてもらいました。
それなのにまた、妻夫木聡の裸・・しかもゲイ役、綾野剛との絡みあり、のせいで同じ轍を踏みに行ってしまいました。
文句を言うなら見に行かなきゃいいのに、と思いますが、今度はわからないじゃない、と自分に言い返します。
そう、今回はそんな私でも楽しめる部分がいくつかありました。
たくさんの方が指摘していますが、妻夫木聡の演じたゲイは、いわゆるオネエ言葉を連発する女装のゲイではなく、おそらく、その他多数のゲイの姿であったことや、沖縄の基地問題を、米兵の性暴力を正面からとりあげることで浮き彫りにしたことも、メジャーな映画で表現されたことの意味は大きかったと思われます。
物語は、世田谷区で起きた夫婦殺害事件の犯人が逃亡中、というところから始まって(画面の入り方がハリソン・フォードの『逃亡者』!)、その犯人が、新宿で妻夫木聡と付き合うことになった綾野剛か、千葉の漁港にあらわれた松山ケンイチか、沖縄の無人島で生活する森山未来か、というサスペンスの要素を含みながら進んでいきます。
いったい犯人は誰やねん、というところが巧妙で、犯人の似顔絵も全員に似ているし、三つのほくろはさすがにあとで、ずるいと思いましたが、そのミステリーは最後まで楽しめました。
最後に犯人がわかるのですが、まったくもってすっきりしませんでした。しかも、肝心の犯人が殺されるって・・。
被害者の関係者に殺されるならわかります。その場合は、2時間ドラマのセオリーだと、けっこう早い段階で殺されるはずです。そうなると見どころは、その関係者が誰か、なぜ殺したか、になって、最後の崖のシーンに至るわけです。
『怒り』では海辺でしたが、ちょっと、エンタメか文学かどっちかにしてよ、と思うくらい大げさな死に方してました。あそこまでいくと、太陽にほえろの松田優作です。
作者の吉田修一さんも、「ダ・ヴィンチ」のインタビューか何かでおっしゃってましたが、わざとそこを狙っているようです。大衆小説でもなく、純文学でもないところ。あるいは、どちらも超えたところ?
それは難しい課題だわ、と映画を見て思いました。2時間ドラマもそうですが、観衆の快楽をつかむセオリーが決まっているからこそ、胸を打つ瞬間が生まれるということもあるからです。
それこそ『後妻業の女』はエンターテイメントに徹していて、まったく罪悪感のない主人公だからこそ、殺害シーンでの「黄昏のビギン」が響いてくるわけです。あるいはベッド・ミドラーの歌声が。
どちらにも転べない場合、観客としては醒めてしまいます。『怒り』は観終わったあと、なんかあざとかったわ、とまで思ってしまいました。
「もやっと感」の原因の一つはたぶんそれで、もう一つは、やっぱり「男の世界」に集約されていたところでしょうか。
ツイッターで、「BL求めて行くなんて」という非難も目にしましたが、私には、女が出てこないBLの世界とかぶりました。形式として、であって、内容のことではありません。
読んだ人の話を聞くと原作は違うみたいですが(読めよ)、映画には、物言う大人の女が池脇千鶴以外出てきませんでした。しかもほんの少し。広瀬すずの母親とか、居酒屋のおかみさんとか、原日出子とか、なぜしゃべらない。宮崎あおいは泣いてばかりだし、広瀬すずとともに、あくまで保護の必要な子供の設定になっていたと思います。
メインは男性陣で女性はその盛り上げ役に見えました。
同じ、李相日監督の『フラガール』が好きなので、その点が残念です。あの作品では主役は女性たちでしたが、脇の男性たちも独立した人として描かれていたと思います。
極めつけは、渡辺謙の「男の背中」でした。出たー! と思わず心の中で叫びました。顔で良くない? な、泣けない・・。
相手を信じられない自分への怒りと、自分をそんな目に合わせた社会への怒りがブレンドされている作品だ、と理解はしました。
けれど、渡辺謙でいえば、風俗で働いていた娘に対する近所の醜聞に耐える父親で、妻夫木聡でいえば、ゲイであることを世間(会社)にばれたくない小金持ちで、そこまではありがちなことなのに、耐えたり隠したりすることを、人間の弱さとしてクローズアップしすぎるから見ていて、息苦しい。
風俗で働くことや、ゲイであること自体には、もっとあっけらかんとした強さ(主体性)もあるはずなのに、その視点がどうして出てこないのかが不思議でした。そういう「怒り」はないのでしょうか。
もっと言えば、そうした視点を提供するのはフェミニズムで、ああ、だから物言う女が出てこないのか、「男の世界」が壊れるからか、とうがつのです。
去年公開された、ハリウッド映画の『マッド・マックス』には、フェミの視点が取り入れられていたと聞き、楽しく見た私は納得しました。
一方の、渡辺謙の背中・・、ねえそれ、そんなに気持ちいいですか。それがこの国の映画賞の基準ですか。
沖縄編で、広瀬すずが、大きな体の米兵にレイプされているとき、公園の水道の陰に隠れて、膝を震わせて座り込んでいた同級生の男の子の姿だけが、私にとって真実でした。