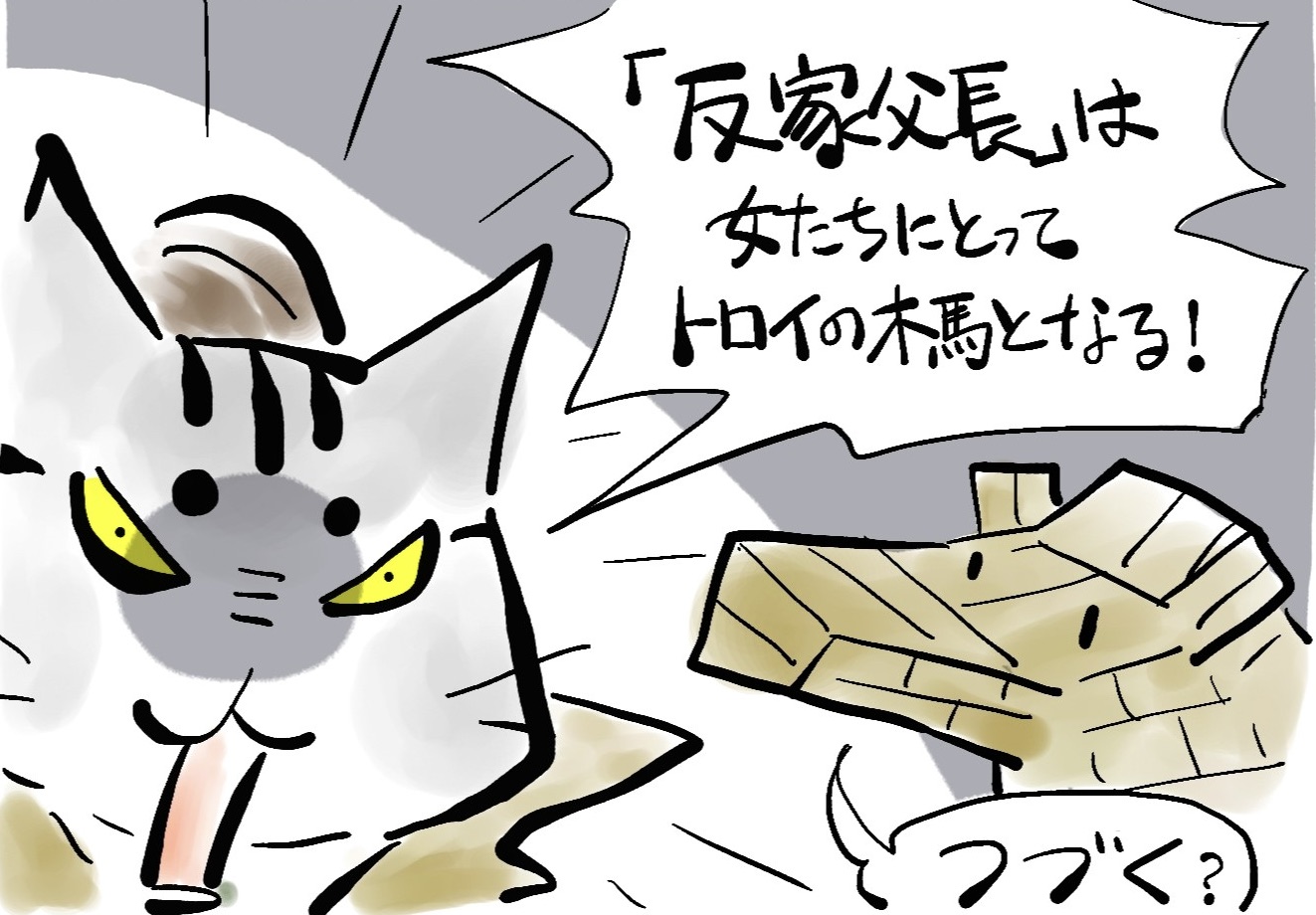差別というのは日常に転がっている。何気ない会話の中に、視線の中に差別を見つけた時私は緩んでいた心が緊張に引き戻される感覚を覚える。
「2丁目とか行って、オネエたちと話してみたいけど、女の人に狙われたら困る~(笑)どんなにかっこよくても、女同志は無理。いくら彼氏がいないからって、そこまで困っちゃいないわ(大笑)」
なんでもない日常会話の中で、親しくなりかけた知人から漏れた言葉には、差別がいっぱいだった。オネエが支持され、TVでもてはやされ、LGBTという言葉の広まりと共に、理解も深まっていると思われているこの時代でも、まだまだ出るこの手の会話。自分とは別世界の出来事として語られる感じは相変わらず。むしろエンタメの一つにでもなっているような、一つのお家芸みたいに見られているような感じさえしてしまう。もちろん、存在が肯定されることはうれしい。20年前、30年前には自分を表す言葉が、オカマかレズ、もしくは変態しかなかったのに比べ、差別的でない言い方で自分を人に話すことだってできるようになったことはすごい進歩だ。生きやすくもなっている、でもその一方で、ある一定の所から理解が深まっていないのではないか、これからも深まることはないのではと思うことがある。“自分とは別世界に生きる人達で、周りにもいるかも知れないけど、私は深く理解する必要はない、だって何となく知ってるもん”そんなノリを感じることがあるからだ。
個と個として理解を深めることなく、概論で深める心を伴わない理解は時として凶器にもなる。
「最近LGBTとか言われる人が社会で優遇されてるけど、ああいう人がいてもいいけど、ちょっと特別扱いされ過ぎてない?あれどうなんだろうね?ふつうの人だって仕事なかったり、いじめあったりいろいろあって苦労してる人もいるのに、そういう人助けないで、なんかずるいよね」
私がマイノリティだと知らない人から出た言葉。同性パートナーも生命保険の受取人になれる保険が出来て、同性パートナーを配偶者として認める会社があるという記事を読みながら出た話しだった。一緒にその話を聞いていた数人もなんとなく同調している。
「みんな平等に税金使ってもらわないと困るよね。言ったもんがちみたいな感じじゃない。生活保護の人だって、パチンコとか行くんでしょう。私も行きたいよ。そんなお金あれば。」
優遇なんてされてないし、“ふつうの人”より優遇されていることなんて何もない。当たり前に“ふつうの人”が使えるシステムを、使えなかったセクシャルマイノリティがようやく普通に使えるようになった、しかもほんの一部で。それが優遇なんて!しかも民間会社のシステムに税金なんて使われてないし、そもそもセクシャルマイノリティのための政策に多額の税金使われてないでしょう・・・・・!突っ込み所満載の会話。しかしそんな稚拙な会話をしている当人たちは、なんか物知り顔で社会を論じている風になっている。
見えないものがなくなっているような今の社会で、誰もが情報通で、誰もが評論家になっている。それはセクシャルマイノリティだけの話ではない。
7月26日に起きた神奈川の「津久井やまゆり園」での事件。しょうがい者を家族に持つ私にとっては、体が震える事件だった。私はあの日から、カラダに心に染み込んだ昔の記憶が刺激され怖くてたまらない。“ふつうの人”、隣に住む気のいいおばさんや、子供から信頼される熱血教師にも潜んでいた“差別の視線”。それは特別な人が抱く感情ではないのだ。そして、表面では隠せても心の奥にある“差別の視線”は、他人ごとではなくなった時に露わになる。
あれは小学校5年生の時だった。トモダチの家に遊びに行き、優しい顔のお母さんが私にだけ聞こえる声でこういった。
「アンティルちゃんは大変ね。お姉さん来年中学ね。学校どうするの?○中に行くの?でも偉いわ。大変なのにアンティルちゃんのお母さんもあなたも明るくて。お姉さんがあんな障害を持って、私なら生きていけないわ。偉いわね。」
凍りついた私をよそに、友達が夏休みの計画を母親に打ち明けた。
子供「お母さん、今度アンティルの家に泊まりに行ってもいい?アンティルとアンティルのお姉さんと夏休みの宿題するの。」
「ちょっとこっちに来なさい。(少し離れた台所に行く)アンティルちゃんの家には行くなと言ってるでしょう。あのこのお姉さんの病気、うつるかもしれないのよ。あなたがどもったりしたらママ、生きていけないわ。勉強だって、一緒にやったらバカになるわよ」
戻ってきたその子の顔は恐怖に歪み、私に言った。
「ごめんねアンティル、お泊りに行けない」
その後ろで母親が満面の笑みを浮かべていた。
「犯人をそうさせたのは、大麻だ、病気だ、施設だ、介護システムだ、安い労働をさせた施設だ・・・」とあちらこちらで論議になっているが、私はこの論議が嫌でたまらない。
差別の問題、自分の心に眠る差別と偏見に向き合うことなく、事件を“特別なこと”、“特別な人”の異様な出来事とし済まそうとして悪を叩こうとする人達の声が顔となり、私の頭の中であの母親の顔と重なっていく。
あの事件、私には優生思想の広まりの中で起きた、それを肯定する人の犯行にしか思えてならないのだ。この時代に優生思想を黙認し、差別を肯定する人は一部の“キチガイ”だけじゃない。肯定も否定もしない人達だ。一部の報道で、しょうがい者が安楽死できる社会をと、しょうがい者の家族の“負担”を考えているかのような内容の手紙を犯人が衆議院院長に書いたと報じられている。この社会を考えているふり、正義感の匂いは、今ネットの中で蔓延している匂いと似てはいないだろうか。
あの犯人に何があったのか、どういう状態だったのかはわからない。本当に病気だったのかもしれないし、薬がなんらかの作用をしたかもしれない。でもこのような事件が起きた理由、今後起こさないために必要なのものを犯人の体内や社会のシステムだけに原因を求めるのでなく、必要なのは、私たちの心の中にある。ネットに向かう“ふつうの”論客達の声の広まりを見ながら私は恐怖を拭えない。