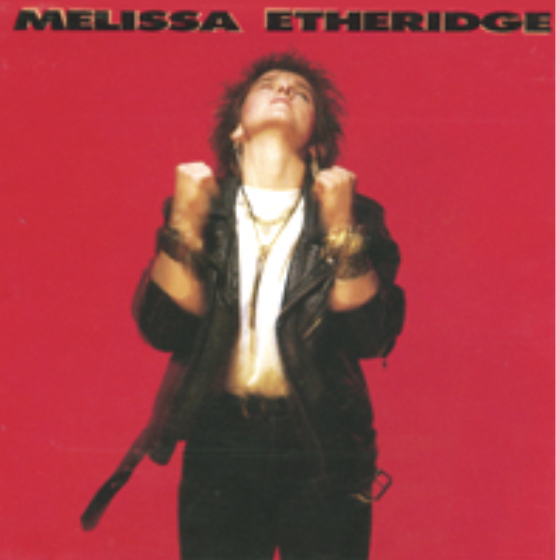冷たい風が肌につき刺さるような寒い夜、温かい飲み物を手に、ケイト・ブッシュの『雪のための50の言葉』(50 Words For Snow)に耳を傾ける。物静かなピアノの音色がからだのなかに浸み込むようなプロローグ。<雪の中から生まれた僕・・・>と一人称の少年の心象風景を、ケイトは抱擁感に満ちた歌声で綴りはじめる。<この世界はとても騒がしいの。 ・・・・僕は氷と塵。僕は空>。
ケイト・ブッシュのアルバムは、そのプレイスイッチを入れた後、またたく間にいまここに居る現実を忘れさせ、ケイト・ブッシュというアーティストが創り出す物語世界へ聴く者を誘う。『雪のための50の物語』は2005年にリリースされた『エアリアル』(Aerial)から6年という月日を経て2011年に発表されたいまの時点での彼女の最新アルバムだ。
1978年「嵐が丘」(Wuthering Heights)で衝撃のデビューを果して以来、30年以上のキャリアを常に第一線で歩み続ける最も偉大なる英国ロック女性アーティストとして世界中の人々から称賛、尊敬されている。私も大好きなアーティスト。
リアルタイムで初めてケイトのアルバムを聞いたのは1985年に出た『愛のかたち』(Hounds Of Love)。そのアルバムからシングルカットされたいくつかの曲のプロモーションビデオが、当時公開された映画『未来世紀ブラジル』を彷彿とさせる作品や、好みだった個性派俳優ドナルド・サザーランドが科学者役でケイト演ずる娘の父親に扮し、巨大なマシンで雲を撃ち幸福の雨を降らせる物語は見事な映像美のSFショートフィルムのようであり、かつてはこれらを何度も繰り返し見入った。
「嵐が丘」からすでに30年もの年月が経つが、そのアグレッシヴで鮮やかな楽曲はいまでも瞬時にトリップし、当時のビデオでの取りつかれたような摩訶不思議な彼女のパフォーマンスが脳裏によみがえり身体が反応する。この頃のケイトは『天使と小悪魔』というデビューアルバムのタイトルが示すように、小悪魔的な天才アーティストという雰囲気が漂っていたが、いまはむしろロック界のジャンヌ・ダルクのような存在感であったのかもと思う。他に類をみない前衛性、この上ない美しい旋律と、狂気を孕んだ唸りと揺らぎ。だがそこにはさまざまな芸術作品(本、映画、演劇など)にインスパイアされて膨らんだ創造世界から、愛をつきつめ、人間の底知れない内面を追究し、精神のギリギリまで自らを追いつめてコントロールする。その独創的な世界観に他のアーティストたちは追随を達し得ない。
「嵐が丘」はエミリー・ブロンテの同名小説がモチーフとなっているが、映画『ブロンテ姉妹』(1979年アンドレ・テシネ監督)でエミリー・ブロンテを演じた女優イジャベル・アジャーニが放ったパッション、知的さ、美しさ、そしてアーティストとしての業のようなものに当時は同類の匂いを感じた。その『ブロンテ姉妹』の荒野を思うとき、ふと中島みゆきの「ローリング」が思い出されたりもする。
大スターの名声に奢ることなく常に実験的なサウンドを追究したケイト・ブッシュ。デビューから疾走していたころの作品は彼女自身何度もダビングを繰り返し神経的にも追いつめられたというが、それらを聴く側も深く浸かりすぎるとなかなかこちらの世界に戻ってこられない麻薬のような激しいものもあった。1985年の『愛のかたち』でその過剰な激しさはつきものが落ちたようにバランスよく解凍していく。そして1989年の『センシュアル・ワールド』(The Sensual World)では愛する人の肌と肌が触れ合うときののぞくぞくするような官能的でスリリングなサウンドを生み出していく。
ケイト・ブッシュのアルバムは、いまここにいる私が異空間にタイムスリップし、イングランドの冷たい霧のたちこめる風景を背に夢と現を彷徨いながら、人々や動物と交差する。まるで短編小説のなかに迷いこんだかのように。
俗世間から遠くはなれた世界に生きているようなケイト。そんな彼女の言葉が世界中の多くの人々を虜にするのは、そこに歌われる人間の心理が普遍的なものだからだろう。
そして彼女はしっかりといまの世界を見つめている。『雪のための50の言葉』の「スノーフレイク」を聞いて私はそう確信した。
<この世界はとても騒がしいの。降り続けて。あなたをみつけるわ>。
現在は愛する家族にかこまれて幸せに満ちたケイトだからこそ、聴く者を癒すことができるのかもしれない。<私たちが必要なら、いつでも声をかけて。うんざりな世の中は天使の手に預けて。>『雪のための50の言葉』の物語は「天使にかこまれて」で頁を閉じる。