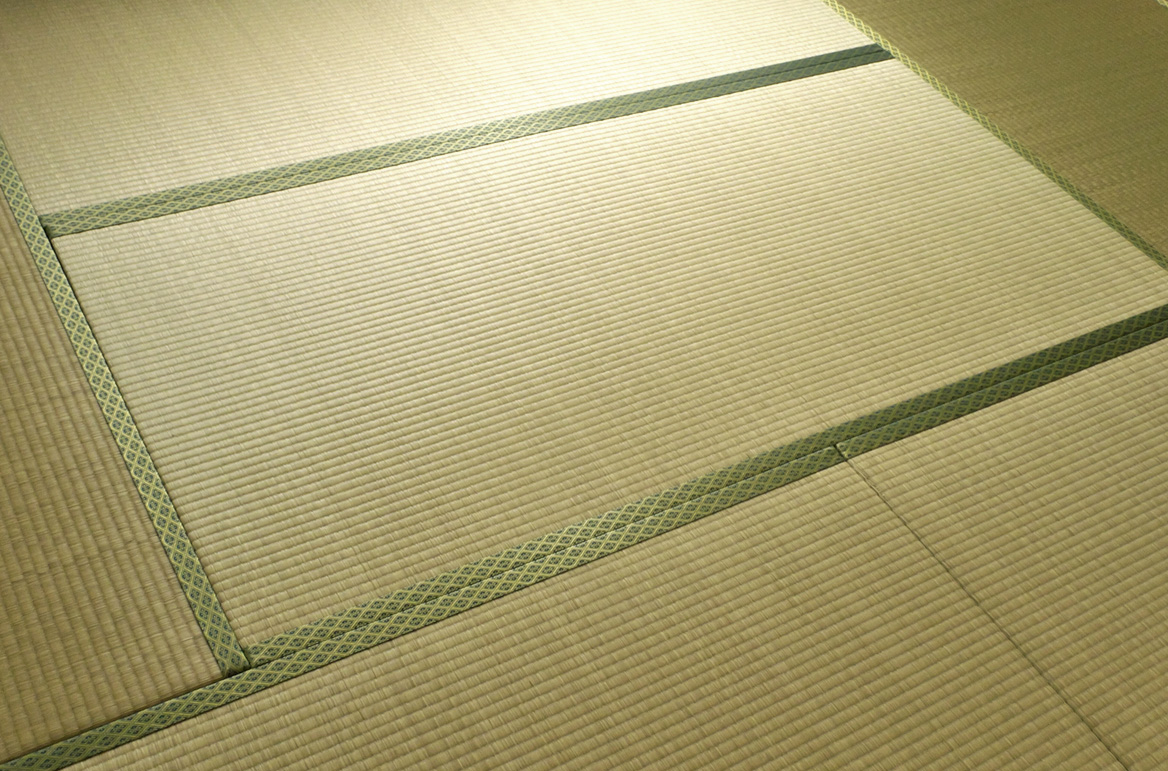恵美子さんとお嬢さんと私は、恵美子さんの練ったプランから少し迂回しながら、プロポーズという目的地に向かって突き進んでいた。
恵美子さんのもとを訪ねるたび、「仕郎からメール来たかしら?」という一言が、「こんにちは」と同じくらいの感覚で出てくるようになった。そして仕郎からメールは来ていない。震災の晩以降、一切の連絡がない。
やきもきした恵美子さんは、大胆にも支店に電話をかけてきた。
銀行が開店する9時を少し過ぎた頃「菊池さん外線で電話だよ」と言われ、出ると恵美子さんである。
『ミナトちゃん、仕郎のことで電話してごめんなさいね』
「いえいえ、大丈夫ですよ」
そう言ったものの、銀行内でこの話をすることにはさすがに罪悪感があった。悪いことをしているというか、人の目が気になる。外回り中だったなら顧客と自分の一対一だが、社内にいる間は身内の目があるし、同じフロア内で話している電話の内容というのは案外よく聞こえる。この期に及んで、私はまだ上司に何の報告もしていなかった。
私の空気を察してか、恵美子さんは「差し支えがあるようだったら、『はい』か『いいえ』で答えてちょうだい」と、ドラマのようなことを言った。傘寿をとうに過ぎた恵美子さんの妙に芝居がかった調子に、非日常感を感じて少しわくわくする。良くないスリルである。
『仕郎からメールはあったかしら?』
「いえ、まだですね」
『ミナトちゃんにも予定があるでしょうから、早く連絡しなさいって書き置きもしてきたんだけれど』
書き置き? 山田仕郎は一人暮らしの筈なので、部屋に行く用事でもあったのだろうか。
突っ込んで聞きたいけれど、状況的に聞けない。
『もう日にちがないから、ここで伝えるわね』と恵美子さんは続け、翌週の週末の日付を言った。
『この日のお昼は予定を空けておいてね』と言った恵美子さんの後ろでお嬢さんが、『日が落ちる前にミナトちゃんはお帰ししますから!』と叫んでいる。お元気である。
「はぁい」と笑いながら言って、いくつか相場の話をし、電話を切ると課長がすぐ後ろにいた。いつから立っていたのか気付かなかった。やましいことだらけであったが、今更、こんなタイミングで報告するつもりはない。
「最近よく言ってる、あそこか」
「はい」
受話器の音は案外音漏れするので、聞こえていたかも知れないなぁ、とぼんやり考えた。恵美子さんから日付を告げられた時、メモを取らずにカレンダーを眺めるにとどめた数分前の自分を誉めたい。休日の日付のメモなんて握っていたら怪しすぎる。
とりあえず、課長の目に映るのは、卓上カレンダーを片手に相場の話をしていた私なので、セーフである、多分。
「お客さんの懐に入り込むことは、いいことだがなぁ」
そう言い残して、課長は壁面の書類棚の方へ歩いて行った。そっと周りを見回すと、ロビンちゃんが不思議そうにこちらを見ていた。
かくして、山田仕郎からは何の音沙汰もないまま当日を迎えた。
待ち合わせの場所は丸の内のオフィスビルの一角で、恵美子さんが予約したお店はその商業ゾーンに入っているフレンチである。結局、あの後恵美子さんのマンションに行く機会があり、日取りを決めたいきさつからお店を予約した顛末まで、全て聞いてしまったのである。
平均気温を上回る暖かさです、と前日の天気予報が言った通りになり、その日は大変春らしい陽気だった。東京駅で降りて、電力需給の関係でどこまでも薄暗い地下通路をを歩きながら、お嬢さんが用意していたスーツを思い出す。ツイードっぽい厚手のスーツだった。私はというと、ワンピースで、あまりの暖かさにコートを脱いで手で持っていた。
何となく、気温の変化などお構いなしに、母親に用意されたスーツで現れそうだなぁと思っていたら、案の定その姿で待ち合わせ場所に立っていた。直立不動で、どこか遠くの方を見ている。全然こちらに気付かないので駆け寄ると、とりあえずこちらに気付いたが何も言わない。
「こんにちは、お待たせしちゃいましたか?」と謝ると、
「僕は、早めに行動するようにしていますので」と言ったきり、一歩も動かない。
「じゃあ行きましょうか」と私が言って、私が先導した。エスカレーターが見えると、山田仕郎はスッと前に出て、ごく自然な動作で先に乗り、エスカレーターから降りると、そのまま待っている。「お店は2階ですよ」と声をかけると頷いたものの、やはり先に歩こうとはしない。
お花ちゃんにあれだけ適当に扱われていたので、何も、男が女の荷物を持つのは当然でしょ、とか、車道側は男が歩くよね、とか、そういう思想と自分は別のところにあると思っていた。だがこれは何かおかしい。開始早々、まだ食事も始まっていないのに、そして全然お互いのことを知らない筈なのに、山田仕郎の所作からは一貫した何かを感じた。このまま行くと、お店で予約名を告げる役割もこちらに回ってきそうである。
「予約は山田さんのお名前ですか」と確認すると頷いたので、もうどうにでもなれと思って、店の入り口でドアを開けて微笑むギャルソンに「予約の山田です」と言い放った。私が。
これは山田仕郎なりの渾身のボケで、実は会ってからずっとツッコミ待ちで、私は試されているのだろうか。
案の定上座に座ってしまった山田仕郎が真面目な顔でメニューを吟味する様子を眺めていると、不思議な心持がした。