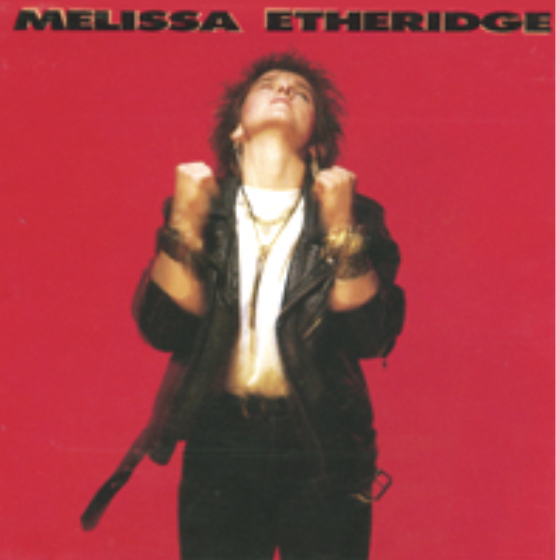11月某日、相も変わらずNHK「紅白歌合戦」の出場歌手発表なるニュースが、メディアを駆け巡る。まだやるのか紅白、だれがみるのか紅白・・・である。
私は中高生のころ、邦楽アレルギーみたいな時期があった。邦楽というか歌謡曲アレルギーといったほうがよいか。クラシック音楽以外は鎖国状態であった家への反動も大きかった。ある大晦日の晩、恒例の紅白を見ながら家族団欒という場を外した私に家族のひとりが言った。「紅白を見なかったということを正月の親戚の集まりで言うんじゃないよ」と。当時の私には衝撃的な忠告だった。紅白を見ないということがいったいいかほどに世間体を悪くするというのか。いまだに紅白報道がはじまると、自身に起こったこの出来事を思いだす。
〈私たち日本人が六十年以上にわたって「紅白」を見続けてきたのは、そこに〈安住の地〉を見出してきたからである。〉とは昨年出版された太田省一著『紅白歌合戦と日本人』という本の帯に書かれた言葉だ。おいおい、私たち日本人がってのはやめてくれないか、と思いながらも、生家での紅白を見ない者は非国民的な同調圧力の根源が何かしら語られているのではないかと気になり読んでみた。歌は世につれ世は歌につれ、といった戦後の大衆音楽史観的な事柄に多くの頁をついやしつつ、個々の歌手への薀蓄を述べていくあたりはかなりオタク的な感も。そんな書の冒頭に興味深いことが書いてあった。1945年まだラジオ放送の時代に提案された紅白企画担当者による番組構成上の3つのエレメンツ、それは「3つのS(セックス、スポーツ、スピード)」と要約される。こと男性と女性、は絶対的なもので番組構成上最大の武器であり、〈男女対抗、つまり性別(セックス)に基づく対戦という形式は、体格や体力差が影響するスポーツではありえない〉、歌だからこそ男女対等が可能。占領初期のGHQが求める婦人の解放、男女平等を、スポーツをモデルとする歌合戦で実現できると考えた、とのこと。
番組誕生から数十年にわたって頑なに拘り続けた男女対抗という性別二元論。中村中が2007年紅組で初出場。2012年、美輪明宏が白組で初出場となり少々揺らぐ。初出場決定の際「私は白と紅の中間の桃色組。衣装はヌードです」と語ったという美輪明宏が短髪黒髪の男装で「ヨイトマケの唄」を歌い話題をさらったのは記憶に新しい。

私が唯一手元に置き聞き入る美輪明宏のCDが1枚ある。レコードでは1975年に発表された『白呪』だ。「メケメケ」も「愛の賛歌」も入っていない全10曲中9曲が美輪自身の作詞作曲によるオリジナルアルバム。兵士たちが行進する軍靴の足音、北の地青森から南の沖縄まで〈売られ買われて 今日も旅行く〉と語りかけるようにはじまる「祖国と女達(従軍慰安婦の唄)」を1曲目とするアルバムのA面(あえてレコード時代を喚起して)。そこで美輪は、戦時下とその直後の弱き立場にいる者たちの哀しいありさまを綴る。2曲目「悪魔」ではその最中人々が狂気に陥る様を。「ポタ山の星」、「ヨイトマケの唄」ではどん底での労働、貧しさといった現実の酷さ突きつけながらも、父ちゃん、母ちゃん、子どもたちへの慈しみ溢れる愛情を。5曲目「亡霊たちの行進」、葬送行進曲ではじまるこの曲は〈見てくれ 見てくれ 戦の答えを〉と戦後の亡霊と闘い抗う。そして第一部(A面)は幕を閉じる。B面、第二幕「陽はまた昇る」「別れの子守歌」と浪漫漂うエレジーで酔わせ、コミカルな「あたしはドジな女」で聴く耳をやわらげ、祈るように唄う最終曲「さいはての海に唄う」でアルバムは終わる。それにしても「祖国と女達」の1コーラスごとの最後に囁く“バンザイ バンザイ”のなんと冷めたことだろう。この“バンザイ”が、最後に〈大日本帝国バンザイ バンザイ バンザイ〉という叫びに代わり冷徹に国家をつきはなす。
前出の書は、紅白は日本の時代ごとの変化に伴って視聴者の郷愁をよびさます安住の地を創り出すという。そんな安住の地は私はいらない。「さいはての海に唄う」に響く大海の波音、そこに見出すやすらぎこそが歌に込められた安住の地、と私はおもう。
今年も美輪明宏は白組から紅白出場というが、桃色といわず十人十色組で「祖国と女達」を歌い、紅白歌合戦は今年でお終いと宣言・・・そんなことをふと妄想するのであった。