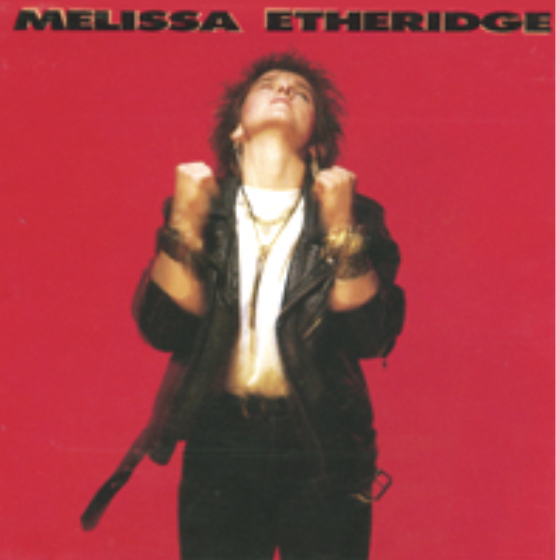今夜は夏の番外編ということで、クィーンについて書きたい。8月17日サマーソニックで観た彼らのライブがあまりにも素晴らしかったからだ。
私とクィーンとの出会いは小学生の頃にまで遡る。5年生で新しい組となり知り合ったばかりのクラスメイトの女子、Mさんから誕生会の招待を受けた。ただし条件がある。それはプレゼントにクィーンのレコード(ドーナツ盤といわれた7inchシングルレコード)を持ってくること。背も高く中学生にも思えるくらいに大人びた雰囲気のMさんと仲良くなりたかった私は、その条件を承諾し小金井の今はなき長崎屋というショッピングセンターの中にあった名曲堂へ、Mさんが書いてくれたメモを片手にクィーンのレコードを買いに行った。Mさんからクィーンというのはイギリスの4人組のロックバンドであると教えてもらいはしたものの、そのとき私はクィーンの音楽なんて聞いたこともなかった。英語もまだ学校で習っていないから、Mさんが私に依頼した曲のタイトルが難しくて覚えられなくメモしてもらったのだ。私が買ったのは「ボヘミアン・ラプソディ」。誕生会はMさんの母親が女将をしていた居酒屋で催された(もちろん営業時間外の土曜の昼にジュースで乾杯)。集まった彼女の友達は、私と同じくそれぞれに違う曲のクィーンのシングルレコードをプレゼントに持ってきた。お店にあるステレオで順々にそれらのレコードを、クィーンがグラビアでたんまり露出していたロック雑誌を眺めながらみんなで聴いた。
とにかく「かっこよかった」。私にとって未知の世界のロックミュージックに無我夢中で耽溺し友達にもそのすばらしさを教えてくれるMさん、そして英語で何をいっているかなんて全くわからなくてもこれまで聞いてきたどんな音楽とも違う激しいエネルギーを放出するクィーンの音楽。その後、私はMさんからクィーンのシングル盤を全部貸してもらい、カセットテープに録音し歌詞をノートに書き写し、我が家にあった唯一のステレオラジカセでヘッドフォンをつけて何度も何度も聞き狂った。家族の人々にはどんなに美しい旋律を奏で4?5オクターブの声を変幻自在に操るフレディの歌の上手さをもってしてもクィーンは歓迎されず、「野蛮」な騒音として認識すらされなかった。清く正しく真面目で保守的な家庭内にはありえなかった文化、クィーンの放つ美しい「野蛮」さに、当時の私は、何かしら窮屈で抗うことができなかった家の抑圧からの解放を得たのかもしれない。
今回のクィーンのコンサートは1982年生まれのアメリカ人アダム・ランバートがヴォーカリストとして加入。『アメリカン・アイドル』というオーデション番組で全米各地からの応募者が毎回課題曲を与えられ歌い振り落とされていく中で、2009年度の準優勝となったアダム。このTV番組は当時リアルタイムで見ていたが、初めて彼を見たときから、その歌力としなやかさと華やかさを兼ねたオーラにくぎ付けになり、この人は必ずや近い将来クィーンのヴォーカリストとなるだろうという確信を私は感じていた。そして機は熟した。ソロアーチストとしても活躍し、同性愛者であることもカミングアウトし、どんどんと精悍にそして野性的な風貌と風格を兼ね備えてきたアダム・ランバートは、フレディ・マーキュリー不在のクィーンを今世紀の新たなステージへと引き上げた。ギターのブライアン・メイ、ドラムのロジャー・テイラー、すでに初老に達したオリジナルメンバー2人もアダムの歌声に呼応しフレディがいたころに勝るとも劣らない、張りのある激しくのびやかな貫禄のプレイで魅了した。フレディの不在という、いまだファンの身にある惜別の思いに対して、全身全霊をもってかつてのヒット曲の数々を歌うアダム・ランバートからほとばしるエネルギーは、いまこの会場の天上にて美しく華麗に生まれなおしているクィーンの新たな門出を見守る者としてのフレディの存在をも呼び起こした。「ボヘミアン・ラブソディ」ほか数曲で映し出されたフレディの映像から、まるでわが父の魂のバトンを受け渡されたかのように歌い継ぐアダム・ランバート。
フレディをはじめ各メンバーみなインテリジェンスな素のあるクィーン、いまだ唯一無二の華麗なる美意識を持ち続け、フレディの持つ野性的なエネルギーと新しいサウンドへの嗅覚と貪欲こそがクィーンの普遍的な魅力なのだとあらためて再確認する。「ラブ・オブ・マイ・ライフ」、「サムバディ・トゥ・ラブ」・・・、私がいま大好きなクィーンの曲は“愛”を歌うものが多い。大きな愛だ。性別、国籍、そんなものを大きく踏み越え、愛の業ともいえるくらいの過剰さ。人の根源が持つ本能的な愛(性欲も含む)を知的なデリカシーとの絶妙なバランスで作り上げられた名曲の数々。この夜のステージで、アダム・ランバートは自身のなかにも存在するのであろうこの愛のカルマを体現した。
小学生のときノートに書き写し刻み込まれた歌の数々を私もいっしょに歌いまくった。そこにはノスタルジーやセンチメンタルはなく、さあこれからまた新しい何かが生まれていくのだという期待と多幸感にあふれて。