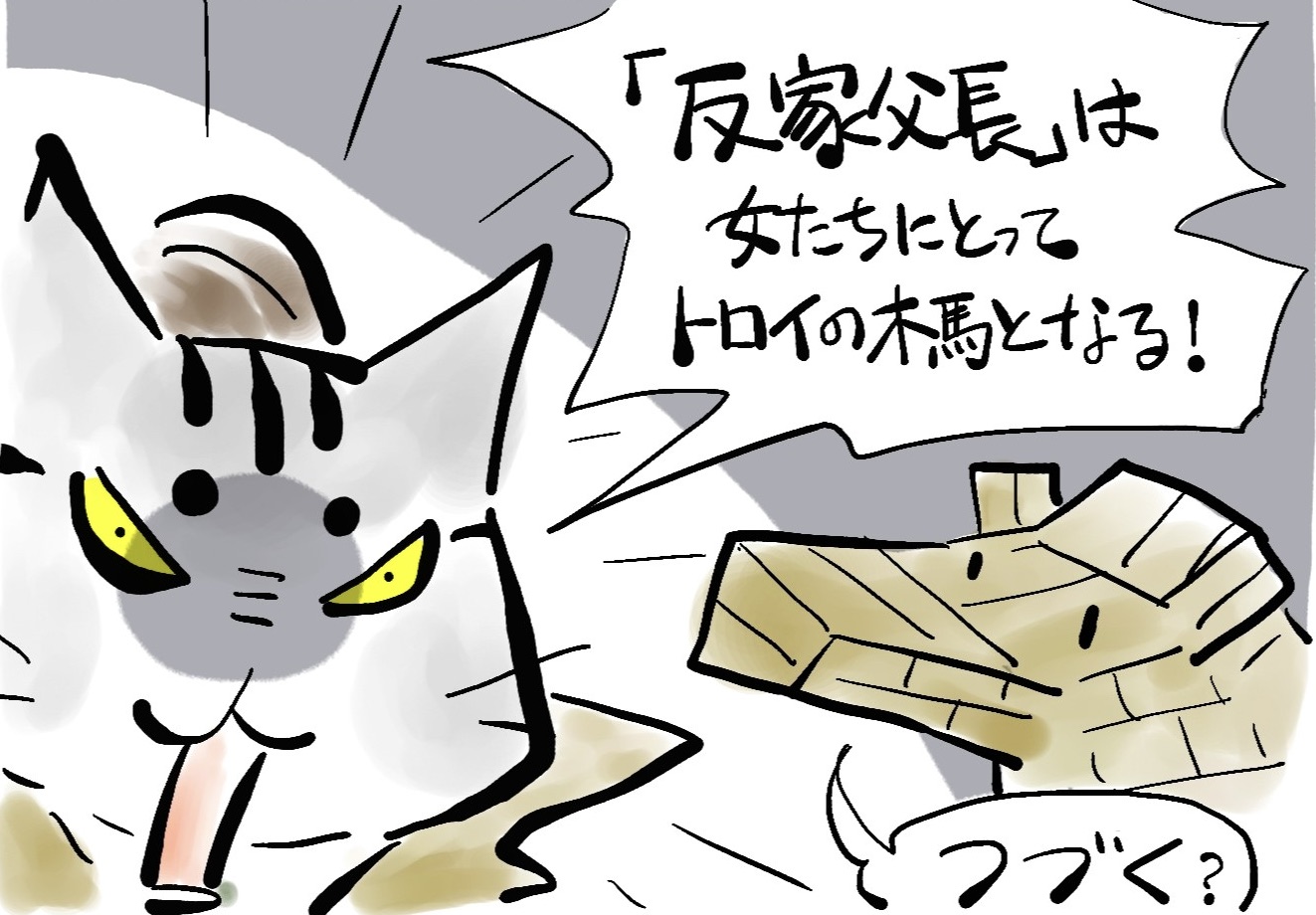Loading...

時代は90年代そこそこ。今にしてみれば、まだバブルの名残りがプンプンだった頃、私は社会人として東京にいた。入社してから数年、仕事を覚え始め、自分で考え、自分の手でモノを作るということの楽しさにハマリ始めていた。私という人間が現れたことに慣れ始めた仕事の現場では、その反応が数パターンに分かれていた。
見かけは“オトコ”名刺には“オンナの名前”という人間の登場に慣れて、距離を縮める人、距離を縮めたように装いながらも、私のことをいろいろ詮索しようとする人、
私に露骨な嫌悪感を抱く人。
会社の中にはほとんどおらず、曜日ごとにいろんな現場を持たなければならない私は、実に多くの人と関わっていた。その視線に怯える気持ちは常に消えなかったが、学生の頃とは違う“開き直り”が私にはあった。『私は私、何か問題でも?』名刺を差し出した時や、私がオンナだとわかる時の、相手の興味津々の目線に、先に視線をはずしたら負け、と、動物のような闘いを繰り広げる毎日。私は新たなベクトルを手に入れたことで、自分を支えることを知り始めていた。私の生き方だけでなく、私が作るもの、私の仕事が私を表す一つの要素になっていた。。少しずつ積み上げ、崩し、また積み上げ、仕事を通し私を見る人が増えて良くも悪くも評価されることで、私は自分を取り戻していった。
その頃、私は自分より一回り歳の離れた女性たちと仕事をすることが多かった。仕事というものを通して築く人間関係、そして信頼関係は、それまでのどの人間関係より地に足の着いた、でも緊張感が抜けることのない関係だった。
私が徹夜で書いた原稿用紙にダメだしが入る。
「こんなの使えないわ。もういい。私が全て書き直すから」
「こんな仕事されたら迷惑よ」
そんな言葉が出るのは日常茶飯事だった。それでも私はまた原稿用紙に自分から向かい続けられた。その現場で自分のキャリアを築き上げていった彼女達の指摘はいつも完璧だった。
「今回は完全じゃないけどまぁ、使えるわね」。そう言われると、私は生きていることを、排除されていた社会に自分が立っていることを実感できた。自分の手で、足で、一つ一つ扉を開けているそんな気分になった。
仕事を通して私を信頼してくれた人達は、私の味方にもなっていった。仕事が終われば、下積みでお金のなかった私にお酒を飲ませてくれて、私に暴力的な好奇心を向ける人の間で私を守ってくれていた。
そんな一人が、Fさんだ。仕事にストイックで、そしてその仕事を心底好きだったFさん。怖すぎて人が近寄らないFさんと週に3回、10時間近く2人で原稿用紙に向かう生活が始まった。しごかれ、それでも自分の考えを伝え、話し合い、それでもダメだしされ・・・その繰り返し。その中で一緒に築いていったモノがまた一つまた一つ増えていく2年間だった。
それから数年後、Fさんとの仕事が終わると決まった日。Fさんは私にこういった。
「30代も後半になってくると、オンナは消耗品になるのよ。」
Fさんはこれまでの10年以上のキャリアに見合わない“クビ切り”に遭っていたのだ。理由は“世代交代”「もうこの仕事が終わったら仕事はすべて無くなるの。フリーだからね、しょうがないけど。スーパーで働こうかって思ってる。」
その頃、私は20代前半。今にして思えば、その悔しさを完全に理解していなかったと思う。「Fさんなら絶対大丈夫。私も会社に話してみるから!」
私の力などなんの役にもならなかった。
仕事がなくなったFさんは、本当にスーパーで働いていた。Fさんの才能は誰もが認めていたのに、でもその才能が消えていくことには無関心だった。私はただFさんのそばにいた。
それからさらに数年後、仕事の忙しさに追われ、日に日にFさんと会う時間がなくなっていた頃、TVの中にFさんはいた。スーパーに勤めながら、自分のやりたいことは何かを徹底的に考え抜き、そのために何が必要か見極めたFさんは、自分の才能を想像も絶する苦労で磨き続けたのだ。この世界にFさんあり。Fさんは自分を信じ、そして諦めず、そして闘い抜いた。
今でもFさんはTVの中にいる。「30代後半のオンナは使い捨てられる。オンナは新鮮な方がいいんだって」そう言ったFさんは、怒りだけにしがみつかず、自分を鍛えて男社会に自分の存在を知らしめたのだ。自分を誰よりも信頼して。
私の前にはいつも、年上のオンナ達がいた。私は彼女達によって育てられた。最近は会うこともなくなったFさんに今、無性に会いたい。