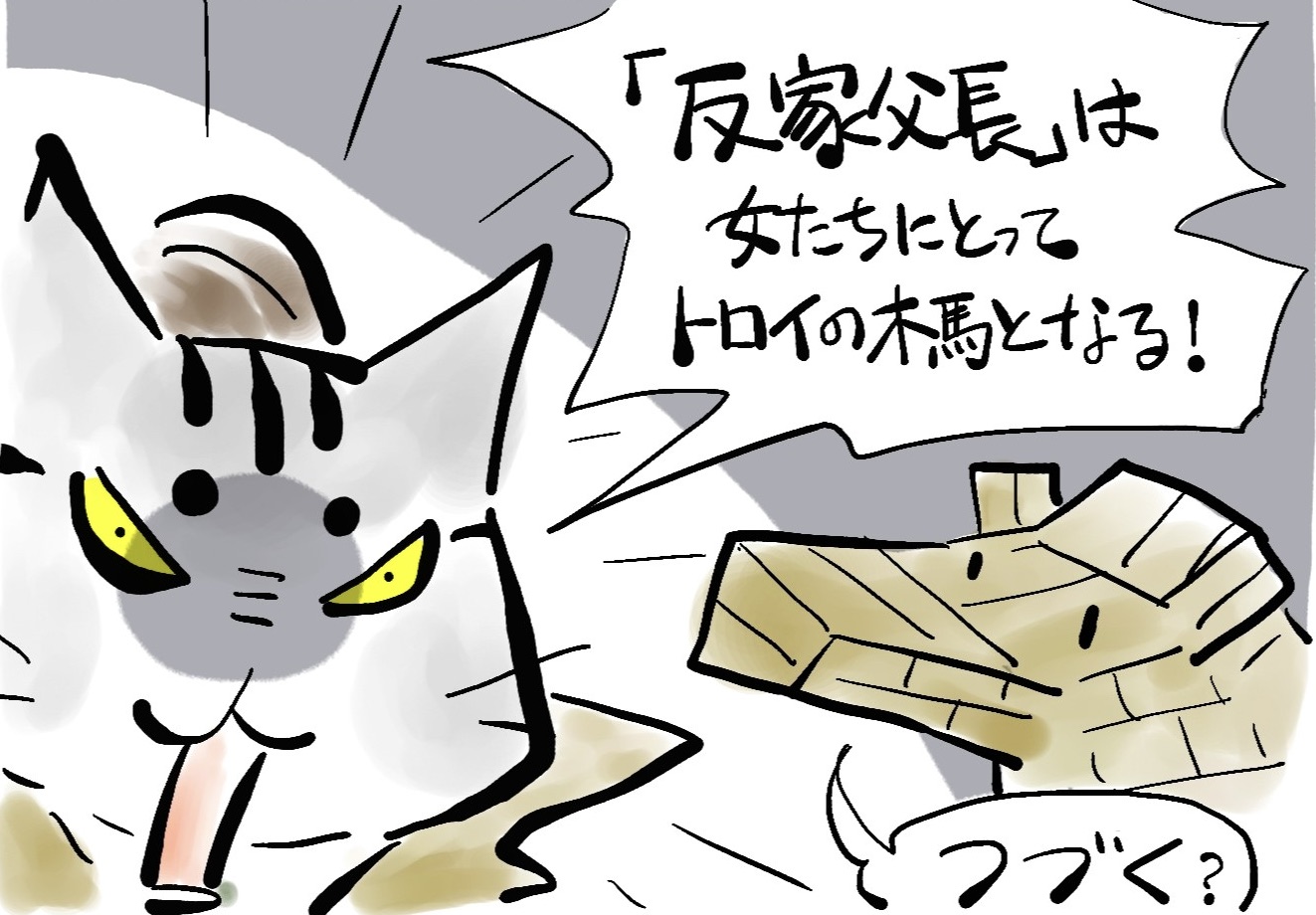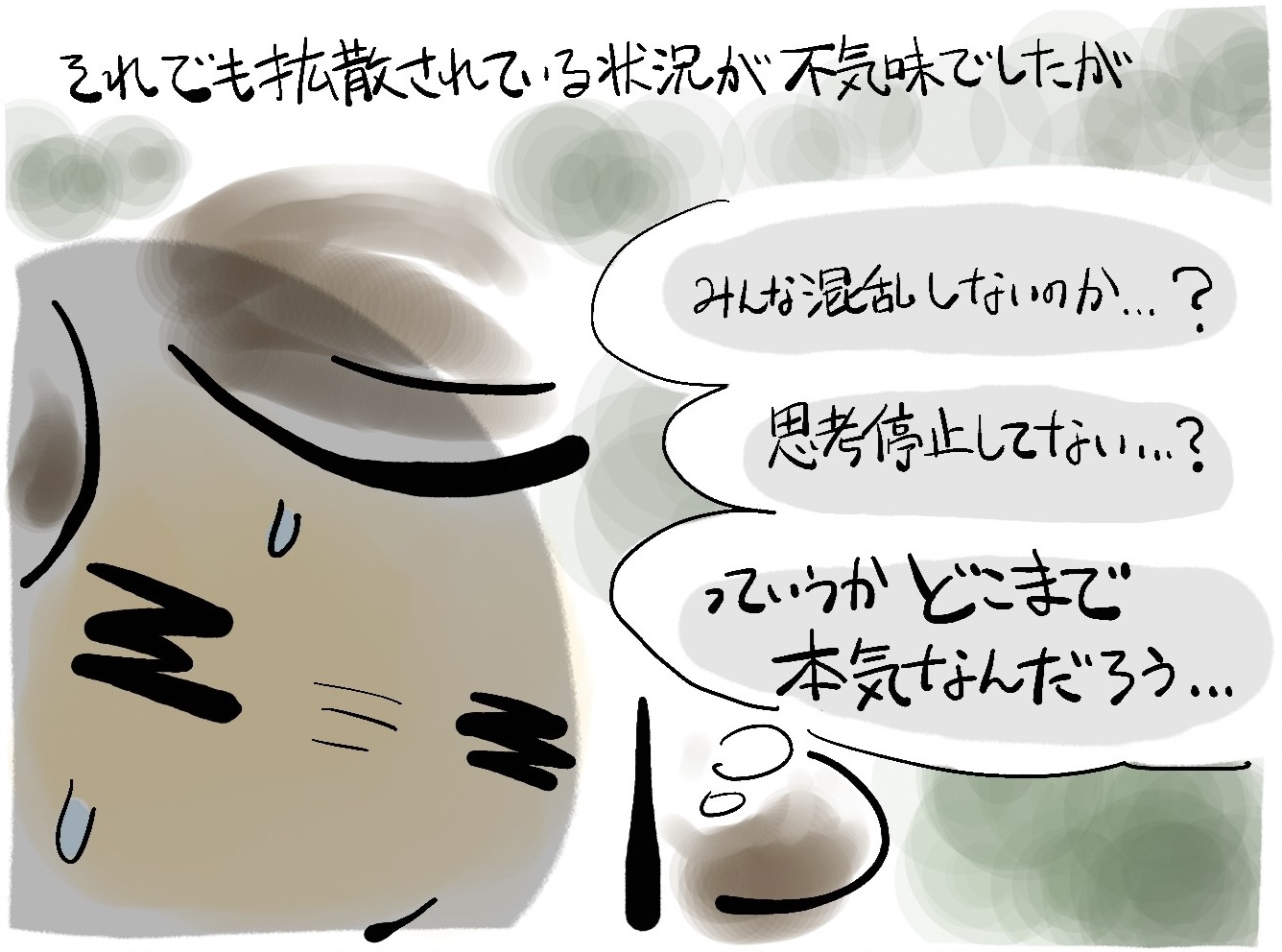更新が遅くなってすみません。
地元の大阪に帰ってきました。
春先に、父から仕事を手伝ってくれ、と言われて、それはないわ、と思っていたものの、そのあと毎日のように考えてしまって、やってみるか、と思い始めて、再び返事を訊きに来た父に、お願いします、と頭を下げたのでした。
自分で言うのも何ですが、なかなか大きな決断でした。そのうち、私が決めた、というより、なにか抗えないものに巻き込まれていくようなことかもしれない、と漠然と思うようになりました。
というわけで、新宿二丁目は去ってしまいました。
「捨ててゆく私」ではありますが、このままコラムを続けることになりました。二丁目で働きながら感じる何かを書く、といった初志とは異なりますが、これからも書かせていただきます。今後ともよろしくお願いします。
大阪へ帰ると決めてから、半年の猶予をもらいました。そのあいだに、徐々に周りの人に話していきました。
「社長の息子だったの?」「ぼんぼん!」「家業を継ぐんですって」「そんなオチが!」
と、にぎやかな席では、そんな言葉たちが飛び交いました。
「いやいや社長といっても、零細企業で・・」「家業ではなく、父の経営している会社に入るだけで・・」「これでオシマイじゃなくて・・」
と言葉少なめに抵抗してみるのですが、ドラマティックな仕立てを好まれるのか、
「零細っていうけど、社員は何人?・・ふんふん、それだけいればたいしたものよ」「本屋の息子だなんてぴったりじゃない」「新たな旅立ちね!」
と、どうしても現実に沿った流れに変えられず、ついに、「まあ、共産党系の会社ですけどね」と意味のわからない返しをして、興ざめさせていました。
とはいえ、大勢の前ではからかい口調の人たちも、マンツーマンになれば色々と不安な胸のうちを聞いてくれました。その中で、「茶屋君も思春期が終わったってことだよ」と仰ってくれた方がいました。「ようこそ、大人の世界へ」とも。
年齢を気にせずに言えば、たしかにそうなのかもしれません。
二丁目に来た当初の、自分がしていた半分女装みたいな格好を思い出しました。
だんだんとその必要性が薄れて行って、服もすべてメンズに変わりました。
それでも一人称「あたし」は変わらず、やはり女っぽいと言われ続けていましたが、それでも二丁目以前の、自らそう仕向けていた状態ではなく、そうした演出をしなくなった(と自分では思う)状態で、そう言われるのとではわけが違いました。
「女みたい」と言われても、もうどうでもいいや、という感じです。だからといって、今度は言動が男装に向かうのかというと、それも違う気がしました。
そんな状態でも、色っぽいことが少しは起きて、いろんなことが思い通りにはいかないことを思い知ったりもして、今年に入ってちょうど一息ついたような、それを「思春期が終わった」と言うのなら、そうかもしれないと思ったのです。
職場もその後飲みに行くゲイバーも出会う人はみんなゲイという環境は、とてもラッキーなことでした。変な例えですが、ノンケの世界ってこんな感じなのかな、といったふうです。異性が意識しあうのがあたりまえ(同性が意識しあうのがあたりまえ)、好きなタイプは人それぞれ、それが日常としてある感じです。セックスの隠し方が違う。
エロ本を隠れて読んでいることがばれても、男だから・・みたいな許容があるけれど、そのエロ本のグラビアが男の裸なら、げっ! と拒絶が入る違いというか。
けっきょく隠すとしても、実は「エロ」ってすべての物事の中心にあるといっても過言ではない気がします(って、たぶん誰かのパクリです)。
みんながゲイの中で、そのエロが中心にあって、そんな居心地のいい世界で、私は散々飲んだくれて、いろんな自分の姿を見たのでした。
二十九歳から三十七歳まで、十年ほど遅い(それどころじゃないかも・・)思春期だったのかもしれません。そういう過程が私には必要だったのかな・・と思います。
月末に仕事を辞めてから、二週間ほど友人宅に居候させてもらって、最後の東京生活をぶらぶら送りました。
毎日好きな時間まで寝て、行きたいところへ行って、会いたい人に会いに行って、また飲んで、ずっと読めないでいた分厚い小説を一気読みして・・、「大人になる」ってこういうことができなくなることかもしれない、などと、ふと思いました。
もちろん今までも毎日働いていましたが、背後に保護者がいるような気楽さがありました。その実際の保護者の元へ帰るはずなのに、この先はもう保護者がいなくなっていくという現実に緊張します。
父親の仕事を手伝いに帰る、という話に、「親にいい子だと思われたいのか」とか、「いつまで親離れができないの?」といったことも言われましたが、それは違いました。むしろ親離れしたから帰るような気持ちでした。あと十年をたたずして始まるだろう、親の体のことを思うと、まだ元気なうちに、近くにすべりこんでおいたほうがいいような気もしたのです。いずれ向き合うことなら、私もまだ若いうちに(若いかどうかはさておき)。
学生時代の友達のなかで誰よりも早く子どもを産んだひとは、このコラムを読んでくれるたびに、「茶屋君のコラムは現実を忘れるために読むねん」と言っていました。
二十代から、子育てに、ダンナとダンナの母親との関係に、社宅での付き合い、ヤクルトレディーの仕事に追われていた彼女には、私の生活は別世界だったのかもしれません。
その彼女にも電話で報告すると、「それはええことやわ。茶屋君の自分探しはそれだけ時間がかかった、ちゅうことやね」とあっさり言って、今はPTAと思春期の娘への対応が悩ましい、と笑いました。