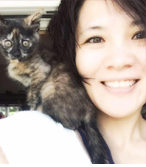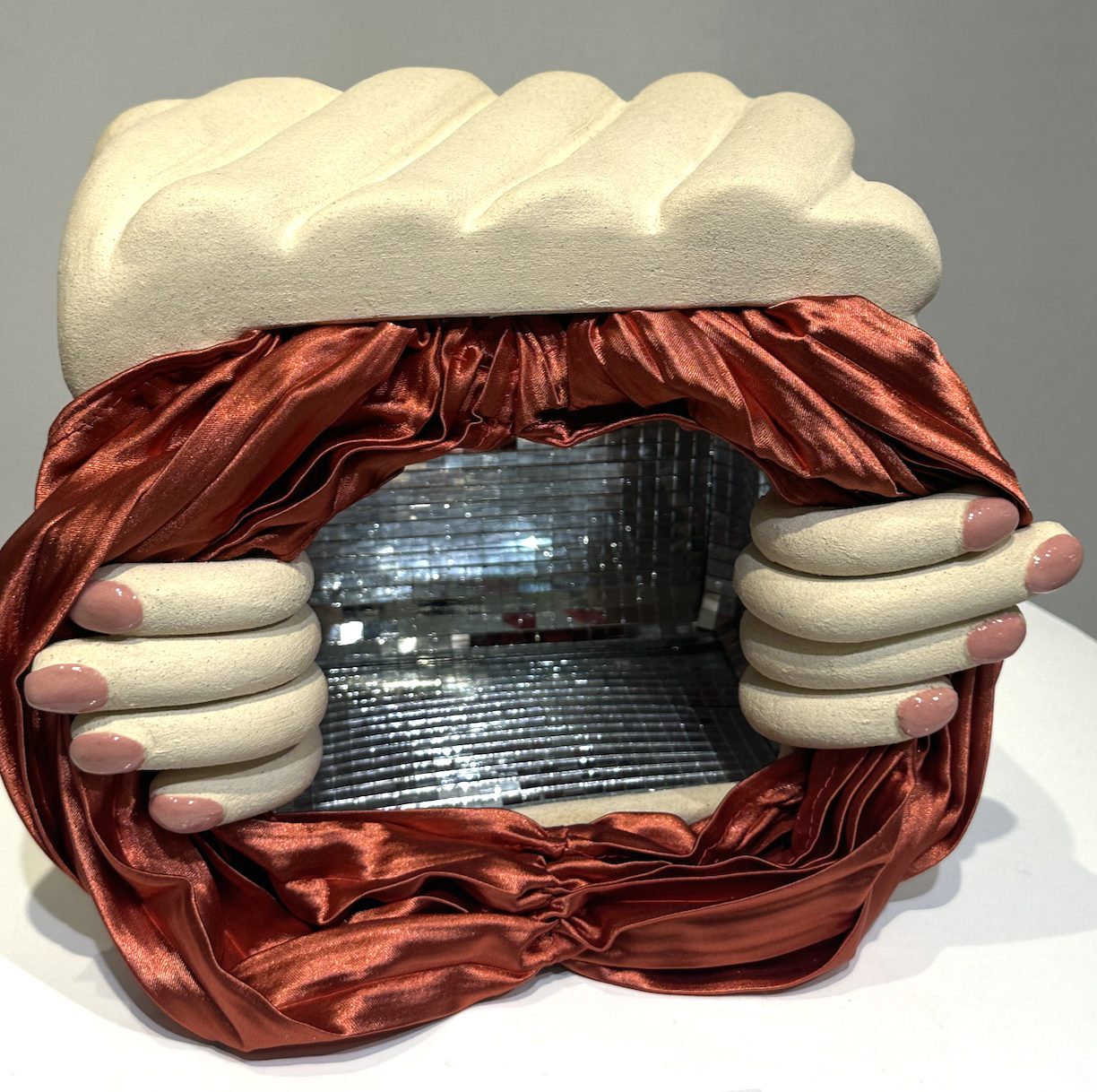先週末、被災地のボランティアセンターに行った。特に事前に申し込みは必要ない。朝と午後、決められた時間決められた場所に行き、そこで名前を登録するだけ。事前に必要なのは東京でボランティア保険に入ることだが、現地でもできる。誰もが気軽に行け働ける、よくできたシステムだと思う。
週末だったので受付の30分前からすでに多くの人が受け付けに列を作っていた。聞いてはいたが年配の男性が目立った。ボランティアセンターのスタッフは皆若く、てきぱきと声をあげながら慣れた調子で働いている。
受付で登録を済ますと、今度は名前の書かれたピンクの付箋をもらい、それを仕事を振り分ける人の所に持っていく。ちなみに男性は黄色い付箋。仕事を振り分ける人は、ファイルされている仕事内容をみながら、黄色やピンクの付箋をファイルに貼り付けていく。力仕事は黄色、そうでもない仕事はピンクと分けているようだった。
私はピンク5枚黄1枚のグループに回された。仕事は「壁の拭き掃除」と知らされた。泥かきやヘドロ掬いなどやるべきことがたくさんあると聞いていたので、壁の拭き掃除という仕事は意外だった。
聞けば作業内容はセンターが決めるのではなく、「こういう作業をしてほしい」という依頼が各家から送られて来るのだそうだ。その要望を電話などで事前に聞き取り調査をしてから、ボランティアに来た人をマッチングして派遣するという方法。
さていよいよ出発。出発前に一人リーダーを決めてくれ、とセンターの人に言われた。フェミとしては少しだけ緊張感が走った。案の定たった一人の男性にリーダーをお願いします、という雰囲気になったからだ。違うグループでは「力仕事の現場なので、リーダーは男性がいいかと思います。女性でもできますけど」と言っている女性スタッフがいたので、このボランティアセンターではリーダーは男性、という暗黙の了解ができているようだった。
結局、一緒に行った友人がリーダーになったのだが、それは、男性が携帯を持っていなくてセンターとのやりとりに不都合が生じるから、という理由。
ちょっとしたことだけれども、仕事が当たり前のようにジェンダー化されているのは、やっぱりね、というか、新鮮ね、というか、日本らしい、というべきか。もちろん口に出して抗議することはなく、はいはい、おばさんは掃除得意よぉ、リーダーなんてできないわぁ、と迎えに来たバスに乗り込みはするのだけれど。
バスで連れていかれたのは海から2キロほど離れた住宅街だった。区画整備された新興住宅地で、新しい家が目立つ。震災直後はがれきの山だった道も今はゴミ一つなく、穏やかな日曜の住宅地そのものだ。ボランティア作業を希望した家は、小さな庭のある、窓の大きな、感じのいいお家だった。ガレージの天井が少しひしゃげてはいるが、外側からは震災を想像することはできない。が、ひとたび中に入ると、2メートル近く浸水したという一階は、がらんどうだった。海水が断熱材まで染みこんだ壁は触るとズブと指が入り、天井の方も泥がはねていた。畳はすでにはがされていて、大きな家具は運び出された後だった。もちろん住める状態ではないのだが、水道などのライフラインは通っている。
その家で私たちを待っていたのは40代半ばくらいの女性だった。夫と中学生の息子二人は全員無事だったそうだ。彼女は女性ボランティアの顔は一切見ず、男性の顔を見ながら今日の作業の説明をした。壁と床の拭き掃除と台所掃除。何度もボランティア派遣を受けているとかで、慣れた様子だった。
正直に言うと壁や床を拭くのは、明らかに無駄だと感じた。すでに壁紙のほとんどは海水でふやけ破れていたし、床も同様で、海水でワックスが浮き出ていた。たまたまグループの中に日本語を話さない外国人がいたのだけど、彼女は「この床、剥がすよね?」と聞いてきた。誰が見てもそう感じたのではないか。
もちろん頼まれたことは何でもやろうと思っていたし、仕事を選ぶ立場ではないとはわかってる。何よりも私はものすごく張り切っていたのだ。だからこそ役に立ちたかった。だからこそ、念のために聞いてみた。
「壁紙は、このままお使いになるんですか?」と。そこで女性は初めて私の顔をみて、こういった。
「主人に聞かないとわかりません」
わからないけど汚いからとりあえずキレイにしておきたいという思いなのだろう。それでも複雑な気持ちになった。これは大人5人で関わる仕事なのだろうか。本当に必要な人に必要なボランティアはいっているんだろうか。窓からは、隣の家の老夫婦が窓を二人だけでふいているのが見える。もしかしたら“この程度”の仕事であれば、午後に帰ってくるという息子たちとやってもいい仕事なんじゃないか。これって災害ボランティアというよりは「家のことは妻・母任せ」の家のお手伝いをしているだけなんじゃないか。
とはいえそんなことをぶつくさ考えているのは私だけのようで、リーダーとなった女友だちは、すごく張り切っていた。ふだん建築現場で働いてる彼女は、「奥様のご要望通り動きましょう」と業者のようなことを言い出し、彼女のリーダーシップによって他のメンバーも「了解っ!」と仕事人の気分で盛り上がり、掃除を始めたのである。もちろん私も仕事はした。でも、「本当にこれでいいのかな。いいのかな」という思いは最後まで抜けなかった。
帰りに石巻市に寄った。あまりに広大ながれき。そして腐った魚の山。数百羽の海鳥が腐った魚をくわえ空を飛び回っていた。その臭いは離れても離れても離れても消えなかった。その中で暮らしている人もたくさんいる。
この魚の山をどんどん片付けたい。台所仕事で体力が余っていたせいか、すぐにでも働きたい気持ちになった。50人くらいのピンクの付箋の女たちがくれば1時間でじゃじゃじゃっ! と片付けられるんじゃないか。水を流して道をたわしでこすり、せめて臭いをもう少し軽減するような仕事ができるんじゃないか。もちろん今だって、311直後に比べればずっとマシなはずだ。それでも突然やってきた者の目から見たには、深い悲惨にみえる。いったいいつまでこの光景を保存しておくんだろう。なぜ、片付けがこんなにも進んでいないんだろう。例え、恐ろしいものを見ることになったとしても、怪我をしたとしても、とにかく瓦礫を片付けたい。縦に倒れたままの車を、せめて元に戻したい。街をきれいにしていきたい。それができないのが、もどかしいのだ。どうかどうか役立つ仕事をさせてくれ。掃除させてくれという思いに溢れた。
ボランティアをやりたいと思った時に、すぐにボランティアにかけつけられ、仕事ができるシステムはよくできていると思う。一方で、性別での乱暴な割り振りや、仕事内容があまりに精査されていないシステムが、つくづくお役所的だったのは事実だ。縦の命令系統があり、ただ人間は自動的に派遣され、意味を問うことなく機械のように手を動かしただけ。
「怪我をしたら誰が責任を取るんだ」「何かあったらどうするんだ!」という声が聞こえてくる。でも、自分で責任を取るから仕事をさせてくれ、と思う。そういうのがボランティアだと私は思う。私が私の責任において仕事をしたい。というか、そのための「ボランティア保険」ではないのだろうか。
今度来るときは・・・と床を拭きながら思った。家が崩れたお年寄りや、家族のいない一人暮らしの老人の被災後を支援するという具体的な活動をしている団体の所に行こう。私に“むいている”ボランティアの形を探っていこう。
一泊二日の旅で、せめてお金を落とそうと、地元のお店に何軒か寄った。津波のお話を聞いた。どこまで水が来たか、当日何をしていたか、今はどうしているのか。でも、誰も、絶対に、放射能の話はしなかった。私もしなかったし、その場にいた誰もが、そういう話はしないように注意深く避けているようにすら感じた。
地元の知人は「放射能の話はできない」と言っていた。今ですら悲惨なのに、これ以上考えるべきことが増えるなんて耐え難いからだ、と。だけど、みんなわかっていないわけじゃない。どこか感情に蓋をしながら生きている。感情にきちんとぴったり蓋をして、絶対に開かないように用心しながら生きている。こんな時に本当のことなんて話せない、こんな時に本音は話せないという抑圧が働くのは、同調圧力だけではない。自分の心を守るために必要なのかもしれない。
途方にくれながら、言葉を失ったまま、東京まで車を走らせた。
被災地の人が「放射能のことを語れない」過酷。
夫や息子に迷惑をかけないで主婦としての仕事をしよう、早く日常を取り戻そうと「台所を磨いて」と頼むその切実。
とにかく店を開けようと、客のいない店で暗い顔で寿司を握る男たち。
そして三ヶ月前と同じがれきが山積みになったままの世界。
簡単な掃除をして帰る私。
永遠にも感じられる、復興への道のり。