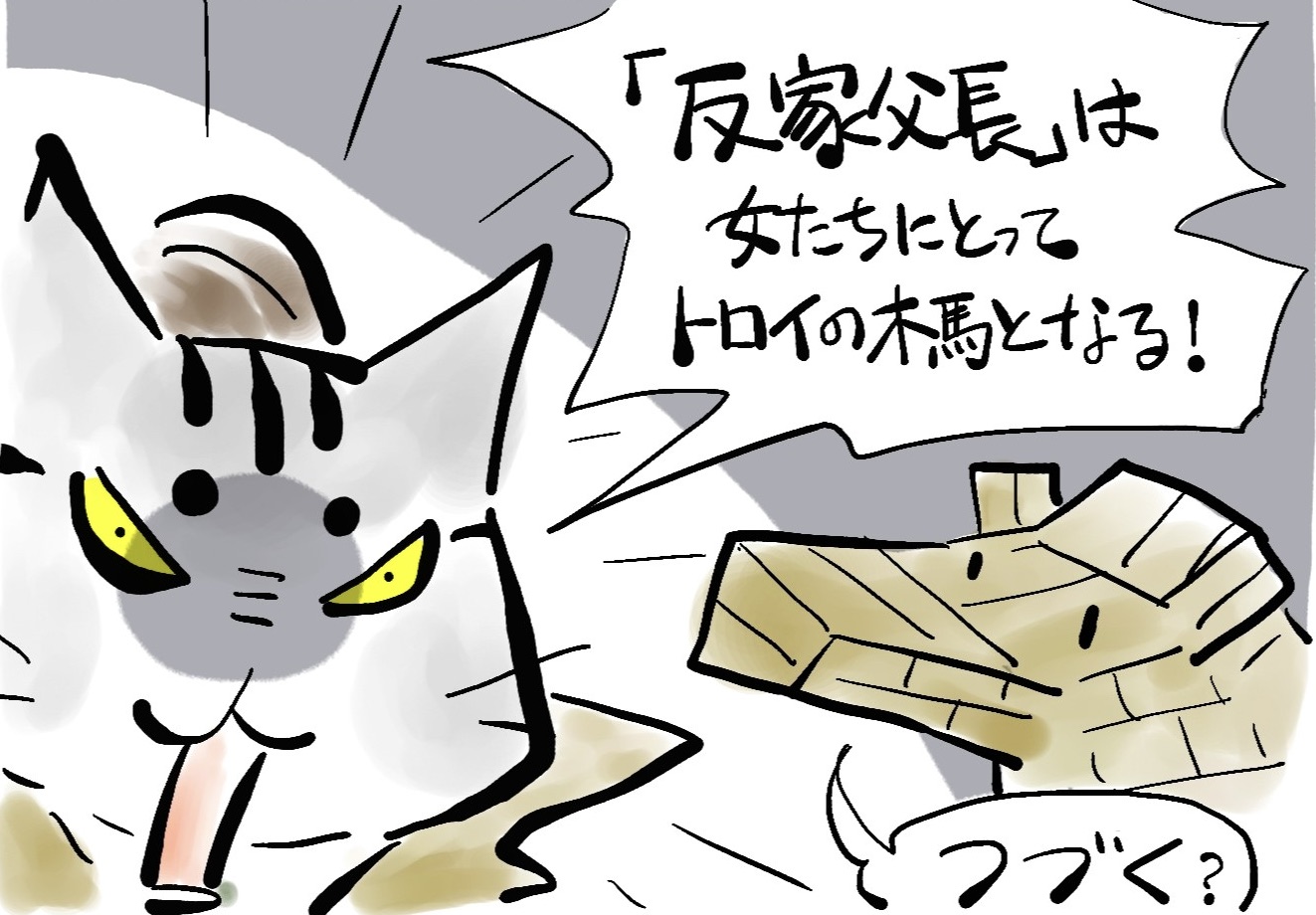私は、10代の頃に描いた夢の世界を生きている。手術をし、希望のカラダを手に入れ、仕事も得て、望めば性別だってできる環境にいる。でもそんな中で私はあの頃よりも苦しい。それは多くの人が味わっているであろう生活の、仕事の、人間関係の悩み。社会から疎外されていると感じていたあの頃よりも、ずっと苦しい。社会と手をつなぐことって案外つらいもんだ。そんなことを考えながら私は、あの頃の自分を思い出している。
電気屋の仕事を始めた頃、私は大学時代の友人とよく遊ぶようになった。一人暮らしの友だちの家に行って飲み明かしたり、ドライブに行ったり。昔以上に同級生たちとつきあい始めた。その頃の私はTと離れ、そして苦しみながらも、自分が立つのがやっとなくらいのほんの小さな場所だけど、自分が立っていられる場所を見つけたように思っていた。
私を支えていたもの。それは私の声だった。耳をすませばいつも私の心の中から声がした。それはゆるぎない真実のように、上質な呪文のように、私を導いていた。
「私は誰にも恥じることなんかない。自分を裏切らずに生きていればきっと周りは認めてくれる。人として生きるんだ。」
そしてこの頃から私は友人達にカミングアウトをし始めた。
ア「あのさぁ・・・実は人(その頃の私の1人称)オンナの人が好きなんだ・・・」
「やっぱり」「うん、知ってたよ。」
だいたいの友だちがそんな風に反応し、最後にこんな言葉をかけてくれた。
“ニューハーフ”という言葉が誕生したそんな時代だった。
友「アンティルはアンティルでしょう。」
中には、カミングアウトの後に「いつかまともになってほしい」と他の友人に話していたという人もいたが、面と向かって私を否定したり、拒否する人はいなかった。カミングアウトという私の一番身近な社会への宣言は、自分自身の足だけが私を支えるものだと教えてくれた。そして私はこの頃からようやく社会の輪郭が見えたような気がした。それは海の向こうにおぼろげに見える島のような感覚。その感覚を獲た時、私は地面に踏ん張って立とうとしている自分の重力と底力を知った。
自分がちゃんと生きていれば周りの人は私を否定しないと、強く思えた私はいったい何に支えられていたんだろう。
テレクラにも電話してみた、無理やり男とデートしてみた、好きでもないオトコの部屋にも行ってみた。でも、私にはやはりオトコと過ごす未来など考えられなかった。“オンナが好き”な私。Tがいなくなっても、誰になんと言われても私はそんな自分を認めて前に進むことしかできないと思った。自分を自分で引き受けるそんな覚悟があの時の私を支えていたのかもしれない。
自分がどうなるのかわからない大きな不安を抱えながらもしっかり2本足を踏ん張って立っていたあの頃。踏ん張る地面の中に潜む残酷さも冷たさを感じながらもその上に立つ心を持っていた自分をもう一度取り戻したいと思っている。
40歳の私。自分の歩く場所を必死に探し、その歩みを力にしていた私からみたら今の私はなんという臆病だと、自分をなじりたくなる。社会と友好条約を結び、溶け込み生きようとする私はなんだかひどく情けなく思える時もある。私が対峙している社会は、苦しんでいる場所は、オトコが作ったシステムで動く社会。そんな社会で“自分”のままで社会に留まり続けるのは難しい。この社会の中で“自分らしくある”ことは、社会から疎外されていたと感じていたあの頃より、辛く、厳しいことなのかもしれない。