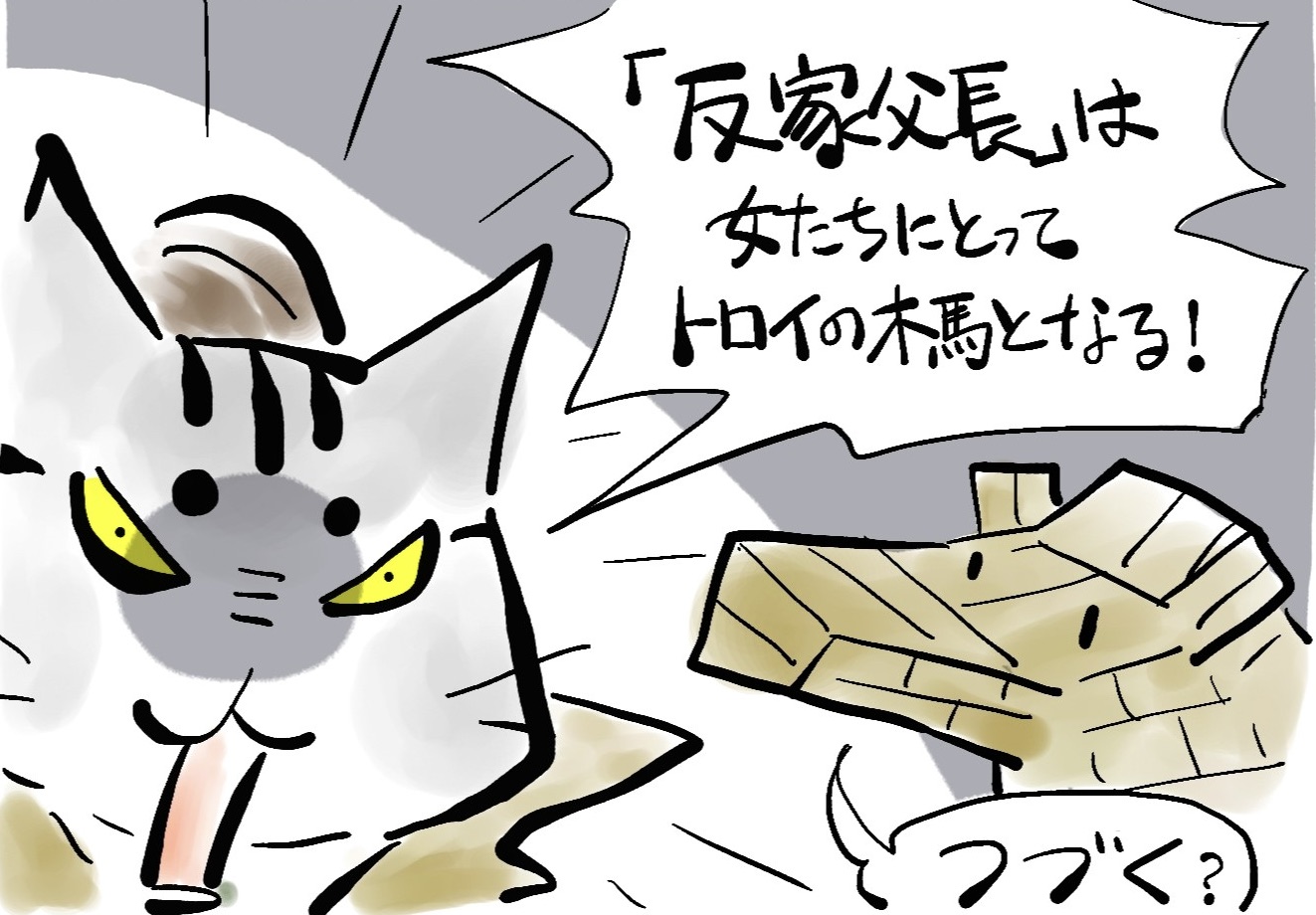Tが婚約してから数ヶ月後、私はTとの関係に絶望しつつも、届く連絡を断ち切ることもできず、味方と呼べる人もなく、この社会のどこに自分の置き場所を探していいものかもわからず暮らしていた。穴の中に住んでいるような生活の中で私は家業の手伝いを始めた。
その頃わたしは家業の電気屋で修行を積んでいた。
親は戸惑いながらもほんの少しよろこんでいたようだった。一人暮らしを始めてからは自分の生き方に意見を言われるのが嫌で、寄りつかなかった家。でも私はちゃんと仕事がしたかった。油まみれになり、休みもなくいろんな家に行って頭を下げ、モノを売り、修理する父親の仕事。家業を継ごうなんて思ったこともなかったが、父一人しかいないその仕事の見習いとして働き始めた。
私の仕事は車や自転車で商品を宅配し、その使い方を教えるという仕事だった。多い時には500キロ走り、1日3件ほどの家を回った。気楽だった。黒いスーツに白いワイシャツ。男物の革靴を履いて一人ハンドルを握る。自分がしたい格好を誰の目も気にせずしながら仕事ができる。親も私の格好に何かを言うことがなかった。私に仕事を教えることのほうが父親にとってはうれしいことだったのだろうか。
ピンポーン
出迎える人たちは私=“店の人”という見方が優先して訝しく思う人はほとんどいない。スーツを着た若い男の配達員。それが私だ。
私「アンティル商会です。配達に参りました。」
配達した商品の説明にかかる時間は20分。お客さんのほとんどは主婦だった。
淡々と説明して帰る家、“男”の配達員に警戒して玄関口で説明を受けるお客さん。お客さんを訪ねるたびに、社会と接点を持つことを恐れつつも、
つながっていたいという想いが悲鳴のように私を貫く。人を避けつつも
人に会いにいく仕事に希望を見いだそうとする私。そんな日々の中で私は日に日に想いを募らせていた。「性別とか関係なく私は私として生きていきたい。」
その日も私はいつものようにハンドルを握っていた。
それは私がいつものようにTとのことで深く傷ついた翌日、高速で2時間ほどの所になる田んぼの中にある大きな家に配達に行った時だった。出迎えてくれたのは60歳前の女性だった。いつものように商品を説明し、帰ろうとした時、その人は私に昼食を食べていってと声をかけてくれた。高校を出たばかりの少年に見える私が一所懸命説明する姿にその人は何か感じるものがあったのか、「ちゃんとご飯を食べてるの?」客間に私を通しもてなしてくれた。私はこの仕事で救われていたのだ。社会にも自分の居場所を見つけられず、友人にも本当のことを打ち明けることもできず、でも“人”に対し絶望しきれない私は、人と触れ合えることがうれしかった。
「いつもお総菜を買って食べてます。でも貧乏だからいつもシュウマイ3個がごちそうです」
「まだまだ修行中なんです。」・・・・・
私と“普通”に接してくれる。男に見えるとか見えないとかそんなこと気にしてビクビクすることも忘れ、人の心と触れ合える体験が私にはうれしかった。
「この辺りは昔ほとんど家がなくてねもっと静かだっただよ。」
「へぇ〜そうなんですか、このお宅はすごく古そうですね」・・・・
陽が沈みかけるまで私はお茶と会話を楽しんでいた。
「夕飯も食べていきなさい。イノシシの肉なんて食べたことないでしょう。待ってな!」
「はい。でも・・・・」
イノシシの肉は少し獣臭かったけど、幸せな味がした。
「いっや、またこの辺来たら寄りなさい。いつでもいいからさ。」
「はい。」
すっかり陽が沈み、人が辿りつきそうもない遠い海の色のような空の中、私は車を走らせた。心がふんわりとしたもので包まれているようだった。Tに悩み、社会を敵視し、人目を避け生きながらこの世の中に絶望仕切れない私の肩にそっと手を置いてくれるような人との出会い。
私はハンドルを握りながら未来を見たいと思った。