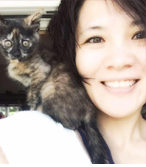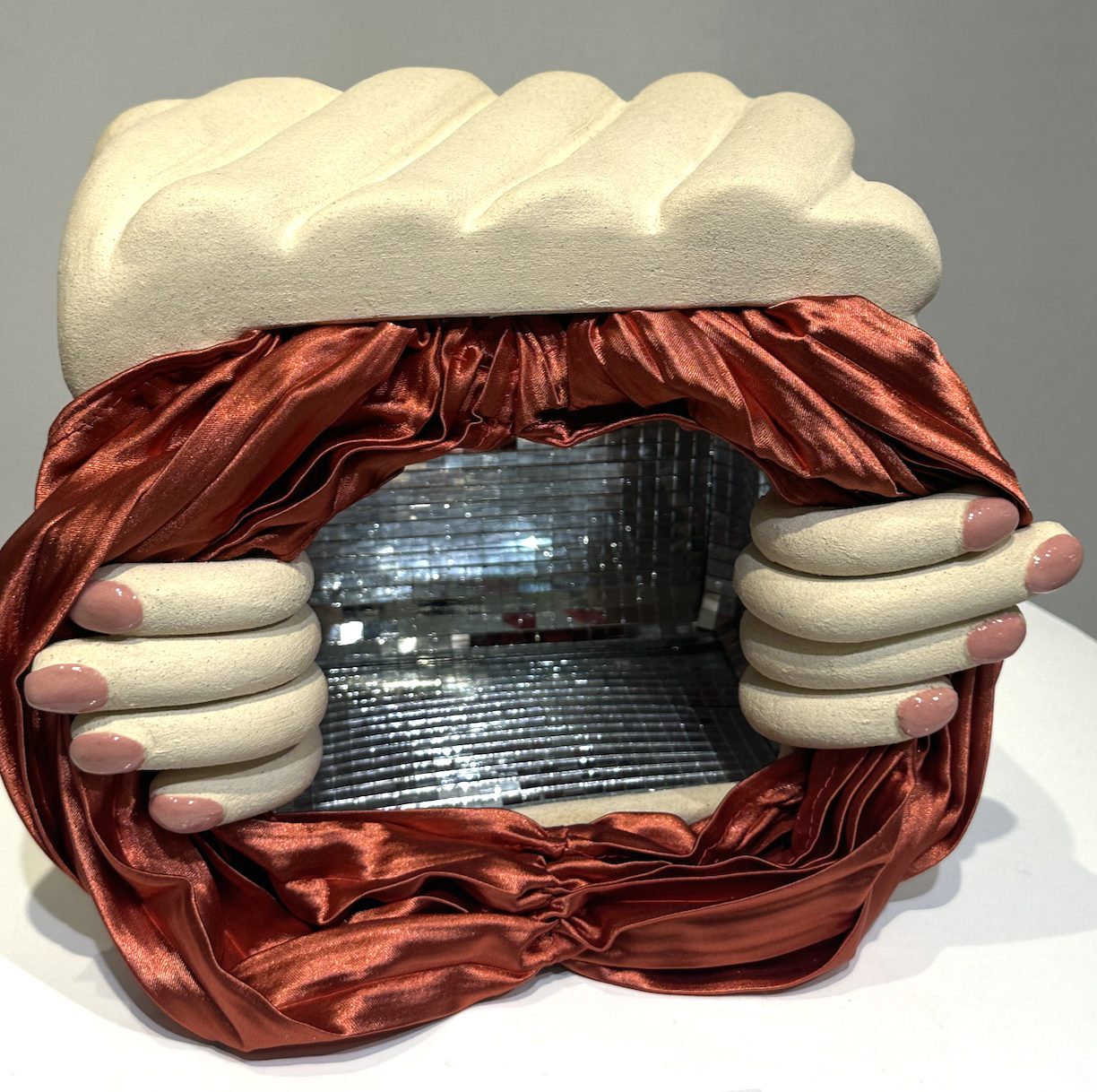Loading...

よく行く飲み屋のママ(60代・元女子プロレスラー)は霊感が強いらしい。「母親が死んだ時、ふと窓の外を見たら父さんが立ってたのよ。待ってたんだねぇ」 自分を一番大切に思ってくれた故人が迎えに来るのだと、ママはいくつかのサンプルをあげながら話してくれた。迎えに来てくれるのは大抵の場合は異性のパートナー。サンプルを聞く限り、家を共にした相手、サイフを共にした相手、墓を共にする相手だ。
「いい話しよねぇ~」5人も入ればいっぱいになる狭いカウンターで、見知らぬ客に混じり私も「ふむふむ」ってうなづいていたけれど、この先、家も墓もサイフも誰かと1つにする予定のない私には、誰が迎えに来てくれるのでしょう、ね。阪神大震災後の独居老人の死亡率がニュースになっていたが、新聞やニュース番組によっては「孤独死」というネーミングを大袈裟なほどに、おどろおどろしく取り上げていた。孤独死。なんだか孤独じゃない死に方があるような響き。
「迎えに来た相手がイヤだった時、お断りしてもいいものなのでしょうか」なことを聞きたくてうずうずしながら考えていたのは、先日新聞に投稿していた男の文章だった。1月12日付けの朝日新聞「声」に掲載された36才の男会社員のもの。「看護師の新妻支え家事分業」。要約すれば、僕と妻は家事半分ずつやってます。それだけの内容。なのだけれど、私は3度読み返したのだけれど、いくら読んでもこの男が何を言いたいのか分からずに、ただただ、こんな男を夫にした女の人は気の毒だなぁ、という気分にさせられるのだった。
だって。家事半分やっている(半分しかやっていない、という言い方だってある)だけで、新聞に威張って投稿するんですもの。アタシも投稿しようかな。「あたし、1人でウンコできます」とか。そんな気分にさせられる、男36才家事やってるぞ、記事。
とは言っても。男が家事をやっているくらいで投書したり、本を書いたりする例は今までだっていくらだってあった。保育園にお迎えに行くだの、子どもの弁当をつくるだの、大根の値段を知っているだの、得意料理は天ぷらだの、洗濯が好きだの、アイロンがけにはうるさいぞとか。そんな事を言ったり書いたりする例はたくさんあったはずだ。それなのに、なぜこの男の投書から目が離せず、お会いしたこともない妻に同情したかと言えば、今までの「僕、家事、好きなんですよ」とは明らかに違う香りがこの30代の男の文章からはするからだろう。
「私は自分の仕事だけでなく、医療現場で人の命を守る妻を支えることで1つの社会貢献をしているという自負を持っている」
「たとえ『夫も家事をするのは当たり前』とは言っても、妻は常に感謝の気持ちを忘れない」
「男女平等と言えば権利の主張に走りがちだが、まずはお互いに感謝の気持ちを忘れないことが大事だと思う。」
「私は理想の夫と自画自賛しているところだ。」
ちなみにこの男性、妻が家事を半分していること(看護師で忙しいのに、きっちり半分やらされている、という言い方だってある)には感謝していない。もしかしたら気が付いていないのかもしれない。
家事してますアピールが、「僕ってリベラル」「僕ってフェミ男」であった時代は終わり。今や、「僕って偉大」である。男女平等。逆行しているのか、進んでいるのか、ワケのわからん状態だ。それにしても、もぅう。いちいち、大袈裟なんだもん、男さんって。家事を少しくらいやったからって、社会貢献だぁ、男女平等だぁ、理想の夫だぁ。困っちゃいます。
篠田節子の小説「百年の恋」は、超エリート女と結婚した貧乏フリーライター男の物語だ。必然的に家事全般を引き受ける男が、女性の編集者に泣き言をもらすこんなシーンがある。(手元に小説がないので、正確な描写ではないけれど。)「妻は、(僕に)感謝をしないんです。汚れたパンツを洗っても、食べカスのついた服を洗濯しても」同情を買おうとする男を、女の編集者は一蹴する。「ふざけんじゃないよ」と。女は、私たちの母親も、その母親も、ずっと黙ってパンツ洗って来たんだよ。男のパンツを洗ってきたんだよ、と。感謝しないだって? 感謝して欲しい? あんたのその気持ちが、彼女(妻)には伝わっているんだよ。(だから女は男に、自分の持ち物には触らないでくれ、と、汚れたパンツをそのまま溜め込むのだ)
男のオレがここまでやっているんだから。という奢りを感じるから、男に物事を頼むのは面倒だ。男のオレがここまで謝っているんだから。という奢りを感じるから、男とケンカして勝つのは面倒だ。だから、アタシはとりあえず男が死に目に迎えに来てくれないことを祈るのみだ。「オレが迎えに来てやってるんだよ。当然、一緒に来るだろう?」 お願い。あたいを迎えに来て、ままん。と、霊感の強い元女子プロレスラーの話に私はじっと耳を傾けつつ、甘えてみる。だってかっこいいんだもーん。