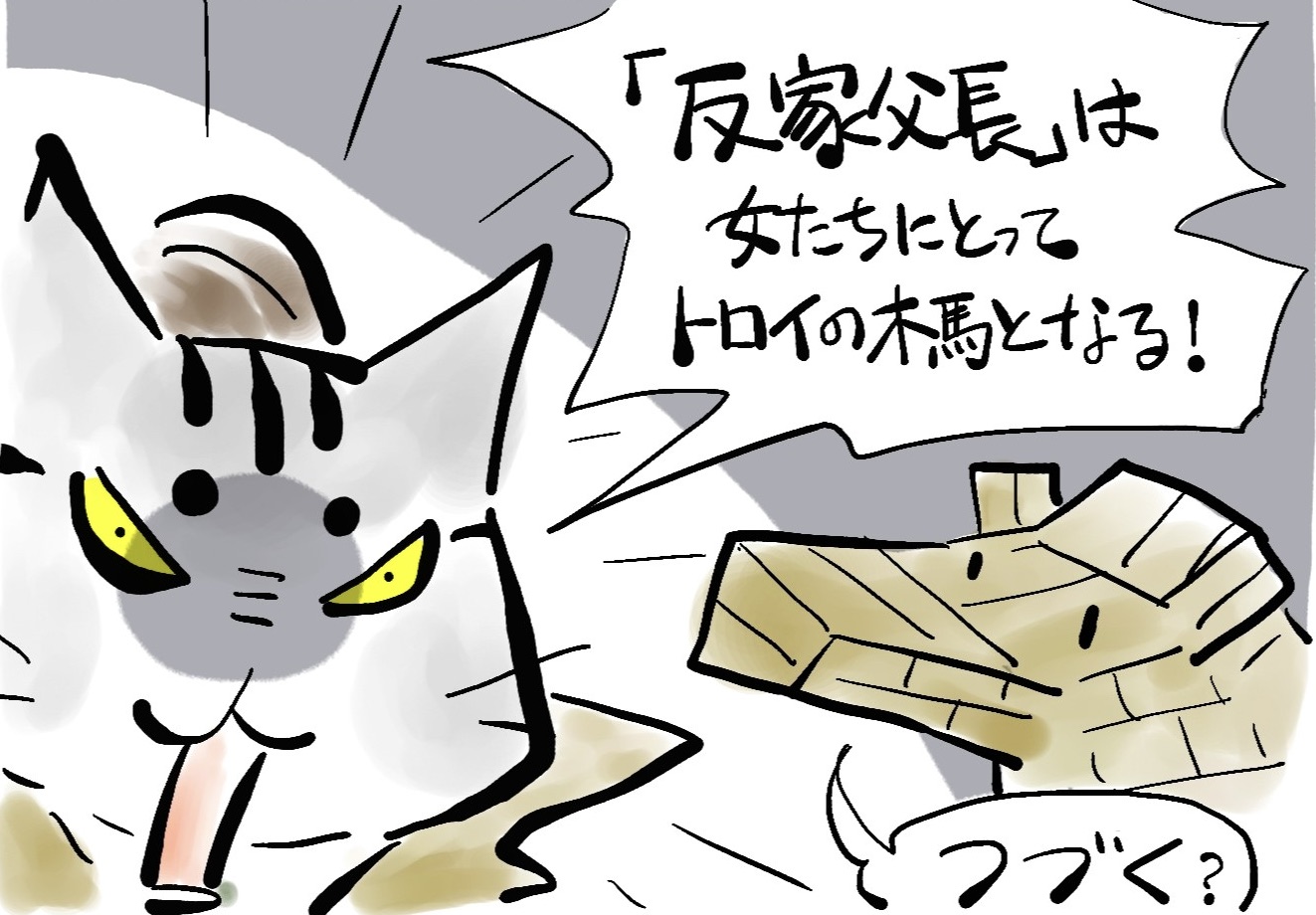みなさん、私とTとの話し嫌気が差していないでしょうか?
15歳から8年にわたるTとの関係を語るとそれは愛情、疑い、嫉妬、セックスの繰り返しでした。本当にこの繰り返しを続けながら私は奈落の底へと落ちていってしまったのです。そのことを書こうとすると、あの時の渦に巻き込まれます。冷静に簡潔にTとのことを書き終わろうと思うのですが、様々なエピソードが私の指をあの頃の一瞬一瞬に運んでしまうのです。
あの日を思い出すと窓から差し込んでいた西日が私の記憶を染め上げます。
一人ぼっちでTの部屋で待つ寂しさもTの電話を待つ苦しさに比べればマシでした。この部屋にTは帰ってくる。そう思えばガマン、ガマンだったのです。私は心の叫びをぶちまけないように自分の心をなだめて待っていいました。しかしKとの生活が書かれた手帖が、私を揺さぶります。絶対言わないぞ。今日は楽しく過ごしてTとまた楽しい生活を送るんだ。と。
T「ごめんね。出かけなきゃならなくなっちゃった。駅まで来るまで送るね。」
夕方に帰ってきたTは言いました。その言葉に動揺した私は、口にするまいと思っていた言葉をこぼしてしまったのです。
ア「どこに行くの?」
これでも私には精一杯飲み込んだ言葉でした。Kと何をしていたの?どしてどこに行くの?セックスはしたの?私とはどうするつもり?言葉が刺となってに口から出ようとして、その痛さに耐える私をを無視するようにTは着替えを始めました。
T「またね。」
こんな時、私の孤独はカラダ中を被い、2度とTと会えなくなるのではないかと恐怖で身動きがとれなくなるのです。それは絶壁の上に立たされたような気分でした。
ア「Kと会ってたの?!」
こうなると私の口はから吐き出されるのは嫉妬から生まれる言葉ばかり。
ア「ひどいじゃない、これからまた会いに行くんでしょう!」
ア「いない時間何してたの?待ってたのに!!」
ア「なんで私を呼んだのー・・・・!」
T「もう帰って。」
乗り込んだ車の中では、もう何の言葉も出てこない。言葉にしたことの後悔と、会えなくなる不安で自分の心が見えなくなって少しでも遅く駅に着くことを望むばかり。
T「じゃあここで」
ア「隣の駅まで送ってくれない?」
Tの車は最寄りの駅のロータリーに止まって、私が降りるのを待っていました。なかなか降りない私にかかる言葉は、
T「降りて」
出来るだけゆっくりドアを開けて、足を降ろし、ドアを握りしめる私を振り払うようにTはドアを締めるのです。そうタクシーの自動扉のように。
その場所から離れない私を恐れることなく、Tは走り出します。アクセルの踏み方に迷いがないことがわかって、私は哀しくなるのです。その哀しさはカラダに感情を溢れさせるスイッチにもなりました。
やだ!やだ!!やだ!!!行かないで!!!!
私は走り出した赤い車を追いかけます。どこかのドラマの一シーンのようです。
そう、これが私とTのあの頃の日常。ドラマのように車は止まることはそうそうありませんでした。しかしたまに私のスタミナが続くとき、走り続け車に追いついてしまった私をみかねて車を止める時もありました。そんなことを毎週続けても私はTと離れることを選ばなかったのです。
TがKの所に行くことを止められるまでには1年。それは私の涙と汗の歴史です。Tの男のイメージに近づくために私は理想の男を演じました。嫉妬でその仮面を外さざるをえなくなることも多かったのですが、それでも私は“男”として自分を上書きし続けました。動物の亡骸を抱く日々。そのエピソードはまた次回に。
※先月から「別冊:本当にあった笑える話」から「本当にあった笑える話ピンキー」に引っ越しました! マンガを読んでくださっている読者の方、今後ともよろしくお願いします!!