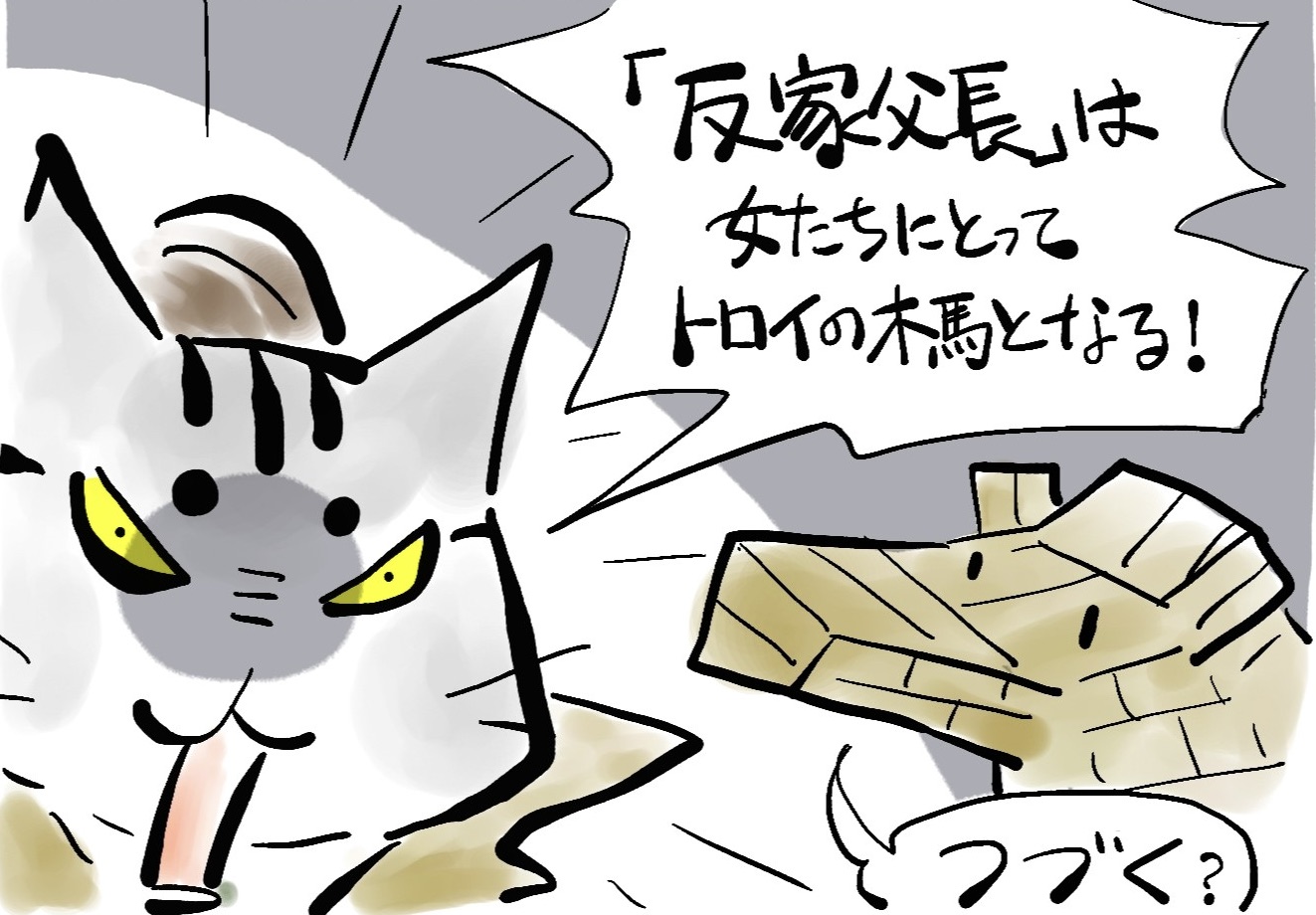ラブホテルそれはセックスをする所・・・。
そんなことはわかりきっているはずなのに、私はWの言葉に驚いた。
W「Tとしていたように私として。」
上着を脱ぎ、ストッキングを脱ぎ、そしてブラジャーをはずそうとするWの顔はひどく緊張している。その真剣な眼差しに、私は言葉をなくす。
ア「えっ、でも・・・・・」
W「私、アンティルとそういうことしたいの。」
セックスに明け暮れた高校時代。そういうことには慣れているはずだった。大好きなはずだったのに私はWが求めに頷くことができない。それはWとのセックスとTとのセックスが違うものに思えたからかもしれない。周囲からの偏見とTが抱える“オンナと付き合うこと”の罪悪感が二人の関係に黒い影を落としていた日々。その日々から生まれたエネルギーの全てがセックスへと流れていった。泣きながら「愛している」だの「離れたくない」などと言いながら、快楽をむさぼる昼ドラのようなセックス。負のエネルギーは私達のセックスをより盛り上げていた。しかし、Wとのセックスにそれはない。どんな風にセックスをすればいいのかわからない。普通のセックスがわからない。
ア「でも・・・・」
私が下を向いて呟いたその時、私の手がひとりでにふわふわと宙を浮いた。
ア「(ゴク)驚きのあまり唾を飲み込む私」
Wは私の手を自分の右の乳房に持っていったのだ。それはまるで絵に描いたような誘惑。頭には“チャタレー夫人の恋人”のテーマソングが流れ出す。チャララララララ~チャッチャチャ~チャチャーそしてボーっとする私に追い討ちをかけるように、Wが抱きついてきた。
ア「ちょっと待って!!」
W「えっ・・・」
ア「なんでこんなことするの」
W「好きだから」
ア「でもまだちゃんと付き合ってもいないじゃない」
W「何よ!いつもこういうことしてるんでしょう!だったらいいじゃない!!」
この時、私はWがセックスを楽しみたくてしようとしているのではないことに気がついた。
ア「何でセックスがしたいの?」
W「好きだから!」
ア「本当に?!」
W「・・・・・・・・」
ア「・・・・・・・・」
W「お母さんがしていたことがどんなことか知りたいの!だってわからないんだもん。なんでオンナの人が好きなのに私を産んだのか!!」
お母さんが死んでからさらにWは“母の生き方”に悩まされていたのだ。自分が生まれてきた理由は?自分へと注がれた母の愛情とは?母親の愛情を一身に受けて育ったWにとって、母親を否定することは自分を否定することだった。
W「でも私オンナの人が好きだってことがどういうことなのか、わかったの。アンティルのこと好きなの。そばにいてほしいの。だからアンティルならいいの。」
ラブホテルに流れる涙。しかしこれまで私とTが流してきた涙とはあまりに違いすぎる。どうしても私はWとセックスする気にはなれなかった。Wときちんと向き合いたいという気持ちもWとのセックスへの興味も私にはない。あるのはこの場から逃げ出したい気持ちだけ。
ア「ここまで来ておいてごめ・・」
そういいかけた瞬間、私の唇にWの唇があたった。
ア『えっこれはまさか・・・(心の声)』
ア「ちょっと待ってW。もしかしてWはセックスするの初めてなの?」
W「・・・・・・・・・うん。これがファーストキス。セックスもしたことない」
処女。私の脳裏に2文字が浮かぶ。気がつくとWはブラジャーをはずしていた。