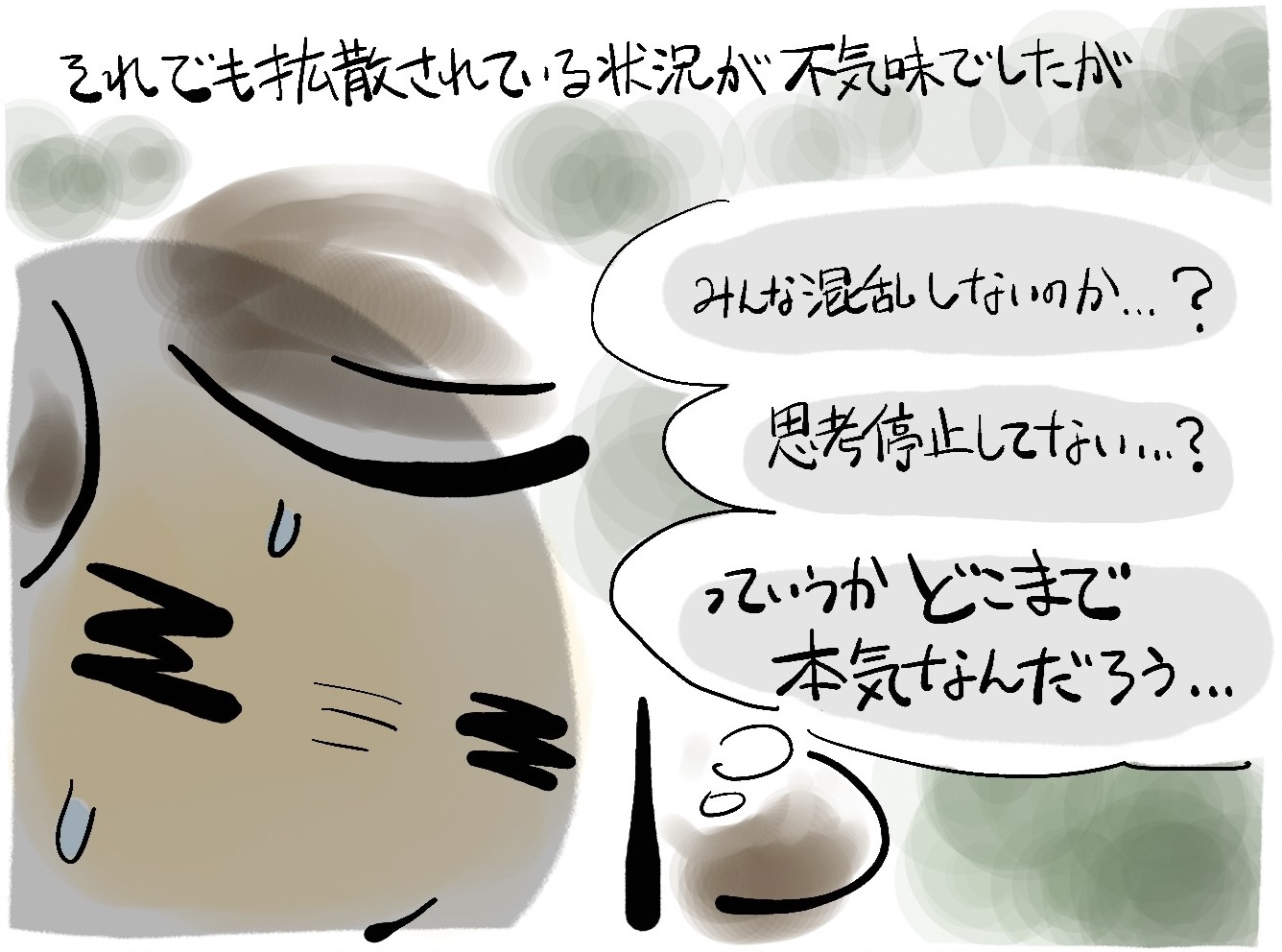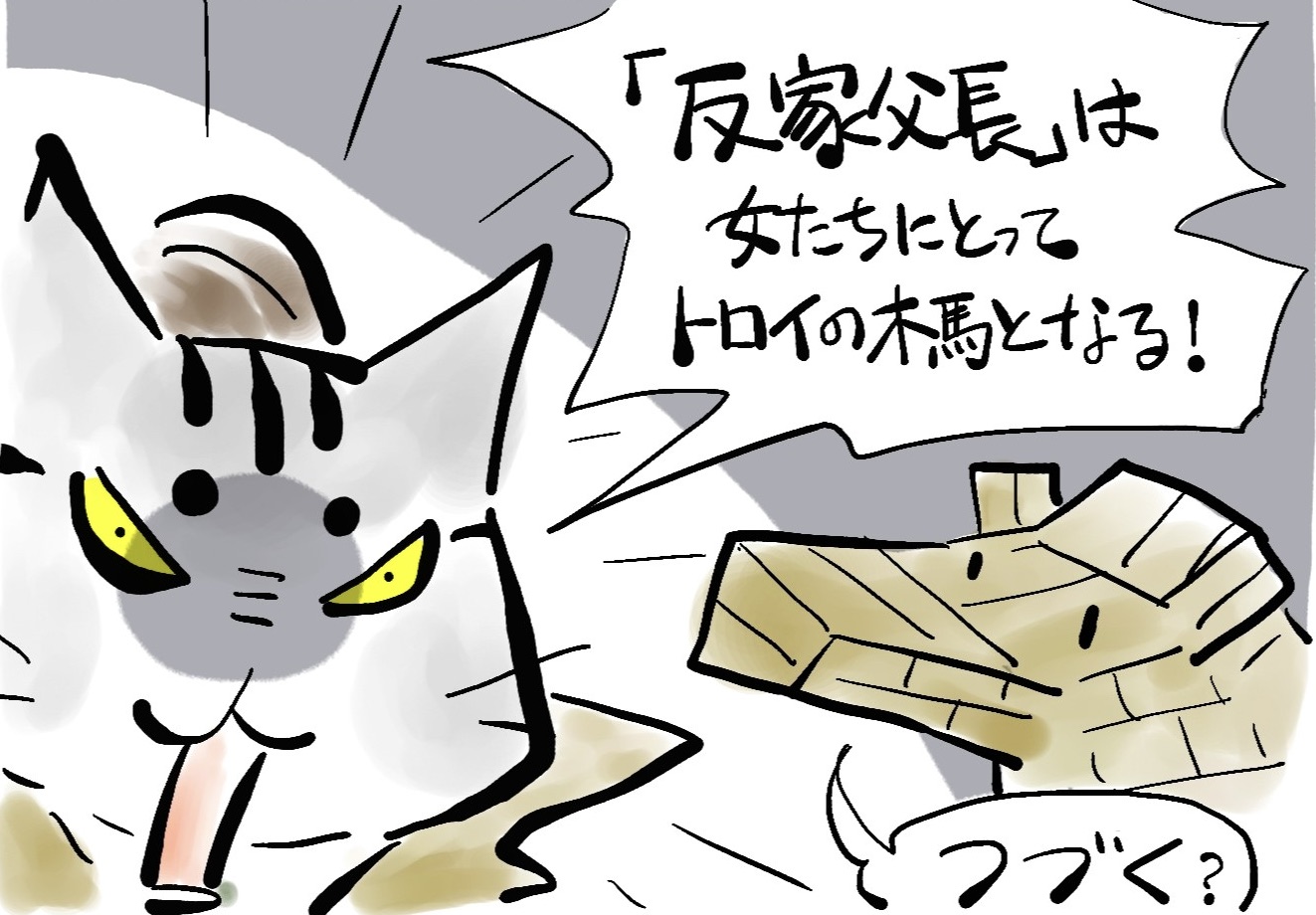”T子とKのドライブミュージック”
ダッシュボードから落ちてきた1本のテープに私とTの視線が釘付けになる。
「・・・・・・・・」
私の予感がすべて本当だったとことをテープは物語っていた。
衝撃と共に悲しみと寂しさと怒りが幾重にも混ざり合った感情がこみ上げてくる。それはカラダの奥底、ちょうど胃の下あたりでぐるぐると円を描き、口をめがけて飛び出そうとする物体のようだった。
『出てきちゃだめ!』
弱々しく響く悲鳴のような声はその物体には届かないことは誰よりも私自身が知っていた。
ア「T。やっぱり付き合ってるんだね。」
T「これは違うの。こういうの作るのが好きな人でみんなとドライブに行った時ね・・・」
ア「いつから・・・」
T「だからね。違うんだって」
ア「違うはずないじゃん。まだバイトやってるの?」
声を張り上げないように冷静を装って話すだけで精一杯で突き上げられる言葉を無視することなどできない。
ア「風邪で寝込んだ時からもう付き合ってたの?」
T「・・・・・」
ア「Kと付き合っていることをバイトで知らなかったのは私だけなの?」
そう言いながら私はTの目を覗き込んだ。
T「・・・・・」
ハンドブレーキの上に涙がポタポタと落ちる。
T「もう帰る。」
ア「教えてよ!いつから付き合っていたの?!」
T「言いたくない。」
ア「なんで今日ここに来たの?!」
T「・・・・」
ア「Kとあの海に行ったの?」
T「・・・・行った。・・・・・」
気がつくと私は声を上げて泣いていた。
T「じゃあ。私もう帰るから・・・」
ア「・・・・・」
車を出て、扉を閉めることが出来ず、ぼーっと立つ私を無視するようにTが扉をバタン閉める。ブロロロローーー
Tの車が走り出す音を聞きながら、私はまた新たな感覚を体験していた。
底のない絶望の谷に落ちて行くマイナスの浮遊感。それは自分のカラダが奪われていくような感覚だった。
『なんで来たんだよ。なんでそっとしておいてくれなかったんだよ。』
落ちてゆきながら私は叫んでいた。立っていられなくなって地面に座り込んだ私を通行人が見ている。ヒソヒソと聞こえる声。この世界はおまえが生きる場所ではないと言われているようだった。