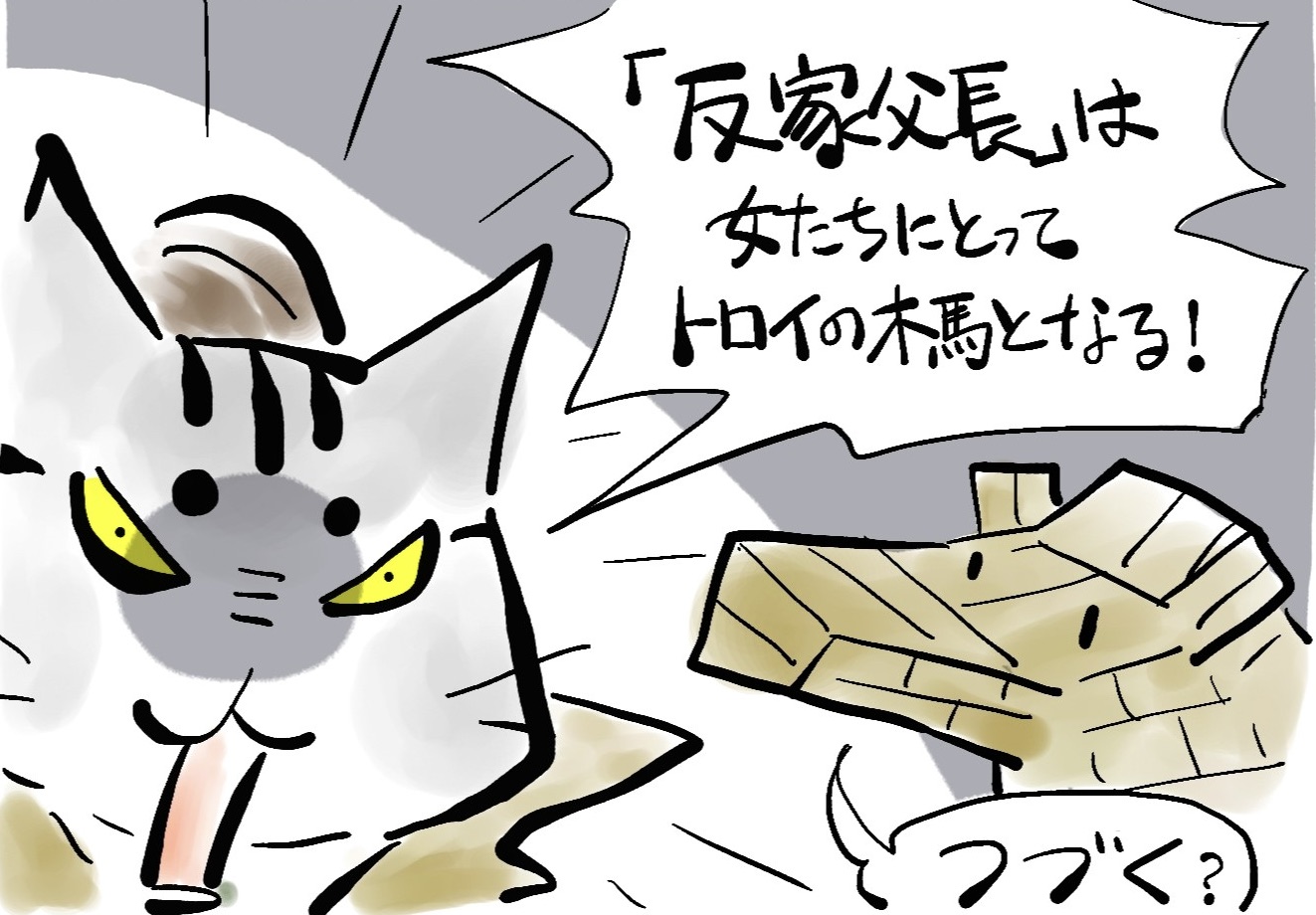「アンティル!お母さんがお母さんが・・・・」
朝5時に鳴り響いた電話の向こうでWが泣きながら私を呼んでいた。始発電車に乗り込み1時間あまり。病院に着いた時には太陽が坂の上の病院を照らしていた。誰もいない病院の階段を駆け上がり、いつもと違う病室のドアをあけると横たわった母親を囲むようにWの父親と弟が立っていた。涙が残る弟の横で父親が呆然とした表情で立ちすくんでいる。Wの母親はすでに息をひきとった後だった。タオルで母親の顔を拭いていたWが私に気付き、手を引っ張り廊下に誘う。そして冷たく光る病院の廊下に差し込む朝陽の上に立ち、大声で泣き出した。
「お母さんが死んじゃったよ。最期に血をいっぱい吐いて苦しそうに死んでいったの。手にもベットにもいっぱいの血がついて苦しそうに苦しそうに死んじゃったよ。」
Wの背中めがけて降り注いでいた朝陽が、泣き崩れてしゃがみこむWを通り越し私の体を包む。朝陽と“死”という正反対の所にあるようにおもう2つのものが同時に私の目の中に飛び込んでくる。それはあまりにかけ離れていて一瞬夢を見ているような気分になった。
遺体の引き取り手続きでバタバタとしはじめた病室で、私は初めてWの母親の顔をのぞき込んだ。血を拭き取った跡が残るベットが最後の姿を想像させた。たいして仲がいいわけではなかった高校の同級生の母親の死顔。その死顔を見ている自分。オンナが好きなオンナであったWの母親は娘に近づく私をどう思っていたのだろうか。
その日から私はWの家族と共に葬儀の準備にとりかかった。葬式が終わるまでの数日間、Wの家族と寝起きを共にしたのだ。それまで朝しか会うことがなかったWの父親と弟と朝晩共に過ごす日々。Wの親戚の誰より近い所でW家の葬儀に関わっていたあの頃を思うと、不思議でたまらない。なぜ私はあそこにいたのだろう。しかしその時の私は、そこにいることを自然なことだと受け止めていた。
通夜の前に遺影が出来上がってきた。アルバムの中からWが選んだ1枚の写真。遺影に写るWの母親は、フクヨカな顔をしていた。頬がこけ、目だけが強く光っていた顔とは別人のようだった。私はWの家にいるWの母親を知らない。この部屋でWの母親は何を考え、何を思っていたのだろうか。葬儀の準備で誰もいなくなった部屋で一人、その遺影と向き合った時、私は初めてWの母親が歩んできたオンナが好きだった一人のオンナの道を想像した。
友達の多い人だったため、葬儀には多くの人が手伝いに来ていた。その中でも特に積極的に手伝っていたのがFさんだ。FさんはWを励まし、不慣れな準備を助けていた。Fさんは、母親が親しかった団地のグループのメンバーに指示を出し、頼もしく動きまわる。WのFさんを頼り胸の内を語っていた。
なぜ母親はオンナの人が好きだったのか。それならなぜ結婚したのか。苦しそうな最期は、Wの心の中に大きな疑問を残した。