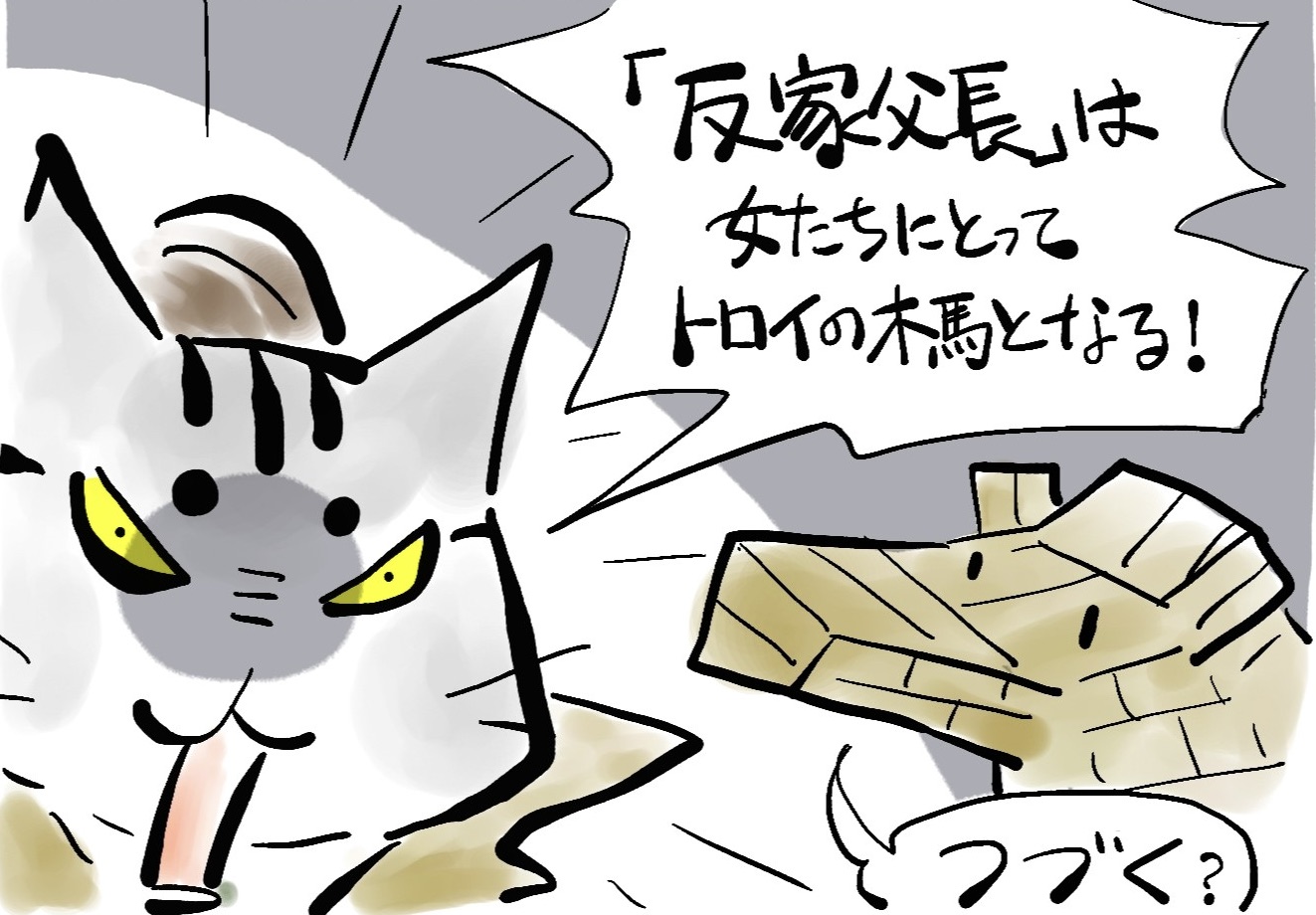雨上がりの空から降る朝陽が私の部屋に陰をつくる頃、私は悲しみ以外の感情を持たない人間になっていた。
「T、もう起きたの。こんな時間から電話?! Kくんなの?」
Tの母親のその言葉を聞いた瞬間、苺事件以来の疑惑となっていたTとKの関係は真実になった。彼氏と朝まで電話しているTを叱るというより、むしろ微笑ましく見守るようその声は、二人の関係を何よりも表しているようだった。
TとK、Tと私。好きという感情で結びついたそれぞれの二人。同じはずなのにその間には何と大きな差があるのだろう。その絶望は私の将来を映す鏡のようだった。私の人生は深く暗い穴。私はどこまでも続く暗闇の穴を落ちていく。
穴の所々にできた隙間から差し込む地上の光に手を伸ばし、掴むことなくただただ落ちていく人生。
『いっそ、光など見せてくれなきゃいいのに・・・。』
私はそう思いながら「やっぱり。」と呟いた。
子供の頃から私には一つの大切な知恵があった。それは喜びを喜ばないことだった。
誰かの心。誰かの言葉。どんなにうれしいことがあっても、そのことによって浮かれないように自分をいさめることが、私が私を守る知恵だった。喜びの後にあるのは悲しみ。その方程式がいつも心を制御した。期待してそれを得られない時の寂しさよりも、喜ばないことのほうが傷が少ない。それは私が経験上学んだ生きる知恵だった。万が一その方程式を破り、期待した時には必ずしっぺ返しが待っていたのだ。Tとの出会いは、これまでに最大のしっぺがえしを私にくらわした。Tとの楽しい日々、Tとの気持ちいいSEX。自分の心をあらわにしてはいけないということを知り尽くしていたはずなのに。子供の頃得た教訓は、その後の私を予言していたというのに。私はTに“心の全て”を見せてしまったのだ。オンナが好きな私の心。Tへの想い。そして生まれてはじめて心をさらけだした人に私は捨てられた。
この日から長い間、私は背中に板を載せ歩く感覚を捨てることができなかった。
板に書かれた大きな字は私がこの社会に溶け込むことができないということを示す印だ。自分の背中でありながら、その板を降ろすことも叩き割ることもできないまま、苛立ちを持つ暇もなく、その重さだけが私の感覚となってのしかかっていく。それはオンナが好きな私に与えられた罪なのか、心を人に見せた罪なのか・・・。
涙さえ出せない春の朝、私はゆっくりと深い穴に落ちていった。