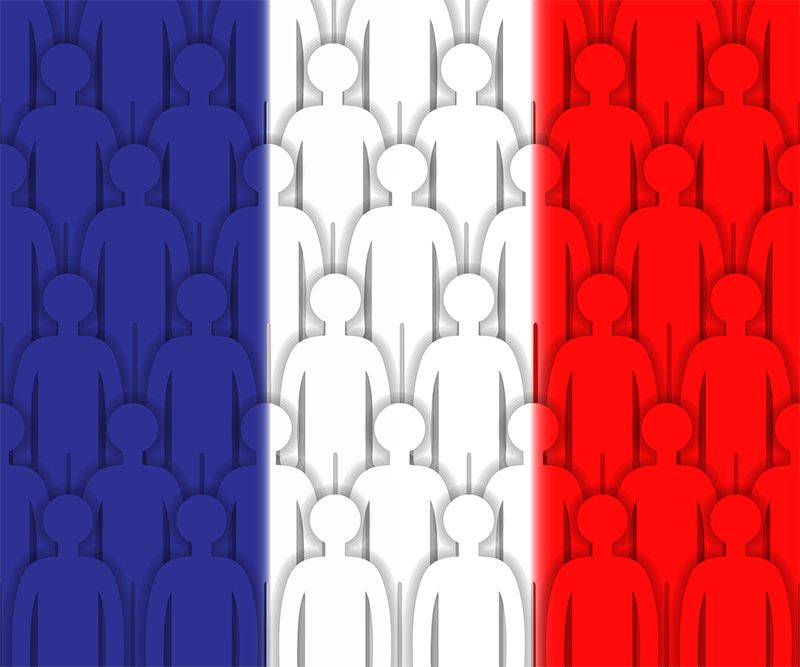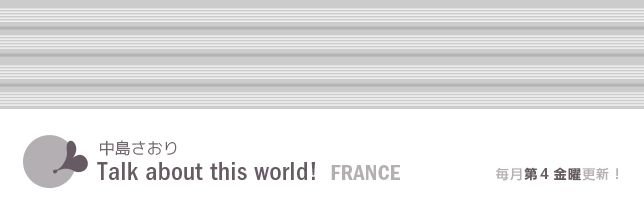
「性的魅力があるけれどふしだらではなく、結婚しているけれど存在感があり、仕事はするが成功し過ぎず、夫を尻にしかず、ほっそりしているけどダイエットのし過ぎでなく、限りなく若さを保っているが美容整形はしておらず、幸せいっぱいのママだがオムツ換えにも子どもの宿題にも手一杯にならず、よき家庭の主婦ながら古いおさんどんではなく、教養があるが男たちよりはない白人女、絶えず我々の前にちらつき、我々が似ようと努力すべきらしい理想の女性は、ずいぶん退屈そうに私には見えるが、いずれにしても私はお目にかかったことがない。そんな女はいないと思っている」。
いきなり、多くの女の理想像を叩き割ってくれる、ちょっと面白いフェミニストのエッセイを紹介しよう。ヴィルジニー・デパントのKing Kong Theorie (Grasset)だ。2006年に出版された本だから、もう12年も前になるが、自らのレイプ経験、売春経験を「かわいそうな犠牲者」としてでなく語り、売春、ポルノを擁護した特異な言説で、「新フェミニズム」と宣伝される一方、批評家には酷評された。16カ国語に翻訳されたが日本では紹介されていない。
出版当時、著者は37歳。小説を6冊出した後の初めてのエッセイだ。名前はずっと前から知っていたが、ちゃんと読んだことはなく、今回、読んでみたのは、「ワインスタイン事件から11年も前に、ヴィルジニー・デパントは、女性を拘束している支配と恥の関係を看破していた。当時は理解されなかったが、今こそ誰もがキングコング・セオリーを読み直すべき!」という『Télérama』の記事に煽られたからだった。
読んでみた結果、ワインスタイン事件や♯Metoo運動の直接関係があるとは思わなかったが、12年前にこのエッセイを発見した若い世代の女性の意識に大きな影響を与えたに違いないとは思った。
ともかく常識をひっくり返す言説が自身の体験とともに語られているため、レジュメが難しいので、私の興味を引いた内容を断片的にお伝えすることにする。
最初の主題は「レイプ」である。著者は17歳のとき、友人と2人でヒッチハイクをした際に集団レイプに遭う。そのとき彼女は、もう仕方が無いと抵抗しなかった。ポケットにナイフを持っていたにもかかわらず、それを男たち相手に使うという可能性を微塵も思いつかなかった。それよりもナイフが見つかったら自分に向けられるのではという恐れから「見つからないように」とばかり願っていた。ことが終わってから、彼女の持っていた凶器を発見した男たちはビックリして「こんなものがあったのに何もしなかったってことは、こいつも案外、気に入ってたってことだな」と言ったそうだ。そうじゃない、女は「自分は弱い、抵抗できない」と刷り込まれているのだ、と彼女は考察する。そして女が抵抗し、レイプ犯を殺傷することができるようになったとき、男は簡単にレイプしたりできなくなるだろうと考える。
レイプ事件は彼女に深い傷を残したが、彼女はヒッチハイクをやめたりはしなかった。そしてアメリカのフェミニストの書物のなかに慰めを見いだす。そこには、「危険があるからという理由で男の子には許されていながら女の子には許されないことがある。平等でなく、女の子には自由がない。そうであるなら、私に危険とともに自由を与えよ。私にレイプされる自由を与えよ」という内容のことが書かれていた。
次のテーマは「売春」である。
ヴィルジニー・デパントは、「出会い系サイト」の元祖のようなミニテル(PC普及以前に使われていたビデオテックス用テレテル)を使って「売春」をしていた経験を語る。そのころ就いていた薄給の仕事よりも実入りが良かったことと、自分の「女」を売って報酬を得ることはレイプで失ったものを取り返す快感があった。自分の経験から、「売春とは女にとってアプリオリに悪である」「売春する女は惨めで搾取されている」という常識をひっくり返し、きちんと報酬が払われ、本人が納得してやっているのであれば、売春は女が自分の体を自分で自由にして金銭的対価を得られることであるとして評価している。
ポルノグラフィについての章は、私には今ひとつよく分からなかったが、ポルノで扱われる女性は男性にとって低いもの、物扱いされていること、ポルノとマスターベーションの関係(マスターベーションをしない女は自分の欲望を自分のものにしていないのではないかというような考察)が書かれていた。
最後に「キングコング」について触れておく。2005年、ピーター・ジャクソンによる『キングコング』を解説して彼女は、キングコングは男性でも女性でもない。その手のなかでセックスを持たず平和であったヒロインは、彼女を探しに来た男に着いて行くのをためらうが結局は受け入れ、キングコングの元での平安を捨てて男の文明世界に赴く。しかしキングコングが追って来て文明を破壊する。制服の男たちが、国家が、獣を殺す。美女はそれを妨げられない。彼女は自分の原始の力と切り離されて近代社会の中で生きなければならない。キングコングは「男女が分化する以前のセクシュアリティの隠喩で、男と女の、大人と子どもの、善人と悪人の、原始人と文明人の、白人と黒人の接点にいる。二極対立する前の異質な要素の混合状態なのだ。」
正直に告白すると、安穏に保護され(虚勢され)た女の人生を生きてしまった私には、面白いとは思うものの共感できないことが多いのだが、考える種はいろいろもらったように思う。
『キングコング・セオリー』は、若い世代のフランス女性の共感を呼び(私にヴィルジニー・デパントを教えてくれたのは、当時20代前半の女性で、現在では30代後半になっているだろう)、現在、2度目の舞台化がされている。