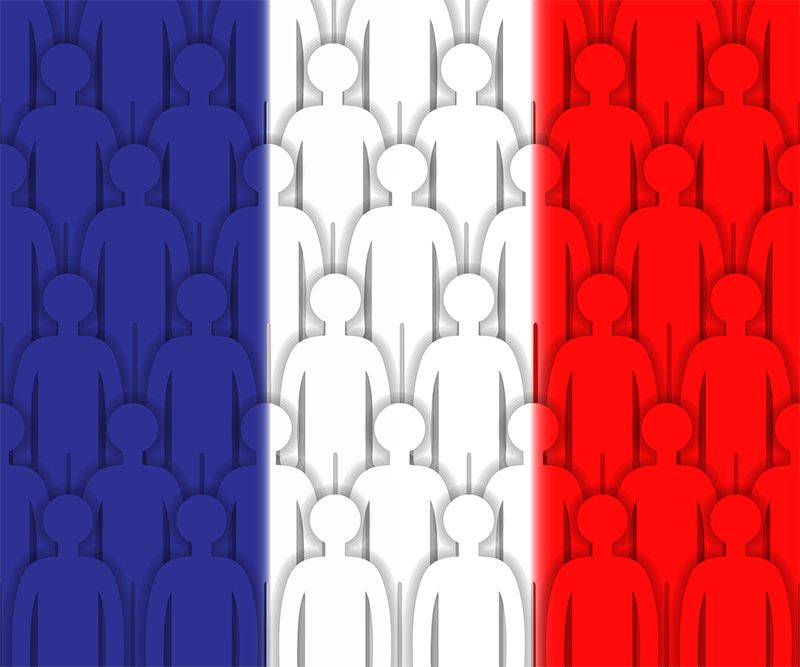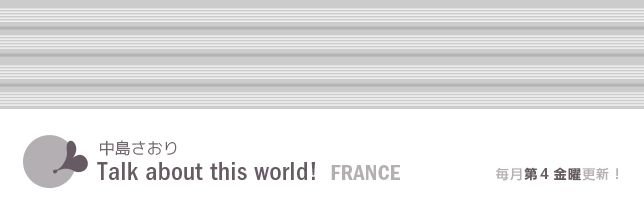
10月はハリウッドの大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラに大物女優たちが一斉に声を上げた事件が大きく報道され、これを受けてフランスでは、「私もセクハラ・性暴力被害を受けた」と語り出す女性が増えている。セクハラ・性暴力被害者のためのフリーダイヤル3919へのコール数は5倍に膨れ上がり、ツイッター上には証言が溢れ、とうとうパリをはじめ全国15都市でデモが行われた。
フランスの女たちに地殻変動が起こっている。
性暴力被害を語ることが、フランスでどれほど難しかったか、私は9月末に出版されたばかりの『Parler(話す)』(Flammarion)という本で知った。著者は、元ヨーロッパ・エコロジー=緑の党スポークスマンのサンドリーヌ・ルソー。昨年5月、同じ緑の党の男性国会議員ドニ・ボーパンを同僚女性4名でセクハラ・性暴力で告訴した一人だ。訴え自体は、犯行が時効という理由で不起訴処分になったが、この行動によって彼女は多くの女性から自分たちも同様の被害を受けたという告白を受けることになった。ルソーは党を辞し、性暴力被害を隠さず語ることで、女性たちを癒し社会の意識を変えて行こうと呼びかけるため、被害者の声を聞くアソシエーションを組織する…
彼女は書く。
「数字は恐ろしい。10人の性暴力被害者のうち、告訴するのはたった1人だ。そして告訴された者のうち9割は不起訴処分になる。つまり加害者が100人いるとすれば、有罪と認められるのはたった1人。社会を蝕む病原菌はこの加害者への恐るべき寛容さだ。それは女性の沈黙と恐怖を貪ってはびこっている。信じてもらえない恐れ、理解してもらえない恐れ、信用を失う恐れ。職を、友人を、家族を失う恐れ。私はこの本を、道を切り開くつもりで書いた。後から、他の、もっと多くの人々が、同じ道を歩むことができるようにと。私は、「ノー」と言って、正義が行われることを要求した女性の先人たちに続いた。私は、話すのは黙っているより辛いと女たちが言うのを聞いた。黙るというのは、ひとり忘れて「次のページを繰る」ことができると思うことだ。それはほとんどの場合まちがいだ。傷は見えなくてもなくならない。沈黙の掟を破ることは、初めは苦痛かもしれないが、自分自身と和解し、強くなるための療法なのだ。話すことでようやく、暴力を振るった者たちに、風向きが変わったと感じさせられるのだ。こうした支配に立ち向かい、私たちが受けている暴力とハラスメントを告発すること以上に強く力を持つ女性の解放はない。話そう、憎しみも罵りもなく、しかし話そう」。
彼女は、ボーパンに壁に押し付けられ、胸を揉まれ無理矢理キスされそうになったが、周囲に話しても「仕方がない」「黙っていろ」と言われた。ボーパンは党内で「原子力の専門家」と言われる重要人物で、告発した場合、党の活動にどんな影響が出るかも考慮せざるを得なかった。フランスでは、セクハラで上司・同僚を告発した女性の95%がその後、職場を去っている。彼女は仕事を辞めたくなかった…
彼女が2016年になって告発すると、2011年の事件を「なぜすぐに訴えなかった」と非難された。
ボーパンは彼女が「噓をついている」と反論した。「大人同士の誘惑し誘惑される関係」であって、彼女の告発は「中傷」であると彼は言い立てた。
セクハラ事件はいつも「同意があった」という反論で打ち消される。同意の有無が曖昧で明確な線が引きにくいことを利用して、「同意があった」あるいは「同意があったと思ったのは無理もない」と加害者は言い逃れをする。しかしそれで9割が「同意あり」と見做されるのは、どう考えても公平さを欠いていないか?
サンドリーヌ・ルソーはインタビューに答えて言っている。
「ノーと言っているのにイエスだと、なぜ思うのか。ノーと言ったらノーだと、何も言わない場合もノーだと理解してもらわなければならない。」
「何も言わなくても同意ということがあると言う人がある。そういうことはあるかもしれないが、それ相当の時間付き合って互いに意志が通じている場合だろう。」
厳密には、会ったその日に双方が恋に落ちることもないとは言えないから、同意の有無を判断するのは実際、難しいケースもあるかもしれないことを私は認めよう。しかし被害者が訴えている以上は、明確に「同意があった」と判断できないのであれば、「同意はなかった」と考える方が自然ではないだろうか。
男性たちはどこか勘違いをしている。いっしょに仕事をしたり、就職や学業の相談で女性が近づいて来たときには手を出してよいと思っていないか?
私自身、そういう情況下で性的なアプローチをされた経験がフランス人からも日本人からもある。こうした「相談に来た女は俺に好意を持っている。やってしまえばこっちのもの」的な発想が、男性に性暴力を許し、犯罪的な行為にも目をつぶる元凶になっていると思う。
私はふたつのことを提案したい。ひとつは、この勘違いを正し、「相談に来た女は相談の内容を解決してくれることを期待しているのであって、性関係を求めて来たのではない」と男性に広く理解してもらうこと。もうひとつは、愚かな誤解から脛に傷持つ男性たちであっても、女の同意がないことに気づいて行為をやめた経験のある男性には、「あれは誰にでもあることだ。俺だってもしかしたら」と性暴力で訴えられている男性と連帯してしまわず、踏みとどまるか行為に及ぶかは決定的な差であり、「俺はあいつとは違う。行為に及ぶのは犯罪である」と女性の方と連帯してもらいたい。
さて、時を同じくして日本でも、性暴力被害を顔と実名を出して訴えたジャーナリストの伊藤詩織さんが手記『Black Box』(文芸春秋)を出版して、自身に起こった事件の経緯、捜査・司法の問題点、被害者支援のあり方について訴えている。
就職相談に訪れた、二人きりで会ったのは初めて(それ以前に二回会ったときは同席者がいた)の泥酔した女性をホテルでレイプしたというこの事件は、ドニ・ボーパンの悪質「壁ドン」に較べてもさらに数倍も犯罪的に思えるけれども、逮捕状も差し止められ、不起訴処分になっている。こういうケースを裁判すらしないで野放しにしていたら、世の男性はどこまで許されていると勘違いするだろうか。
性犯罪事件での起訴が多い国ほど、実際の性犯罪被害者は少ないともいう。日本はレイプ事件の少ない国だそうだが、田中賀寿子大阪地検検事によると、表面に出ているのは実際の4%に過ぎないそうだ。
勇気を出して「話し」た詩織さんを1人にしないで、彼女の切り開いた道を辿ろう。日本でもMeTooと声を上げよう。