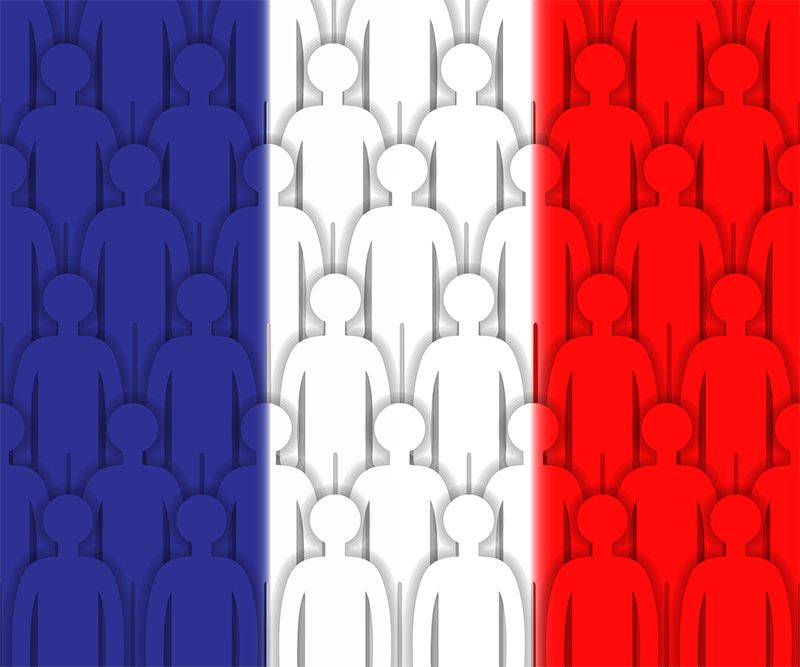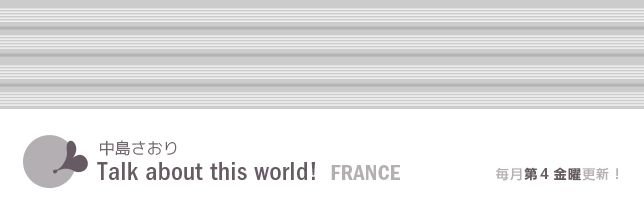
出生率ヨーロッパ第一位!
フランスは最新(2015年のデータ)の比較でもアイルランドを制して欧州トップの座を守った。「子どもの生まれる国」というイメージが日本でもすっかり定着したフランス。
しかしそんなイメージの影で、実はフランスの出生率は現在、右肩下がりの傾向にある。2014年には2,01だった合計特殊出生率は2015年には1,96。人口が減らないために必要な2,10を下回っており、最近 INSEE(国立統計経済研究所)が発表した2016年の数字は1,93とさらに低下している。
その理由は、経済のかげりと失業だとINED(国立人口問題研究所)のレポートは言う。先の見えない不安から「生み控え」が起こっているのは世界的な傾向だが、フランスも例外ではないということだ。
それでも下げ幅が他の国と較べて小さいのは、家族政策の充実が出生率を下支えしているからだと分析されている。たしかに、よく言われるように様々な託児システム、育児休業制度が整っており、二人以上の子どものある家庭に支給される家族手当や低所得家庭への住宅援助などが、経済的にも子どもを持とうとするカップルを支えている。女性が仕事と子育てを両立できる国が出生率が高くなるというのは、すでに定説となっているところだが、フランスはかなりこれに成功していると言えるだろう。ただし、保育システムの完備だけでは十分でなく、低年齢の子どもを他人に預けることに抵抗がないフランス人のメンタリティも貢献しているとINEDのレポートは指摘している。
ところで、出生率に与える影響は小さいが(生まれる子ども全体の2,5%くらい)が、生殖医療の貢献はまだ上昇が望めるかもしれない。フランスは1982年という早い時期に試験管ベビーを成功させた国なのだが、その後の無法状態を取り締まるべく1994年に生命倫理法ができ、それに沿って生殖医療に施されたさまざまな制限が厳しいのだ。人工授精や体外受精が保険の対象にならない日本から見れば、人工授精6回、体外受精4回までが100%も保険負担で、生殖医療に関する法整備もされているフランスは圧倒的に進んでいるが、生殖医療が、いわゆる「不妊治療」に限られていること、つまり女性の年齢が自然に生殖可能年齢(現在の規定では43歳以下)であること、異性愛カップルで少なくとも2年以上同居しているというような条件が時代に合わなくなってきたということはあるかもしれない。
最近の傾向として、女性が子どもを産む時期が遅くなっている。平均初産年齢は28歳だが、新生児の母親の平均初産年齢は30,3歳(2015年)。40歳以上の場合が全体の5%ある。キャリアをある程度積んでから母親になりたいと考える女性が増えていること、また単純にあまり若い頃には人生を一緒に築こうと思う男性に出会っていない場合が多いことが背景にある。ところが、女性が最も妊娠しやすいのは一般に22歳。35歳を過ぎると格段に妊娠能力は落ちてしまう。
そういうことから生殖医療、とりわけ卵子提供による妊娠に頼る人は増えている。卵子提供による体外受精は30年前から実践されており、25%から30%の成功率だが、フランスでは卵子提供者が少ない。これは、卵子提供者が報酬をもらうことが禁じられているためだ。ベルギーや、スペインなど「卵子ビジネス」が成立する他国では、数に余裕がある。そのため、フランスで卵子を必要とする人の半数は、ベルギー、スペインまたギリシャやチェコに卵子を貰いに行く。また、フランスでは女性本人が若いときに卵子凍結をしておくことも禁じられているため、出産高齢化に伴い、卵子凍結の許可を求める運動も起こっている。
生殖医療に訴えられるのが、異性愛カップルに限られるという点も改革される可能性が見えてきた。最近、調査会社BVAが2016年11月28日に3038人に対して行った、家族に関する対面式の調査が発表されたが、この中で、61%のフランス人が、女性同性愛カップルの人工授精に賛成している。2014年に行われた同様の調査に較べて6ポイントも上昇している。また、フランスでは現在禁止されている代理母による出産も50%以上が認めるべきとしていて、こちらも2014年に較べて7ポイントのアップ。私が『パリの女は産んでいる』(2005年)でこの主題を取り上げた頃から較べるとかなり様変わりしている。
しかし、生殖医療の幅を広げることは、「家族」の概念も変えて行くことになるし、生命倫理の問題も孕んでいる。出生数が増える、出生率が上がるというだけで考えて良いことではないかもしれない。