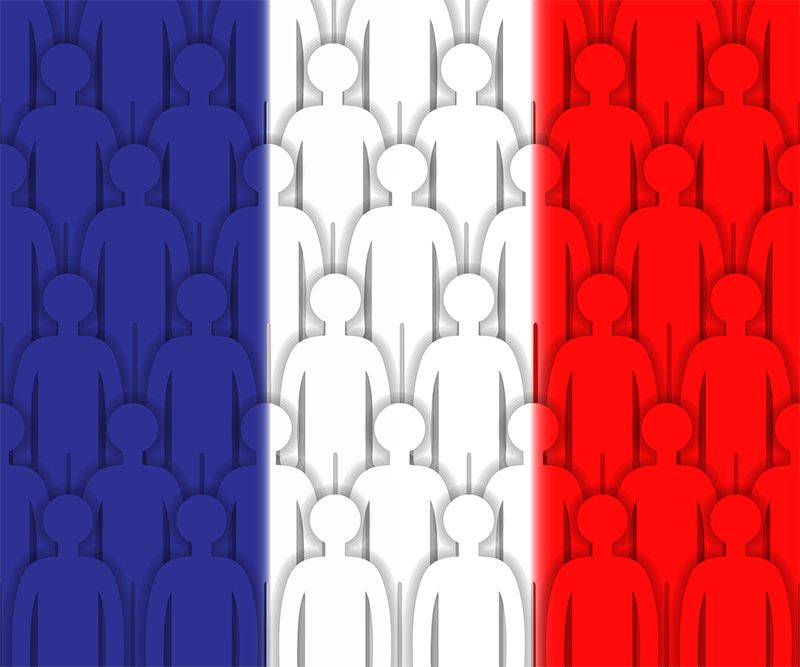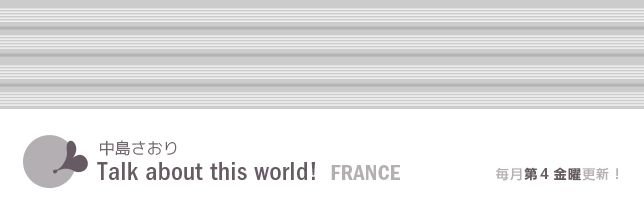
今、フランスはバカロレア(大学入学資格=高校卒業資格試験)の真っ最中だ。土日を挟んで一週間、一日4時間から6時間の試験を最低9科目を受験するバカロレアは、毎年、伝統的に哲学の試験をもってスタートを切る。
今年の出題は、「われわれの道徳的信念は経験の上にうちたてられているか」、「欲望とは、その性質上、際限のないものか」(文系)、「われわれは常に自分の欲するものを知っているか」「なぜ歴史を研究する意義があるのか」(社会・経済系)「少なく働くことはよく生きることか」「知のためには証明しなければならないか」(理系)
国民が一生に少なくとも一度は、こんな問題に必死に取り組むことが課されている国というのは、世界を見渡しても珍しい。
バカロレアの「哲学」は、フランス人たちがひとしきり騒ぐ年中行事でもあり、受験など遠い昔となった大人も「どれどれ今年の問題は?」と興味をもつ。
著名人たちが受験生だったころ哲学で何点を取ったかという記事も毎年、フランスのマスコミを賑わす。たとえば前大統領、ニコラ・サルコジは20点満点中9点で、合格点(10点)を取れなかったということは周知の事実だ。現大統領フランソワ・オランドはといえば、13点でまあまあの及第点。極右政党、国民戦線二代目党首のマリーヌ・ルペンは、自信満々で試験場を出たのにまさかの12点。不満で答案を取り寄せたら、「これは法学の解答で哲学の解答ではない」と書いてあったため、ふむ、私は法律に才能があるのかと法学を専攻することにした、と吹聴している。
しかしなんといっても優秀なのは、ミッテラン政権下で弱冠38歳で首相を務め、最近ではオランド政権エロー内閣、第一次ヴァルス内閣で外相を務めたローラン・ファビウスの20点満点だろう。この人は高等師範学校、パリ政治学院、国立行政学院とフランスの文系エリート校を総なめしている。一方、ただただ出来たというのではない武勇伝を残しているのは、今はポンピドゥー・センターに名前が残るだけで日本人の記憶にとどまっている(というわけではないかもしれないが)第五共和制第二代大統領、ジョルジュ・ポンピドゥーだ。4時間も続く試験の途中、ちょっと離れたところにいたパリ美人と目が合った。彼女が絶望的な眼差しで彼を見つめたので、未来の大統領は男気を出して自分の下書きをボールに丸めて彼女に送ってやった。パリ美人は思いがけない高得点を取り、若き日の大統領はすれすれの点で合格した。残り2時間で、もう一つの題で作文するには熟考している時間がなかったのだった…。
しかし大学受験の点数が一生うんぬんされるとは、フランスの政治家も大変だ。それほど、「哲学」はフランス人にとって何ごとかであるということか。
「哲学」の重視は他のヨーロッパ諸国とも際立ったフランスの特徴だ。ウェブマガジンSlateの記事によれば、イタリア、スペイン、ポルトガルでは必修科目だが、フランスと同じような教育をするのはポルトガルのみ。イタリアで教えられているのは「思想史」で、教えるのも歴史の先生であることが多い。スペインでは「公民」を一年教え、もう一年を「哲学史」に割く。ドイツ、スイス、ポーランド、スェーデンでは、必修科目ですらなくなり、選択科目になる。ドイツでは学校で「宗教教育」をするので、どの宗教も学びたくない生徒が代わりに「哲学」を学ぶ。イギリスでは、「哲学」の授業といえるものは存在しないそうだ。関わりのある教科といえば、「宗教の比較をする授業」と「論理的な文章を書く練習」だろう、とこの記事の筆者アナベル・ローランは言っている。
面白いのは「論理的な文章を書く練習」がフランス人から見ると「哲学」と類似の科目に見えるということで、これはまことにその通りなのだが、「倫理、政治経済」で「アダム・スミス=『国富論』=神の見えざる手」とだけ暗記している日本の高校生にはなぜだかまったく分らないだろう。
しかしフランスの高校生が習っている「哲学」は、まさに日本の「倫理、政治経済」よりはよほど「論理的な文章を書く練習」に近いものなのだ。
「高校最終学年で勉強するのは哲学ではない、哲学することなのだ」とフランスの哲学教師たちは言う。そこがイタリアやスペインで教えているものと本質的に異なる点でもある。思想史や哲学史では、過去の哲学者が何をどう考えたかを勉強する。フランスの学校の「哲学」も、哲学者の考えについて学ばないわけではないが、それが目的ではない。それを使って自説をどう展開するかの方に、はるかに重きがおかれているのだ。
だからこんな風に注意される。
「ある問題が哲学的であるのは、哲学者と呼ばれる人がそう考えたからではない。その問題にすでに哲学的な答えが存在するからではなおさらない。直接問題を扱うことを避けて偉大な哲学者の後ろに隠れるのは、優雅なやり方ではあるが、要するに逃げである」
ちなみにこれは著名な哲学者の言葉ではない。高校生のための受験参考書を書いた高校の哲学の先生の言葉である。私はこの言葉を、具体的な誰彼というわけではないが、多くの人に言ってやりたい気がしないでもない。
と、ちょっと脱線したが、要するに、フランスの高校における「哲学」は、世界的に見てもユニークだということが言いたかった。そしてなぜユニークかというと、これがフランスの歴史、啓蒙思想が国家の形成を支えたというフランスの歴史に起源を持っているかららしい。
バカロレアを開設したのはナポレオン帝政で、「哲学」の試験は、バカロレアが始まった1808年から存在しているが、フランス革命の精神が幾度もの政体変化を経て継承されてきたフランスでは、哲学を通じて自由に考える市民を養成しようとする理念が生きてきた。フランス革命に大きな影響を与えたモンテスキューは、共和制は市民が自由にその判断を行使することにかかっていると考えたからだ。
だから学校で教える「哲学」では、生徒や教師個人の考えの方が、歴史的、百科事典的な知識よりも優先される。
自由にものを考える市民を作る教育を着想した、200年前のフランス人たちには脱帽する。たとえ最初のバカロレア取得者は31人で、長い間、全人口の1%しか享受できないエリート教育であったとしても。今日では、国民の7割が、「自由にものを考える」教育を受けた経験をもって成人になる、その種を先人たちは撒いたのだ。
「哲学」の試験の存在に異議を唱える人もあるが、200年の伝統は簡単には覆らない。理数系科目に押され気味ではあるが、それでも「哲学」がフランスの中等教育から消えることはないだろう。「文系」の高校生は週8時間、「社会・経済系」で週4時間、「理科系」で週3時間、実業高校でも週2時間「哲学」を学ぶ。「哲学」がカリキュラムにない職業高校にも、導入しようとする動きが出て来ている。
日本では、内実は「思想史」の授業であった「倫理・社会」さえも高校のカリキュラムから消えて30年、「倫理」という科目が、公民科の授業のなかに細々と選択科目として名を残すのみで普通高校でも開設されないことがあり、少ない時間で思想家の名前と著作物とキーワードを暗記するのみになっている。「自由にものを考える市民」を育てようとする思いがずいぶん違うようである。