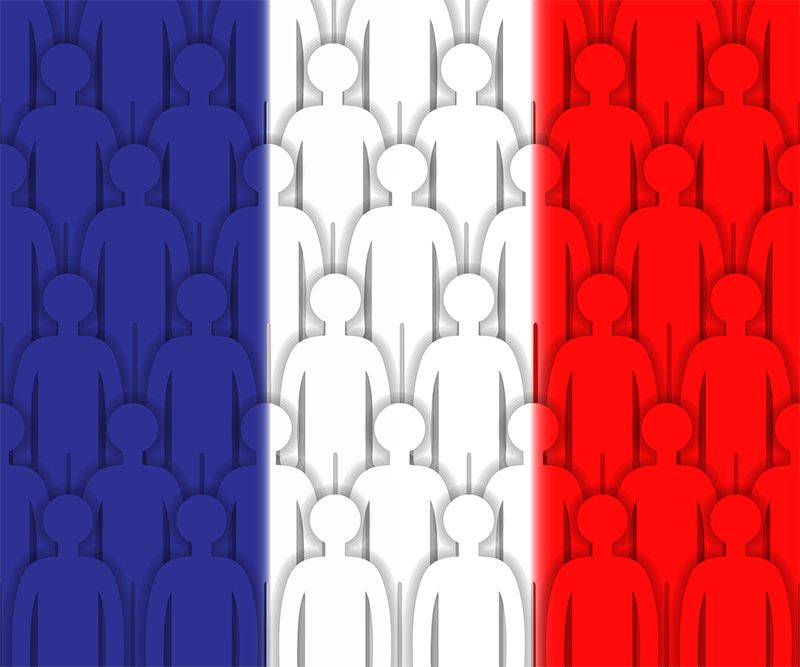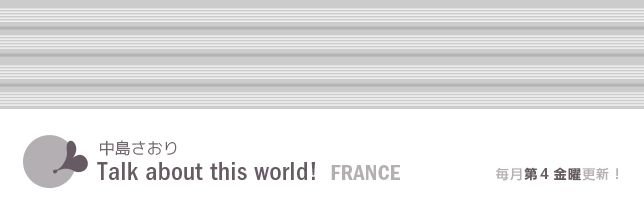
大晦日の夜、ケルン(を初めとするドイツの諸都市)で起こった集団性暴行事件は、日本では、難民受け入れとの関係でばかり報道されているが、フランスではフェミニズムの文脈でも問題にされている。
大勢の男たちが女性たちを取り巻き、身体を触ったり、淫らな言葉を投げかけたり、暴力をふるった。女性たちが訴え出た数は1月10日時点で500件を超え、その後も増え続けている。その犯人たちが見るからに浅黒い肌の中東、北アフリカ出身の男たちだった。取り調べが進むに連れて、ドイツの警察は、多くがこの地域出身の不法滞在者、難民申請者であることを発表した。
ケルン在住のジャーナリストで70年代パリの女性解放運動の闘士でもあったベテラン・フェミニスト、アリス・シュヴァイツァーは、さっそくメルケル首相の難民受け入れ政策を批判した。
「誤った寛容主義と信教の自由のため、我々は、イスラム教徒のなかに狂信者が台頭するのをあまりにも長いこと見過ごして来た。そして戦争のために、女に何の権利も認めない粗暴な男たちがヨーロッパに押し出されて来た。」
このように、女性蔑視をイスラムと結びつけて西洋文化としてのフェミニズムに対置させる言説に対し、若いベルリンのフェミニスト、アンヌ・ヴィツォレックは、「セクシャル・ハラスメントも性暴力も、移民・難民が入る以前からドイツにはあった。それは社会全体の問題だ。外部の者が犯したときだけ声高に語るのではなく、常に語らねばならない問題だ」と反論し、性暴力事件を移民・難民問題にすり替える議論に警告を発した。
ヴォツォレックと同じ考えに沿って、ドイツ在住のイスラム研究者ジュリー・ビヨーは「オクトーバーフェスト(バイエルンの首都ミュンヘンで10月に開催される大規模なビール祭)でも同じことは起こっているが、誰もバイエルン文化の問題とは言わない。移民・難民が犯人だとイスラムの問題だと言うのは危険な議論のすり替えだ」と論じる。
男たちがこのような犯罪を犯したのは、本当に「文化」や「宗教」のせいなのだろうか。それとも、社会的に居場所のない若い独身者のフラストレーションのせいなのだろうか。考えてみる余地があるだろう。
難民収容所では、同じ難民の女性たちが日常的に被害に遭っているが、彼女たちは訴えも起こさないので可視化されないことも指摘された。
しかし、文化的な要素をまったく考慮しないのもどうなのだろうか。なるほど、イスラム教の支配する国から来た男たちの目に、身体を露出する服装で夜の外出をする西欧の女性はカルチャー・ショックで、ひょっとすると売春婦に見えるのかもしれない。そういう意味で、宗教に内在するかどうかは別問題として、異文化の軋轢はたしかにあるだろう。
フランスの哲学者で筋金入りのフェミニスト、エリザベート・バダンテールは、「フェミニストは人種差別主義者と非難されることを恐れて、口をつぐむべきではない」と語った。
しかし、このバダンテールとシモーヌ・ド・ボーヴォワールを引用して、「移民・難民の流入がフェミニズムに終止符を打つのではないかと心配している」と、移民排斥を訴える極右政党FNの党首、マリーヌ・ルペンが書くに至っては、完全にフェミニズムの人種差別利用と言えるだろう。マリーヌ・ルペンは、ごく最近でも「中絶反対」を唱え、フェミニズムとは全く相容れない思想の持ち主なのだ。
フェミニズムは西洋的価値なのか、より普遍的な「男権主義」との闘いなのか、ドイツの性暴行事件は、現在の西欧におけるフェミニズムの二つの異なる流れとその問題を浮彫りにして見せた面がある。