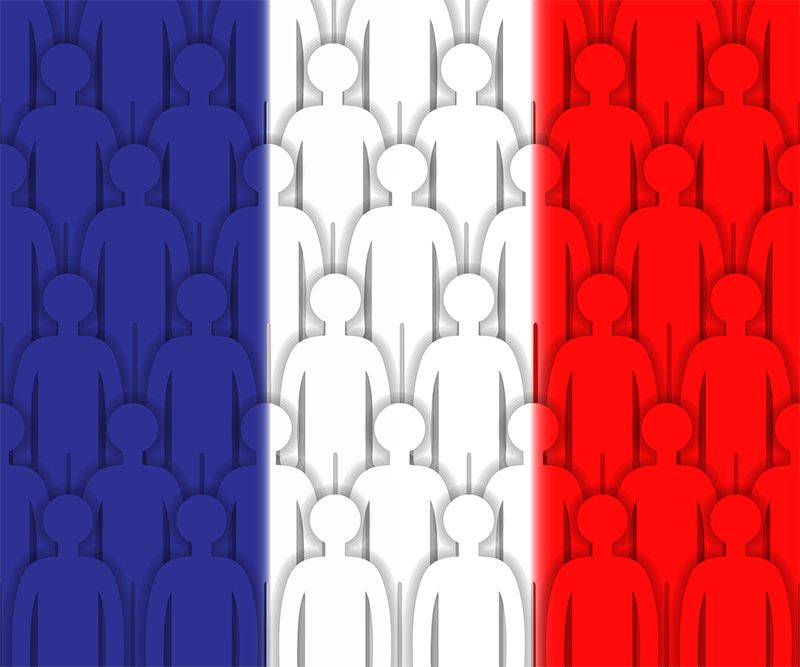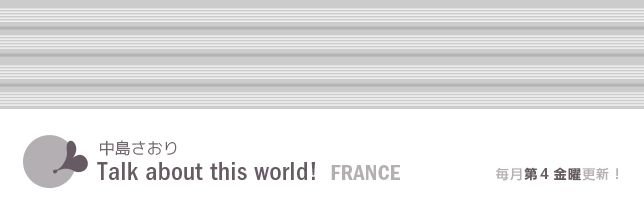
女たちは残念ながら、女というだけで一致して統一戦線を組むことはできないようだ。ひとりの女は、ただ女であるだけでなく、人種とか宗教とか、さまざまなアイデンティティーを兼ね備えており、それがいちいち交錯するのだから、一枚岩になれと言われてもむずかしいかもしれない。
「フランスのフェミニズムの主流は人種差別的なフランスの法律を支持することでムスリムの女性を取り落としている。」という寄稿が最近、英国の『ガーディアン』紙に掲載された。筆者はクリスチーヌ・デルフィ、1977年にシモーヌ・ド・ボーヴォワールといっしょにNouvelles Questions Féministes (新フェミニズム問題)と題する雑誌を創刊し、 MLF (女性解放運動)の闘士だった筋金入りのフェミニストだ。
そこまでの権威に言われるまでもなく、イスラム教徒の女性が普段、頭に巻いている長いスカーフ、あれを「学校にしていってはいけません」と法律で決められているとなると、フランスの言い分を知らない日本人はおそらく誰でも違和感を抱くだろう。
これは2004年にできた法律で、「公共の場で明らかな宗教的印をつけてはならない」という信念に由来している。どうしてまたそういう信念があるかというと、フランス共和国は、フランス革命以来、長年の闘いによって宗教の支配を脱し、宗教の影響を公生活から閉め出した歴史を持っているからだ。個人的には何を信じようが信教の自由は保障する。ただし国は特定の宗教と関係を持たない。学校教育はとりわけ、19世紀から20世紀初めまで、国家権力と宗教的権威がしのぎを削る場だったので、学校と宗教の関係にはとても敏感だ。フランスで暮らしていると、それは理解できる。
とはいっても、それは長年フランスにおける権威だったカトリック勢力に対抗してのことだ。イスラム教は、戦後、旧植民地から、イスラム教徒の移民が大量に入って来てからが俎上にのぼった。コンテクストがまったく違う。
今や、フランスの「非宗教性の原則」は、イスラム教徒に向けられて、「イスラム教徒はフランスの非宗教性原則に馴染まない」とか「民主主義に馴染まない」とか、さんざん言われている。イスラムを詳細に検討していくと、なるほどそういう議論にも根拠がまったくないわけではないのかもしれない。が、現実には、イスラム教徒でありながらフランスの非宗教原則に抵触せずに生きているムスリムもたくさんいる。まあ、もちろんそういう人はわざわざスカーフをしたりしないかもしれないので、スカーフは踏み絵になるのかもしれないが…
フェミニストたちがムスリムのスカーフに取る態度は「イスラム教では女は不浄で男を誘惑に引き摺り込むという理由でスカーフを身につけさせる。スカーフはムスリムの男たちに女が抑圧されている証拠。脱ぎ捨てなければ」というものである。実際、そういう面もあるのだろう、父や兄の抑圧から逃れた移民女性の訴え、スカーフへの告発というのは実際にある。しかし、クリスチーヌ・デルフィも言うように、「だとしたら、そういう女の子を学校から閉め出すことは、抑圧的な家庭に彼女たちを押しやることにしかならない」のではないか?
私には、ことさらにスカーフなど無害な服装に文句をつけるのは違和感があり、ムスリムいじめのように感じられるのだが、フランス人である夫は、「あんなものを着けさせられて、気の毒な女性たちだ」としか思わないようなので、根が深いものを感じる。
フェミニストであることとムスリムであることとは、両立し得ないだろうか? そんなことはあるまい、と思う。それをうまく両立させられたら、硬直したフランス社会の活路になるのではないか、とも思ってみる。
デルフィは、ムスリム女性がイスラム文化を内包した、自分たち自身のフェミニズムを発達させたいと思うのを許容しなければならないと訴えている。
さて、話はまったく違うが、これを書いている今日、東京では安保法制に反対する「ママの渋谷ジャック」が行われている。フェミニズムもまた、所属する社会や文化の影響を免れないとするなら、日本のフェミニズムはおそらく、フランスよりも、「母親」が大きな役割を果たすものなのかもしれない。が、どこの世界にあっても、女のパワーは新しい道を拓く希望であるような気がするのは、オプチミスト過ぎるだろうか。