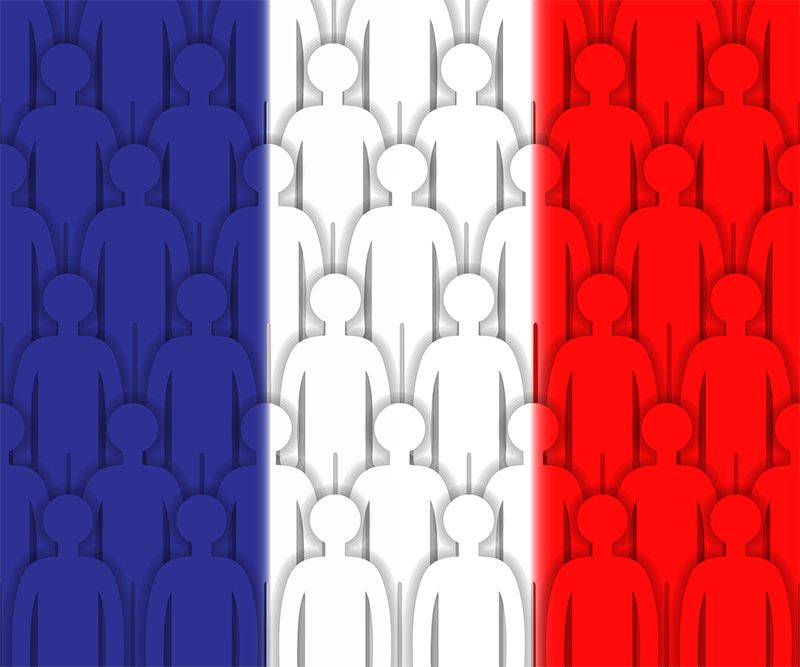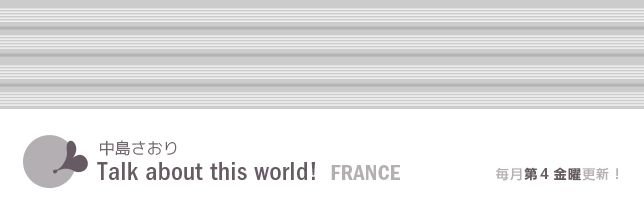
ミシェル・ウエルベックの最新作 « Soumission »(服従)を読んでみた。
今年の始め、発売前から「イスラム教にフランスが乗っ取られる話」ということで、非常にポレミックな作品とメディアが騒いだが、発売になった当日、奇しくも週刊紙「シャルリー・エブド」襲撃事件が起こり、身の危険を感じた著者は急遽、プロモーションをすべて打ち切って田舎に隠れたという話だった。
そんなこともあって、空前のベストセラーになったが、それから1ヶ月、実際に読んだ人々の感想は一様に、「それほど危険な小説ではなかった」に収斂している。
イスラム教を面と向って馬鹿にするようなところは見られないし、最後にイスラム教に改宗する主人公を皮肉に取ることはできるとはいえ、「イスラム嫌い」の小説とは思われないのだ。
ぱっとしない大学教授がぱっとしないセックスをして、イスラム教の大学になってしまったソルボンヌに務めるため、日和見でイスラム教に改宗する「可もなく不可もない小説だった」という感想が多い。
けれども私は面白かった。
2022年のフランスが舞台。2017年の大統領選では、すでにまったく人気のないオランドが2期目を務めたことになっている。そして新たな大統領選、PS(社会党)のオランドも、2大政党のもう一方であるUMP(国民運動連合、保守系)も第一回投票で排除されてしまい、決選投票に残ったのは、人種差別的な極右政党FN(国民戦線)のマリーヌ・ル・ペンとイスラム穏健派政党Fraternité Musulmane(ムスリム兄弟会)のモアメッド・ベン=アベス。この候補が非常に賢く巧妙であることから、PSもUMPも他の中道政党も極右を制するため「拡大共和国戦線」を張ってアベスにつく。こうしてフランスにイスラム政党の大統領が誕生するのである。
フランスでは、政教分離原則のためイスラム政党というのは作れないから、現在、ありもしないイスラム政党の2022年時点での勝利という設定に現実性はほとんどない。しかし近年、大きく成長しているFN(昨年の欧州議会選挙でフランスでトップ得票、国政選挙で初めて議員を2名選出、今年1月の国会議員補欠選挙でも第2回投票で破れたとはいえ、第1回投票でトップ得票など)の前に既成政党がますます無力に見えるのは事実、2017年の大統領選ではFNが決選投票に残るだろうと予想されている。
一方、一部の過激派イスラム教徒と、それに触発されて勢いを増すイスラム嫌いに対処するため、穏健なフランスのイスラム教徒をまとめて代表する組織が必要だという声は以前からある。つい最近も、ベルナール・カズヌーヴ内相が、テロ事件を受けて、現在うまく機能していないCFCM (フランス・イスラム教評議会)に代わる新しい組織の必要を訴えたばかりだ。この考え方を押し進めるなら、穏健なイスラム政党まではあと一歩かもしれない。イスラム系の移民の国会議員が少ないことは確かで、もし彼らが自分たちの代表を議会に送るなら、政治地図は塗り替えられるだろう。
小説のなかでは、ベン=アベスが大統領になったとたんに犯罪率が減るのだが、社会的に疎外されているイスラム教徒に場所が与えられれば、治安の改善につながるとは考えられる。
またベン=アベスの統治が意外にうまくいく例のひとつに「ゲイの結婚に対する反対」など、フランスの保守的な層の主張が、イスラム教の大統領のもとで実現した、という点を挙げている。現代社会に注がれる批判的眼差しのうち、復古的な価値観につながるものは、イスラム教からの批判とも重なることに注意を向けている。
小説は実際の未来図を予想しているわけではない。が、鋭い社会批評に基づいており、フランス社会のいくつかの面を小説家の想像力で膨らませ、ブラック・ユーモアを漂わせながら、それを見せてくれる。
ただ、どうしても受け入れがたいのは、女性の運命である。仕事はやめさせられ(そのため失業率は減る)、体中を覆う着物を着せられ、一夫多妻制のもと、自分で選んだのではない相手に嫁がされるらしい。前半では主人公は毎年、新しい女子学生とつきあっては夏休みに捨てられる生活をしているが、去って行った女たちは誰も幸せになっていない。自分もそろそろ歳を取ってきた。料理のうまい妻と若い妻を斡旋してもらって新しい生活に入るのも悪くない、と考えているようだが、さて、この女性観はどうしたものだろうか。